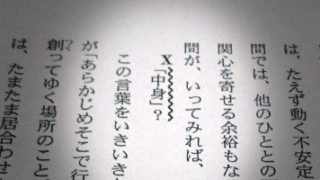 勉強法・推薦図書・その他
勉強法・推薦図書・その他 講談社青い鳥文庫が児童に最適である理由 漢字は「書き」の前に「読み」が必要
児童向けの文庫の中では、「講談社青い鳥文庫」がとてもよいです。優れた文学作品が多く出版されていることが第一の理由ですが、「ほぼすべての漢字に読み仮名が...
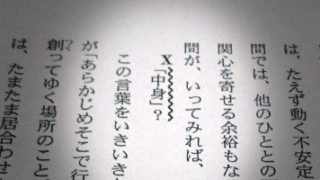 勉強法・推薦図書・その他
勉強法・推薦図書・その他 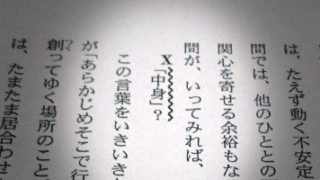 記述対策
記述対策 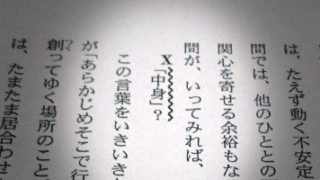 記述対策
記述対策 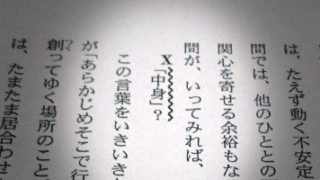 記述対策
記述対策 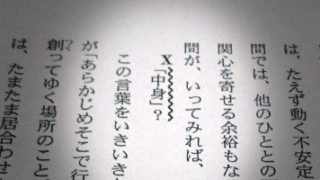 記述対策
記述対策 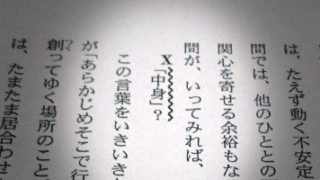 記述対策
記述対策 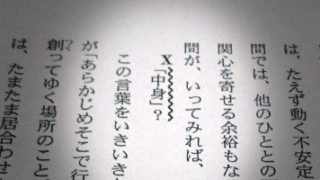 記述対策
記述対策 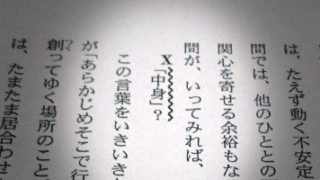 記述対策
記述対策