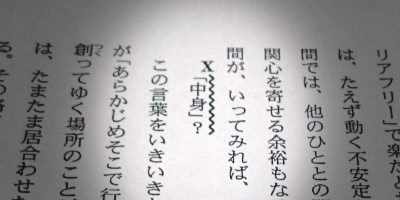問題/論証/結論
問題提起(論点設置)
↓
論証(結論に至るプロセス)
↓
結論(答え)

実際に書くときには、「論証の前」に「結論」を出しておいたほうがいいです。
そのように「論証の前」に「結論」を書いてしまう場合、小論文の最後に書く「結論」は、内容的に2回目になりますので、表現がまったく同じにならないように工夫して書きましょう。
問題提起(論点設置)
↓
結論(答え)
↓
論証(結論に至るプロセス)
↓
結論(2回目なので表現は工夫する)

「結論」を一度先に書いておけば、最後の「繰り返しの結論」はなくてもそれほど問題視されません。(減点や加点の対象になりません)
試験というのは「時間」や「字数」の制約がありますから、「まとめ」の書き方の自由度が高いスタイルで挑むほうが気が楽ですよ。
2行しか余ってなくてもそれなりに書けますし、さらに言うと「論証をしっかり書いたら残りの字数がなくなってしまった」という場合、まとめは書かなくても大丈夫です。なにしろ1回書いているので。
論証は「説明(考察)」+「例示・データ」

「論証」は、基本的には、「説明部(意見)」と「具体部(例示・データ)」に分けましょう。
トゥールミンのモデルでいうと、
Claim(主張)
Warrant(理由付け・説明・正当化)
Data(個別の事象)
の3つが論証に必要なものです。
Claim(主張)がない小論文はそもそも成立しません。そのうえで、「理由付け・説明・正当化」と「個別の事象(例示・データ)」は、「どちらかだけをたくさん書く」というのではなく、両方書き込むようにしましょう。
「説明」→「例示・データ」の順番が基本

論証の部分は一般に「本論」と言いますが、「本論」のパラグラフは「説明→例示・データ」という流れで書くことが基本です。
その「セット」が3つできるなら、「本論」のパラグラフは3つになります。
小論文では「説明」→「例示・データ」のセットを「1つ」つくることが基本

小論文は、たいてい600字~800字くらいなので、「説明→例示・データ」という「セット」を「1つ」つくればよい場合が多いです。
設問に「理由を2点挙げて論ぜよ」というような特別な指示がない限り、「説明→例示・データ」の「1セット」を書く方針でOKです。
「1セット」で書く場合には、「説明」と「例示・データ」でパラグラフを分けても問題ありません。
「流れ」について
序論/本論/結論
(1
(1)Ploblem Statment 問題提起(論点設定)
(2)Thesis Statment 主張(結論)
(3)Reason 理由(端的な理由・理由が複数あればその数など)
(4)Warrant 説明(理由の詳細・前提の明示など)
(5)Example (例示)

ん?
じゃあ全体のパラグラフが「5つ」ある場合にはどうすればいいの?

真ん中の「本論:Body」は、パラグラフを複数に分けてもいいということなんだね。

基本的に
「序論」(1)(2)(3)
「本論」(4)(5)
「結論」(3)(2)の繰り返し(表現は工夫して変える)
というイメージです。