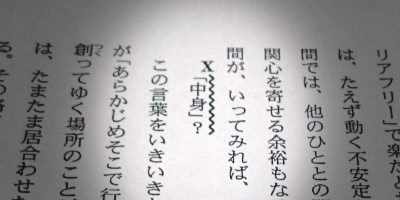(一)
それが大人の権威を支える現実的根拠であった。
論点収集
傍線部の論理関係は
それが ー 大人の権威を支える現実的根拠であった。
主語S 述語P
というものである。
少し並べ替えて簡素化すると、
その現実的根拠が ー 大人の権威を支えた。
主語S 述語P
とすることもできる。
文脈から考えて、これは「原因・きっかけ・推移」を問うている「cause型」の「なぜか」であるので、「その」の指示内容を過不足なくまとめ、「述語P」とのつながりを検討しよう。
「それ」という指示語が指している箇所は、「同じ仕事を共有する先達と後輩の関係(が成り立つ基盤)」である。傍線部の直後に、「そういった関係」とあることからも、「同じ仕事を共有する先輩と後輩の関係」という部分は、決定的に重要な論点となる。
同じ仕事を共有する先達と後輩の関係という現実的根拠が、【 】から。
さらにさかのぼると、
産業革命以前の大部分の子どもは、学校においてではなく、それぞれの仕事が行われている現場において、親か親代わりの大人の仕事の後継者として、その仕事を見習いながら、一人前の大人となった。
と述べられている。
まさにここが【 】を埋める理由とみなせるので、ここをまとめると、次のような〈下書き〉が成立する。
〈下書き〉
産業革命以前の職業現場における、同じ仕事を共有する先達と後輩の関係という現実的根拠によって、後継者としての子どもは、一人前になるために先達しての大人の仕事を見習う必要があったから。(→大人は権威であった)
答案化(簡潔化)
「現実的根拠」などの傍線部内の語句は、修正して使用する。もともとの傍線部の「結論」にあたる語句なので、素直にカットしてよい。
〈答案〉
産業革命以前の職業現場では、子どもと大人が実際に同じ仕事を共有する基盤があり、後継者としての子どもが一人前になるためには、先達である大人の仕事を見習う必要があったから。
〈さらに簡潔な答案〉
産業革命以前の職業現場では、子どもと大人が実際に同じ仕事を共有する基盤があり、後継者である子どもは、一人前になるために先達である大人の仕事を見習ったから。
〈論点チェック〉
産業革命以前の職業現場 ①
子どもと大人は仕事を共有 ① 「同僚」「仲間」なども可
後継者としての子ども ①
先達としての大人 ①
一人前になるため ①
(子どもは大人を)見習った ①
(二)
その意味では、中世の教師は、逆説的にきこえるかもしれないが、教える主体ではなかった。
論点収集
傍線部の論理関係(SーP)は、
中世の教師は ー 教える主体ではなかった
主語S 述語P
というものである。
「なかった」とあるので、「では『何』だったのか」ということに言及したい。そのつもりで「その」という指示語の指すところを確認していこう。
◆中世の教師は、近代の教師によりも、同時代の徒弟制の親方に似ている
◆中世の教師は、テクストを書き写し、解読し、注釈し、文書を作る人
◆その職業を実施する過程の中に後継者を養成する機能が含まれていた
さらに段落をさかのぼると、
◆中世には学校はあったが、教育という観念がなかったという。
◆目的意識的な働きかけができなかったということではない。
◆中世の生徒が、文書を作る職業~の予備軍であったために、見習いという方式がそれに適合していた
ここでは、「教える主体ではなかった」ということに対し、「教育という観念がなかった」または「目的意識的な働きかけをしなかった」と説明すれば、ひとまずOKだが、「では、結局何なのか?」という観点で傍線部直後にも注意を払うと、「同じ仕事を追求する先達と後輩」とある。たとえるなら「部活動の3年生と1年生」みたいなものである。この「先達」という語を拾っておくとよい。
〈下書き ver.01〉
中世の教師は、文章家としての職業を実施する過程に、後継者養成の機能が含まれていたという意味で、逆説的に聞こえるかもしれないが、教育の観念を持たず、目的意識的な働きかけをしない、ただの先達にすぎなかったということ。
さて、「逆説的にきこえるかもしれないが」という部分は、「が」という逆接の接続助詞によって、直後の述部とは逆接関係になる。内容的にも「主張」に含まれるものではないので、傍線部における「核」としての論理関係には組み込まれない。したがって答案作成で重視する必要はない。
とはいえ、傍線部内の表現である以上、まったく無視するわけにはいかない。うまく書けるなら、「教育をしなかったのに、後継者を育成していた点で、教育をはたしていた」というように、「逆説の関係」が可視化されていたほうがよい。
答案化(簡潔化)
〈答案〉
中世の教師は、文章に関わる職業を実施する過程で後継者を養成してはいたが、教育の観念をもたず、生徒に目的意識的な働きかけをしない点で、ただの先達にすぎなかったということ。
〈さらに簡潔な答案〉
中世の教師は、生徒に対する目的意識的な教育の観念をもたなかったのに、ともに文章の仕事をすることで後継者が育った点で、教育的行為を成し遂げていたということ。
〈論点チェック〉
中世の教師は (ないと減点)
文章の仕事を実施する過程で ①
後継者を養成していた ① (生徒を教育していた)
が (できれば逆接関係にする)
教育の観念はない ①
目的意識的な働きかけをしない ①
先達にすぎなかった ①
(三)
教師と生徒の関係のこの難しさに対処するために、近代の教育の諸技術が工夫されたということができるだろう。
傍線部内に「この」という指示語があるので、指示内容を取り込むことになる。
(教師は)教師的人間像を普遍的な理想的人間像であるかのように思いなして、それを子どもにおしつける。
しかし、
子どもが教師的人間像を受けいれることは、生徒の大部分が教師後継者ではなくなった近代の大衆学校では、ごく限られた範囲でしか通用しない。
この「関係」をまとめると、次のような〈下書き ver.01〉が成立する。
〈下書き ver.01〉
教師は、教師的人間像を普遍的な理想的人間像として子どもにおしつけるが、子どもが教師的人間像を受けいれることは、生徒の大部分が教師後継者ではなくなった近代の大衆学校では、ごく限られた範囲でしか通用しないということ。
ただし、次のことを考慮すると、傍線部の後ろも「論点」として拾っておきたい。
(1)傍線部が一文全体に引かれていない。
(もっと伸ばして考える必要がある)
(2)傍線部は「難しさ」という体言までであるのに、「どういうことか」と問われている。
(「難しさ」を「述語化」して解答できるほうがよい)
(3)傍線部が、段落の先頭にある。
(同段落内に必須の論点がある可能性がある)
その観点で傍線部のある段落そのものを確認すると、
子どもの自発性を尊重しつつ、
大人が意図する方向へ子どもを導こうとする教育の技術を発達させる動機には、
やはり、後継者見習いの関係が成り立ちにくくなったという事情が投影している
という、傍線部を含む一文の内容と同じ構造を発見することができる。
つまり、「後継者見習いの関係が成り立ちにくくなったという事情に対処するために(対処することを動機として)、近代は、教育の技術を発達させてきた」と述べていることになる。
構造的に、この「後継者見習いの関係が成り立ちにくくなった」という情報は、「(教師と生徒のこの関係の)難しさ」と内容的には同じことを述べている。
しかも「成り立ちにくくなった」という表現は、あえて漢字で書けば「難くなった」ということであるから、「難しさ」の意味内容も反映されている。
したがって、この「後継者見習いの関係が成り立ちにくくなった」という箇所を、答案に必須の論点としてみなすことにする。
以上により、次のような〈答案〉が成立する。
〈答案〉
近代の学校では、教師が教師的人間像を普遍的・理想的人間像として押しつけても、教師後継者ではない大多数の生徒は受け入れず、見習いの関係が成り立ちにくいということ。
〈さらに簡潔な答案〉
近代の学校では、多様な職業を志望する大部分の生徒は、普遍化・理想化された教師的人間像の強制を受け入れないため、後継者見習いの関係が成り立ちにくいということ。
〈論点チェック〉
近代の学校では、 (ないと減点)
教師が教師的人間像を普遍的・理想的なものとして押し付けても ②
多様な職業を志望する大多数の生徒は受け入れない ②
後継者見習いの関係が成り立ちにくい ②
(四)
近代の学校教師は、子どもを社会人に育てあげる能力をほとんど失ったにもかかわらず、いや失ったがゆえに、子どもへの理解を無限に強いられる。
傍線部そのものは長いが、設問は、
教師が「子どもへの理解を無限に強いられる」とはどういうことか。わかりやすく説明せよ。
というものである。
他の設問には書かれていないのに、この設問にだけ「わかりやすく」という付帯条件があるということは、「本文の表現からだけでは正解を記述できない」ということを意味している。もちろんこのような付帯条件がなくても、文脈から正解を推論しなければならない問題はありうるが、書かれていればなおのことそうである。
また、傍線部全体を問うているわけではなく、「子どもへの理解を無限に強いられる」という部分のみが焦点化されていることにも着眼しよう。この問いは、この部分を中心的に聞いてきているわけである。
さて、この部分で「わかりやすさ」が求められている箇所はどこだろうか。「わかりやすくせよ」と言うからには、問われている部分に「わかりにくい」表現がなければおかしい。その観点で最も考えなければならないところは「無限」である。「無限」とは、「きりがない」ということであるから、なんとなく読んでしまうと、「子どもへの理解を永続的に強いられる」というように読解してしまう可能性がある。
しかし、そのように、「無限」を時間的な意味合いで読解してしまうことは誤読である。もしも「これからずっとそうなる」という意味での「無限」であるならば、この傍線部の別箇所に、わずかでもそれを支える根拠が存在するはずである。ところが、それがない。
また、本文全体の流れからすると、「これからずっと子どもへの理解を強いられる」という文意は、主旨とやや食い違いが生じることになる。なぜならば、「教師の側が子どもを理解しなければならない」世の中になってきたのは、「近代」に入ってからだからである。「中世はそうではなかった」ときっぱり書いてある。
ということは、「子どもへの理解を強いられる」状態は、せいぜいここ100年くらいの出来事なのである。その、「ここ100年くらいで発生した状態」に対して、「永続的に(すなわち無限に)それが続く」と判断するのは、早計である。数年後に大きな社会変革があり、「学校に通う子どもがみんな文筆家を目指す世の中」が来ないとは限らない。
以上のように、「文全体」で判断していけば、ここでの「無限」は「時間」に対してのものではないことがわかる。では何なのか? ――これは、量・程度に対しての「無限」なのである。つまり、「数えきれないほどたくさんある」という意味での無限なのである。
何がたくさんあるのか? ――「子ども」である。より正確に言えば、「ひとりひとり異なる子どもの個性」である。
最終段落の2つ前の段落に、「工場の技師や商社のセールスマン、あるいはふつうの社会人を志望する生徒」という例示的表現があったことに着眼しよう。ここは、生徒の志望が多様化したことを意味している。多様化したからこそ、数ある生徒に対し、そのすべての多様性を見なければならなくなったのである。
したがって、「多様」とか「個性」といった論点を抽出できると、「わかりやすい」説明に近づく。「多様」という表現も「個性」という表現も本文にはないが、「わかりやすく」という設問の付帯条件を加味すれば、むしろこのくらいの「作文」ができたほうがよいことになる。
〈答案〉
近代の学校教師は、後継者を養成する方法での教育ができないため、子どもの自発性を尊重しつつ、意図する方向へ導くために、すべての子どもの多様性を見出す必要に迫られるということ。
〈さらに簡潔な答案〉
近代の学校教師は、後継者を養成する能力を発揮できないため、子どもの自発性を尊重しつつ、意図する方向へ導くには、あらゆる子どもの個性を知らなければならないということ。