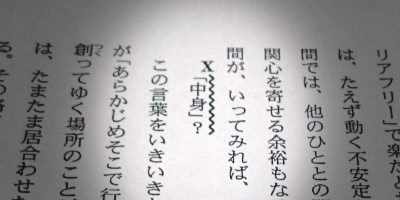大前提
答案をつくる際の姿勢として、次のことを意識しておきます。
答案は、設問と傍線部「以外」を読んでいない人に対してわかりやすく説明するつもりでまとめる。
(設問と傍線部は「共有している」という前提で答案作成する)

傍線部があれば、その傍線部「以外」から「解答根拠」を拾ってくることがまずは大切です。
答案の仕上げについては、本文に存在しない表現を用いることもありますが、「本文のここを根拠とした」と言えるものになっている必要があります。
最も重要なのは「主語(目的語)述語」
一文で構成する答案は、「主語(目的語)述語」の関係を最重要視します。

「目的語」は学校では一意に定義されていないのですが、
(1)行為の客体を示している
(2)主に「~を・~に」がついている
ものだと考えてください。
「~に」で示される客体は「補語」と呼ばれることも多いのですが、ここでは「目的語」にまとめてしまいます。
「目的語」があれば「主語・述語」と同じく重要視する

文構成については、「主語」と同等に「目的語」にも注目しましょう。
どうしてかというと、「ある述語」にたいして、「主語」と「目的語」はどちらも「必須」のものになるからです。「述語」に対して「必須の前提」になるということは、論理的な答案を作成するにあたり除外することができません。
「ある述語」からみて、「主語」と「目的語」は同等に重要なものである。

「目的語」は「連用修飾語」の一種なので、一文を「主部 ― 述部」という「2つの要素」にざっくりと分ける場合、次のように「述部」を構成する一要素になります。
献身的なキャシーが ― ポートマンを 支える。
口の軽いジョセフが ― ヨハンソンに ネタバレした。
【 主 部 】 【 述 部 】
しかしながら、次のように書けば、「目的語」のほうを「主語」にして同内容の文にすることも可能です。
ポートマンは ― 献身的なキャシーに 支えられる。
ヨハンソンは ― 口の軽いジョセフに ネタバレされた。
【 主部 】 【 述 部 】

つまり、「目的語」というのは、大きく分けると「述部」を構成するものなのに、書きようによっては、「主語」のほうにすることできる情報なんだな。

そうです。
そのため「主―述」の関係において欠かせない要素なんですね。
主語・目的語は、「ある述語」にとって「必須の前提」になるので、傍線部の外側にあっても、答案に取り込むことが基本である。
「どういうことか」
「どういうことか」という設問に対する基本姿勢は、傍線部そのものの「わかりにくい部分」を「本文を読んでいない人(設問と傍線部以外を共有していない人)」に伝わりやすく言いなおすことです。

「わかりにくい部分」というのは、多くの場合、
「指示語」
「比喩的な表現」
「多義的(意味広範)な表現」
になります。
(ⅰ)「指示語」は「指示内容」を過不足なく書く。
「指示語そのもの」は答案から除外する。
(ⅱ)「比喩的表現」は「実態」をつきとめてそちらを書く。
この場合「比喩そのもの」は答案から除外する。
(ⅲ)「多義的(意味広範)な表現」は、その文脈における意味に規定する。
もとが客観的な表現であれば除外する必要はない。補足によって説明を果たす。
「なぜか」
「なぜか」は、傍線部内の「結論(主に述語)」の「前提」を説明します。
したがって、多くの場合「述語」に対応する「主語」は「重要要素」になり、その一方、「傍線部における述語そのもの」は答案に必要とされません。
なお、答案化する際に、必要な構成要素に「指示語」や「比喩的表現」といった意味不明瞭な表現がある場合、「どういうことか」の方法論にならい、表現を修正する必要があります。

このあと「3種類」の「なぜか」の話をするのですが、込み入った文になってくると、次の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)が複合的に問われていることもあります。
強調しておくこととしては、(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)のどれであっても「主語」は答案に書くことが基本であり、「述語」は書かないケースが多いということです。その理由は後述します。
3つの「なぜか」
細かい話に入ります。「なぜか」は「理由」が問われている問題ですが、ひとくちに「理由」と言っても、大きくみて次の3つがあります。
(ⅰ)原因・きっかけ( cause 型 )
「ある結果」に対しての「実態としての前提」を答える。
(ⅱ)目的・意図・効果・影響( effect 型 )
「ある結果」によって成立が期待される「次の状況」を答える。
(ⅲ)論拠・判断材料( warrant 型 )
「筆者(表現主体)」がそのように「判断」した「論拠」を答える。

単純に「なぜか」と問われている場合は(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)のどれになるのか考える必要がありますが、「いえるのはなぜか」と問われている場合は(ⅲ)で確定して大丈夫です。
(ⅰ)原因・きっかけ
(ⅰ)は、「ある結果(現象)」に対して、実態として「前」にある出来事を答えます。

この場合の「ある結果」は、何らかの意図や目的をもった行為ではなく、「成り行きで結果的にそうなる」ものです。
たとえば、「氷が解けると水になる」とか、「森を切り開くと砂漠化が進む」といったものです。
答案は「傍線部」から見て「現象的に先行する条件」を答えることになります。
したがって、傍線部の主語と答案の主語が異なることもありえます。
一方、「主語」がないと「何の話」をしているのかわからなくなってしまうので、「主語」は書きこんでおくことが基本です。特に「主語(主部)」が傍線部自体に明記されていない場合は、必ず書き込みます。

ただし、「このときよしおが叫んだのはなぜか」というように、設問において主語が規定されている場合には、答案において主語を省略しても大丈夫です。
「設問」は、「出題者」と「解答者」が「お互いわかっているもの」だからです。
(ⅱ)目的・意図・効果・影響
(ⅱ)は「傍線部の論理」が成立するとして、「次」に起こる(起こりうる)ことを答えます。
言いかえると、傍線部の「アクション/イベント」が成立することで、どんな「エフェクト」が想定されているのか、ということを答えることになります。

「次に起こる(起こりうる)こと」は、「成り行きで結果的に起こること」ではなく、傍線部の行動の「前」に「主体者が予測・期待していたこと」になりますから、小説問題では「目的・意図」と考えたほうがわかりやすいですね。
この場合、「次に起こること」が解答の「核心」であり、「傍線部そのもの」が条件的な「前提」になります。
つまり、「意図型」の「なぜか」は、実態の流れとしては、「傍線部そのものの成立」を前提(先行条件)として、そのうえで「次に起こる(起こりうる)ことを書く」ことになります。
したがって、答案の字数に余裕がある場合には、「傍線部そのもの」+「次に起こる(起こりうる)こと」のすべてを書き込んでよいことになります。

たとえば、今日中に家に帰りたいよしおが、終電間際に駅に向かって走っていたとして、「よしおが走っているのはなぜか」と問われた場合、
「よしおは、走ることで終電に間に合うと思ったから」とか、
「よしおは、走らなければ終電に間に合わないから」などと書くことができます。
もちろん、「解答の核心」は「理由にあたる部分」なので、「傍線部そのもの」は、状況次第で圧縮したりカットしたりすることになります。
「傍線部」はすでに「出題者」と「解答者」のあいだで共有されているので、「応答的」にはいちいち繰り返さなくてもよいものですが、「論理的」にはあったほうがよいものです。
さらにその「傍線部」は、多くの場合、「主語」が省略されていたり、「比喩的な表現」であったり、「指示語」が含まれていたり、そもそもわかりにくいものになっています。
したがって、「意図型」の「なぜか」は、
傍線部そのものの説明 + 傍線部が成立すれば起こること から。
① ②
* ②は必須/①はあるほうがよい
というイメージで答案を構築します。
(ⅲ)論拠(判断材料)
傍線部の論理を簡素化した際、次のような構造になっている場合、「論拠w」を問うているケースが多いといえます。たとえば次のようなものです。
彼は ≒ 大納言だ。(述語が主語に対する何らかの名称・たとえになっている)
彼は ー 誠実に働く。 (述語が主語の状態や性質になっている)

こういう場合の「述語」は、「主語」の「中身そのもの」を説明しています。
仮に「述語」の「表現」が「行為」であっても(たとえば「行く」「隠れる」「疑う」など)であっても)、実質上は「主語」の「状態・性質」を意味している場合も少なくありません。
問いの形式がシンプルな「なぜか」である場合は、(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)すべての可能性がありますが、「いえるのはなぜか」と問われている場合は、(ⅲ)の「論拠」型だと判断してOKです。
「論拠」型の例を見てみましょう。
〈傍線部の例〉
言語は ー 記号である。
↑ ↑
主 語 述 語(主語に対する何らかの名称)
〈答案の例〉
言語は、 ー 物体や現象の代替として機能するから。 (記号であるといえる)
↑ ↑ ↑
主 語 論 拠 答案には不要
ここでの「論拠」は、「主語」の意味内容を説明しているとも言えますし、「述語」の意味内容を説明しているとも言えます。
「物体や現象の代替として機能する」という「内容」が、「言語」についても「記号」についても当てはまるからこそ、この「論拠」を介して、「言語はー記号である」と言えるわけです。

ということは、この構造は、丁寧に書けば「三段論法」であるといえます。
言語は、物体や現象の代替として機能する。
物体や現象の代替として機能するものは、記号である。
よって、言語は ー 記号である。
もう一例見てみましょう。
〈傍線部の例〉
戸締りは ー 完璧だ。
↑ ↑
主 語 述 語(主語の状態や性質)
〈答案の例〉
戸締りは、 ー すべての窓とドアを施錠したから。 (完璧であるといえる)
↑ ↑ ↑
主 語 論 拠 答案には不要
この例でも、「論拠」は、「主語」の意味内容を説明しているとも言えますし、「述語」の意味内容を説明しているとも言えます。

そういったことから、この「論拠」型の問題は、多くの場合「主語」の意味内容を「述語」に沿うかたちで説明する問題になります。
ちょっとしたコツがありまして、このタイプの問題は、
主語は、 論拠 という点で、述語である。
という構文に放り込むと考えやすくなります。
このタイプの発展型として、
「AはBではない」といえるのはなぜか
「AはBとは違う」といえるのはなぜか
と問われることがあります。
この場合、「A」が「B」と「逆」であることを説明すればよいことになります。つまり「相違点」を説明するということです。

たとえば、
「入試において、国語は重要ではない」といえるのはなぜか。
という問題があり、本文において、
国語は ー 合否に影響しない
≠
合否に影響するものが ー 重要である
という関係が読解できる場合、答案は、
「国語は合否に影響しないから。」というものになります。
「論拠」型の問題は、「2つのもの」の「類似性」を説明することが基本姿勢なのですが、逆に「相違性」を説明させる場合もあるということですね。
【発展】 「論拠」型の「どういうことか」
「どういうことか」と問われているときであっても、「S ≒ P(Sの別名・たとえ)」あるいは「SーP(Sの状態・性質)」という傍線部の構造である場合は、「論拠・判断材料」の補充が求められている可能性があります。

(1)傍線部の主語が、いわゆる「主題主語」である。
(2)傍線そのものが短く、「補充」が必要である。
という場合、「論拠w」が必要になることがけっこうあります。
考え方は「いえるのはなぜか」に近いのですが、「どういうことか」と問われている以上、
主語の説明 ー (+ 論拠 )ー 述語の説明 ということ。
というように、「主語ー述語」をしっかりと説明したあとで、あくまでも「補充」の観点で「論拠」を追記することになります。

国立大学の二次試験などは、すべての問題が「どういうことか」になることもありますが、よく見るとそのうちの一つ二つが、「論拠」型の問題になっている場合があります。
つまり、「いえるのはなぜか」に近い「どういうことか」の問題が、それなりの頻度で出現するということです。