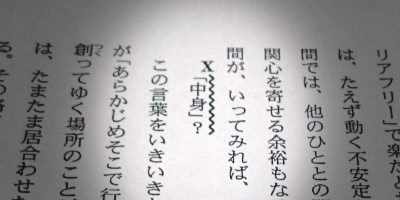(一)
傍線部「自体」が意味している内容を正確につかむことが求められる難問である。
これは「定着」あるいは「完成」という状態を前にした人間の心理に言及する問題である。
傍線部は「人間の心理」という「体言」に引かれているわけであるが、「どういうことか」と問われているので、答案の構文は、
人間は ~ 心情になるということ。
といったように、「用言化」して解答したほうがよい。
さて、傍線部が存在する文は、
これは、 〈 傍 線 部 〉 に言及する問題である。
↑ ↑
主語S 述語P
という構造になっている。
傍線部が文全体ではなく「部分」に引かれていることに注意しよう。
「主語S/述語P」は、たしかに「直前の推敲の話」を意味しているけれども、「傍線部そのもの」が傍線部の内部を指しているわけではない。
たとえば、次のような例を考えてみよう。
ボブソンは、「グローブはいつも時間をかけて磨いている」と述べた。
これは、一流のスポーツ選手に共通する心理に 言及する問題である。
主語S 述語P
主語である「これは」は、たしかに直前の「ボブソンの発言」を指している。
ところが、傍線部自体については、ボブソンの話を限定的に意味しているわけではないことになる。傍線部は、ボブソンの話そのものではなく、一流のスポーツ選手全般の話をしているのである。
設問(一)を解くにあたってまず重要なのはこの理解である。「これ」という指示語に着眼するあまり、直前部のみで解答を作成してはならないということだ。
傍線部を再確認すると、「人間の心理」とある。しかし、「これ」の指す内容は、「詩人の話」に矮小化されている。
つまりこの「詩人の話」は、「完成・定着という状態を前にした人間の心理」の「例示」として挙げられている話なのである。ここは「詩人」の話が語られているが、筆者の主張を伝えることさえできれば、たとえば「絵画」「書道」「俳諧」「歌合せ」「ダンス」などの話でもよかった箇所なのである。
「例示」がある場合、その「前」あるいは「後」、場合によっては両方に、その例示を挙げてまで言いたかい主張があるはずである。そちらが解答の〈核心〉になる。
したがって、さらにさかのぼって、〈①段落〉から〈核心〉を探してみよう。
白は、完成度というものに対する人間の意識に影響を与え続けた。紙と印刷の文化に関係する美意識は、文字や活字の問題だけではなく、言葉をいかなる完成度で定着させるかという、情報の仕上げと始末への意識を生み出している。白い紙に黒いインクで文字を印刷するという行為は、不可逆な定着をおのずと成立させてしまうので、未成熟なもの、吟味の足らないものはその上に発露されてはならないという、暗黙の了解をいざなう。
ここでの「意識」や「了解」という語は、「心」の状態であるのだから、傍線部の「心理」と対応している。ここをまとめるとよい。
以上のことから、ひとまず次のような〈下書き ver.01〉が成り立つ。
〈下書き ver.01〉
人間は、言葉をいかなる完成度で定着させるかという、情報の仕上げと始末に際し、その不可逆性ゆえ、未成熟で吟味の足りないものを発露してはならないと暗黙に了解するということ。
ここには「言葉」と書かれているが、先ほど見たように、傍線部は、
「定着」あるいは「完成」という状態を前にした人間の心理
という部分のみに引かれているので、傍線部直前の例示である「詩作」に限定されるような「言葉」の話題にとどめないほうがよい。
課題文を最後まで読んでいくと、「書や絵画、詩歌、音楽演奏、舞踊、武道」などと、言語にはとどまらない「表現活動」が示される。さらに、「音楽や舞踊における『本番』という時間は、真っ白な紙と同様」と述べられる。さらには「武芸(弓)」の話まで出てくるのであり、筆者はそれらの話題も、「表現を完成させる際の人間心理」の例として扱っている。
つまり、課題文全体を読んだうえで述べれば、「定着・完成を前にした人間の心理」の話題は、「言葉」の話題に限定されるものではないのである。
以上のことから、「完成あるいは定着を前にした人間の心理」という表現における「完成あるいは定着」とは、言語活動にとどまらず、「あらゆる表現活動における表現行為」を全般的に意味していると読解するほうが適当である。その一つの例として、筆者は「推敲」の例を挙げたのだ。
したがって、この設問に答えるにあたっては、前後の話題に取り込まれてしまうことを避けたほうがよい。そのため、「白い紙」「書く」という語句は出さずに、「表現活動」「表現行為」などとしておくほうがよい。
以上により、次のような〈下書き ver.02〉が成り立つ。
〈下書き ver.02〉
人間は、表現行為の不可逆性ゆえ、定着の際に完成度を意識し、未成熟で吟味の足りないものを発露してはならないと暗黙に了解するということ。
さて、先に「詩人」の話は安直に使用しない、と述べたが、「これ」という指示語があることからも、もちろんまったく関わっていないわけではない。〈核心〉とは言えないまでも、無視をするのは極端であるから、何らかの言及はしておくほうがよい。ただしそうであっても、「詩人」の話として限定されてしまうものではなく、人間の表現行為全般にあてはまる論点を抽出するべきである。
たとえば、この「詩人」の例を、「画家」「写真家」「俳人」「舞踏家」などにしたとしても、「逡巡する」「微差に執着する」といった「客観表現」は、そのまま通用する。したがって、「逡巡」あるいは「微差に執着する」といった意味内容は答案に使用可能である。
以上により、次のような〈答案〉が成立する。
〈答案〉
人間は、不可逆な表現の定着の際、微差に執着し、逡巡するほど完成度を求め、未成熟で吟味不足のものを発露せぬよう暗黙に了解するということ。
〈さらに簡潔な答案〉
不可逆な表現行為の仕上げや始末に及ぶ人間は、未成熟で吟味不足の完成度にならぬよう、細心の注意を払うということ。
〈論点チェック〉
人は (ないと減点)
不可逆 ① 「訂正不能」なども可
仕上げや始末 ① 「完了」「成立」なども可
微差に執着・逡巡 ① 「細心の注意を払う」なども可
完成度を意識 ①
未成熟で吟味不足にならない ②
*「述語」が「心理」的な表現になっていることが大切
(二)
このような、達成を意識した完成度や洗練を求める気持ちの背景に、白という感受性が潜んでいる。
傍線部の論理関係がわかりづらいので、前半と後半を入れ替えてみよう。
Aの背景に、Bが潜んでいる。
という表現は、
Bの影響によって、Aが起きている
Bがあることによって、Aが生まれる
Bを理由にして、Aが成り立つ
Bが根拠となって、Aが成立する
などと言い換えることが可能である。
たとえば、〈傍線部イ〉は、次のようにできる。
白という感受性があることによって、達成を意識した完成度や洗練を求める気持ちが生まれるということ。
(これは、「こうしてもいい」ということであるので、もちろん傍線部の構造を変えなくても問題ない。同じ意味内容で、文法の屈折なく書くことができていれば同じ得点になる。)
その「白という感受性」については、〈③段落〉で「白い紙の上には訂正不能な出来事が固定されるというイマジネーション」という説明があるので、そこを使用する。
〈下書き ver.01〉
白い紙の上には訂正不能な出来事が固定されるというイマジネーションによって、達成を意識した完成度や洗練を求める気持ちが生まれるということ。
「達成・完成度・洗練」といった語については、十分意味が伝わる表現なので、そのまま答案に出してもいいくらいだが、冗長でもあるので、解答欄に自然に入れるためにも、
表現をよりよい出来に練り上げる
くらいのレベルで簡潔にまとめてしまってかまわない。
傍線部の直前にある「美意識」を取り入れておくと、次のような〈下書き ver.02〉が成立する。
〈下書き ver.02〉
白い紙の上には訂正不能な出来事が固定されるというイマジネーションによって、表現をよりよい出来に練り上げようとする美意識が生まれるということ。
最後に、段落の最後にこの傍線が引かれており、
このようなAは、Bである。
という構文になっていることに着眼したい。
「このようなAは、Bである」という構文は、それまでの内容をAでまとめ、新しい話題をBで示すときに使用されやすいかたちだ。
そのため、次の文からは、Bについての説明が始まっていくことが多い。その構文理解でいえば、「白という感受性」は、「新しい話題」と言えないこともない。実際にその直後から、「白い半紙に文字を書く時の気持ち」について語られていくのだから、この「半紙に向かう子ども」の話は、「白という感受性」の話の内容にふみこんだ説明とみなすことができる。
もちろん、段落が変更されているので、〈傍線部ウ〉の論点は、同段落内である〈④段落〉と、論理的接続関係にある〈③段落〉に重さがあると考えるほうが自然だが、「このようなAは、Bである」という「発展を導きやすい構文」と〈⑤段落〉の内容に着眼すると、後ろをまったく無視するのも危険である。
さて、そのような考察を経て〈⑤段落〉を眺めてみると、内容的には〈④段落〉と同様に、「紙の上に不可逆の表現をしてしまう」ゆえに「推敲する」人間の話が述べられていく。ではどこが「発展」しているのか? ――追加されている「文意」をチェックすると、「つたない」とう「気持ち」にかかわる語句が繰り返されていることがわかる。これらは、位置的にみて、次の〈設問三〉の中心的論点になるであろうから、多くは〈設問三〉のほうで使用するにしても、このニュアンスは、補助的に〈設問二〉に取り込んでおきたい。
たとえば、「訂正不能な出来事が固定される」という説明を、「訂正不能なつたない人為が固定される」などと代入してみよう。「人間が行う表現行為」が、「そもそも未熟である」という思いがあるからこそ、人はたった一回の表現を、練り上げようとするのである。このように、「人間の行為がそもそもつたない」という「気持ち」を取り込めば、「感受性」へのふみこみが、いっそう充実することになる。
以上のことから、「傍線部後ろの〈発展的内容〉に関しても、補充としての言及はする」という意識を反映し、コンパクトに入れておくと、次のような〈解答例〉が成立する。
〈答案〉
白紙の上には訂正不能な拙い出来事が固定されるというイマジネーションによって、表現をよりよい出来に練り上げようとする美意識が生まれるということ。
前後の文脈から、「白紙」という「紙の話題」として書いて問題ないと考えられるが、厳密には「白という感受性」と述べられているのであり、この言い方は「紙」に限定された話ではなく、「白」という「概念」についての意識を主題にしている箇所だといえる。
そのため、本来であれば「紙」という語を使用せずに述べたほうが「白という感受性」の説明としては適切である。ここを「概念」の話として処理するならば、「白いものを汚してしまうと取り返しがつかない」といった説明が可能である。
〈さらに簡潔な答案〉
白いものへの表現は訂正不能であるという想像力によって、少しでもよい表現に練り上げて完成させようとする美意識が生まれるということ。
〈論点チェック〉
白いものへの表現 ① 「白紙に表現をする」なども可
訂正不能(不可逆) ① 「取り返しがつかない」なども可
想像力 ① 「イマジネーション」なども可
よりよい表現に練り上げて完成させる ② 「より美的な表現に向上させよう」なども可
美意識が生まれる (ないと減点) 同趣旨ならOK
(三)
この、推敲という意識をいざなう推進力のようなものが、紙を中心としたひとつの文化を作り上げてきたのではないかと思うのである。
「この」という指示語があることからも、「推敲という意識をいざなう推進力」は、直前の内容をまとめればよい。
傍線部直前の、「白い紙に消し去れない過失を累積していく様を把握し続けることが、おのずと推敲という美意識を加速させるのである。」という箇所と、その二文前の、「取り返しのつかないつたない結末を紙の上に顕し続ける呵責の念が、上達のエネルギーとなる。」という箇所は、内容上、同じことを述べている。まずはこのことをおさえておこう。
さて、傍線部内の「推進力」と、直前にある「加速」とは、意味上の対応が認められる。推進力があるから加速するのである。ということは、傍線部内の「推進力」の説明としては、「白い紙に消し去れない過失を累積していく様を把握し続けること」を使用することになる。
「推敲」は、傍線部内の語ではあるが、本文別箇所を参照しなくても意味がわかる語であるので、そのまま使用して問題ない。言い換えるのであれば、傍線部直後にある「推すか敲くかを逡巡する心理」を使用し、「表現の向上を志して逡巡する心理」などとすることができる。
以上により、次のような〈下書き ver.01〉が成立する。
〈下書き ver.01〉
白い紙への消せない過失の累積を把握し続ける呵責の念が、表現の向上を志す逡巡の美意識を推し進め、【 】文化を作り上げたということ。
最大の問題は「【 】文化」である。
この本文において、「文化」の「説明」をきっぱりしている箇所が他のどこにもないのである。
もしも、ここで私たちが、実際の社会生活をイメージしすぎて、「そうだよな、履歴書とか、合格証書とか、運転免許書とか、とにかく〈紙に記されたもの〉が、社会の中で中心的な役割を担っているよな……」と考えてしまうならば、それは「深読み」になってしまう。
なんとか答案化できる根拠を探していこう。傍線部直後の、「もしも、無限の過失をなんの代償もなく受け入れ続けてくれるメディアがあったとしたならば、推すか敲くかを逡巡する心理は生まれてこない」という箇所に強い意識を向ければ、これは、「紙がなかったら、逡巡する心理は生まれなかった」と言っていることになる。ということは、「逡巡する心理を伴う文化的営為」は、「紙から生まれた」と述べていることになる。
ということは、「紙を中心としたひとつの文化」とは、このように、「紙に対する逡巡の感情を元にして、派生的に成立していった文化」と述べることができる。ところがこの付近では、そういった文化の説明は、具体的にはまったく語られない。語られないどころか、直後からは「紙」とは対比される「インターネット」の話が始まってしまうのである。
しかし、さらに読み進めると、〈⑥⑦段落〉で「インターネットの話」をした後で、再び「紙の話」に戻ってくるのである。
~ 白い紙の上に決然と明確な表現を屹立させること。不可逆性を伴うがゆえに、達成には感動が生まれる。またそこには切り口の鮮やかさが発現する。その営みは、書や絵画、詩歌、音楽演奏、舞踊、武道のようなものに顕著に現れている。 ~ 聴衆や観衆を前にした時空は、まさに「タブラ・ラサ」、白く澄みわたった紙である。
「紙と対比するもの」として「インターネット」の話を出し、さらにそれを、「一方」という明確な対比のラベルでひっくり返し、「紙」の話に戻ってくるのであるから、この〈⑧段落〉は、内容上〈⑤段落〉との関連性を強く持っていると言える。文章全体を大きな目で見れば、〈⑥⑦段落〉の「インターネットの話」は、中心的論点である「紙の話」をより深めるための、「対比の補足」であるという見方もできる。「歴代の巨人軍の選手ではクロマティが一番かっこいいと」いうことを主張するために、他のメンバーの話をあえてすることを考えてみるとよい。その際の「他のメンバーの話」は、「主張そのもの」ではなく、いわば「引き立て役」である。
本文での「インターネット」の話も、その役割に近い。そのことから、〈⑥⑦段落〉の「インターネットの話」をいったん( )に入れて、〈⑤段落〉と〈⑥段落〉を接続してみると、内容上は、非常に近い話をしていることがわかる。そしてそこには、
その営みは、書や絵画、詩歌、音楽演奏、舞踊、武道のようなものに顕著に現れている。
と書かれている。つまり、「紙に表現をする」というときの逡巡する心理が、「紙媒体」という物理的制約を超えて、「紙を用いない表現活動」にまで影響を与えてきたのである。「紙を用いた表現活動」が中心となり、その周縁にある「紙を用いない表現活動としての文化」に強い影響を与えていったのであるから、これを比喩的に「紙を中心とした文化」と述べていると読解することができる。
以上のことから、傍線部後半については、
紙に表現する際の意識が影響を与え、紙媒体を超え、あらゆる表現活動としての文化が発展したということ。
などと解答することがひとまずできる。
〈下書き ver.02〉
白い紙への消せない過失の累積を把握し続ける呵責の念が、表現の向上を志す逡巡の美意識を推し進め、その影響から、紙媒体を超えた表現活動としての文化を発展させたということ。
以上より、次の〈答案〉が成立する。
〈答案〉
白い紙への消せない過失の累積を把握し続ける呵責の念が、表現の向上を志す逡巡の美意識を推し進め、その影響が紙媒体を超えた表現文化に至る文化を発展させたということ。
〈さらに簡潔な答案〉
白紙に過失の痕跡を残す後ろめたさが、逡巡を経て表現を屹立させる美意識を推し進め、ひいては紙媒体を超えた表現文化の発展に寄与したということ。
〈論点チェック〉
白い紙 (ないと減点)
消せない過失の累積を把握し続ける ① 「過失の痕跡を残し続ける」なども可
呵責の念 ① 「後ろめたさ」なども可
表現の向上を志す逡巡の美意識
推敲の美意識 (ないと減点)
紙媒体を超えた表現文化 ① 「諸芸術や武道に至る表現文化」なども可
(四)
断定しない言説に真偽がつけられないように、その情報はあらゆる評価を回避しながら、文体を持たないニュートラルな言葉で知の平均値を示し続けるのである。
「主語S」は「インターネットは」「インターネットの情報は」「インターネットの言葉は」といったものになる。文中に「ネット」と書かれているので、「ネットは」と書いてしまってもよい。
そのうえで、
(a)文体を持たないニュートラルな言葉で
(b)知の平均値を示し続ける
という論点の意味内容をつかんでいこう。
「a:文体を持たないニュートラルな言葉」については、意味上、「書き手独自の特徴がない、どこにも属さない言葉」ということである。文中の、
世界の人々が同時に考える
あらゆる人々が加筆訂正
無数の人々の眼にさらされ続ける情報
といった論点をまとめよう。そうすると、
世界のあらゆる人が加筆訂正できる、偏りのない表現形態で、
などのように書くことができる。
「b:知の平均値を示し続ける」については、文中の、
皆が共有できる総合知
情報はある意味で無限に更新を繰り返している
無限に更新され続ける巨大な情報のうねり
変化する現実に限りなく接近し、寄り添い続ける
情報は常に途上であり終わりがない
といった論点をまとめよう。そうすると、
変化する現実に応じて、皆が共有できる総合知を、無限に更新し続ける。
などのように書くことができる。
「知の平均値」は、「あらゆる人々の知性が総合され、もっとも平均的な情報を表出したもの」であるといえる。
たとえば、インターネット上の百科事典において、「読売ジャイアンツ」の項目を「一人」が書けば、「日本プロ野球機構の最も強い球団であり、別名巨人軍である。なお、ジャイアンツに在籍したことのある選手の中で、最も魅力的な選手はクロマティである」などと、個人的な「思い」が存分に発揮されてしまう可能性がある。
しかし、このインターネット上の百科事典は、それこそ世界の無数の人々の目にさらされているので、「いや、最も魅力的な選手は松井だ」とか、「そもそも最も強い球団は埼玉西武ライオンズだ」といった「別の意見」が出てくるのである。
そういった「個人のつぶやき」がものすごい数で押し寄せてくると、「ジャイアンツに在籍したことのある選手の中で、最も魅力的な選手は長島・王・吉村・桑田・ガリクソン・上原・松井……」といったように、「個人」の意見は埋もれていくことになる。結果的に、最も得票数の多かった選手が、「現時点の調査で最も魅力的な選手」ということになるだろう。それが「集団の意見」として採用されることになる。
以上をまとめると、次のような〈下書き ver.01〉が成立する。
〈下書き ver.01〉
無数の人々の眼にふれ、変化する現実に応じたインターネットの情報は、あらゆる人が加筆訂正できる、どこにも属さない言葉で、皆が共有できる総合知を、現実に応じて無限に更新し続けるということ。
圧縮すると、次のような〈答案〉が成立する。
〈答案〉
インターネットの情報は、世界のあらゆる人が加筆訂正できるという、偏りのない表現形態で、皆が共有できる総合知を、変化する現実に応じて無限に更新し続けるということ。
〈さらに簡潔な答案〉
インターネットは、万人が加筆訂正できる偏りのない表現形態で、皆が共有できる総合知を、変化する現実に応じて無限に更新し続けるということ。
〈論点チェック〉
インターネットの情報は (ないと減点) 「ネットは」などでも可
あらゆる人が加筆訂正できる ①
偏りのない表現形態で ①
変化する現実に応じる ①
皆が共有できる総合知を ①
無限に更新し続けている ①
(五)
この、矢を一本だけ持って的に向かう集中に中に白がある。
傍線部問題でありながら、「論旨をふまえながら」という付帯条件があるので、
(ⅰ)本文全体の論旨に言及する。
(ⅱ)傍線部に応答する。
ということをしなければならない。
傍線部への応答的解答の中に「論旨」を織り交ぜて書いていってもよいし、「論旨」を前提として書いたうえで、傍線部に応答するという表現をしてもよい。
後者であれば、〈ⅰ:前提〉と〈ⅱ:応答〉を2つの文に分けてもかまわない。
さて、本文で述べてきたことは主に4点である。
(1)白は、「完成」「定着」の際の、逡巡する(推敲する)感受性である。
(2)「推敲(逡巡)の感情」が前提となり、表現を向上させようとする意志が生まれる。
(3)紙がなければ、「推敲(逡巡)の感情」は生まれなかった。
( ⇔ インターネットは無限に未完のメディア)
(4)紙に対する「推敲(逡巡)の感情」を基盤として、諸々の表現行為が発展した。
(1)(2)(3)(4)に言及しつつ、傍線部に答えればよい。あるいは(1)(2)(3)(4)をコンパクトにまとめてから、傍線部に応答すればよい。しかし、この字数の中に「論旨」を詰め込むのであるから、ある程度は自身の語彙力で「圧縮」する必要がある。
〈解答例〉
白は、個人の表現の痕跡を残す際の逡巡と覚悟の感受性であり、紙媒体を超え、空間への表現行為にまで影響を与える。その美意識は、二の矢への依存心を退けて射るような、行為の不可逆性を自覚したうえで洗練を極めようとする決意の中に見出されるということ。
〈別解〉
不可逆性を自覚し、より高水準の達成を目指すものとして、二の矢への依存心を退けて的に向かう行為があるが、その専心の中に、紙媒体を超えて空間への表現にまで影響する、個人の表現行為の痕跡を残す瞬間の逡巡と覚悟の感受性、すなわち白があるということ。

以上です!