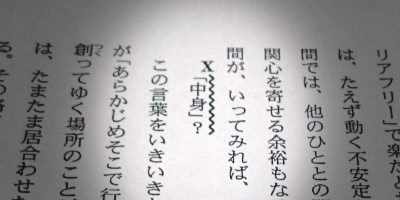(一)「歴史学の存在そのものが、この巨大な領域に支えられ、養われている」とあるが、それはどういうことか、説明せよ。
解答例
歴史学の存在は、記録の有無、事実、可能性、反事実にわたって、画定できず、あいまいなまま増え続ける膨大な事柄によって基礎づけられているということ。
ポイント
歴史学の存在
(a)記録の有無、事実、可能性、反事実
(b)画定できない
(c)あいまい・不確か・つかみどころのない
(d)増え続ける膨大な出来事
によって基礎づけられている
(二)「歴史そのものが、他の無数の言葉とイメージの間にあって、相対的に勝ちをおさめてきた言葉でありイメージなのだ」とあるが、どういうことか、説明せよ。
解答例
歴史とは、国や社会の代表的価値観により重視され、集団の自己像を構成してきたものであり、他の無数の言語と表象を退けて、優先的に選び取られたものであるということ。
ポイント
歴史自体が(歴史とは)
(a)国や社会の代表的価値観に重視され
(b)集団の自己像を構成
(c)他の無数の言語と表象を退けて
(d)優先的に選び出されたもの
(三)「記憶の方は、人間の歴史をはるかに上回るひろがりと深さをもっている」とあるが、それはなぜか。説明せよ。
解答例
記憶は、物質や生命現象にまで存在する一方、歴史は、人間が主体的、主観的に操作できる範囲に局限され、言葉やイメージに等質化された集積にすぎないから。
ポイント
記憶は
(a)物質や生命現象にまで存在する
歴史は
(b)人間が主体的、主観的に操作できる
(c)範囲に局限され
(d)言葉やイメージに等質化された集積
(四)「歴史という概念そのものに、何か強迫的な性質が含まれている」とあるが、どういうことか、説明せよ。
解答例
歴史という考え自体に、個人から集団に至る記憶の集積として、人の社会制度や習俗のすべて、またそこに生きる個人の生の様態を強制する力が内在しているということ。
ポイント
歴史は
(a)個人から集団にいたる記憶の集積
(b)社会制度や習俗の一切を成り立たせる
(c)そこに生きる個人の心身や生の在り方まで
(d)決定づける力を備えている
(五)「それらとともにあることの、喜びであり、苦しみであり、重さなのである」とあるが、どういうことか、説明せよ。
解答例
歴史とは膨大な記憶を周縁に置いて措定されたものであり、自身を含む無数の他者の共存的な自由を本質とするが、一方、集団の環境を構成することで個人の生を決定する力を持つため、個人の意志が、潜在的に関係する他者の生に関与する責任をも負うということ。
ポイント
歴史とは
(a)膨大な記憶を周縁に置いて措定されたもの
(b)自身を含む無数の他者の共存的な自由を本質とする
(c)集団の環境を構成することで個人の生を決定する力を持つ
(d)個人の意志が、潜在的に関係する他者の生に関与する責任をも負う