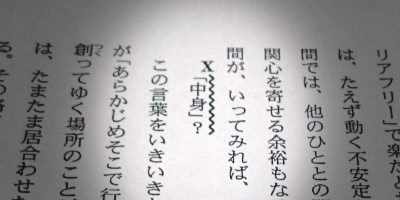小論文の構成を考える際には、「four square writing method」が有効です。
アメリカの小中学生が学ぶ形式なのですが、とても汎用性が高い思考法なので、小論文を書くときの「メモ書き」にぜひ取り入れてみましょう。
下図のように4分割した四角形のなかに、構成を書き込んでいくやり方です。
┌─────┬─────┐
│ 根拠a │ 根拠b │
├─────┼─────┤
│ 根拠c │ 結 論 │
└─────┴─────┘

じゃあ、この「4スクウェア」には「問題提起」は含まれないの?

「問題提起」は別枠で前に書きます。
小論文でいうと、それが「序論」になりますね。
「根拠a・b・c」のところが「本論」にあたります。

よく「小論文は具体例が大事」って言われるけど、この場合はどこに書くの?

「根拠」というのは、大雑把に分けると、
(ⅰ)(理由となる)説明
(ⅱ)例示やデータ
になります。
通常は、同一パラグラフ内で(ⅰ)(ⅱ)をセットにして、次のように書きます。
┌─────┬─────┐
│ 説明a │ 説明b │
│ 例示a │ 例示b │
├─────┼─────┤
│ 説明c │ 結 論 │
│ 例示c │ │
└─────┴─────┘
あんまり難しく考えずに、「同一パラグラフ内の【前半】よりも【後半】のほうがいっそう具体的になるのが普通」くらいに考えておくといいですね。

ふむふむ。

なお、字数が短くて、例示を「1つ」しか書けないようなケースであれば、次のように、「例示のパラグラフ」を独立させてもOKです。
┌─────┬─────┐
│ 説明a │ 説明b │
│ │ │
├─────┼─────┤
│ 例 示 │ 結 論 │
│ │ │
└─────┴─────┘
これはそもそも字数が短いときの対応なので、「説明a」と「説明b」もセットにしてしまって同一パラグラフ内に押し込んでも大丈夫ですよ。
〈パラグラフ①〉序論
〈パラグラフ②〉説明a・説明b・例示
〈パラグラフ③〉結論
とか、
〈パラグラフ①〉序論
〈パラグラフ②〉説明a・説明b
〈パラグラフ④〉例示
〈パラグラフ④〉結論
となって大丈夫です。

ああ~。
「小論文」のテキストの解答例を見ていると、結論のひとつ前のパラグラフを「まるまる例示」にしているものが多いね。

小論文全体のなかで例示を1つだけ出すのであれば、「説明」のパラグラフと「例示」のパラグラフをそれぞれ独立させても問題ありません。

それぞれを「1つのパラグラフ」にして「
根拠a・b・c と書きましたが、
〈 メリット / デメリット / メリット優位の理由 〉
〈 相手の主張 / 自分の主張 / 具体例 〉
〈 原因分析 / 対策 / 効果 〉
〈 プランの特徴 / 他プランとの比較 / 適用後の展望 〉
といったように、
普通は「3つの論点」があれば「パラグラフを3つ」にするわけですが、すべてコンパクト版にして、1つのパラグラフに畳み込むことも可能だからです。

「問題提起」は別枠で前に出す感じです。
なお、「問題提起」をしたら、つづけて「結論」も示しておくのが普通です。
さらに「理由」まで示しておくといいとも言われますが、実際にはその「理由」についてしっかり説明するところが「本論」になるので、「序論における理由の表記」にはそれほどこだわらなくていいです。「書けたら書く」くらいで問題ありません。
あるいは、「理由は3つある」とか、「以下に、メリットとデメリットを見比べて考察する」とか、「これからどういう展開で根拠を述べていくのか」について軽く言及するくらいでもかまいません。
| 問題提起 → 結論 → 理由(書けたら書く) |
| 根拠a | 根拠b |
| 根拠c | 結論 |

通常の場合、
〈パラグラフ1〉 問題提起+結論(+理由)
〈パラグラフ2〉 根拠a
〈パラグラフ3〉 根拠b
〈パラグラフ4〉 根拠c
〈パラグラフ5〉 結論
というようにして、「5つの形式段落」で書くことになりますが、真ん中の「根拠a・根拠b・根拠c」のところはそれぞれを短めに書いて、ギュッと「1つのパラグラフ」にすることもあります。

ということは、「小論文」というものは、全体で「3つ~5つ」くらいのパラグラフで書くことになるんだな。

そうです。
「300字で書け」とか、極端に短い場合は、「1つか2つ」くらいで書くこともありますが、たいていは「500字~1,200字」くらいありますので、全体で「3つ~5つ」くらいのパラグラフになると考えておきましょう。
では実際に「4スクウェア」にどんなことを書いていけばいいのかについてみていきましょう。

「根拠a」「根拠b」「根拠c」って3つも書くのはたいへんだね。

いや、これ慣れるとかえって簡単なんですよ。
ひとまず見ていきましょう。
What / Which / How

ひとまず「ある問い」があるとします。
「小説を読む意味は何か」とか、
「車を買うとしたらどこのメーカーがいいか」とか、
「街にゴミがあふれている問題をどうすべきか」とか、
いろいろな形式の「問い」がありますが、小論文の題材になるのは、「何(What)」「どちら・どれ(Which)」「どうやって(How)」のいずれかです。
やみくもに書き始める前に、What / Which / How のどれが求められているのか、考えるといいですよ。
論点並行型 (並べる)

「意味づけ型( What 型)」の小論文の場合、論点を複数に分けて、それぞれ述べていく方法を使うことがあります。
これを「論点並行型(並べる型)」と考えます。
| 【問題提起】「ポイズン」は名曲か。【結論】名曲である。 |
| ①歌詞がいい。 | ②メロディーがいい。 |
| ③歌いやすい。 | 歌詞がよく、メロディーがよく、歌いやすい。 したがって、「ポイズン」は名曲だ。 |

前述したように、「4スクウェア」の「①②③」のところは、小論文でいう「本論」に該当します。
「右下」のところが「結論」ですね。
比較検討型 (比べる)
| 【問題提起】ポルシェとフェラーリはどちらがよいか。【結論】ポルシェがよい。 |
| ①エクステリア ポルシェ > フェラーリ | ②インテリア ポルシェ > フェラーリ |
| ③走行性能 ポルシェ > フェラーリ | ①②③においてポルシェが上回る → したがって、ポルシェがよい。 |

「論点」を3つに分けて、それぞれ比べるという方法ですね。
| 【問題提起】ポルシェとフェラーリはどちらがよいか。【結論】ポルシェがよい。 |
| ①ポルシェの特徴 | ②フェラーリの特徴 |
| ③ポルシェのほうがいい点 | ①②について、③の理由でポルシェが優位だ。 したがって、ポルシェがよい。 |

それぞれの特徴を述べたうえで、それらをふまえて、③で「優劣」を考察する方法です。
原因/効果型 (つなげる)
「流れ」
| 【問題提起】ゴミ問題をどうすべきか。【結論】〈プランA〉がよい。 |
| ①原因 | ②対策(プランAの特徴) |
| ③展望 | ①について②をすれば③になる。 したがって、プランAがよい。 |

「原因の分析」「対策の詳細」「仮説」という「流れ」をつくるやりかたです。
「プラン」を出す場合は、シンプルにプランのよいところを猛プッシュする作戦もあります。
メリット猛プッシュ
| 【問題提起】ゴミ問題をどうすべきか。【結論】〈プランA〉がよい。 |
| ①メリットx | ②メリットy |
| ③メリットz | x、y、zのメリットがある。 したがって、プランAがよい。 |
メリット/デメリット見比べ型

メリットとデメリットを見比べるスタイルもあります。
| 【問題提起】ゴミ問題をどうすべきか。【結論】〈プランA〉がよい。 |
| ①メリット | ②デメリット |
| ③メリットがデメリットを上回る理由 | ②よりも①を優先したほうがよい。 したがって、プランAがよい。 |
複数のプランの見比べ
| 【問題提起】ゴミ問題をどうすべきか。【結論】〈プランA〉がよい。 |
| ①効果 プランA > プランB > プランC | ②コスト プランA > プランB > プランC |
| ③持続性 プランA > プランB > プランC | ①②③のいずれもプランAが優れている。 したがって、プランAがよい。 |
例示の置き場所

さて、「例示」というのは、ふつう「本論のパラグラフそれぞれの後半(あるいは真ん中)」に置くのですね。
ですから、①②③という「3つ」の論点がある場合、本来的には「①に適した具体例」「②に適した具体例」「③に適した具体例」という合計3つの具体例を書くことになります。
論点のぶんだけ「意見&例示」があるイメージですね。
しかし、そうは言っても、「小論文」くらいの字数だと、複数の具体例を出すスペースがありませんので、たいていは「1個」多くて「2個」ですよね。
そういう場合の例示の出し方にはコツがあって、今まで見てきた①②③の意見を一気に「1つのパラグラフ」に書ききってしまって、次のパラグラフで①②③に該当する例示をドカンと出す手法があります。
そうすると、次のような書き方になりますね。
〈パラグラフ①〉 問題提起+結論
〈パラグラフ②〉 根拠a・b・c
〈パラグラフ③〉 具体例
〈パラグラフ④〉 結論
| 【問題提起】 【結論】 |
| ①効果 プランA > プランB > プランC | ②コスト プランA > プランB > プランC |
| ③持続性 プランA > プランB > プランC | ①②③のいずれもプランAが優れている。 したがって、プランAがよい。 |