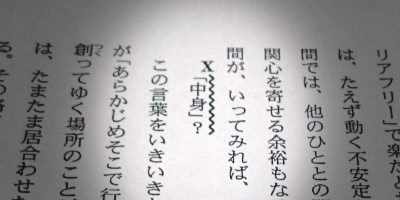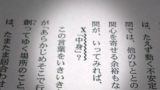実際の高得点者の答案と見比べると、良書は限られてくる。
東京大学の二次試験の現代文は、きわめて質のよい問題なので、仮に東大を受けないとしても、数年分の過去問を解くことは非常に有益なことです。多くの過去問に対し、多くの人々が、本気で解答例を考えており、考察の数が多いぶんだけ、方法論を比較検討しやすいからです。
もちろん、実際に受ける場合は、10年分くらいの過去問に取り組みたいところです。とはいえ、他の科目を圧迫してまで現代文に時間をかけるのは得策ではありません。国語の内訳で言っても、記述に関しては古文漢文のほうが得点が取りやすいので、どちらかといえば古文漢文に時間を使ったほうがよいです。
どの科目もそうですが、特に現代文は、「やみくもに時間だけかける」という学習が最も無駄になる科目です。たとえば「歴史」は、解答の方向性をほぼ決められるので、その決められたゴールに向かって学習すればよいことになりますが、現代文は、書物によって、解答の方向性がずいぶん異なります(赤本と青本でもすいぶん違います)。そのため、「得点になるとは考えにくい答案」に向かって学習時間をかけても、その努力が得点に結びつかなくなってしまいます。したがって、「ゴール」すなわち「どういう答案が点になるのか」ということについて、方向性をもって進まなければなりません。
「模範解答と採点基準」を大学側が発表しているわけではないので、どのような答えを書けば、どのくらいの得点になるのか、正しくはわかりません。しかし、まったくわからないわけではありません。得点の開示があるからです。「国語」全体での得点開示になりますが、合格する受験生の「古文漢文」の答案はかなり似たものになりますし、「古文漢文」は比較的採点基準を想定しやすいので、たとえば次のような推論をしていくことができます。
「この受験生は120点中75点を取ったけれど、この古文漢文の答案だと、75点中40点は古文漢文で取れているだろう。ということは、 現代文で35点くらいは取っているだろう。」
そうやって、受験生の再現答案を複数見比べていくと、「どう書けばよいのか」について、輪郭をつくっていくことができます。各予備校も当然この作業をしていますが、どういうわけか、公表する解答例が、その作業にまるで一致していないものになっている場合もあります。
そこで、以下には、「これなら高得点になっているはずだ」と考えられる答案を出しているテキストをいくつか紹介しておきます。
推薦図書
番外編(書籍ではない)
東進ハイスクール「過去問データベース」の解答例
無料で会員になれますので、最も格安です。しかも、解答例の質がよいです。特に、2006,7,8年あたりから現在までの答案が、高得点になっていると考えられます。
解答例が良質であり、しかも無料であるという点で、東大志望者は会員登録して「東進の解答例」を見ることをおすすめします。ただ、「解説」がついている年度と、ついていない年度があります。また、解説自体がやや高度なので、腰を据えて読む必要があります。
Z会の過去問シリーズ
「再現答案をできる限り収集して、高得点になると考えられる解答例を作成する」という作業を長い歴史のなかで実施しているのは「Z会」です。Z会には東大の過去問を添削する教材があります。解説も添削も良質です。