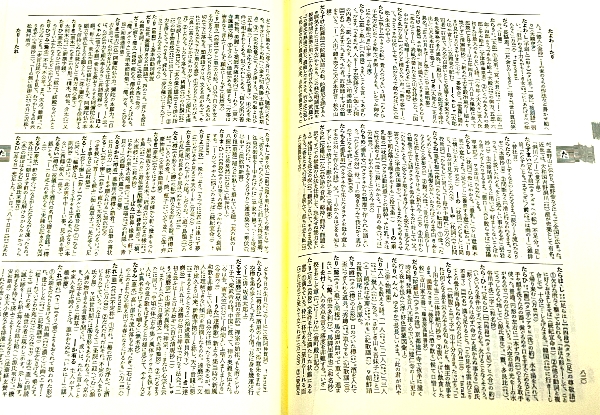記述問題について
現代文の解答は、まずは「記述」の考えが基本になります。

選択肢問題であっても、まずは「書くならどうすべきか」という観点が重要になります。
どんな問題でも、まずは「記述問題の解答姿勢」がベースになると考えましょう。
記述問題の解答姿勢(主な設問形式3パターン)
(a)「どういうことか」の場合、傍線部内の各要素をわかりやすく言い換える。傍線部内に「主語」がないことも多いが、字数的に可能であれば解答には「主語」を補うほうがよい。
(b)「なぜか」の場合、傍線部の「前提」となる「原因・理由」「目的・意図」などが問われているため、それらを探し出し、答案化する。
(c)「言えるのはなぜか」の場合、「論拠」が問われており、実質上「傍線部そのものの意味内容」を具体的に説明することが答案の「核」となる。そのうえで「前提」も補えるとよい。

「傍線部問題」は、原則的に以上の3パターンに分かれます。
もちろん、これ以外の問い方もありますが、それらは(a)(b)(c)の「応用版」と言えますので、この3つを「基本」と考えておくとよいです。
よい答案の三条件(応答/論理/表現)
(ⅰ)応答
「設問」にきちんと対応する答案になっている。
「設問の条件」を無視していない。
(ⅱ)論理
「どういうことか」であれば、答案の構成が、傍線部の論理関係(主語・目的語⇒述語)と、同じ意味内容になっている。
「なぜか」であれば、答案の構成が、「結論(主に述語)」に対する「原因・理由」または「目的・意図」になっている。
「言えるのはなぜか」であれば、答案の構成が、「傍線部内の抽象表現」に対し、その意味内容を具体化したものになっている。さらに「前提」も補足しているといっそうよい。
(ⅲ)表現
傍線部にかかわる「指示語」「比喩的表現」などを、わかりやすく言いかえることができている。

「表現」については、細かく言うと次のような方針があります。
答案作成における表現の注意点
(1)指示語は答案に持ち込まない。(指示対象のほうを書く)
(2)比喩は答案に持ち込まない。(実態のほうを書く)
(3)例示は答案に持ち込まない。(一般化する)
(4)傍線部「内」の熟語はそのまま答案に出さない。(言い換える)
(5)傍線部「外」の熟語は答案に使用できる。(言い換えなくてよい)
(6)客観的かつ一般的な名詞は、傍線部の内外問わず、そのまま書いてよい。
(「背中」「旅」「人」「猫」「建物」など)

「指示語を答案に持ち込まない」「比喩を答案に持ち込まない」といったものは、答案づくりの基本姿勢です。
逆を言えば、「傍線部」には「指示語」や「比喩的表現」が混入しやすいということです。
それらを「解決」していくと、点数の入る解答になっていきます。
なお、「指示語」は、「答案の内部の語句」を指しているのであればセーフですが、その場合でも多用は避けましょう。
選択肢問題も、書くつもりで論点を収集する。

選択肢問題であっても、まずは書くような気持ちで論点を収集しましょう。
不正解の選択肢の落とし方などについてはこちらをどうぞ。