- 問1 問題文のはじめの七行、すなわち「雑木林の中の小径は、」から「(通ってよいのだろうか、こんな神々しい道を)」までの範囲において用いられていない修辞法を次の中から一つ選べ。
- 問2 空欄【 X 】に入る漢字として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
- 問3 傍線部(1)「さっき膝の上に来ていた」とあるが、いつ、誰の膝の上に来ていたのか。最も適当なものを次の中から一つ選べ。
- 問4 傍線部(2)「それにしても、婆さまの家を出てからだいぶん経って、誰にも逢わぬ山の道である。」とあるが、この文に込められている心情の表現として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
- 問5 空欄【 Y 】に入る語句として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
- 問6 傍線部(3)「走って、この光の小径を抜け出そう」とあるが、「走って、この光の小径を抜け出」す時の気持ちとして最も適当なものを次の中から一つ選べ。
- 問7 傍線部(4)(5)のように、「わたし」は婆さまの同じ言葉を繰り返し想起しながら、思考を展開していく。
- 問8 傍線部(6)「万葉などに結実した歌言葉の日常を遺していた」とあるが、どういうことか。その説明として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
- 問9 渡辺京二氏は『もうひとつのこの世―石牟礼道子の宇宙』の中で、「コスモス」を「具体的で統合された森羅万象の世界」としたうえで、石牟礼道子氏について次のように述べている。
- 問10 渡辺京二氏は、石牟礼道子氏の作品について次のようにも述べている。
- 4 突然わたしは思い当った。たとえば相聞という歌の形を。
- 問11 次のア~オについて、問題文の内容に合致するものには1を、そうでないものには2を、それぞれ記せ。
問1 問題文のはじめの七行、すなわち「雑木林の中の小径は、」から「(通ってよいのだろうか、こんな神々しい道を)」までの範囲において用いられていない修辞法を次の中から一つ選べ。
雑木林の中の小径は、木洩れ日のせいで、やわらかい光のトンネル【隠喩】になっていた。誰もその中を通っていなかった。わたしはしばらくそこに佇んだ。神々しいほどの道である。両側から枝をさし交わしている細い白樫や、椿や姫沙羅の発光しているような【直喩】幹の色【体言止め】。そのような木々の根元に寄りそいながら、冬イチゴの広い葉や灌木類が絡みあい、和められた光が反射しあって、冬枯れ色の草の道がぼうと浮かんでいた。
(通ってよいのだろうか、こんな神々しい道を)【倒置法】

選択肢のなかで使用されていないレトリックは「対句法」なので、〈選択肢4〉が正解です。
問2 空欄【 X 】に入る漢字として最も適当なものを次の中から一つ選べ。

もう少し先まで読むと、「婆さまの家を出てから」という描写がありますので、筆者は「婆さまの家」にいて、そこを退出してから五、六百メートル来てしまった、と考えられます。すると、〈選択肢3〉の「辞」が正解になります。
「辞す(じす)」というのは、
(1)あいさつをして帰る。
(2)勤めている職や役をやめる。辞職する。辞任する。
(3)勧誘や申し出などを断る。
の意味があります。ここでは(1)の用い方ですね。
「去」「過」「帰」「出」は、文法的かつ内容的に前後とつながりません。
問3 傍線部(1)「さっき膝の上に来ていた」とあるが、いつ、誰の膝の上に来ていたのか。最も適当なものを次の中から一つ選べ。
林は枯れ葉のみじろぐ音や、羽虫たちの行き交う音、遠く近くで啼く小鳥たちの声にひろびろと満たされていた。ふとわたしは、心の奥にひっかかる親しい声を後ろに聴いたような気がして、再び立ち止まった。愛らしい声がたしかに、後ろの方から追ってくる。
まさか。もうあの一軒家を辞してから五、六百メートルは来てしまったのだ。振り向いて仰天した。(1)さっき膝の上に来ていた白っぽい三毛猫の子である。走って逃げるべきかととっさに考えたが、足は引き返す方に踏み出してしまった。まだねむたそうな目つきの、耳だけはぴんと立てたのが、頭をふりあげふりあげ、かすれたような声で、
「ぎゃおー、ぎゃおー」
というように鳴いてくるではないか。それは胸にこたえる声だった。

31行目まで読むと、「さっき囲炉裏のそばで婆さまと話しこんでいたとき、膝の上に来ていたのだった」とあり、35行目には、「わたしは思わず膝を立てた。ねむっていた小猫が、ころっと落ちかけて膝にしがみついた」とあります。
ということは、「猫」は、婆さまの家(山中の一軒家)に「わたし」がいたとき、「わたし」の膝の上に来ていたことになります。
正解は〈選択肢2〉です。
問4 傍線部(2)「それにしても、婆さまの家を出てからだいぶん経って、誰にも逢わぬ山の道である。」とあるが、この文に込められている心情の表現として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
草にひっかかり、ひっかかりしながら走って来て、こちらがかがみこんで手をのばすと、三尺ばかり前のところでよたよた止まり、咽喉を仰向けながら、ひどいしゃがれた声でまた鳴いて、大きな欠伸をした。唇はピンク色だが、鼻の下には黒いチョビ髭のような斑点が少しあった。
追っかけて来ているのを知らなかった。(2)それにしても、婆さまの家を出てからだいぶん経って、誰にも逢わぬ山の道である。

「だいぶん経って」「誰にも逢わぬ」という表現から考えると、〈選択肢3〉が適合します。
だいぶん経って = 遙々と
誰にも逢わぬ = 寂しい道
という対応が認められます。
不正解の選択肢
1 物音一つしない道なのにずっと気づかなかったとは。

「枯れ葉のみじろぐ音」「羽虫たちの行き交う音」「遠く近くで啼く小鳥たちの声」とあるので、「物音一つしない」とはいえません。
2 あの険しい山道を引き返して行くことになろうとは。

「険しい」とする根拠がありません。どちらかというと、のどかでおだやかな道のような描写になっています。
4 人跡まれな山中で小猫を放し飼いにするなんて。

「放し飼い」かどうかはわかりません。

ああ~。
勝手に抜け出て来ただけかもしれないよね。
5 小猫の人恋しさにもっと早く気づくべきだった。

傍線部そのものの表現からは読み取れないので、「設問の条件」にあいません。
問5 空欄【 Y 】に入る語句として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
拾い取って掌に乗せた。びくびくふるえている。【 Y 】顔をみながら、しんじつ困った気持になった。後戻りして返してくるより仕方がない。二年生くらいの女の子がいた。頼んで抱いていてもらおう。それから(3)走って、この光の小径を抜け出そう。

「顔をみながら」という表現につながる擬態語としては、「じろじろ」か「しげしげ」がいいですね。
「じろじろ」は「無遠慮に目を向けるさま」で、
「しげしげ」は「物をよくよく見るさま」です。
「じろじろ」はちょっと失礼なニュアンスがある表現です。「猫」をじっと見ることは特に失礼ではありませんので、ここでの文脈にあいません。正解は〈選択肢2〉の「しげしげ」です。

これって、もしも「じろじろ」が正解なら、「しげしげ」も正解になっちゃう関係だよね。

そうですよね。
「しげしげ見る」ことに「失礼」のニュアンスが加わると「じろじろ」になるわけですから、「じろじろ」が正解になるのであれば、より意味の広い「しげしげ」も同時に正解になってしまいますね。
問6 傍線部(3)「走って、この光の小径を抜け出そう」とあるが、「走って、この光の小径を抜け出」す時の気持ちとして最も適当なものを次の中から一つ選べ。
追っかけて来ているのを知らなかった。それにしても、婆さまの家を出てからだいぶん経って、誰にも逢わぬ山の道である。
拾い取って掌に乗せた。びくびくふるえている。しげしげと顔をみながら、しんじつ困った気持になった。後戻りして返してくるより仕方がない。二年生くらいの女の子がいた。頼んで抱いていてもらおう。それから(3)走って、この光の小径を抜け出そう。
1 わずらわしいものからようやく解放された気持ち

「わずらわしい」がおかしいです。「筆者」が「猫」を迷惑に思っている描写はありません。
2 帰って来ないものたちを追い求める気持ち

「追い求める」がおかしいです。「猫」を「家」に帰して、自分はそこから遠ざかるわけですから、むしろ「遠ざかろうとする」気持ちになるはずです。
3 神々しいものに包まれた温かく幸せな気持ち

「神々しい」が大げさです。また、「走って抜け出す」という行為と「温かく幸せ」という感情は結びつきません。
4 異界めいた世界から早く脱出しようとする気持ち

「異界めいた」が「本文根拠なし」あるいは「大げさ」です。本文のどこかに、この森を「異界」とみなしているような表現がきっぱりあるなら正解に近くなりますが、「異界」と解釈できる表現はありません。
たしかに「神々しい道」とは述べていますが、「異界」とまでは言っていませんね。
5 後ろ髪を引かれつつも振り切ろうとする気持ち

正解です。
この後の部分には、追いかけてきた猫に対する「涙が出そうになった」」「いじらしさよ」といった表現がありますので、「猫」に対して割り切れない思いを抱えていることは明らかです。それを「後ろ髪を引かれ」と表現するのは適切です。
また、「走って~抜け出す」ということは、婆さまの家に置いた猫を離れることを意味しますから、「振り切ろう」という説明も適切です。
問7 傍線部(4)(5)のように、「わたし」は婆さまの同じ言葉を繰り返し想起しながら、思考を展開していく。
(i)傍線部(4)「こういう山ん中でございますけん、猫ん子でもなあ、人恋しさにいたしますとですもんなあ」という想起された言葉は、思考の展開においてどのような役割を果たしているか。最も適当なものを次の中から一つ選べ。
胸に抱いて歩き出すと、婆さまのさっきの言葉が唄うように耳許に聞えた。「(4)こういう山ん中でございますけん、猫ん子でもなあ、人恋しさにいたしますとですもんなあ」涙が出そうになった。お前は何の生れ替りなの。人恋し人恋しと口に言えなくて、こういう山の中で、何代も何代も死に替り生き替りして来たものの化身なのか、いじらしさよ。ふわふわ玉のような小さな躰の中に血が通って、ふるえている温い三毛猫の子ども。
こんな愛らしい者や年老いた者たちの、後ろに追ってくる声を置いて、かつてこの山の中を走って抜け出た娘たち若者たちが、どれほどいたことか。海辺に出るにも町に出るにも、五里六里とこんな杣の道を、お月さまや星の明りを道づれに、茨のとげでひっかき傷だらけになって、わらじを踏み替え踏み替え、どのような思いで越えたことだろう。

傍線部の直後に、「お前は何の生れ替りなの」という心情があります。
さらに後ろに、「こんな愛らしい者や年老いた者たちの、後ろに追ってくる声を置いて、かつてこの山の中を走って抜け出た若者たちが、どれほどいたことか」とあります。
ということは、筆者は「追いかけてきた猫」を、「かつてこの山を出ていこうとした者を追いかけた人々」に重ね合わせたということになります。
その観点で選択肢を検討しましょう。
選択肢検討
1 小猫は山の中に残った者の生れ替りである、という「わたし」の気づきに確証を与えている。

「小猫」が「山の中に残った者の生れ替り」というのは、「筆者」が「そう感じた」だけのことであり、何か証拠を挙げて証明できるものではありません。
したがって、「確証」がおかしいです。
2 「わたし」と小猫を、山中を抜け出た者たちと山中に残った者たちに、重ね合せる触媒となっている。

本文と整合しています。
「触媒」とは「特定の化学反応の反応速度を速める物質」のことですが、ここでは、「婆さまのセリフ」によって、「筆者」は「わたし/小猫」=「かつて山を出ていった者/それを追いかけた者」という関係を想起しています。
ということは、「婆さま」のセリフが「筆者の思い」を呼び起こす「触媒」になったといえますので、これが正解です。
3 「わたし」を小猫の飼い主に見立てることで、「わたし」が故郷に帰ってきたように感じる契機となっている。

「わたしを小猫の飼い主に見立てる」がおかしいです。
そのような文脈はありません。
4 「わたし」の小猫に対する愛情を搔き立て、小猫を返しに行こうという決意を固めさせている。

その直前の状況で、「婆さまの家」に連れて行くために「胸に抱いて歩き出す」という行為をすでにはじめているので、この「婆さまの声を思い出すことで → 返しに行こうという決意を固めた」という因果関係はおかしくなります。
5 山中に暮らす者の人恋しさとそこを抜け出た者の非情さへと、「わたし」が思いを致すきっかけとなっている。

「抜け出た者の非情さ」がおかしいです。
「筆者」は「かつて山を出ていった者」を「非情」とは言っていません。
(ⅱ)傍線部(5)「こういう山ん中でございますけん、人さま恋しさにしてなりませんとですもん。猫ん子でもなあ」という想起された言葉は、思考の展開においてどのような役割を果たしているか。最も適当なものを次の中から一つ選べ。
残らなければならなかった人びとは、帰って来ないものたちを待ち続け、一代でも帰って来ず二代、三代と待って、互いの距離がはなれるほどに、想いだけが鳥になったり蟹になったり、彼岸花になったりしているのではあるまいか。
突然わたしは思い当った。たとえば相聞という歌の形を。男と女という以前に人もその他の生命も、一人では衰弱して死んでしまう存在なもので、呼び合わずにはいられない。それが風土というものの詩韻をつくり出す。だからあの婆さまは、
「猫の子でも、人さまを恋しさにして」と言ったのだ。
「どうしよう、三毛ちゃん」
さっき囲炉裡のそばで婆さまと話しこんでいたとき、膝の上に来ていたのだった。婆さまは、火箸で燠火の底に埋めた唐藷をかき出していたが、焼けぐあいを剌してみて、「焼けましたごたる。こういう物どもは、食べなはりませんど?」
とたずねた。
「いえいえ、喜んで」
両手を重ねてさし出しながら、わたしは思わず膝を立てた。ねむっていた小猫が、ころっと落ちかけて膝にしがみついた。婆さまは藷の熱灰を吹き吹き、小猫を見やりながら詫びるように言った。
「(5)こういう山ん中でございますけん、人さま恋しさにしてなりませんとですもん。猫ん子でもなあ」
それは優しい、唄うような声だった。

「相聞」というのは、『万葉集』における「部立」のひとつです。「ジャンル」みたいなものですね。
部立には主に「相聞」「挽歌」「雑歌」の3つあります。
「相聞」はお互いの消息を交わし合う歌です。多くは男女のあいだで交わされる歌です。親子・兄弟・姉妹・友人など、親しい間柄で贈答された歌もあります。
「挽歌」は人の死に関する歌です。
「雑歌」は、上記の2つ以外の歌です。行幸・遊び・宴げ・旅などさまざまなイベントなどの歌が多いです。

ふむふむ。
「人恋しい」って感じの歌は「相聞」なんだな。

そうですね。
28行目では、「(生命は)呼び合わずにはいられない。それが風土というものの詩韻をつくり出す。だからあの婆さまは、「猫の子でも、人さまを恋しさにして」と言ったのだ」と述べられています。

まあたしかに、人が人を呼んだり、人が猫を呼んだり、猫が人を呼んだり、「生命同士」が「他の生命体を恋しく思って呼びかける」というのは、どこにいても行われる営みだよね。
その「呼びかけ方」は、「寒い地方」と「暑い地方」では異なるだろうし、「都近辺」と「都から遠く離れたところ」では異なるだろうから、「その地方独特のことばの響き」を作り出すよね。
「生命同士」が「恋しく思って呼びかけあう」という「営み」が、その地方独特(その風土の)ことばのリズム(詩韻)を作っていくんだろうね。

そうすると、正解は「1」になりますね。
選択肢検討
1 生命の呼び合う声が風土の詩韻をつくり出す、という「わたし」の気づきを証明する例となっている。

正解です!
2 「わたし」が、生命は互いに呼び合わずにはいられないのだ、と思い至る直接の契機となっている。

時系列がおかしいです。
「呼び合わずにはいられない」というのは、「筆者」が「帰り道」で思い当たった「相聞」の歌の形についての話題です。「婆さま」のこのセリフは、「筆者」が「婆さま」の家にいるときに、筆者の膝から落ちそうになった猫を見ながら発せられたものなので、「直接の契機」とは言えません。
もしもこの「セリフ」が「直接の契機」になるのであれば、「婆さまの家」にいるときに、このセリフを聞いた時点で、「生命は互いに呼び合わずにはいられないのだ」と思うはずです。
3 「わたし」から囲炉裡端の場面の記憶を引き出すが、それは人恋しさの原因を解明する鍵となっている。

「人恋しさの原因を解明」がおかしいです。「人恋しさ」がどうして発生するのかということの「原因」は、本文では解明されていません。
4 小猫をひとりにすると衰弱して死んでしまう、という予感へと「わたし」を導いている。

「小猫が衰弱して死んでしまう」という話題がありません。
5 父や祖父母の使っていた言葉を理解し習得するための第一歩を、「わたし」に踏み出させている。

「習得」がおかしいです。
本文の最後には、「死んだ父や祖父母たちが使っていた、古雅な天草言葉の、奥深い詩韻に招き寄せられての旅だった」とあるので、「婆さま」の使うことばによって、「父や祖父母たちの使っていたことばを思い出した」くらいであれば正解になります。
しかし、「理解」まで言っているかはちょっとあやしいです。さらに「習得」とまで言っている表現はありませんので、「本文根拠なし」で×になります。
問8 傍線部(6)「万葉などに結実した歌言葉の日常を遺していた」とあるが、どういうことか。その説明として最も適当なものを次の中から一つ選べ。
「このよな山ん中まで、わざわざ来てもろて、申し訳なさよ」
婆さまは小さな声でくり返しながら、中屈みの膝を浮かせては立ってみたりして、落ちつかなかった。
「ああ、お客人にさし出すもんが、なあんもなかよ」
わたしはなんとせつないことを聞くものよと思っていた。旅の途中のとびこみで、もてなされるなど思いもよらぬ身である。死んだ父や祖父母たちが使っていた、古雅な天草言葉の、奥深い詩韻に招き寄せられての旅だった。その天草言葉はなんと、(6)万葉などに結実した歌言葉の日常を遺していたことだろう。

「婆さま」のことばを聞いて、筆者は「天草言葉の奥深い詩韻」と述べています。
本文で出てくる「相聞」という歌の形式は、『万葉集』にもよく見られるものですが、筆者はこの「相聞」的なことばの響きを、「いまの天草言葉」にも見出しているのですね。
遠い昔からある「天草言葉」は、『万葉集』にも結実したような詩韻の響きをもっており、それがそのまま現在の人々の日常会話にも遺っている、と述べていることになります。
選択肢検討
1 『万葉集』を生み出したのは古代天草の風土であるが、その詩韻を現代の日常語の中になお響かせているのが天草言葉であるということ

『万葉集』を生み出したのが「古代天草の風土」であるとは述べられていません。
歴史的に見てもおかしいです。『万葉集』はもっと広範囲にわたる地域の歌をおさめています。
2 『万葉集』には庶民の日常生活から生まれた歌も収められたが、そうした庶民の歌の伝統を今に伝えているのが天草言葉であるということ

「天草言葉」が「庶民の歌の伝統を今に伝えている」とは述べられていません。
3 『万葉集』を生み出した優雅な時代の香りが、現代の天草で日常的に話されている唄うような言葉の中になお伝えられているということ

「優雅」が「本文記述なし」です。
4 『万葉集』の相聞歌などを生み出した日々の生活が天草には変わることなく残っていて、その古雅で奥深い言葉を支えているということ

「(万葉の時代の)日々の生活が天草には変わることなく残っていて」が「本文記述なし」です。
5 『万葉集』の相聞歌などに結実した生命の呼び合う声が、天草という風土の詩韻をつくり出し、その日常の言葉にも響いているということ

もともとこの地(天草)にあった「生命の呼び合う声」が、天草という土地における「ことばのリズム」をつくっていき、それは、この地で詠まれた『万葉集』の相聞歌に見出せる。その「ことばのリズム」は、今なお、日常の言葉に残っている。
ということを述べている選択肢です。
本文で述べていることと一致していますので、正解です。
問9 渡辺京二氏は『もうひとつのこの世―石牟礼道子の宇宙』の中で、「コスモス」を「具体的で統合された森羅万象の世界」としたうえで、石牟礼道子氏について次のように述べている。
彼女は前近代的な文字なき民の一員ではないのです。その代弁者でさえないと私は思います。その層からどうしようもなく超出する自我において、彼女の文学の核がはぐくまれたことを忘れてはなりません。ただ彼女は、コスモスから剝離する自分の意識が生む孤絶感を、個的自我に即して表出するという、数多の近代文学者がたどった道をたどらずに、逆にその孤絶感を、近代と遭遇することによってあてどない魂の流浪に旅立った前近代の民の嘆きと重ね合せたのです。

言っていることは難しいのですが、がんばって考えてみましょう。
「その孤絶感」というのは、「コスモスから剝離する自分の意識が生む孤絶感」をさしています。
「コスモス」というのは、「具体的で統合された森羅万象の世界」と定義されていますね。かみくだいていうと、「あらゆる生命体がいる、まとまりのあるこの世界全体」ということです。こういう世界から「自分がはみだしている」ように感じる「孤絶感」を、たいていの文学者はかかえています。
あまたの近代文学者は、この「世界から自分がはみだしている」という「孤絶感」を、「個的自我」すなわち「自分自身における、唯一で独特の自己意識」にあてはめて表現しました。

ああ~。
多くの近代文学者は、「俺って、世界になじんでないなあ~。それが俺だよなあ~。文学に表現するかあ~」って感じの文学をつくったんだな。
たしかに、芥川龍之介とか、太宰治とかの作品は、「この唯一の俺は、世界となじんでいなくて孤独だぜえ~」ってオーラがバンバン出てるよね。

石牟礼道子は、そういう感じではなくて、「近代」という時代の到来になじんでいくことができず、「前近代」に取り残されてしまったような人々の気持ちに「同化」するような文学をつくっていったのですね。
たとえば、「都会で仕事をもつために山を出ていく人」と「それを見送る人」の「それぞれの悲しみ」なんていうのは、「近代になることで発生した、前近代的な人たちの悲しみ」なんですね。それより前の時代であれば、ずっとその山の中にいるわけですから、「山を出ていく人の悲しみ」も「それを見送る人の悲しみ」もないわけなんですよ。近代に入ってそういう悲しみが出てきたのですね。
石牟礼道子は、そういう「前近代の民の嘆き」を「自分の嘆きのように」重ね合わせて文学化していったんですね。
「猫が追いかけて来ることに対する憐みの情」を「山を出ていく人を見送った山の人の悲しみ」に重ね合わせているこの文章などは、まさにそういう「前近代の民の嘆き」を「自分の嘆き」に重ねた文学性があるといえます。
右の傍線部を踏まえて問題文を読み解く場合、「前近代の民の嘆き」に該当するのは具体的にどのような嘆きか。最も適当なものを次の中から一つ選べ。
1 神々しいまでに美しい山中の村を離れ、海辺の村へ嫁に行く娘たちの嘆き

「嫁に行く」が「本文根拠なし」です。
2 可愛がってくれた人の後を追ったものの、家に連れ戻されてしまった小猫の嘆き

「前近代の民」の説明がなく、「猫」の話で終了しているので、傍線部に対する説明になっていません。
3 町へ行ったまま帰って来ない者たちを、山中で待ち続ける者たちの嘆き

整合しています。これが正解です。
4 客人を十分にもてなすこともできない不便な生活をつらく思う婆さまの嘆き

「今」の話しかしていませんし、何より「婆さま」が「不便な生活をつらく思う」という内容は本文にありません。
5 天草の山中で、他所から隔絶し発展から取り残されたことを悲しむ人びとの嘆き

「発展から取り残されたことを悲しむ」という内容は本文にありません。
問10 渡辺京二氏は、石牟礼道子氏の作品について次のようにも述べている。
話はたえずあと戻りして渦を巻き、時間・空間の基準点は不明確になる。むかしといまの区別がない。過去は現存し、現存するものはたえず過去と混りあう。すべての存在が過去・現在、遠近の区別なく、一斉にせり立ってくる。
問題文の中にも、過去がよみがえる箇所が何箇所かある。それに該当しないものを次の中から一つ選べ。
1 愛らしい声がたしかに、後ろの方から追ってくる。

今まさに追いかけて来た猫の声を聞いた場面ですから、「過去がよみがえる」わけではないですね。
「該当しないもの」として、これが正解です。
2 胸に抱いて歩き出すと、婆さまのさっきの言葉が唄うように耳許に聞えた。

過去に聞いた「婆さまの言葉」を回想しています。
3 こんな愛らしい者や年老いた者たちの、後ろに追ってくる声を置いて、かつてこの山の中を走って抜け出た娘たち若者たちが、どれほどいたことか。

実際に筆者が見たシーンではありませんが、過去の事実をイメージしています。
4 突然わたしは思い当った。たとえば相聞という歌の形を。

「思い当った」のは「今」ですが、「相聞」という歌の形は『万葉集』の部立であるので、過去に接したことのある和歌を思い出しているような場面になりますね。
5 さっき囲炉裡のそばで婆さまと話しこんでいたとき、膝の上に来ていたのだった。

過去に体験した場面を回想しています。
問11 次のア~オについて、問題文の内容に合致するものには1を、そうでないものには2を、それぞれ記せ。

本文との照合をしながら検討しましょう。
選択肢検討
ア 婆さまは、「わたし」が訪ねる約束になっていたのをうっかり忘れていた。

「約束」をしていた事実はありません。合致しないので「2」です。
イ 婆さまは朴訥な人柄で、「わたし」との会話も途切れがちで続かなかった。

「会話」はふつうに続いています。合致しないので「2」です。
ウ 婆さまの家の近くには、二年生くらいの女の子が住む家などが数軒あるだけだった。

家が何軒あるのかはわかりません。合致しないので「2」です。
エ 婆さまの家を出てから山路を急いでいた「わたし」は、猫の声を耳にしてはじめて足を止めた。

猫の声を聴く前から、「わたしはしばらくそこに佇んだ」とあります。合致しないので「2」です。
オ 婆さまと別れた後で、「わたし」は天草言葉の奥深い詩韻の由来に気づいた。

本文の内容と整合しています。「1」です。

解説は以上です!
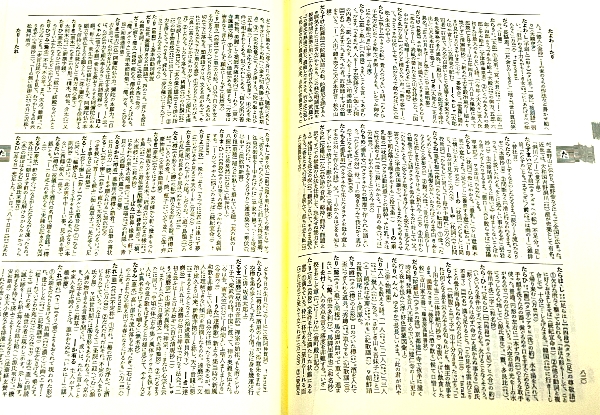
コメント