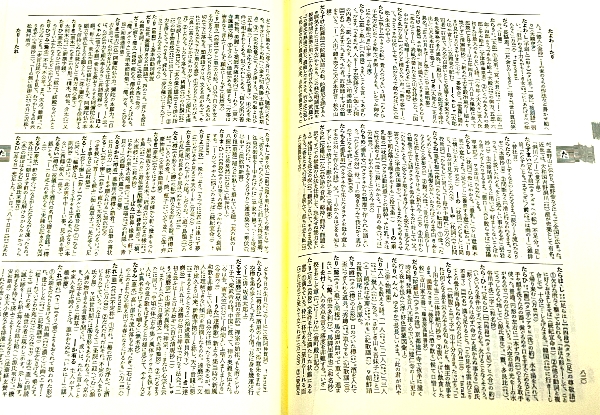①段落

第①段落の内容について、少し補足をしておきましょう。
近代的な法は「自律」的な「個人」を前提にしている。

「自律」とは、「自分を律すること」を意味します。
つまり、「自分のことを自分で決める」ことを「自律」といいます。対義語は「他律」です。
「自律」と「自立」はまた別のことばです。
「自立」のほうは、「他にたよらず、自分のことを自分ですること」です。対義語は「依存」です。

「自分のことをすべて自分でやることはできないので、真の自立とは何にも依存しないことではない。依存先を多く持ち、分散して頼ることのできる人こそ自立している人だといえる。したがって、自立の対義語は依存ではない」
という論調が最近は増えています。しかし、「辞書」の水準では「自立⇔依存」の対義関係は成り立ちます。「語」としては「自立」の対義語は「依存」だと考えておきましょう。

さて、本文では「自律」のほうの語を用いていますね。
要するに、近代的な法とは、「自分のことを自分で決めている個人」を前提にしているということです。
続きを読んでいきましょう。
あるひと(行為者)が自由に行為を選択できる状態にあり、また行為者がその行為の原因とみなされる場合、その行為の結果にたいして、法的な責任があるとみなされる。

法が適用されるのは「自律した個人(自分のことを自分で決められる個人)」なので、逆を言うと、「自分のことを自分で決められない立場」の人が悪いことをした場合、罪に問えなかったり、罪が軽くなったりします。
「少年法」などは、その典型的なものです。少年は「完全に自律しているとは言えない」ので、大人と同様の刑法は適用されません。法的な責任が「保護者」と「少年」に分散していることになります。
そして、行為者の(行為選択の時点での)状態が、その法的な責任に大きな影響を与える。行為者がどこまで自由に行為を選択したのか、どこまで意図していたのか、どこまで結果を予見できたか。行為者の意図や予見可能性によって、責任の重さは大きくかわってくる。

これも逆のことを見てみると、たとえば「刑法第39条」などが例になります。
刑法第39条は、以下の条文です。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三九条
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
要するに、「自由に行為を選択できず、意志が薄弱で、結果を予見できないと判断される人」は、「責任のない人」とみなされることになります。
裁判とは、行為者のその時点で置かれた状態を勘案して、行為者の責任(の重さ)を判定し、その責任の重さに見合った刑罰を与えることを決定する制度だといえる。たとえば、あるひとを故意に死に追いやった場合は殺人罪(刑法第一九九条、死刑または無期もしくは五年以上の懲役)が適用され、過失によって人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法第二一〇条、五〇万円以下の罰金)が適用される。

「裁判」というのは、「ある悪事」に対して万人に同じ罪を与えるのではなく、「悪事をした人」の置かれている状況をしっかりと見て、その人そのものにどのくらいの「責任」が発生しているのかをまずは考えます。
そのうえで「刑罰」を決めていくのですね。
行為者の「年齢」や「身体能力」や「精神状態」など、様々な事情が考慮されます。また、同じ人間であっても、「意図していた/意図していなかった」という違いで、罪状が異なっていきます。
第①段落のまとめ

〈第②段落〉に入る前に、ざっくりと〈第①段落〉をまとめておきましょう。
〈第①段落〉では、
近代的な方は、自律的な個人を前提にしている。
と述べられていました。
「自律的な個人」というのは、「自分で行動を決めて、自分をコントロールする人」ということです。
近代の法では、「自分で行動を決められる人の意図的な行為」を前提として、罪に対する罰が決められます。逆を言うと、ある悪事をしても「意図的」でなければ罪が軽くなります。
その点で、「同じ結果」を引き起こしたとしても、それが「意図的」であったかどうかが「責任」の大きさに影響します。
たとえば、ある暴力で人が亡くなっても、それが「意図的」であれば「殺人」であり、それが「意図的でない」となれば「過失致死」ということになります。
第②段落
しかし、差別問題においてこのような行為者(の意図)を考慮した「責任」観をとることはできない。たとえば、差別語の概説書には次のように書かれている。

ここでは、重要な表現を導くディスコース・マーカー(論理の流れを示す目印)が3つ存在します。
(1)逆接の接続詞「しかし」の後ろは要点
(2)要約系の指示語「このような」の後ろはキーフレーズ
(3)具体例の前後は要点(「たとえば ~ 。」の前後は要点)
したがって、
「差別問題において行為者の意図を考慮した『責任』観をとることはできない」
という論点は、重要度が高いことになります。

〈第①段落〉では、
「日本の法制度では、罪をおかした人にどのくらいの『責任』があるかを考えて、それに応じて『刑罰』の度合いが決まる」
というような話だったよね。
ということは、「しかし」以降は、
「差別の問題については『行為者が意図していたか/していなかったか』は『責任の大きさ』に影響しない」
と言っていることになるね。

そういうことになりますね。
具体的にどんなことを述べているのか、「たとえば」の中身を見ていきましょう。
具体例(引用)の内容(差別後の概説書の内容)
差別語・不快語をめぐる問題のなかで、ほとんどの場合、筆者・話者は「差別するつもりはなかった」「ついうっかり筆(口)が滑ってしまった」と言い訳し、悪意がなかったことを強調します。

たしかに、世の中の「差別した人」の言い訳を見てみると、「差別する意図はなかった」という場合が多いですね。

ああ~。
セクハラするおじさんとかは、「かわいがっただけ」とか「からかっただけ」とか言うよね。
そこには、問題が二つあります。

評論の内容をまとめるときに、「二つある」と述べている場合、その片方だけに言及することはNGです。
必ず「二つとも」拾うようにしましょう。
一つは、筆者・話者の主観的意図が問題にされているのではなく、発した言葉や表現が、いまの時代に、わたしたちの社会で、客観的にはどういう文脈として受けとられるかが問われるということです。

きっぱり「主観的意図が問題にされているわけではない」と述べられています。
普通の刑法については、「意図していたかどうか」は大きな問題になりますが、「差別」の問題にかんしては、「意図」は重要視されないのです。
「発した言葉や表現」が、「客観的」に「差別的であったかどうか」が問われるのです。
つまり、「差別する意図」がなくても、「その表現は差別だ!」と一般社会がみなせば、「差別」に該当するとうことですね。
「差別してやろう」と悪意をもって差別発言をする人は、ヘイトスピーチ(差別的憎悪扇動)をまき散らしているごく一部のレイシスト(人種差別主義者)を除けば、そんなに多くいません。

「ヘイトスピーチ」をまき散らす「レイシスト」は、たしかに意図的に「差別」をしています。
しかし、そういう人でなく、一般的な人からでも、「差別発言」というのは頻繁に出てきます。
たとえば、「女のくせに」とか「男らしくない」といった表現は、私たちの日常の生活にけっこう出てきますが、「女」「男」という「属性」に当てはめてその人を評価するのは、現在の社会では差別的な表現とみなされやすいです。

マンガなんか読んでると、「女・子供はすっこんでろ!」とか平気で言ってるよね。

完全な差別発言ですね。
「女・子供」を排除すると「成人男性」しか残らないことになります。「成人男性」にとっては、そこに利権などの「うまみ」があるんですよ。「差別」をすることによって、おいしい話を「成人男性」という集団で独占する構造になっています。日本社会はこの構造が根強いですね。
つまり、筆者・話者の主観的意図とは関係なく、その表現内容において、差別性があると認められれば、21世紀の社会では人権侵害と指摘されるようになったわけです。

「差別する意図」が「あったか/なかったか」ではなく、いまの一般社会で、みんなが「それって差別だよ」みなせば、「差別(人権侵害)」になるのです。それが21世紀の社会なのです。
二つめは、関係性が問われる問題だということです。差別語・不快語をめぐっては、その言葉を使用する人、向けられる人、受け止める人、使われる場所と状況によって、その意味あいがちがってきます。

親友や兄弟姉妹に「バカだな~」と言われるのと、「初対面の人」や「職場の上司」に「おまえバカじゃないの?」と言われるのは、「傷つき度合い」が異なりますよね。
そういう意味で、同じ表現であっても、「発言者」「受信者」「立場」「状況」などによって、それが「差別」なのかどうか判断が分かれることになります。

ああ~。
友達に「もう、バカ」って言われるのと、職場の嫌いな上司に「は? おまえバカ?」って言われるのとでは、「ムカつく度合い」がぜんぜん違うよね。
「似たような発言」であっても、そういった「関係性」によって、「発信者の意図」も「受信者の捉え方」もだいぶ変わってくるよね。

さきほどの「女・子供はすっこんでろ」っていう発言も、「政治家が内閣に女性や若手を入れない場面」で発せられるとしてら「ひどい発言」ですよね。
しかし、何かの戦の場面で、屈強なおじさんが、かよわい女性や子供を巻き込まないために発せられるとしたら、むしろ「かっこいい発言」とみなされるかもしれません。
第③段落
重要なのは、ヘイトスピーチを例外として多くの差別発言が明確な「意図」をともなったものではない、ということだ。差別は自分が気づかないうちに相手を傷つけてしまっていることであり、「普通」「あたりまえ」としていたことなのである。

この〈第③段落〉は、「引用」の直後にありますよね。
「引用」は「具体例」と同じ扱いなので、その「前後」には重要文があります。
実際、この〈第③段落〉には、「重要なのは」という表現があります。わざわざ「重要」と示しているので、重要な箇所になります。
さらに、「~ということだ」「~のである」という「統括型」の文末になっています。
ポイント
次のような文末になっている文は、「統括型」の文であり、他の文に比べて重要度が高い。
~のだ
~のである
~のではないか
~ということだ
~ということである
*多くの場合、すでに前の部分で語られた内容を「説明的にまとめている文」になっている。
(必ずそうなっているわけではない)

さて、〈第②段落〉の冒頭の部分をもう一度見てみましょう。
しかし、差別問題においてこのような行為者(の意図)を考慮した「責任」観をとることはできない。たとえば、差別語の概説書には次のように書かれている。

「差別問題においてこのような行為者(の意図)を考慮した「責任」観をとることはできない。」という「主張」の直後に、いきなり「たとえば、~」という「例示」がありますね。
「論理」には、通常の場合「主張/理由(説明)/例示(具体化)」という「三項関係」があります。みなさんが小論文などで書く場合には、「「主張→理由(説明)→例示(具体化)」の順序で書くことが基本ですが、入試で出会う評論文などでは、この順序になっているとは限りません。
しかし、「理由(説明)」の部分が存在しない説明文というものはありません。設問として問われる以上、必ずどこかには書かれているはずです。
こういう場合、いったん「例示」を( )に入れてみて、その前後の文脈をつなぐと、論理が流れているケースが多いので、ここでもそう考えてみましょう。
②しかし、差別問題においてこのような行為者(の意図)を考慮した「責任」観をとることはできない。(たとえば、~)
↓ ↓ ↓
③重要なのは、ヘイトスピーチを例外として多くの差別発言が明確な「意図」をともなったものではない、ということだ。差別は自分が気づかないうちに相手を傷つけてしまっていることであり、「普通」「あたりまえ」としていたことなのである。

構造としては、〈②段落〉の冒頭の「主張」に対して、〈③段落〉が「理由(説明)」の役割を果たしていることになります。
補足問題 第2段落の「引用」部分(差別語の概説書)を150字以内で要約せよ。

引用の内部が3つの形式段落になっているので、それぞれ縮めてみて、最後に統合しましょう。
①差別語・不快語をめぐる問題のなかで、ほとんどの場合、筆者・話者は「差別するつもりはなかった」「ついうっかり筆(口)が滑ってしまった」と言い訳し、悪意がなかったことを強調します。
(a)差別語・不快語の問題では多くの場合、筆者・話者は悪意がなかったことを強調する。

「 」の中身は具体例なので省きます。
②そこには、問題が二つあります。一つは、筆者・話者の主観的意図が問題にされているのではなく、発した言葉や表現が、いまの時代に、わたしたちの社会で、客観的にはどういう文脈として受けとられるかが問われるということです。「差別してやろう」と悪意をもって差別発言をする人は、ヘイトスピーチ(差別的憎悪扇動)をまき散らしているごく一部のレイシスト(人種差別主義者)を除けば、そんなに多くいません。つまり、筆者・話者の主観的意図とは関係なく、その表現内容において、差別性があると認められれば、21世紀の社会では人権侵害と指摘されるようになったわけです。
(b)そこには問題が二つある。一つめは、現在の社会では、発した言葉や表現が客観的にどういう文脈で受けとられるかが問われることだ。

「悪意を持ってレイトスピーチをするレイシスト以外には、悪意をもって差別発言をする人は多くない」
という部分は、筆者の主張(悪意のない発言でも差別になる)とは別のことを語っており、「そういう人たちは例外的存在だ」という位置づけになっています。そのため筆者の主張に入れるほどの重要度がないので、要約からはカットします。
③二つめは、関係性が問われる問題だということです。差別語・不快語をめぐっては、その言葉を使用する人、向けられる人、受け止める人、使われる場所と状況によって、その意味あいがちがってきます。
(c)二つめは、人間関係、場所、状況によって、言葉の意味が違ってくるということだ。

「言葉を使用する人、向けられる人、受け止める人、という部分は、意味内容としては要約に入れたいのですが、長いので「人間関係」くらいに圧縮してしまう必要があります。
こういうときにやってはいけないのが、
「言葉を使用する人や向けられる人が~」などと書いてしまい、「受け止める人」を抜かしてしまうことです。
記述問題や要約問題で、「列挙的な表現」を答案に出す必要がある場合、「3つ」あれば「3つとも」書くべきですし、「4つ」あれば「4つとも」書くべきです。しかし、実際には「列挙的表現」をすべて書き抜くと字数が足りなくなるので、「一気にまとめる表現を編み出す」という手法が必要になります。ここでは「人間関係」がそれにあたります。
たとえば、「短距離走、マラソン、棒高跳び」などと書いてあるものを、答案において「短距離走やマラソンは~」と書くことはNGです。「棒高跳び」が抜けているからです。
その場合はすべて書ききるか、「陸上競技」などと一言でまとめる表現を編み出すか、どちらかにしなければなりません。なお、難関大の入試では「一言でまとめる表現を編み出す」能力が問われやすいです。

「列挙的表現」は、「構成要素を落とさず書く」か、「一言でまとめる」ということなんだね。

そうです!
さて、(a)(b)(c)を統合して要約文をつくると、次のようになります。
要約文
差別語・不快語の問題では多くの場合、筆者・話者は悪意がなかったことを強調するが、そこには問題が二つある。一つめは、現在の社会では、発した言葉や表現が客観的にどういう文脈で受けとられるかが問われることであり、二つめは、人間関係、場所、状況によって、言葉の意味が違ってくるということだ。

「では、〈第④段落〉に進みましょう。
第④段落
「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」という言葉を取り上げてみよう。ここでは差別は「足を踏む」という行為に喩えられている。「足を踏む」ことはしばしば不注意や偶然によるものである。たとえば、満員電車でバランスをくずし、他の乗客の足を踏んでしまったことはないだろうか。)この例からもわかるように、差別的な言動の行為者は、必ずしも明確な「意図」を持つわけではないのだ。

例示が終了したところに、「のだ文」(統括文)があることに注目しましょう。
(1)例示の前後は要点
(2)統括文(のだ文)は要点
という2つのディスコースマーカー(論理の流れの目印)に基づき、
差別的な言動の行為者は、必ずしも明確な「意図」を持つわけではないのだ。
というところは、とても大切なところだと判断します。
第⑤段落
差別をめぐって、差別者と被差別者にはいちじるしい【非対称性】がある。差別者は差別を差別だと認識していない。そのため、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くさなければならない。この意味で差別批判とは、(b)新しい差別を発見する/発見させる行為である。しかし、いっぽうで差別者からすれば、差別と認定される自身の言動は悪意のない、「普通」「あたりまえ」のことであり、取り立てて問題にする必要のないものでしかない。このように、差別が日常的な慣習と区別されるものではないために、非難された差別者の弁明(「わざとやったのではない」「そんなつもりでいったんじゃない」)は悪質な言い訳や言い逃れに聞こえてしまう。これがさらなる非難を呼び起こしてしまう。

空欄【 】には、「非対称性」という語が入ります。
その根拠は、直後にある
差別者は差別を差別だと認識していない。
そのため、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くさなければならない。
というところです。
(a)「差別する側」は、自身の言動を「差別」だと意図していません。
(b)それに対して、「差別されている側」は、「これは差別だ」ということを「差別する側」に認識させなくてはなりません。
(a)と(b)の間には、次元の異なる「落差」があります。

ああ~。
「これは差別です!」/「これは差別ではない!」
という議論であれば、「対立」しているといえるけれど、
「これは差別だ!」/「え? え? どういうこと?(意図そのものがない)」
という状態は、「対立」にもなっていないね。

そうですね。
そもそも「同じ土俵に立っていない」状態になっているので、「対立以前」の状態だといえます。
いわば「つりあいがとれていない状態」だと言えますので、空欄【 】に入る語は、「非対称性」が最もよいといえます。
「対称」というのは「つりあいがとれている」ということであり、カタカナ語では「シンメトリー」といいます。したがって、「非対称性」というのは、「つりあいがとれていない状態」を意味していることになります。

他の選択肢の落ち度は?

「両極性」は、「両極として対立しつつも、他を自己のあり方の条件とし合っていること」を意味します。たとえば、電池の「プラス極/マイナス極」とか、地球の「北極/南極」などは、「両極」になりますね。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」は、前述したように「対立以前」の状態なので、「両極」とは言えません。
***********
「臨界性」は、「さかい・境界」のことなのですが、一般的に「臨界」という場合には、「物質がある状態から別の状態へと変化する、そのきわ」という意味で使用されます。いわば「変化前のぎりぎりのところ」というニュアンスです。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」のあいだに「変化前のぎりぎりの境界がある」とは言えません。
***********
「相補性」は、「相互補完性」のことであり、「お互いが補い合っている関係」を意味します。ある意味「公平な関係」であると言えます。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」は、「お互いが補い合っている関係」ではありませんし、「公平な関係」とは言えません。
***********
「非連続性」は、「つながりがないこと」です。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」は、「つながりがない」とは言えません。たとえばですが、昨日まで「差別側」にいた人が急に反省して、「差別を受けている側のつらさを訴える側」に回る可能性もあるわけです。そういう点で、両者は「断絶」しているわけではありませんから、「非連続性」とまでは言えません。
〈補問〉傍線部(b)「新しい差別を発見する/発見させる行為」とはどういうことか。50字以内で説明せよ。

ここで、〈④段落〉の理解を深めるために、〈補問〉に取り組んでみましょう。
現代文の本質的な学習は「記述で書いてみること」です。「書いてみると内容面の理解が深まる」というのはよくあることです。
傍線部問題は、まず何よりも「傍線部を含む一文」をしっかり把握しましょう。予備校などではよく「傍線部をのばせ!」と述べる講師がおりますが、そのアドバイスのとおり傍線部をのばしてみると、「指示語」があったり、「同義表現」があったり、答案の〈核心〉となるヒントを発見することがあります。
差別をめぐって、差別者と被差別者にはいちじるしい非対称性がある。差別者は差別を差別だと認識していない。そのため、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くさなければならない。この意味で差別批判とは、(b)新しい差別を発見する/発見させる行為である。しかし、いっぽうで差別者からすれば、差別と認定される自身の言動は悪意のない、「普通」「あたりまえ」のことであり、取り立てて問題にする必要のないものでしかない。このように、差別が日常的な慣習と区別されるものではないために、非難された差別者の弁明(「わざとやったのではない」「そんなつもりでいったんじゃない」)は悪質な言い訳や言い逃れに聞こえてしまう。これがさらなる非難を呼び起こしてしまう。

「この意味で」という指示語がありますね。
この問題は、この「指示語」を解決することが〈核心〉です。
「記述」であれば、「この」が指している内容を書かなければなりません。「選択肢」であれば「この」が指している内容をふまえていない選択肢はすべて×です。
ざっと下書きを書くと次のようになります。
下書き
差別者が差別と認識していない行為に対し、被差別者(差別を受けている側)が、差別と認識させること。

選択肢問題であればこのくらいで照合していけば正解を選べると思います。
〈本問〉の〈問3〉の選択肢を検討しましょう。
〈問3〉選択肢の検討
1 差別を認識し、批判できるのは被差別者だけであるということを被差別者自身が認識し、差別者の言動の悪質さを差別者に認識させること。

たしかに、「差別を受けた側が声をあげていかなければならない」という主旨のことが語られていますが、「批判できるのは被差別者だけ」と限定してしまうのはおかしいです。たとえば、ある「差別ー被差別」の関係を外部から見ていた人や組織が「それは差別ですよ」と指摘するケースもあるでしょう。〈言い過ぎ(限定しすぎ)〉で×です。
また、「差別者に認識させること」は、「その行為が差別である」ということであり、「悪質であるかどうか」は異なる話題です。〈論点が違う〉で×です。
2 被差別者が差別だと感じている言動は、差別者には「普通」「あたりまえ」のことであり、差別者には差別意識はないと被差別者が認識すること。

ここで問われていることは「その先」のことです。
差別者が「意図せず」に行っている行為が「差別である」と認識させる
という論点が必要です。
〈核心不在〉で×です。
3 被差別者が差別だと認識しているにもかかわらず、差別者が差別であると認識していない言動について、それが差別であると差別者に認識させること。

「下書き」の内容と整合しています。正解です。
4 被差別者が差別だと認識している言動について、差別者がいくら弁明をしても、それは悪質な言い訳に過ぎず、弁明は無意味であると差別者に認識させること。

ここで問われていることは「その前」のことです。
差別者が「意図せず」に行っている行為が「差別である」と認識させる
という論点が必要です。
〈核心不在〉で×です。
選択肢4については、〈本文根拠なし〉とも言えます。
5 差別者の日常的な行為こそが差別であると認識するのは被差別者だけであるため、それを差別者に自覚させるのは被差別者の役割であると被差別者が認識すること。

ここで問われていることは「その先」のことです。
差別者が「意図せず」に行っている行為が「差別である」と認識させる
という論点が必要です。
〈核心不在〉で×です。
記述の仕上げ

では、これが「記述問題」である場合に、どのように仕上げていくべきか考えていきましょう。

仕上げ?

記述問題は、大学によって採点基準も違いますので、「どこまで書けばOKか」というのは判断しにくいところなんですよね。
ただ、「どういうことか」の問題の場合、
(1)傍線部内の語句は極力無視しない(言及する)。
(2)可能であれば言いかえる。
という基本姿勢を反映させるほうがいいですね。
その点で、先ほどの「下書き」は、傍線部内の「新しい」と「発見する」が無視されてしまっています。できれば、「無視していません」という姿勢を示せるといっそうよいですね。
「新しい」はそもそも「客観的な語」であり、それ以上平易に説明することが難しいので、そのまま「新しい」と書いても大丈夫ですが、「発見する」のほうは、それが文脈上どういう行為を意味しているのかを取り出せたほうがいいです。
その観点で直後を見てみると、「取り立てて問題にする」という表現があります。「差別を発見する」というのは、文脈上「差別を取り立てて問題にする」ことと一致しますので、ここを使用できるといいですね。
記述解答例
差別者が差別と認識していない行為に対し、被差別者が取り立てて問題にし、初めて差別と認識させること。

ああ~。
「取り立てて問題にする」という論点を入れると、「発見する」に言及したことになるし、「初めて」などと書いておけば、「新しい」に言及したことになるね。

「取り立てて問題にする」は、同段落内にある表現なので、迷わず使用して大丈夫です。
「新しい差別」の「新しい」は、それを言いかえた表現が周辺にないので、答案内で言及するのはちょっと難しいですね。「新しい」とそのまま書いても減点はされませんが、文脈が変わらないように気をつけて、「新たに」とか「今までにない」などと書いておくといいですね。
傍線部内の「新しい」を、「新たに」と言い換えるのは、「ほとんど同じだろう」と思うかもしれませんが、ここは〈核心〉ではない部分ですし、前述したように「新しい」のまま書いても問題ない語といえますので、ガラッと言い換えなくて大丈夫です。

ふむふむ。
別解(発展的答案)
差別と認識されていない行為を、被差別者が新規の差別として可視化し、行為者に差別と認識させること。
*「可視化」は「顕在化」などでもよい。

得点は同じなのですが、「新しい」を「新規」、「発見する」を「可視化」などとする手段もあります。これは、「熟語にして書く」という応用テクニックです。
難関国立の問題などでは、このテクニックがないと字数に収まらない問題などもあるので、「あ、こういう方法もあるんだ」と知っておくといいですね。
いずれにしても、「今まで取り上げられてこなかった差別」は、「被差別者(差別を受けている側)」が、「これは差別ですよ!」と「可視化」して、比喩的にいえば「差別のカタログ」に「新規登録」しないといけないのですね。
「可視化」というのは、「見えるようにすること」です。この文脈であれば「顕在化」などと言うこともできますね。
ところが、「差別している側」は、そもそも「差別しているつもりがない」ので、「そんなつもりじゃない」と弁明することが多くなります。ところが、多くの場合「そんなつもりがなかったならいいんですよ」とはなりませんね。

ああ~。
「そんなつもりはなかった」とか、「気分を害してしまったとしたらすみません」とか言うと、
「それは無神経すぎる!」とか、「やれらた側が気にしすぎってことですか?」とか、さらなる非難につながっていくおそれがあるね。

では〈第⑥段落〉に行きましょう。
第⑥段落(前半)
ここでは近代的な法(刑罰)が前提とする「責任」の考え方がくずれている。差別においては、行為者の意図や予見可能性を考慮して「責任」の重さを考えることができない。差別者は、たいていの場合、差別を差別だと認識していないからである。これにたいして、反差別運動は被差別者が「足の痛み」を感じるかぎり、行為者に「責任」があるとみなしてきた。「責任」があるかどうかを決定するのは、行為者(とその周囲の状況)ではなく、その行為の影響をうけた人物なのである。このように、反差別運動において、法的な「責任」の考え方、(c)責任の成立機制が転倒されたことで、「自律」的「個人」=「市民」による無自覚な、意図せざる差別の「責任」を追及することが可能になった。

まず「前提」という語に注意しましょう。
「前提」という語は、この文章の〈①段落〉に登場していました。
①近代的な法は「自律」的な「個人」を前提にしている。

〈①段落〉で述べられていたことは、
近代的な法においては、行為者の意図や予見可能性を考慮して「責任」の重さを考える
ということでした。たとえば人を傷つけたとしても、「意図的」であれば「傷害」になり、「意図的」でなければ「過失致傷」になります。
〈⑥段落〉で述べられることは、この「前提」が「差別問題」においてはくずれている、ということになります。2つめの文にはズバリ、
差別においては、行為者の意図や予見可能性を考慮して「責任」の重さを考えることができない。
と書かれています。
ここを把握したうえで、〈補問〉を解いてみましょう。
〈補問〉傍線部(c)「責任の成立機制が転倒された」とはどういうことか。80字以内で説明せよ。

傍線部を上にのばしてみると、「このように」という「要約系の指示語」があります。
〈要約系指示語〉
このように・そのように
このような・そのような
こういう・そういう
こんな・そんな
こうした・そうした
といった指示語がある場合、それらは前の部分を「広く」指してまとめている。

さらに、傍線部内の「転倒」という語にも注意しましょう。
「転倒」というのは、「本来の順序がさかさになること。ひっくりかえること。」を意味します。
そのため答案では、「何」と「何」がさかさになったのかを説明しなければなりません。
ここは、「もともとの近代法の責任の考え方」と、「差別における責任の考え方」を示して説明すれば、「転倒」の内容に踏み込んだことになります。
ざっと下書きをつくると次のようになります。
下書き
近代的な法は、行為者の意図や予見可能性を考慮して責任の重さを考えるが、差別問題では、行為の影響を受けた人物が行為者の責任を考えるということ。

選択肢問題であれば、このへんで選択肢の検討に入りましょう。
〈問4〉選択肢の検討
1 近代的な法においては、差別は政治や経済といった「構造」の問題とされたが、反差別運動においては、人間性や内面の問題として捉えられた上で行為者の責任が問われるようになったということ。

「このように」の指す内容とは別のことを述べています。
〈核心不在〉または〈本文根拠なし〉で×です。
2 近代的な法においては、責任の重さは行為者の意図や予見可能性によって変わると考えられてきたが、反差別運動においては、行為者ではなく行為の影響を受けた人物が行為者の責任の有無を決定するという発想になったということ。

解答に必要な本文内容と整合しています。
正解です。
3 近代的な法においては、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くす責任を負っていたが、反差別運動においては、被差別者が痛みを感じるかぎり行為者に責任があると見なされるようになったということ。

「被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くす」というのは、「近代的な法」の話ではなく、「差別問題」の話です。
〈対比関係の取り違え(組み合わせのミス)〉で×です。
4 近代的な法においては、行為者が日本人であるかどうか、男性であるかどうか、健常者であるかどうかといったアイデンティティは責任を問う上で全く考慮されていなかったが、反差別運動においては、それが重要な要素となったということ。

「差別問題」においては、「行為者のアイデンティティ(帰属性)」も重要な要素になりますが、この「行為者のアイデンティティ(帰属性)」は、そもそもの「近代的な法」においても無視できない要素です。そのため、「全く考慮されていなかった」が〈本文根拠なし〉で×です。
そもそも〈核心不在〉です。
5 近代的な法においては、行為者が責任を問われる事態は、その行為によって誰かが肉体的苦痛を受けた場合が主に想定されていたが、反差別運動においては、精神的苦痛や社会的・経済的な不利益もふくまれるという発想になったということ。

これも〈選択肢4〉に傾向が似ている選択肢です。
「反差別運動」においては、「肉体的苦痛」だけでなく、「精神的苦痛や社会的・経済的な不利益も含まれる」と書かれているのはたしかですが、それが「近代的な法」のほうに存在していなかったわけではありません。そのため「肉体的苦痛を受けた場合が主に想定されていた」とまでは言えません。
そもそも〈核心不在〉です。
記述問題の仕上げ

では、記述問題の「仕上げ」をしていきましょう。

「傍線部内の各要素について、何らかのかたちで言及はしておいたほうがいい」というやつだな。

そうです。
実際には「重要でない表現はカット」でもいいのですが、字数が許すのであればまんべんなく「言及」しておいたほうがいいですね。
大学名出してしまいますが、特に京都大学などはこういう作業が必要になります。
「責任」は、これ以上わかりやすくできない客観的な語なので、このまま出してOKです。ただ、傍線部内の語をそのまま出す場合には、「行為者の責任」「差別者の責任」とか、何かをくっつけて、より厳密に規定したほうがいいです。
さて、「成立機制」「転倒」あたりは、言い換えて出しておきたいですね。
「機制」は、「仕組み」「機構」のことなので、「成立機制」は、「成り立たせる仕組み」とか「決定する制度」などと書くことができます。
「転倒」は、「逆に」「反対に」といったように、「逆転した」という意味合いを出せるといいですね。
そうすると、次のような答案になります。
記述解答例
近代的な法は、行為者の意図や予見可能性を考慮して責任の重さを考えるが、差別問題では逆に、行為の影響を受けた人物が行為者の責任の有無を決める仕組みになったということ。

では、〈第⑥段落〉の後半に進みましょう。
⑥段落(後半)
「足の痛み」には、肉体的苦痛だけではなく精神的苦痛、社会的・経済的な不利益もふくまれる。また、行為者のアイデンティティ(日本人、男性、健常者等々)も差別か否かを判断するための重要な要素となる。差別を禁止する法の制定は、ヘイトスピーチなど明確な差別表現には有効かもしれないが、反差別運動が法の根拠やその正当性じたいを問い直す運動だったことを考えれば、差別を禁止する法とは矛盾でしかない。

「足の痛み」という比喩は、
「加害者は意図していないけれども、被害者は傷ついている」ことを意味しています。
被害者(被差別者)の側が、「これは差別ですよ!」と言うことによってはじめて、「差別問題」は「議題」に上がります。
その「被害者側(被差別者側)」の「痛み」は、「身体の痛み」だけではなく、「精神的な痛み」も含まれますし、「出世しにくい・就職しにくい」といった「社会的」なものや、「十分な金銭的支援を得られない」といった「経済的」なものも含まれます。

「苦痛」にもいろいろなものがあるんだね。

さらに、「加行為者(差別者)」の「アイデンティティ」も重要な要素になります。
たとえば、プロ野球の「巨人ファン」が同じ「巨人ファン」の悪口を言っても、言われた側は「差別」とは感じにくいかもしれません。ところが、「阪神ファン」が「広島ファン」の悪口を言っていたら、「広島ファン」は傷つき、「差別だ」と感じるかもしれません。
つまり、「差別者」「被差別者」の「所属カテゴリー」が違うからこそ、「された側」は「差別」と感じやすいわけです。その点で、「行為者(差別者)」がどういう帰属性を持っているかというのは、「それが差別かどうか」を判断するときに重要な要素になります。

そうすると、「同じ発言」であっても、「誰が言うか」によって、「差別」とされることもあれば、「差別」とされないこともあるということになるね。
「同じ発言」であっても、「Aさん」と「Bさん」で「罪の重さ」が違ってしまうケースがたくさん出てくることになるね。

まさにそこが問題なのですね。
「Aさん」と「Bさん」が、どちらも「意図せず」に同じ「悪い行動」をした場合、「近代法」に基づければ「罪の重さ」は変わらないはずなのです。
ところが「反差別運動」は、そういった「法のあり方」そのものを「だめだ」と言っていることになります。「差別問題」は、「された側」が「傷ついたかどうか」によって、「罪の重さ」が変化してくるので、「同じ発言」であっても、「Aさんは無罪」だけど「Bさんは有罪」ということが発生しうるのですね。
そうすると、「ヘイトスピーチ」のような「意図的な差別」については、「法の制定」は意味がありますけれども、「無意識の差別」「意図的ではない差別」については、そもそも「された側」が「差別された!」と声を上げなければ「罪」として登録されないので、「法制度」のもとで「これこれこういうことをしたら有罪」という「ルール」を作れないことになります。
「これこれこういうことをしたら、人によっては有罪だけど人によっては無罪」って、法制度としておかしいですよね。
つまり、「それを差別とみなす」のが「被害者側」である「差別問題」は、「行為者」によって「有責性の強弱」がブレるので、「こういうことをしたら罪になる」ということを「誰にとっても例外なく定める」法制度とは「相反する考え方」になります。
本文ではそれを「矛盾する」と述べていることになります。

ああ~。
つまり「反差別運動」というのは、「法律の考え方がそもそもおかしい」と言っている側面があるんだね。

そうです!
「同じことをしたら誰でも同じように罰せられる」というのが「法制度」なのですが、
「反差別運動」の場合は、「同じ行為であっても、傷つく人と傷つかない人がいる。傷ついた場合のみ罰を与えよ!」と言っているのですね。

たしかに、
同じように「壁ドン」されたとして、「行為者がイケメンだったら傷つかないから無罪」「行為者がイケメンじゃなかったら傷つくから有罪」っていうことになるもんね。
「民法」ならいいけど、「刑法」としてそれを規定するのは難しいよね。

この文章では最初のほうに「罰則」という語が出てきましたね。
「罰則」を定めるのは「刑法」の話であり、この文章は「刑法」の話をしていると考えましょう。
「民法」は「主に人と人の利害関係が衝突したときに解決を図るための取り決め」であって、「罰則」がありません。
「民法」は、多くの場合、「損をしている側」と「得をしている側」が争って、その利害関係を決めるものなので、対立に敗れたからといって逮捕もされませんし、国家による罰則も受けません。
そういう意味で、「被害者(と思っている側)」が、「加害者(とみなせる側)」の責任の重さを主張するということは、「民法」ではよくあることです。
しかし、この文章では、「刑法」の制度において、「差別問題」については、「被害者側」が「加害者側」の責任を決定すると述べています。
それまでの法律の考え方では、「加害者側」の責任を決定するのは、「加害者側の意図」「加害者による未来予見性」「加害者のおかれた状況」などですから、「差別問題については被害者が加害者の責任の重さを判断する」という仕組みは、まさに「これまでの考え方が逆転している」ということになります。
第⑦段落
反差別言説において、「内なる差別」「内なる偏見」「内なる優生思想」といった言葉がしばしば登場する。たとえば、相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で入所者一九人を刺殺し、入所者・職員計二六人に重軽傷を負わせた事件を扱った報道番組は「〝戦後最悪〟の障害者殺傷事件が投げかける「内なる偏見」と題されていた。これまで表面化しなかった差別や偏見の存在に社会や個人が気づいたときに、この(3)「内なる」という表現・レトリックがもちいられる。差別は無自覚な行為であり、社会においてしばしば日常的な慣習あるいは偶発的な言動のうちに起こる。たとえ差別を意図せず、その結果を予見できなかったとしても、私たちにはその責任(有責性)がある、とみなすために、「内なる」というレトリックがもちいられる。たとえば、一九七〇年代を中心に活躍し、新左翼が差別問題にコミットすることに大きな影響を与えた津村喬は、自身の著作『われらの内なる差別』(一九七〇年)は、「差別の構造化、構造の差別化」が重要だという問題意識から、当初「差別の構造」というタイトルだったが、出版社の意向によって「われらの内なる差別」に変更されたと述べている。そのために「人道主義」という「卑俗なレッテル」を貼られることになったとしている。いいかえれば、「内なる……」というレトリックによって、差別が政治や経済といった「構造」の問題ではなく、人間性や内面の問題として捉えられたわけである。このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。しかし、いっぽうで、(d)このような反差別運動を可能にした責任観が大きな問題をもたらしている。

「レトリック」とは「修辞」のことです。「修辞」とは、「ことばを工夫して表現すること」を意味します。

「レトリック(修辞)」にはどんなものがあるんだ?

たくさんありますが、もっともポピュラーなものは「比喩」ですね。
他には、「倒置」「省略」「反語」「皮肉」「擬人法」といったものですね。
いずれにしても「レトリック」というのは、「するすると平易に読んでほしくないところ」だと考えておきましょう。読者にちょっと「立ち止まってほしい」からこそ、こういう「素直ではない」表現を使用するのです。

なんで立ち止まってほしいんだろうね。

重要だからです。
重要だから「手の込んだ表現」をするのです。
ということは「レトリック(修辞)が施されているところ」というのは、「表現としてわかりづらいけれども、内容としては重要」という箇所になるのですね。
そのため、傍線部が引かれやすい箇所になります。

ところで、この傍線部は、
「内なる」という表現・レトリック
とあるけれども、この「内なる」という表現には、どんなレトリックが施されているんだ?

これは「比喩」とも言えますし、「省略」とも言えます。
そのどちらも施されているとも言えます。
ここでは、「内なる差別」というのは、「差別の気持ちが一人一人の心の内側にある」ということを意味していますから、「内」というのは「個々人の心の中」を示しています。
「心の内側」とか、「精神の内部」というように「ことばを補う」ことで言っていることが伝わるので、「省略」が起きているということです。
また、「心」の「内部」に「差別・偏見・優勢思想」が「ある」というのは、人間の心的世界(精神世界)を「容器」のようにみなしていることになります。これは一種の「比喩(隠喩・暗喩)」ですから、「レトリックとして比喩(隠喩・暗喩)がほどこされている」と言うことができます。
〈補問〉傍線部(3)とあるが、「内なる」という表現は、どういうことを意味しているか。40字以内で説明せよ。

傍線部の直前に、「これまで表面化しなかった差別や偏見の存在に社会や個人が気づいたときに」とあります。
この「表面化しなかった差別や偏見」が、「内にある」ということが書ければよさそうです。「内なる」という表現をきちんと説明するために、続く文脈を見ていきましょう。

直後は具体例だね。

「具体例」を読み飛ばしてしまうことはできませんが、「具体例そのもの」は重要度は低いです。
したがって、「具体例が終わってすぐのところ」に重要な表現があるだろうというねらいをつけたうえで、具体例を読んでいきましょう。
たとえば、一九七〇年代を中心に活躍し、新左翼が差別問題にコミットすることに大きな影響を与えた津村喬は、自身の著作『われらの内なる差別』(一九七〇年)は、「差別の構造化、構造の差別化」が重要だという問題意識から、当初「差別の構造」というタイトルだったが、出版社の意向によって「われらの内なる差別」に変更されたと述べている。そのために「人道主義」という「卑俗なレッテル」を貼られることになったとしている。

もともと津村は「差別は構造の問題だ」と考えていたわけです。
たとえばですが、小学校で運動会などをやって、「赤組」が勝ったとします。すると、「赤組」の子どもって、「白組」に対して、「白組負けたんだから給食も少なめにしろ」とか、「赤組のほうがえらいんだから、ブランコも赤組優先」とか、いろいろ言い始めるんですよ。
赤組の子どもたちのなかに、もともと白組をさげすんでいる感情があるというよりは、「運動会で勝ち負けがついた」という「構造」によって、結果的に差別が起き始めているんです。
しかし、「差別の気持ち」を「私たちみんなの心の中にある差別の気持ち」とすると、「人間性が高い人は差別をしない」「人間性が低い人は差別をする」というような、「そもそもの人の道」の問題になってしまいますね。
津村の思いとしては、「差別」はもともと「構造」の問題であって、「人の精神性」が中心的主題になる「人道主義」の問題ではありません。ですから、「差別問題」を「人道主義」の話にしたくないわけです。
ところが、本のタイトルが「われらの内なる差別」となってしまったことで、「人道主義の本だ」という低俗な断定的評価を受けることになってしまったのですね。

タイトルでだいぶ印象が変わっちゃったんだね。

ただ、例示はそこまで深く理解できなくていいので、むしろ例示が終了したところに着眼してください。
「例示の前後」は「同義関係」または「主張と根拠の関係」になりやすいところであり、要約的にも重要な箇所になります。
いいかえれば、「内なる……」というレトリックによって、差別が政治や経済といった「構造」の問題ではなく、人間性や内面の問題として捉えられたわけである。このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。しかし、いっぽうで、(d)このような反差別運動を可能にした責任観が大きな問題をもたらしている。

そもそも、
~のだ
~のである
~のではないか
~ということである
~ということだ
といった「統括文」には注意を払ってほしいのですが、特に、
つまり~のである。
という「『つまり』つきの統括文」は、重要度が高いです。
さて、ここは「いいかえれば~わけである」という文になっています。
*「いいかえれば」は「つまり」と似た使い方をします。
*「わけである」は「のである」と似た使い方をします。
したがって、ここは「重要度が高い統括文」だと考えられます。

あ! ここに「内面」という語があるね!

そうですね!
これは「人の内面」のことを意味しています。
つまり「内なる」という表現は、「人の内面」という意味だと読解できます。
「人の内面」というのは、「精神の内部」とか「心の内側」などと説明しても「同じ意味」になりますね。
その論点を取り入れて、答案を作成しましょう。
記述解答例
人の内面(心の内側・精神の内部)には、表面化しにくい差別や偏見の感情が存在しているということ。
〈補問〉傍線部(3)とあるが、「内なる」というレトリックが用いられるのはなぜか。40字以内で説明せよ。

これは傍線部(3)の直後に「~ため」という表現がありますので、そこを拾いましょう。
下書き
たとえ差別を意図せず、その結果を予見できなかったとしても、私たちにはその責任(有責性)がある、とみなすため

40字を超えてしまっているね。

こういう場合は、〈核心〉にならないであろう「ひらがな部分」を削っていきましょう。
解答例
差別を意図せず、結果が予見不能だったとしても、行為者に責任(有責性)があるとみなすため。

続く「傍線部(d)」が述べている「責任観」も、ここを指していると考えられます。
〈本問〉問4 傍線部3「『内なる』という表現・レトリック」が示す内容として適切でないものを次から選べ。

ここまで確認すると、〈問4〉の正解根拠をつかむことができます。
「適切でないもの」を選ぶ問題なので、注意してください。
選択肢検討
ア 無自覚の差別は起こりうる 〈適切〉
イ 差別は日常的な慣習にひそんでいる 〈適切〉
ウ 差別は社会構造に起因する 〈適切でない〉 正解
エ 差別は人間の内面の問題である 〈適切〉

〈選択肢ウ〉は「逆」のことを言っているので、適切ではありません。したがって〈ウ〉が正解です。
〈本問〉問5 傍線(d)「このような反差別運動を可能にした責任観」とは、どのようなものか。最も適切なものを次の中から一つ選べ。
いいかえれば、「内なる……」というレトリックによって、差別が政治や経済といった「構造」の問題ではなく、人間性や内面の問題として捉えられたわけである。このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。しかし、いっぽうで、(d)このような反差別運動を可能にした責任観が大きな問題をもたらしている。

さて、ここでいう「反差別運動」とは、直前の「マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判すること」を指しています。
これがどういう運動なのかは気になるところですが、この問題については、こういった「運動」を可能にした、土台・背景・前提となる「責任観」のほうを聞いていますので、その「責任観」の説明を探します。
すると、直前に「(自己)責任観」という〈キーワード〉があります。
さらにそこに「このような」がついていますので、「このような」の中身をまとめれば、「責任観」の説明をはたしたことになります。
記述問題のつもりで、ざっくりとした「下書き」をつくると、次のようになります。
下書き
差別は、政治や経済といった構造の問題ではなく、人間性や内面の問題であるとする責任観

このへんまで想定して選択肢を検討しましょう。
選択肢検討
1 その意図性や結果の予見可能性にかかわらず、内なる差別意識が表面化し、その存在に気づいた時点で有責性がある、と考える責任観。

「有責性」は、「差別意識の存在に気づいた時」に生じるのではなく、「差別とみなされる行為があった時点」ですでに発生しています。
したがって、「存在に気づいた時点」が「主張と異なる」ので×です。
2 差別が構造化されていることや構造そのものが差別化を生んでいることに気づくことが重要であるという問題意識から生まれる責任観。

「構造」によって差別が生じているというのは、「ではなく」の前にあります。つまり、対比されている側の考え方なので、「逆」で×です。
3 差別は無自覚な行為であり、表面化しにくいものであることから、人道主義的な見地から人間性の問題として捉えるべきだ、とする責任観。

正解です。
4 日常的な慣習や偶発的な言動のうちに起こる差別には潜在的な意図性があるため、近代的な法にはなじまないが、有責性を認める、とする責任観。

筆者の主張は、「差別の問題は、意図がなくても罪になる」ということです。
したがって、「差別には潜在的な意図性がある」という説明は、筆者の主張に反しています。
5 差別者にも被差別者にも無自覚な差別意識があることから、その内なる差別に気づいた段階で、互いに連帯し、反差別運動を行うべきだ、と考える責任観。

ここで述べられていることは、「反差別運動」の中身の話です。
設問で問われていることは、その土台・背景・前提となる「責任観」についてなので、〈核心不在〉で×です。
また、「被差別者にも無自覚な差別意識がある」という論点は、ここでは話題にされていませんので、「根拠なし」とも言えます。
「このような反差別運動」の中身について

さて、では〈傍線部(d)〉における「このような反差別運動」の内容とは、どのようなものなのでしょうか?
〈傍線部(d)〉の直前にはこう書いてあります。
このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。

「マジョリティ」というのは「多数派」のことです。対して「マイノリティ」というのは「少数派」のことです。
社会活動のなかでは、多くの場合、「多数派」が「強者」となり、「少数派」が「弱者」となりますから、
マジョリティ = 多数派 ⇒ 強者 ⇒ 加害者 ⇒ 差別者
マイノリティ = 少数派 ⇒ 弱者 ⇒ 被害者 ⇒ 被差別者
という関係が成り立ちやすくなります。
そのため、本文では「マジョリティ(差別者)」「マイノリティ(被差別者)」という書き方がされています。

それはそうとして、
「差別する側」にいる「マジョリティ」が、「差別される側」にいる「マイノリティ」と連帯して、「差別者を批判する」
というのは、どういうことなんだろう?

たとえばですが、「大相撲」の「土俵」って、「女人禁制」というしきたりがあって、女性は上がれないことになっています。この場合、その「構造」によって「差別」が起きているので、ある意味では「相撲関係者全員」が、「土俵に上がりたい女性」を差別していることになりますね。
また、たとえば戦前の女性には参政権がありませんでした。ある意味では「選挙権を持つ男性全員」が、「選挙に出たい女性」を差別していることになります。
長い間、「差別」というものは、こういう「構造」の問題とされていました。
「大相撲関係者一人一人」にそれぞれ「差別の心」があるとか、「選挙権を持つ男性一人一人」にそれぞれ「差別の心」があるとかいうことではなく、「社会制度」によって、「許可される集団/許可されない集団」が区別されていたのですね。

ああ~。
たとえば、平安時代の「貴族」が「貴族以外」を差別するのも、そういう「構造」になっているからであって、「貴族一人一人に差別の心がある」というわけでもないだろうね。

ところが、これが、「一人一人の心の中に差別の心がある。それはいけないことだ」となっていったのが、わりと最近のことなのですね。
それを表現しているのが「内なる差別」という言い方です。
「内なる差別」という表現を、メディアや社会全体が用い続けることによって、「差別」は「構造」ではなく、「一人一人の人間性の問題」「一人一人の心の持ち方の問題」というようになってきました。

まあ、でもそれは「いいこと」じゃないの。

もちろん、一面的には「いいこと」です。
ただ、社会には「構造的差別」がすでに大量にあって、それを「人間性の問題」としてあわてて是正しようとすると、問題点も生じてきます。
たとえば、さきほどの「大相撲」の例でいうと、「土俵に上がりたい」と言い出した女性に対して、「窓口の人」が、「女性は上がれないことになっている」と返事したとしましょう。「窓口の人」は、「そういうことになっている」からそういう対応をしただけなのですが、言われた女性は「窓口の人の言い方に傷つけられた」という手法を取ることができるようになります。

窓口の人もとんだとばっちりだな。

そうすると、「大相撲関係者」の中でも、「え? 女性が追い返されるなんて、かわいそう」と言い出す人が出てきます。つまり、本来であれば「差別側」にいる人のなかに、「被差別側」に「共感」する人が出てくるのですね。
この「共感」が深まってくると、「被差別側」と手を組んだ「差別側」は、自分が属しているカテゴリーであるはずの「差別側」と闘うことになります。
教員と生徒でたとえると、「宿題が多すぎて困る」という「生徒」に共感した「教員A」が、「生徒」が主催する「宿題を減らせ!」というデモ活動に参加しているようなものですね。
「教員BCDEF」からしてみれば、「教員A」は、「本当は同集団にいるはずの人」なのですが、「批判側に回ってしまっている」ことになります。

「差別は一人一人の心の内側にある人間性の問題なんですよ」という「社会通念」が浸透することによって、本来であれば「差別側」にいるはずの人が、「私はそんな心だと思われたくないぞ」と思ったりして、自分の属する集団を批判したりするようになるんだね。

「差別」は「構造」の問題であって、「男女が違うのは当たり前」「先生と生徒が違うのは当たり前」「大人と子どもが違うのは当たり前」となっているうちは、社会では「これが普通」となってしまうので、この構造そのものを解体しようとする動きはなかなか出てきません。
しかし、「差別は一人一人の心の問題」という前提に立つと、「差別者のカテゴリー」にいる人が「被差別のカテゴリー」にいる人と手を組んで、この構造そのものの解体を目指すような運動も起きてきます。

話はわかるけど、そうすると「差別する側」が「マジョリティ(多数派)」で、「差別されている側」が「マイノリティ(少数派)」とは限らないんじゃないの?
「少数の権力者」が「多数の人々」を差別している場合もかなりあると思うんだけど……。

本文の文脈からそれるので深入りは避けますが、たとえば「メディア」の存在を意識してみましょう。
さきほどの「大相撲」の例で見た場合、「世論(社会の意見)」に大きな影響を与える「新聞」などが、「大相撲側」を支持するスタイルの記事を書き続けている限り、「大相撲側+世論」という「多数派(マジョリティ)」が形成されていると言えます。
つまり、「ある差別」について、「メディア」を中心とした「世論」が「そういうもんだよね」と思っている限り、「差別者側」はだいたい「多数派」になっています。

ああ~。
たしかに、「その差別の直接関係者」だけでなく、「その差別をおおむね容認している人」を付け加えて考えると、たいていの差別は「多数派」によって行われていると言えそうだね。

そうですね。
つい先日、イギリスの公共放送であるBBCが、日本のテレビでずっと昔にやっていた「電波少年」という番組の「懸賞生活」というコーナーを紹介していました。
当時「なすび」と称していたお笑い芸人が、アパートの一室に監禁された状態で懸賞に応募し続けて、当選した懸賞賞品だけで生活していくという企画です。衣服や食料も懸賞で手に入れなければなりません。この様子は、当人である「なすび」が知らないままに全国ネットで放送されており、懸賞生活中の日記も書籍として販売されていました。
BBCの記事は「テレビ局を告発する」というほどのものではないのですが、この出来事について「視聴者の共犯性」を問題視する風潮が、放送当時よりも強まってきています。
つまり、そのテレビ番組を見て、いっしょになって笑っていた視聴者も、人権侵害に加担していたことになるというものです。

「加担」というと、オーバーな感じもするけど、少なくとも「容認」はしていることになるよね。
わざわざそのテレビ番組を選択して、見て笑っているわけだから。

さきほどの話とつなげると、「番組制作者+視聴者」という「圧倒的なマジョリティ」によって、「なすび」は差別されていたと考えることができます。
興味深い点は、このコーナーの放送期間は「1998年1月25日 – 1999年4月18日」なんですね。当時は「視聴者の共犯性」なんてまったく話題に上らなかったんですよ。それが今になって、「見て笑っていた視聴者にも罪がある」という論調になっているのです。
つまり、「意図していなくても差別とされる行為がたしかに存在していて、それを容認している人にも何らかの罪がある」という「論調」が、2000年代初頭からこの20年間で増えてきているということです。