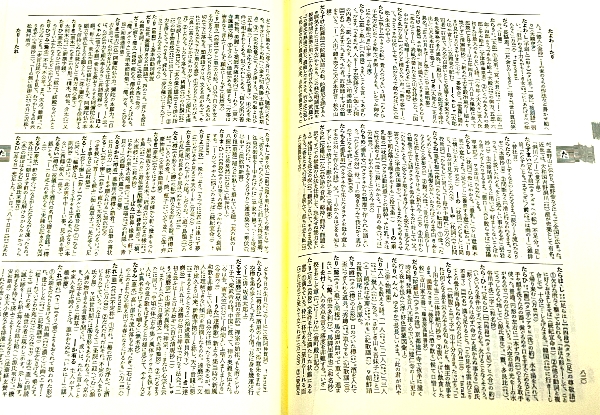重要な語を拾いながら、⑧~⑪段落をいったん通読しましょう。
⑧段落
⑧かなり時間がたってからラジオを導入した途上国での世間の変化もおどろくべきものだった。一九五〇年代のはじめのレバノンでは、それまでなにか問題がおきると村の長老の意見にしたがって行動していた村人たちが、ラジオの導入とともにだんだん「政府」のいうことをきくようになった。具象的な「顔」はみえないが「声」はきこえる。ひとびとはその「声」をつうじて想像もつかないような「ひろい世間」を知り、同時にそれが「国家」というものであることを知ったのである。いいかえれば、ラジオこそがナショナリズムの確実な基盤を用意してくれたのである。特定の国の特定の言語による放送によって「国民意識」がはっきりできあがってきた。誇張していえば「ラジオの誕生」は「国民意識の誕生」だったのである。じじつ、いま世界には二百余の「国家」があるが、その半数以上の放送局は完全な国営事業である。

「ナショナリズム」とは、「国家主義」「国粋主義」「民族主義」などと訳されます。
もう少しくわしくいうと、「自分たちの民族や国家を強化し、その権利の確保や独立、発展などをめざす思想」のことです。
ここでは「基盤」という語がありますが、「ナショナリズムの基盤」とは何のことでしょう。
――直前には、「ひとびとは、ひろい世間が国家というものであることを知った」とあります。そして直後には、「国民意識がはっきりできあがってきた」とあります。
つまり、「ナショナリズムの基盤」というのは、「国家」という範囲の認識があり、そこに生きる人々が「国民意識」をもっていることを意味しています。
特定の国の特定の言語による「ラジオ放送」は、「国家」「国民」という意識を生成していったのですね。

基盤
誇張
にチェックです。
⑨段落
⑨もちろん、新聞という強力なメディアはあった。しかし、同時刻に同一の情報に数百万数千万の「国民」が接触する、というおどろくべき時代がやってきたのである。新聞はそれを購読しないひともいるし、主張もさまざま。なによりも文字の読めないひとには無縁の存在であった。しかしラジオから流れでる声はすべてのひとびとに同時に到達する。

この〈⑨段落〉は、あとで「問4」を解くときに重要な役割を果たします。
「新聞」は多くの人が読んでいたとしても、
(1)同時刻に同一情報に接するわけではない
(2)主張もさまざまである。
(3)購読しない人もいる
(4)文字の読めない人には無縁
という点で、「ラジオ」のすごさには及びません。

接触
購読
無縁
到達
あたりはミスなく書けるようにしておきたいですね。
⑩段落
⑩それに電波というメディアの性質から、周波数割り当ては国際機関によっておこなわれ、放送局の設置は各国政府による許認可制によって管理されることになったから放送は程度の差こそあれ独占的になり、「国民」が接することのできる情報は限定的にならざるをえない。そんなふうにして、われわれは放送をつうじて背後に見え隠れする「国家」という巨大な「交際圏」のなかに組み込まれたのである。テレビの登場は「有名人」の「顔」もみせるようになったから、放送の威力はさらに加速した。

〈⑨段落〉では、「ラジオ」によって「国民」は「同時刻に同一情報に接触する」と述べられていました。
さらに、放送局は「国」が認可・管理していたので(つまり国が独占できたので)、その放送内容も「国に都合のよい情報」に限定することができたのです。
「新聞」の特徴であった「主張もさまざま」というのは、「ラジオ」では起きなかったのですね。なにしろ「政府主体」で独占的・限定的な情報を流すことができたのですから。

独占的
限定的
威力
などは書けるようにしておきたいですね。
⑪段落
⑪SNSの登場でマス・メディアの力が減少した、という説がある。たしかにネット端末が世界中で五十億台あるというのは事実だろうし、それが百億台になることもあろう。だがそれは五十億人が歯ブラシをもっている、というのに似ている。あんまり意味のある数字ではない。五十億人が同時に、しかもいっせいに同一情報でつながっているわけではないからである。じっさいのSNSはせいぜい数百人をつなげるネットワークであるにすぎず、この五十億という数字だってマス・メディアがとりあげてはじめて全世界が知ったのである。局地的に、そして一時的になにかが「炎上」したって、そんなものマス・メディアのおおきな手のひらのうえでアリが一匹、ちょっとうごいたようなもの。それにSNSが語る内容はマス・メディアからの引き写し。あるいはマス・コミ批判。なによりも多いのが放送・出版の前宣伝。SNSはマス・コミに寄生しているだけなのである。そうおもったほうがいい。

X(旧Twitter)やInstagramやFacebookといったSNSの登場で、「ラジオ」「テレビ」といった「マスメディア」の力は減少したと言われます。
しかし、筆者はその意見に否定的です。五十億人が端末をもっていても、そんなものは五十億人が歯ブラシをもっているようなものだと述べています。

歯ブラシ?

まあ、「歯ブラシ」ってたしかにみんなが持っていますけれど、「歯磨き」の時間が決まっているわけではないですし、「磨き方」とか「歯磨き粉の種類」とかは別々ですよね。
「SNSの端末」も、みんなが持っていたとしたって、「みんなが同時刻に、同一情報に接する」わけではないという点で、「ラジオ」や「テレビ」が果たしていた影響力には及ばないと述べたいのでしょう。

でも、それって、何も「歯ブラシ」にたとえなくたって、シンプルにそう説明すればわかるから、なんか、かえって混乱する比喩だよね。

そういう観点ではあんまり上手な比喩とはいえませんが、問題にもなっていますので、割り切って解きましょう。

局地的
宣伝
寄生
あたりはミスなく書けるようにしましょう。
問4
⑪SNSの登場でマス・メディアの力が減少した、という説がある。たしかにネット端末が世界中で五十億台あるというのは事実だろうし、それが百億台になることもあろう。だが(3)それは五十億人が歯ブラシをもっている、というのに似ている。あんまり意味のある数字ではない。五十億人が同時に、しかもいっせいに同一情報でつながっているわけではないからである。じっさいのSNSはせいぜい数百人をつなげるネットワークであるにすぎず、この五十億という数字だってマス・メディアがとりあげてはじめて全世界が知ったのである。局地的に、そして一時的になにかが「炎上」したって、そんなものマス・メディアのおおきな手のひらのうえでアリが一匹、ちょっとうごいたようなもの。それにSNSが語る内容はマス・メディアからの引き写し。あるいはマス・コミ批判。なによりも多いのが放送・出版の前宣伝。SNSはマス・コミに寄生しているだけなのである。そうおもったほうがいい。

指示語「それ」が指しているのは、「ネット端末が世界中で五十億台ある(百億台にはなることもあろう)」ということです。
それが、「五十億人が歯ブラシをもっている」ことに「似ている」と筆者は述べています。
設問は、そのことについて「どういう意味か」と聞いています。傍線部の述語(結論)は「似ている」なので、「どういう点が似ているのか」ということを説明しなければなりません。

みんなが好き勝手な時間に好き勝手に歯磨きすることが、みんなが好き勝手な時間に好き勝手な情報に接するところと似ていると言いたいんだろうな。

ここには、「たしかに、~A~。だが、~B~。」という「譲歩構文」があります。
譲歩構文というものは、一回相手に譲ったうえで、逆接を置き、自説を展開するための構文です。
ここでは、
たしかにネット端末が「五十億台ある(百億台になることもあろう)」
という情報に対して、「だが」という逆接の接続詞を挟んで、
「五十億人が歯ブラシをもっている、というのに似ている」
と述べられています。

「五十億台」というのは、「すさまじい数」を示しているよね。
けれどもこれを「だが」でひっくり返すわけだから、「すさまじい数の端末が存在していても、それはたいしたものではない」と述べていることになるよね。
実際、「あんまり意味のある数字ではない」と言っているから、筆者は「五十億台の端末」を「すごい」とは思っていないことになるね。

そうですね。
その理由を筆者は、「五十億人が同時に、しかも一斉に同一情報でつながっているわけではないから」と述べています。
さかのぼって〈⑨段落〉では「ラジオ」の性質について、「同時刻に同一の情報に数百万人の「国民」が接触する、というおどろくべき時代」と述べています。
筆者はこの「ラジオ」というマスメディアの影響力に比べれば、「SNS」は「たいしたものではない」と述べているのですね。
傍線部の「五十億人が歯ブラシを持っている」という比喩は、このことを示していると考えられます。「歯磨き」というのは、個人個人が自分のすべき時間に行うわけですから、全国民が同じ時間に「歯磨き」を行うわけではないですよね。SNSも同様に、「別々の時間」に、「別々の情報」にアクセスするわけです。
ということは、「同時刻に同一の情報に数百万人の国民が接触する」マスメディアに比べれば、「たいしたものではない」と言えることになります。
その観点で選択肢をみると、
「歯ブラシは、その保有者が同時刻にいっせいに歯磨きをするわけではなく、同じようにSNSも、端末の保有者が同時刻にいっせいに同じ情報にアクセスするわけではない。」
という内容をふまえている選択肢は〈オ〉のみなので、〈オ〉が正解です。
選択肢検討
ア
「五十億人がSNSの端末を持っていること」と「五十億人が歯ブラシをもっていること」の「似ている点」を答える問題であるのに、〈選択肢ア〉にはその論点がありません。「核心不在」で×です。
イ
「五十億人がSNSの端末を持っていること」と「五十億人が歯ブラシをもっていること」の「似ている点」を答える問題であるのに、〈選択肢イ〉にはその論点がありません。「核心不在」で×です。
ウ
「五十億人がSNSの端末を持っていること」と「五十億人が歯ブラシをもっていること」の「似ている点」を答える問題であるのに、〈選択肢ウ〉にはその論点がありません。「核心不在」で×です。
エ
「歯ブラシを正しく使える人が少ない」という情報は本文に存在しません。「本文根拠なし(話題なし)」で×です。
問5

「本文の内容と合致するものを選べ」という設問なので、消去法に頼ることになります。
選択肢を検討していきましょう。
ア
「みずからの手で歴史の改竄までおこなうようになる」が「本文と矛盾」で×です。
「歴史の改竄」の話が出てきたのは「ドイツの例」のところですが、それをしていたのは政府の側です。
イ
「まのあたりにして~NHKを発足させた」が「事実のミス」です。
たしかに、ヒットラーやルーズベルトの「ラジオ利用」をみて、「他の国もラジオの効果に気がついた」とありますが、「NHK」の「発足」そのものはドイツが放送局を国営化する「前」のことです。
ウ
「民主的な近代「国家」への成立へと向かった」が「本文と矛盾」で×です。
レバノンの例では、だんだん「政府」の言うことをきくようになった、と説明されています。「政府」の発信を信じてそのまま聞くのは「民主」とは逆の現象です。
エ
本文で述べていることと整合しています。正解です。
オ
「五十億台をこえるおおくのネット端末を通じて」が「本文と矛盾」で×です。本文では「五十億」とは書いてありますが、「こえる」とは書いていません。「それが百億台になることもあろう」とは書いてありますが、それは筆者の憶測です。
また、「五十億台をこえるおおくのネット端末を通じてひとびとを結びつける」という書き方だと、その五十億台どうしがつながっているような説明になってしまいますが、本文では「せいぜい数百人をつなげるネットワーク」とされています。
また、「その性格を理解してうまく利用しないと、マスコミのつたえる情報を拡散させるだけになってしまう」という部分も「本文根拠なし」です。この書き方だと「うまく利用すれば~」という論点は本文中に存在せず、筆者は単純に「SNSはたいしたことない」と述べているだけです。
問6

設問をしっかり読んで、何が問われているのかを考えましょう。
設問は、
「筆者は、ラジオ放送がナショナリズムの確実な基盤を用意した、と主張しているが、それはなぜ可能となったのか」
というものです。
「それ」が「可能となった」のはなぜか。
ということですから、
「それ」 → 「可能となった」
主語 述 語
という論理関係になります。

たしか、「通常のなぜか」の問題は、
(1)主語や目的語をしっかり説明する
(2)述語につながる情報を拾い、飛躍を埋める
という作業が大切だったね。

そうです!
(1)(2)はどちらから考えてもかまいませんし、書く順番も、(1)(2)をどちらから書いても問題ありません。日本語としてわかりやすいかどうかを重視しましょう。

主語である「それ」は、「ラジオ放送がナショナリズムの確実な基盤を用意した」ということだよね。

そうですね。
この「ナショナリズムの基盤」というのは、〈⑨段落〉のところで説明したとおり、
「国家」という範囲の認識
そこに生きる人々の「国民意識」
になります。

ああ~。
ということは、
国家という枠組みの認識や、国民意識の発生において、ラジオ放送は、○○○な点で貢献したから。
なんていうふうに書けるといいんだろうね。

いいですね!!
ただ、「ラジオ放送は」という主題から文を始めることが求められているので、
ラジオ放送は、○○○することによって、国家という枠組みに生きる国民意識を聞き手(人々)にもたせたから。
なんていうふうに書くといいですね。

ふむふむ。
「ラジオ放送」は、いったいどういうことをして「国家」や「国民」という意識を持たせていったんだろうね。

それについては、まず〈⑧段落〉にある「特定の国の特定の言語による放送によって」という論点を拾うことができますね。「によって」という「因果のラベル」もありますので、「特定の国の特定の言語」という情報は答案にあったほうがいいです。
それから、〈⑨⑩段落〉に、「新聞にはないラジオの特徴」が説明されています。
答案が「ラジオ放送は」という表現ではじまることを考えると、この「ラジオについての特徴」を書き込むことが重要になります。

すると、〈⑨段落〉にある
「同時刻に同一情報に接する」とか、
〈⑩段落〉にある
「(放送が)独占的になり、(情報が)限定的になる」といったことが書けるといいのかな。

そうですね!
キーワードとして
〈論点a〉特定の国の特定の言語
〈論点b〉同時刻・同一情報
〈論点c〉独占的・限定的
〈論点d〉国家・国民意識
といったことばをうまくつないで答案を構成しましょう。
〈下書き〉
ラジオ放送は
特定の国の特定の言語で、
独占的に、
限定的な同一の情報を
同時刻に発信することで、
聞き手を国家という交際圏に組み込み、
国民意識をもたせた
から。

圧縮しましょう。
〈解答例〉
ラジオ放送は
特定の国語で、限定した同一情報を同時刻に独占的に発信し、国家を交際圏とする国民意識を人々にもたせた
から。