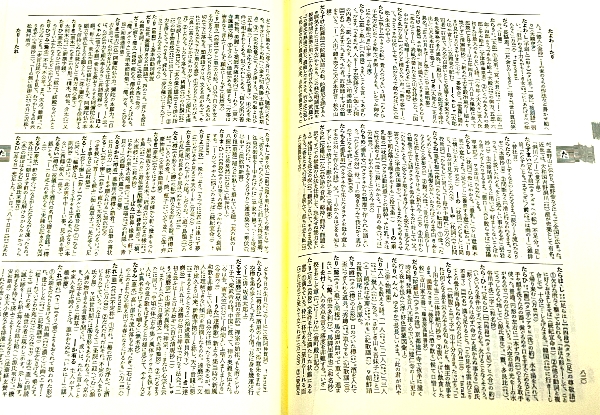重要な語を拾いながら、①~⑦段落をいったん通読しましょう。
①段落
①人類史上、想像もつかなかったような巨大な「世間」ができあがったのは二十世紀になってからの放送メディアの登場だった。放送のおかげでわれわれの「世間」はかつて想像することもできなかったほどひろがったのである。マクルーハンはそれを「人間拡張」と名づけたが、「世間」と「人間」は同義なのだから「世間拡張」といってもいい。とにかくわたしたちすべてが共有できるような、いや、共有せざるをえない「ひろい世間」のなかに放りこまれたのである。

「世間(せけん)」とは、「社会(しゃかい)」と似ている語ですが、「世間」は、「人間同士のかかわりあいのある世界」を意味しやすい語です。
なお、本文では「世間」と「人間」が同義だと述べられています。「人間」というのは「人の間」ということなので、要するに「人々の集団」のことですね。そうすると、たしかに「人々の集団」と「世間」はイコール関係のようなものだといえます。
たとえばですけれど、開国前の日本は、「日本」として「集団」とはいえません。各藩があって、それぞれが「国」とみなされていたので、「日本全体」という「世間」はないわけです。それは諸外国でも同じようなところがありました。
ところが、「情報媒体」としてのメディアが登場すると、「近代国家(いまでいう国の単位)」で、「情報を共有」することができるようになります。すると、「ひとつの国」が「集団の一単位」になっていくのですね。筆者はそのことを「世間の拡張」と述べています。
「メディア」は「媒体・媒介」などと訳されます。「仲介するもの」という意味ですが、主に「テレビ」や「新聞」など、出来事を多くの人に一気に届けられる仲介者を「メディア」を呼ぶことが多いです。大量の情報を扱うので、「マスメディア」ともいいますね。
②段落
②ラジオ放送というものがはじめて実験されたのは一九〇六年、フェッセデンというアメリカ人によるものだったというが、その後二十年ほどのあいだにラジオ受信機というあらたな耐久消費財が発売され、先進国を中心に各家庭で聴かれるようになった。

「メディア」の話がやや焦点化されて、「ラジオ」の話題が出てきています。
たしかに「ラジオ」は、放送メディアの代表的な存在ですね。
③段落
③こまかい歴史は省略するが、その強力な放送メディアにさいしょに注目した政治家のひとりはヒットラーであった。かれの腹心の盟友、ゲッベルスは一九三三年にナチ政権発足とともにラジオ放送局を国営化し、みずから「国民宣伝省」長官になって連日プロパガンダ放送をおこなった。ナチ政権はラジオとともにはじまり、ラジオによってその基盤を確実にした、といってもよい。かれらが政権確立とともに放送局を占拠した、というのはじつに鮮やかな戦略であった。ラジオは単純明快なことばでドイツ国民を心理的に完全に「【 X 】」してしまった。ほかに情報源がなくなれば、人間の思想や行動はわずかな時間でかわってしまうものだ。わたしたちだって、新聞、放送が口をそろえておなじことをくりかえせば、いつのまにやらなんでも信じてしまう。歴史の改竄だって、真実だと思い込んで疑うことを知らない。それを徹底的に実行したのがナチであった。

「プロパガンダ」というのは、「政治的意図に基づいて、多くの人々にメッセージをもって働きかけ、人々の意見・態度・感情・行動・思想を、特定の方向に編成・操作・動員しようとすること」です。
要するに、ヒットラーとその腹心のゲッベルズは、自分たちの政党の有利になるように、国民に対して「自分たち寄り」の情報を流し続けたということになります。

この段落は、
省略
盟友
基盤
占拠
徹底的
とか、覚えておきたい熟語も多いね。
④段落
④さらにゲッベルスがプロパガンダの達人として偉大だったのは、当時まだ不足していたラジオ受信機を大量生産して各家庭への浸透をはかったことだ。ゲッベルスは技術者を督励して「国民ラジオ」(Volksempfanger)の開発をおこない、安価で性能のいいラジオが量産されることになった。その結果ドイツでのラジオ普及率は一九三九年には世帯の七十パーセントをこえた。こうして天下無敵の巨大な「世間」ができた。そのスピーカーからはヒットラーの演説から愛国歌謡にいたるあらゆる世間話がきこえてくる。「国民自動車」(Volkswagen)はいまもその名をとどめる世界有数の自動車会社としてアウトバーンとともにナチの遺産になっているが、「国民ラジオ」もまたたいへんな現代遺産だったのである。

ヒットラー&ゲッベルスは、「ドイツ国民の一体感」を高めようとして、いろいろなことをしました。
そのひとつが「ラジオの国営放送」です。新聞の時代から「情報を握る者が権力を握る」と言われており、「発信者」の立場になることは「権力」のひとつのかたちなのですね。
それが「ラジオ」になると、多くの国民が同じ時間に一斉に聞くわけですから、「感情を揺さぶるのに効果的な時間」とかまで操作できることになります。
それから、次のような車を時々見かけませんか? フォルクスワーゲンビートルです。これはナチス政権の指示でたくさんつくった「国民車」なのですね。
また、ナチス政権は、「アウトバーン」という速度無制限(一部速度制限あり)の高速道路をつくって、ドイツ全土に拡張しました。この工事にはたくさんの失業者が動員されたので、「公共事業」としても成功したものといわれています。
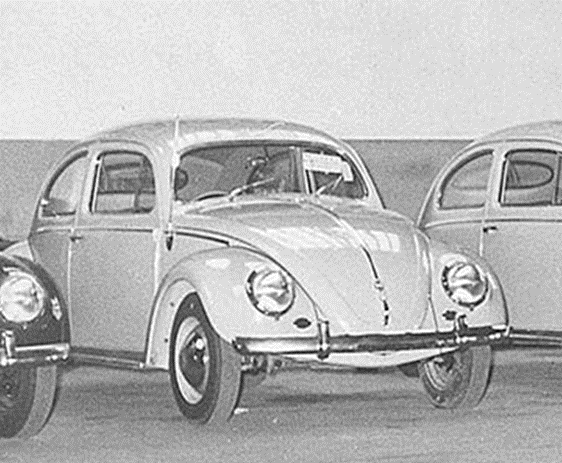

偉大
浸透
督励
普及
歌謡
あたりは気をつけておきたいね。

「浸透」の「浸」には気をつけましょう。
たとえば「浸入」という場合、「侵入」と書くこともあります。「あるエリアに水などが入り込む」ことは「浸入」と書きますが、「人や動物などが入り込む」ことは「侵入」と書きます。
さて、「浸透」という表現は、水や空気のようなものに限定されるので、「浸」のほうの字になります。
⑤段落
⑤ほぼ同時期に、アメリカもまたラジオの力に着目して、受信機の普及と電波の政治的利用をかんがえはじめた。ナチ・ドイツのようにあからさまな放送局の国営はできなかったが、軍事予算を迂回させてRCAという会社をつくった。放送内容はニュース、音楽などが中心だったが、このラジオを利用することをかんがえたのがルーズベルト大統領である。かれは「炉辺談話」(fireside chat)と名づけた定時放送で直接に国民に語りかけた。題名がしめすように、これは演説という気張ったものではなく気楽なおしゃべり、という趣向。これで大統領と国民のあいだの距離はちぢまり、戦争中のアメリカの世論と士気を高めた。「炉辺談話」がはじまったのは一九三三年。ゲッベルスによる「国民ラジオ」の構想とまったく同時代であったことは象徴的な符合というべきであろう。

ドイツのヒットラー&ゲッベルスは、「演説」や「国民歌謡」といった「世間話」を浸透させましたけれど、アメリカのルーズベルトのほうは、「気楽なおしゃべり」で国民との距離を縮めたのですね。
手法はちょっと異なっていますけれども、「ラジオ」を使用して「国民」を「大きな世間」にしていったという点では、ドイツもアメリカも同じことをやったわけです。

「象徴」は本当によく出てくる熟語だね。

「抽象的な観念や概念を暗示している具体物」を「象徴」といいますね。
「具体物」と書きましたが、実際の「モノ」ではなくても、「明示的な(目に見えやすい)出来事」の背景に「暗示的な(目に見えにくい)考え方」などが連想されるような場合、その「明示的な出来事」のほうを「象徴」と呼ぶことがあります。
「その時代に象徴的な事件」などと言ったりしますね。その「事件」を観察することで、「その時代」がどういう時代であったかをうかがい知ることができるというようなケースですね。
ここでは、ゲッベルスやルーズベルトの「ラジオ戦略」が、「メディアをとおして国民の一体感を獲得していった時代」を象徴している出来事であったということですね。
⑥段落
⑥ひとことでいえば、「交際圏」すなわち「世間話」の輪は、ラジオという新発明品のおかげでついに「国家」というタガのなかにすっぽりと包みこまれ、ひとびとはラジオの意のままにうごくようになってしまったのである。

「圏」というのは、「区切られた範囲」ということです。
首都圏(しゅとけん)・大気圏(たいきけん)・通勤圏(つうきんけん)などと言いますね。
「人々が交際する範囲=世間」は、それまではせいぜい「都道府県・市町村」くらいでしたが、ラジオの登場で一気に「国家」の枠組みになっていったのです。
たとえば、いまだに「県」の特性を比較するようなテレビ番組がありますよね。

ああ~。
「秘密のケンミンSHOW」みたいなやつね。

あれが成り立つのは、「県」によっていろいろなことが「違う」からですよね。
つまり、戦前の「世間」は「県」くらいが「範囲」で、だからこそ「県」によって特徴が異なるのですよね。
一方で、「テレビ」があることによって、日本中でその番組を楽しんでいるということは、「国」が「世間の一単位」に拡大していることも意味しています。
⑦段落
⑦ヒットラーとルーズベルトというふたりの象徴的リーダーのラジオ利用をみて、他の国もラジオのおどろくべき効果に気がついた。イギリスはBBCをつくり日本では大正十五(一九二六)年に日本放送協会、すなわちNHKが発足していた。ひとことでいえば、放送というコミュニケーション手段の実用化と「国家」とがセットになって二十世紀初頭の世界に登場したのである。この大変動は劇的であった。

ここでも「象徴」という語が出てきました。
さきほど述べたように、「ヒットラー(&ゲッベルス)」や「ルーズベルト」は、「メディアを利用して国民の統制をはかる」という「明示的な行動」から、「メディアによって人々の行動が誘導されていくという時代の特性」をうかがい知ることができます。
ドイツとアメリカの話が続きましたが、イギリスはBBCをつくり、日本はNHKをつくりました。同じようなことが各国で起きていたのですね。

劇的
は案外間違いやすい熟語だよね。

これ試験に出すと「激的」とか「撃的」と書く人がけっこういます。「劇的」が正しいので、気を付けておきましょう。
「劇的」というのは、「劇を見ているように緊張や感動をおぼえるさま」であって、外来語でいうと「ドラマチック」ということです。
問1【X】 ア
③こまかい歴史は省略するが、その強力な放送メディアにさいしょに注目した政治家のひとりはヒットラーであった。かれの腹心の盟友、ゲッベルスは一九三三年にナチ政権発足とともにラジオ放送局を国営化し、みずから「国民宣伝省」長官になって連日プロパガンダ放送をおこなった。ナチ政権はラジオとともにはじまり、ラジオによってその基盤を確実にした、といってもよい。かれらが政権確立とともに放送局を占拠した、というのはじつに鮮やかな戦略であった。ラジオは単純明快なことばでドイツ国民を心理的に完全に「【 X 】」してしまった。ほかに情報源がなくなれば、人間の思想や行動はわずかな時間でかわってしまうものだ。わたしたちだって、新聞、放送が口をそろえておなじことをくりかえせば、いつのまにやらなんでも信じてしまう。歴史の改竄だって、真実だと思い込んで疑うことを知らない。それを徹底的に実行したのがナチであった。

空欄【X】の後ろにある、
わたしたちだって、新聞、放送が口をそろえておなじことをくりかえせば、いつのまにやらなんでも信じてしまう。
歴史の改竄だって、真実だと思い込んで疑うことを知らない。
という表現から考えると、【X】には、「仮に真実ではないことであっても、信じ込ませてしまう」という意味の語が入ることになります。
選択肢のなかでは「洗脳」がいいですね。「ア」が正解です。
問1【Y】 オ
⑧かなり時間がたってからラジオを導入した途上国での世間の変化もおどろくべきものだった。一九五〇年代のはじめのレバノンでは、それまでなにか問題がおきると村の長老の意見にしたがって行動していた村人たちが、ラジオの導入とともにだんだん「政府」のいうことをきくようになった。【 Y 】な「顔」はみえないが「声」はきこえる。ひとびとはその「声」をつうじて想像もつかないような「ひろい世間」を知り、同時にそれが「国家」というものであることを知ったのである。いいかえれば、ラジオこそがナショナリズムの確実な基盤を用意してくれたのである。特定の国の特定の言語による放送によって「国民意識」がはっきりできあがってきた。誇張していえば「ラジオの誕生」は「国民意識の誕生」だったのである。じじつ、いま世界には二百余の「国家」があるが、その半数以上の放送局は完全な国営事業である。

(ラジオでは~)【 Y 】な「顔」は見えないが、「声」は聴こえるという「対比の文脈」で考えると、空欄【 Y 】には「声」とは異なる性質を示す語が入ることになります。
選択肢を比較していくと、「声」にはなくて「顔」にはあるものとしては、「オ 具象的」が適当です。「具象」とは「かたち・姿をそなえていること」を意味します。
「顔」には「かたち」がありますけれど、「声」には「かたち」がありませんね。

文脈的には、「(ラジオでは話している人は)みえない」っていうようなことを言っているわけだよね。
つまり、「ラジオで話している〈ラジオパーソナリティーその人〉の顔は見えない」ということだから、「具象的」が正解になるんだね。

はい!
「ア 抽象的」だと、むしろ逆のことを言っていることになります。
「イ 象徴的」もおかしいですね。「象徴」というのは、「ある観念や概念を暗示している具体物」のことですが、「ラジオパーソナリティー個人の顔」が、何らかの観念や概念を背景に暗示している」という関係は成り立ちません。
「ウ 即物的」は、せっかくなので2つの意味をおさえておきましょう。
即物的(そくぶつてき)
①主観を排して、実際の事物に即して考えたり、行ったりするさま。「きわめて即物的な表現」
② 物質的なことや金銭的なことを優先して考えるさま。「即物的な生き方」

ああ~。
①②どちらの意味でも、「顔」の修飾語として成り立たないね。

そうですね。
「即物的」というのは、「モノに即して考える」ということで、おもに「考え方」などにつく修飾句です。
したがって、「即物的なラーメン」とか、「即物的なテーブル」といったように、「実際のモノ」に「即物的」という修飾句をつけるのは変です。
「モノ」はもともと物体なので、「即物的」とつけるのはおかしいですよね。

「エ 想像的」も、「みえない」と整合しないよね。

そうですね。
「話しているラジオパーソナリティーの顔」は、「実物」をみることはできませんけど、「想像」することはできますよね。
したがって、「想像的な顔はみえない」という文脈がおかしくなります。
問2
⑤ほぼ同時期に、アメリカもまたラジオの力に着目して、受信機の普及と電波の政治的利用をかんがえはじめた。ナチ・ドイツのようにあからさまな放送局の国営はできなかったが、軍事予算を迂回させてRCAという会社をつくった。放送内容はニュース、音楽などが中心だったが、このラジオを利用することをかんがえたのがルーズベルト大統領である。かれは「炉辺談話」(fireside chat)と名づけた定時放送で直接に国民に語りかけた。題名がしめすように、これは演説という気張ったものではなく気楽なおしゃべり、という趣向。これで大統領と国民のあいだの距離はちぢまり、戦争中のアメリカの世論と士気を高めた。「炉辺談話」がはじまったのは一九三三年。ゲッベルスによる「国民ラジオ」の構想とまったく同時代であったことは象徴的な符合というべきであろう。
⑥ひとことでいえば、「交際圏」すなわち(1)「世間話」の輪は、ラジオという新発明品のおかげでついに「国家」というタガのなかにすっぽりと包みこまれ、ひとびとはラジオの意のままにうごくようになってしまったのである。

「すなわち」という「イコール関係」を示す語がありますので、「世間話の輪」は、「交際圏」を意味していることになります。
ただ、それだけでは正解に至る情報が足りません。
「ひとことでいえば」という「まとめの語」がありますので、もっと前をみておきましょう。構成としては、〈③④⑤段落〉の内容を一気にまとめているのですね。
直前の〈⑤段落〉には「アメリカ」の例があり、そこには「ではなく」という「対比の構文」があります。「ではなく」の後ろには「気楽なおしゃべり」と書かれていますね。
また、さらにさかのぼると〈④段落〉には「ドイツ」の例があり、「ヒットラーの演説から愛国歌謡にいたるあらゆる世間話がきこえてくる」とあります。
要するに、「演説」「歌謡」「気楽なおしゃべり」といった「様々な話題」がラジオから流れてくることで、「国家」という巨大なものが、まるで「町内会」のような「世間」になっていった、ということが述べられています。
選択肢検討
ア
「さまざまな情報を共有する」という説明は、「演説」「歌謡」「気楽なおしゃべり」という論点をまとめたものとして成立します。

「さまざまな」という説明の仕方はちょっとズルい説明なので、記述問題の場合はあまり使用したくない表現なのですが、そうとしか言えない場合もあります。
ここでは「他の選択肢」に「明確な×」が入りますので、この〈選択肢ア〉が正解です。
イ
「気楽なおしゃべり」と、「価値観や生活感情をともにする」は、大きな観点ではズレてはいませんが、「価値観や生活感情をともにする」とまで言ってしまうと、やや「言い過ぎ」になります。
たとえばみなさんも「クラスメート」や「同じ部活の友達」などと「気楽なおしゃべり」をすることがあると思いますが、その人たち全員と「価値観」や「生活感情」を共有しているとまではいえません。

なお、仮に〈選択肢イ〉が「正解」になるとしたら、同時に〈選択肢ア〉も「正解」になってしまいますね。
「価値観や生活感情をともにする」ことが正しいなら、「さまざまな情報を共有する」ことも正しくなってしまうからです。
たとえば、
① お昼は麺類が食べたい
② お昼はラーメンが食べたい
という選択肢の関係で、②が「正解」になることは考えにくいです。なぜなら、②が「正しい」なら、同時に①も「正しく」なってしまうからです。
こういう関係の場合、「言い過ぎ」が起きている選択肢が不正解になります。

「どういうことか」の問題で「2つ」の選択肢で迷ったときには、「傍線部との対応」を考えましょう。
ここでの傍線部は「世間話の輪」というものですね。「話」と言っているわけですから、「情報を共有する」という〈選択肢ア〉は、「言い換え」としてもけっこう近いことを述べていることになります。
それに対して、〈選択肢イ〉の「価値観や生活感情をともにする」というのは、「文脈」だけでいえばちょっと近い気もするのですが、〈選択肢ア〉に比べると「話」という論点の再現性が甘いですね。
ウ
「気楽な会話」はいいとして、「うわさ話」に該当する話題がないので、「本文根拠不在」で×になります。

「ひとことでいえば」というのは、正確には〈③④⑤段落〉の「ドイツの例」と「アメリカの例」を両方まとめているので、「アメリカ」のほうにだけ書かれている「気楽」という語を使用するのは、あまりよいことではありません。使用するなら、ドイツ側にある「演説」などにも言及しておく必要があります。
もしもこの選択肢が、「演説・愛国歌謡・気楽なおしゃべりなどが飛び交った」というように、「ドイツの例」と「アメリカの例」に両方ふれているのであればよいのですが、そうではないので不適格になります。
エ
「統制された情報によって支配」が、「気楽なおしゃべり」と一致しないので×です。

〈選択肢ウ〉とは逆で、これはどちらかというと「ドイツ」のほうの話題にしか言及していません。
オ
「親子兄弟の関係になぞらえられる」が、「言い過ぎ」です。

ここで言っていることは、いままでは「町内会」レベルであった「世間」が、「国家レベル」の「世間」に拡大されたということです。
「国家に所属している構成員(国民)」が「親子や兄弟のように親密になる」とまで言っているわけではないので、×です。
問3

「ヒットラーの例」は〈③④段落〉、「ルーズベルト」の例は〈⑤段落〉にありますね。
重要な部分を拾いましょう。
③
強力な放送メディアにさいしょに注目した政治家のひとりはヒットラー
腹心の盟友ゲッベルスはナチ政権発足とともにラジオ放送局を国営化
連日プロパガンダ放送をおこなった
政権確立とともに放送局を占拠したは鮮やかな戦略
ラジオは単純明快なことばでドイツ国民を心理的に完全に洗脳した
④
当時まだ不足していたラジオ受信機を大量生産して各家庭への浸透をはかった
ドイツでのラジオ普及率は一九三九年には世帯の七十パーセントをこえた
こうして天下無敵の巨大な「世間」ができた
⑤
アメリカもまたラジオの力に着目して、受信機の普及と電波の政治的利用をかんがえはじめた
軍事予算を迂回させてRCAという会社をつくった
ルーズベルト大統領は、定時放送で直接に国民に語りかけた
大統領と国民のあいだの距離はちぢまり、戦争中のアメリカの世論と士気を高めた

ドイツは「演説型」であり、アメリカは「談話型」という違いはあるものの、どちらもラジオの力を「政治利用」したのですね。
選択肢を検討しましょう。
選択肢検討
ア
「自主性にまかせた」が事実と異なります。ルーズベルト自らが国民に語りかけていますので、放送局に内容までまかせたわけではありません。
イ
「非戦略的」が本文内容と矛盾します。アメリカもラジオを「政治利用」したと説明されていますし、この「気楽なおしゃべり」によって「大統領と国民のあいだの距離」をちぢめることに成功していますので、「気張らない利用法」は、むしろ「戦略」であったといえます。
ウ
「民主的な大統領を象徴する」が事実と異なります。「民主」とは「その国の主権が国民にあること」を意味しますが、「ラジオ」は結局は「ルーズベルトから国民への声」を届ける装置であって、「国民を主権者とみなして」いるわけではありません。
エ
「プロパガンダ放送のみを行った」が「言い過ぎ」です。少なくともルーズベルトには当てはまりません。
オ
「歴史の改竄をおかした」は、「ドイツ」の例にはその言及がありますが、「アメリカ」には当てはまりません。
カ
ドイツにもアメリカにも当てはまるので、これが正解です。

今日はここまで!