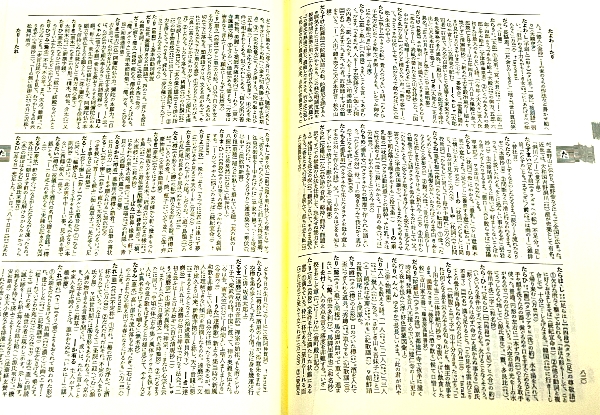「差別」の講義の「第3回」になります。
④段落
「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」という言葉を取り上げてみよう。ここでは差別は「足を踏む」という行為に喩えられている。「足を踏む」ことはしばしば不注意や偶然によるものである。たとえば、満員電車でバランスをくずし、他の乗客の足を踏んでしまったことはないだろうか。)この例からもわかるように、差別的な言動の行為者は、必ずしも明確な「意図」を持つわけではないのだ。

例示が終了したところに、「のだ文」(統括文)があることに注目しましょう。
(1)例示の前後は要点
(2)統括文(のだ文)は要点
という2つのディスコースマーカー(論理の流れの目印)に基づき、
差別的な言動の行為者は、必ずしも明確な「意図」を持つわけではないのだ。
というところは、とても大切なところだと判断します。
⑤段落
差別をめぐって、差別者と被差別者にはいちじるしい【非対称性】がある。差別者は差別を差別だと認識していない。そのため、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くさなければならない。この意味で差別批判とは、(b)新しい差別を発見する/発見させる行為である。しかし、いっぽうで差別者からすれば、差別と認定される自身の言動は悪意のない、「普通」「あたりまえ」のことであり、取り立てて問題にする必要のないものでしかない。このように、差別が日常的な慣習と区別されるものではないために、非難された差別者の弁明(「わざとやったのではない」「そんなつもりでいったんじゃない」)は悪質な言い訳や言い逃れに聞こえてしまう。これがさらなる非難を呼び起こしてしまう。

空欄【 】には、「非対称性」という語が入ります。
その根拠は、直後にある
差別者は差別を差別だと認識していない。
そのため、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くさなければならない。
というところです。
(a)「差別する側」は、自身の言動を「差別」だと意図していません。
(b)それに対して、「差別されている側」は、「これは差別だ」ということを「差別する側」に認識させなくてはなりません。
(a)と(b)の間には、次元の異なる「落差」があります。

ああ~。
「これは差別です!」/「これは差別ではない!」
という議論であれば、「対立」しているといえるけれど、
「これは差別だ!」/「え? え? どういうこと?(意図そのものがない)」
という状態は、「対立」にもなっていないね。

そうですね。
そもそも「同じ土俵に立っていない」状態になっているので、「対立以前」の状態だといえます。
いわば「つりあいがとれていない状態」だと言えますので、空欄【 】に入る語は、「非対称性」が最もよいといえます。
「対称」というのは「つりあいがとれている」ということであり、カタカナ語では「シンメトリー」といいます。したがって、「非対称性」というのは、「つりあいがとれていない状態」を意味していることになります。

他の選択肢の落ち度は?

「両極性」は、「両極として対立しつつも、他を自己のあり方の条件とし合っていること」を意味します。たとえば、電池の「プラス極/マイナス極」とか、地球の「北極/南極」などは、「両極」になりますね。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」は、前述したように「対立以前」の状態なので、「両極」とは言えません。
***********
「臨界性」は、「さかい・境界」のことなのですが、一般的に「臨界」という場合には、「物質がある状態から別の状態へと変化する、そのきわ」という意味で使用されます。いわば「変化前のぎりぎりのところ」というニュアンスです。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」のあいだに「変化前のぎりぎりの境界がある」とは言えません。
***********
「相補性」は、「相互補完性」のことであり、「お互いが補い合っている関係」を意味します。ある意味「公平な関係」であると言えます。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」は、「お互いが補い合っている関係」ではありませんし、「公平な関係」とは言えません。
***********
「非連続性」は、「つながりがないこと」です。
「差別を意識していない者/差別を受けていると思っている者」は、「つながりがない」とは言えません。たとえばですが、昨日まで「差別側」にいた人が急に反省して、「差別を受けている側のつらさを訴える側」に回る可能性もあるわけです。そういう点で、両者は「断絶」しているわけではありませんから、「非連続性」とまでは言えません。
〈補問〉傍線部(b)「新しい差別を発見する/発見させる行為」とはどういうことか。50字以内で説明せよ。

ここで、〈④段落〉の理解を深めるために、〈補問〉に取り組んでみましょう。
現代文の本質的な学習は「記述で書いてみること」です。「書いてみると内容面の理解が深まる」というのはよくあることです。
傍線部問題は、まず何よりも「傍線部を含む一文」をしっかり把握しましょう。予備校などではよく「傍線部をのばせ!」と述べる講師がおりますが、そのアドバイスのとおり傍線部をのばしてみると、「指示語」があったり、「同義表現」があったり、答案の〈核心〉となるヒントを発見することがあります。
差別をめぐって、差別者と被差別者にはいちじるしい非対称性がある。差別者は差別を差別だと認識していない。そのため、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くさなければならない。この意味で差別批判とは、(b)新しい差別を発見する/発見させる行為である。しかし、いっぽうで差別者からすれば、差別と認定される自身の言動は悪意のない、「普通」「あたりまえ」のことであり、取り立てて問題にする必要のないものでしかない。このように、差別が日常的な慣習と区別されるものではないために、非難された差別者の弁明(「わざとやったのではない」「そんなつもりでいったんじゃない」)は悪質な言い訳や言い逃れに聞こえてしまう。これがさらなる非難を呼び起こしてしまう。

「この意味で」という指示語がありますね。
この問題は、この「指示語」を解決することが〈核心〉です。
「記述」であれば、「この」が指している内容を書かなければなりません。「選択肢」であれば「この」が指している内容をふまえていない選択肢はすべて×です。
ざっと下書きを書くと次のようになります。
下書き
差別者が差別と認識していない行為に対し、被差別者(差別を受けている側)が、差別と認識させること。

選択肢問題であればこのくらいで照合していけば正解を選べると思います。
〈本問〉の〈問3〉の選択肢を検討しましょう。
〈問3〉選択肢の検討
1 差別を認識し、批判できるのは被差別者だけであるということを被差別者自身が認識し、差別者の言動の悪質さを差別者に認識させること。

たしかに、「差別を受けた側が声をあげていかなければならない」という主旨のことが語られていますが、「批判できるのは被差別者だけ」と限定してしまうのはおかしいです。たとえば、ある「差別ー被差別」の関係を外部から見ていた人や組織が「それは差別ですよ」と指摘するケースもあるでしょう。〈言い過ぎ(限定しすぎ)〉で×です。
また、「差別者に認識させること」は、「その行為が差別である」ということであり、「悪質であるかどうか」は異なる話題です。〈論点が違う〉で×です。
2 被差別者が差別だと感じている言動は、差別者には「普通」「あたりまえ」のことであり、差別者には差別意識はないと被差別者が認識すること。

ここで問われていることは「その先」のことです。
差別者が「意図せず」に行っている行為が「差別である」と認識させる
という論点が必要です。
〈核心不在〉で×です。
3 被差別者が差別だと認識しているにもかかわらず、差別者が差別であると認識していない言動について、それが差別であると差別者に認識させること。

「下書き」の内容と整合しています。正解です。
4 被差別者が差別だと認識している言動について、差別者がいくら弁明をしても、それは悪質な言い訳に過ぎず、弁明は無意味であると差別者に認識させること。

ここで問われていることは「その前」のことです。
差別者が「意図せず」に行っている行為が「差別である」と認識させる
という論点が必要です。
〈核心不在〉で×です。
選択肢4については、〈本文根拠なし〉とも言えます。
5 差別者の日常的な行為こそが差別であると認識するのは被差別者だけであるため、それを差別者に自覚させるのは被差別者の役割であると被差別者が認識すること。

ここで問われていることは「その先」のことです。
差別者が「意図せず」に行っている行為が「差別である」と認識させる
という論点が必要です。
〈核心不在〉で×です。
記述の仕上げ

では、これが「記述問題」である場合に、どのように仕上げていくべきか考えていきましょう。

仕上げ?

記述問題は、大学によって採点基準も違いますので、「どこまで書けばOKか」というのは判断しにくいところなんですよね。
ただ、「どういうことか」の問題の場合、
(1)傍線部内の語句は極力無視しない(言及する)。
(2)可能であれば言いかえる。
という基本姿勢を反映させるほうがいいですね。
その点で、先ほどの「下書き」は、傍線部内の「新しい」と「発見する」が無視されてしまっています。できれば、「無視していません」という姿勢を示せるといっそうよいですね。
「新しい」はそもそも「客観的な語」であり、それ以上平易に説明することが難しいので、そのまま「新しい」と書いても大丈夫ですが、「発見する」のほうは、それが文脈上どういう行為を意味しているのかを取り出せたほうがいいです。
その観点で直後を見てみると、「取り立てて問題にする」という表現があります。「差別を発見する」というのは、文脈上「差別を取り立てて問題にする」ことと一致しますので、ここを使用できるといいですね。
記述解答例
差別者が差別と認識していない行為に対し、被差別者が取り立てて問題にし、初めて差別と認識させること。

ああ~。
「取り立てて問題にする」という論点を入れると、「発見する」に言及したことになるし、「初めて」などと書いておけば、「新しい」に言及したことになるね。

「取り立てて問題にする」は、同段落内にある表現なので、迷わず使用して大丈夫です。
「新しい差別」の「新しい」は、それを言いかえた表現が周辺にないので、答案内で言及するのはちょっと難しいですね。「新しい」とそのまま書いても減点はされませんが、文脈が変わらないように気をつけて、「新たに」とか「今までにない」などと書いておくといいですね。
傍線部内の「新しい」を、「新たに」と言い換えるのは、「ほとんど同じだろう」と思うかもしれませんが、ここは〈核心〉ではない部分ですし、前述したように「新しい」のまま書いても問題ない語といえますので、ガラッと言い換えなくて大丈夫です。

ふむふむ。
別解(発展的答案)
差別と認識されていない行為を、被差別者が新規の差別として可視化し、行為者に差別と認識させること。
*「可視化」は「顕在化」などでもよい。

得点は同じなのですが、「新しい」を「新規」、「発見する」を「可視化」などとする手段もあります。これは、「熟語にして書く」という応用テクニックです。
難関国立の問題などでは、このテクニックがないと字数に収まらない問題などもあるので、「あ、こういう方法もあるんだ」と知っておくといいですね。
いずれにしても、「今まで取り上げられてこなかった差別」は、「被差別者(差別を受けている側)」が、「これは差別ですよ!」と「可視化」して、比喩的にいえば「差別のカタログ」に「新規登録」しないといけないのですね。
「可視化」というのは、「見えるようにすること」です。この文脈であれば「顕在化」などと言うこともできますね。
ところが、「差別している側」は、そもそも「差別しているつもりがない」ので、「そんなつもりじゃない」と弁明することが多くなります。ところが、多くの場合「そんなつもりがなかったならいいんですよ」とはなりませんね。

ああ~。
「そんなつもりはなかった」とか、「気分を害してしまったとしたらすみません」とか言うと、
「それは無神経すぎる!」とか、「やれらた側が気にしすぎってことですか?」とか、さらなる非難につながっていくおそれがあるね。

では〈⑥段落〉に行きましょう。
⑥段落(前半)
ここでは近代的な法(刑罰)が前提とする「責任」の考え方がくずれている。差別においては、行為者の意図や予見可能性を考慮して「責任」の重さを考えることができない。差別者は、たいていの場合、差別を差別だと認識していないからである。これにたいして、反差別運動は被差別者が「足の痛み」を感じるかぎり、行為者に「責任」があるとみなしてきた。「責任」があるかどうかを決定するのは、行為者(とその周囲の状況)ではなく、その行為の影響をうけた人物なのである。このように、反差別運動において、法的な「責任」の考え方、(c)責任の成立機制が転倒されたことで、「自律」的「個人」=「市民」による無自覚な、意図せざる差別の「責任」を追及することが可能になった。

まず「前提」という語に注意しましょう。
「前提」という語は、この文章の〈①段落〉に登場していました。
①近代的な法は「自律」的な「個人」を前提にしている。

〈①段落〉で述べられていたことは、
近代的な法においては、行為者の意図や予見可能性を考慮して「責任」の重さを考える
ということでした。たとえば人を傷つけたとしても、「意図的」であれば「傷害」になり、「意図的」でなければ「過失致傷」になります。
〈⑥段落〉で述べられることは、この「前提」が「差別問題」においてはくずれている、ということになります。2つめの文にはズバリ、
差別においては、行為者の意図や予見可能性を考慮して「責任」の重さを考えることができない。
と書かれています。
ここを把握したうえで、〈補問〉を解いてみましょう。
〈補問〉傍線部(c)「責任の成立機制が転倒された」とはどういうことか。80字以内で説明せよ。

傍線部を上にのばしてみると、「このように」という「要約系の指示語」があります。
〈要約系指示語〉
このように・そのように
このような・そのような
こういう・そういう
こんな・そんな
こうした・そうした
といった指示語がある場合、それらは前の部分を「広く」指してまとめている。

さらに、傍線部内の「転倒」という語にも注意しましょう。
「転倒」というのは、「本来の順序がさかさになること。ひっくりかえること。」を意味します。
そのため答案では、「何」と「何」がさかさになったのかを説明しなければなりません。
ここは、「もともとの近代法の責任の考え方」と、「差別における責任の考え方」を示して説明すれば、「転倒」の内容に踏み込んだことになります。
ざっと下書きをつくると次のようになります。
下書き
近代的な法は、行為者の意図や予見可能性を考慮して責任の重さを考えるが、差別問題では、行為の影響を受けた人物が行為者の責任を考えるということ。

選択肢問題であれば、このへんで選択肢の検討に入りましょう。
〈問4〉選択肢の検討
1 近代的な法においては、差別は政治や経済といった「構造」の問題とされたが、反差別運動においては、人間性や内面の問題として捉えられた上で行為者の責任が問われるようになったということ。

「このように」の指す内容とは別のことを述べています。
〈核心不在〉または〈本文根拠なし〉で×です。
2 近代的な法においては、責任の重さは行為者の意図や予見可能性によって変わると考えられてきたが、反差別運動においては、行為者ではなく行為の影響を受けた人物が行為者の責任の有無を決定するという発想になったということ。

解答に必要な本文内容と整合しています。
正解です。
3 近代的な法においては、被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くす責任を負っていたが、反差別運動においては、被差別者が痛みを感じるかぎり行為者に責任があると見なされるようになったということ。

「被差別者は差別を差別だと認識させるために、あらゆる手立てを尽くす」というのは、「近代的な法」の話ではなく、「差別問題」の話です。
〈対比関係の取り違え(組み合わせのミス)〉で×です。
4 近代的な法においては、行為者が日本人であるかどうか、男性であるかどうか、健常者であるかどうかといったアイデンティティは責任を問う上で全く考慮されていなかったが、反差別運動においては、それが重要な要素となったということ。

「差別問題」においては、「行為者のアイデンティティ(帰属性)」も重要な要素になりますが、この「行為者のアイデンティティ(帰属性)」は、そもそもの「近代的な法」においても無視できない要素です。そのため、「全く考慮されていなかった」が〈本文根拠なし〉で×です。
そもそも〈核心不在〉です。
5 近代的な法においては、行為者が責任を問われる事態は、その行為によって誰かが肉体的苦痛を受けた場合が主に想定されていたが、反差別運動においては、精神的苦痛や社会的・経済的な不利益もふくまれるという発想になったということ。

これも〈選択肢4〉に傾向が似ている選択肢です。
「反差別運動」においては、「肉体的苦痛」だけでなく、「精神的苦痛や社会的・経済的な不利益も含まれる」と書かれているのはたしかですが、それが「近代的な法」のほうに存在していなかったわけではありません。そのため「肉体的苦痛を受けた場合が主に想定されていた」とまでは言えません。
そもそも〈核心不在〉です。
記述問題の仕上げ

では、記述問題の「仕上げ」をしていきましょう。

「傍線部内の各要素について、何らかのかたちで言及はしておいたほうがいい」というやつだな。

そうです。
実際には「重要でない表現はカット」でもいいのですが、字数が許すのであればまんべんなく「言及」しておいたほうがいいですね。
大学名出してしまいますが、特に京都大学などはこういう作業が必要になります。
「責任」は、これ以上わかりやすくできない客観的な語なので、このまま出してOKです。ただ、傍線部内の語をそのまま出す場合には、「行為者の責任」「差別者の責任」とか、何かをくっつけて、より厳密に規定したほうがいいです。
さて、「成立機制」「転倒」あたりは、言い換えて出しておきたいですね。
「機制」は、「仕組み」「機構」のことなので、「成立機制」は、「成り立たせる仕組み」とか「決定する制度」などと書くことができます。
「転倒」は、「逆に」「反対に」といったように、「逆転した」という意味合いを出せるといいですね。
そうすると、次のような答案になります。
記述解答例
近代的な法は、行為者の意図や予見可能性を考慮して責任の重さを考えるが、差別問題では逆に、行為の影響を受けた人物が行為者の責任の有無を決める仕組みになったということ。
⑥段落(後半)
「足の痛み」には、肉体的苦痛だけではなく精神的苦痛、社会的・経済的な不利益もふくまれる。また、行為者のアイデンティティ(日本人、男性、健常者等々)も差別か否かを判断するための重要な要素となる。差別を禁止する法の制定は、ヘイトスピーチなど明確な差別表現には有効かもしれないが、反差別運動が法の根拠やその正当性じたいを問い直す運動だったことを考えれば、差別を禁止する法とは矛盾でしかない。

〈⑥段落〉の後半はかなり難しいことを述べていますね。
今日のメインは「記述解答例」を考えることなので、ここの解説は次回にまわします。