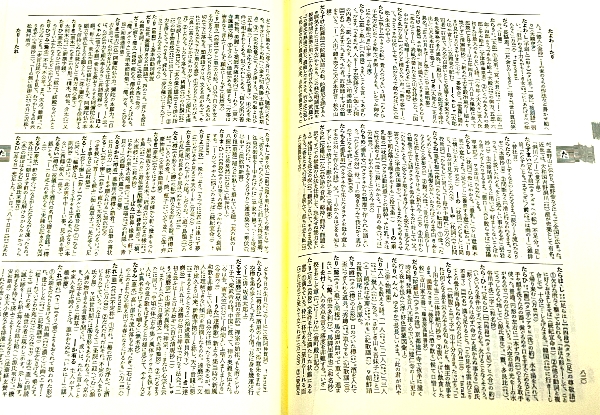おさらい

〈第①段落〉~〈第⑦段落〉の内容は、概ね次のようなものでした。
近代の法制度(刑法)においては、「行為者(加害者)」の側の「意図のある/なし」や「未来予見性のある/なし」などによって、「責任の有無」や「罰則」が決められていた。しかし、「差別問題(反差別運動)」においては、逆に「行為の影響を受けた側(被害者側)」が、「行為者の責任」について判断するようになった。

本文にきっぱり「刑法」と書いてあるわけではありませんが、「罰則」という表現があることなどから、「刑法」の話をしているのだと考えます。
〈第⑦段落〉の最後には、この「責任観」によって、問題が生じているという問題提起がありました。その「問題」については、〈第⑧段落〉から明らかになっていきます。
第⑧段落
この点にかんして社会学者の北田暁大が興味深い指摘をしている。北田は、近代的な法における責任観を「弱い責任理論」、差別批判における責任観を「強い責任理論」と整理している。北田は「強い責任理論」を「近年日本でも注目を集めている他者性の政治学/差異の政治学/承認の政治学といった知的潮流において展開されている他者論・責任論」とみなしている。そして、(e)北田は、「強い責任理論」が反公害運動や反差別運動において重要な役割を果たしたことを認めたうえで、「強い責任理論」を社会的規準として採用することに反対している。北田によれば、「とんでもない責任のインフレ」と呼ばれる状態に陥るのだという。少し長くなるが重要な指摘なので引用しよう。

評論文において、「対比」の概念が出てきたら「超重要」と位置付けて、その対比関係をつかみましょう。
ここでは、
弱い責任理論 ⇔ 強い責任理論
近代的な法に 差別批判に
おける責任観 おける責任観
という「対比」が起きています。

社会学者の「北田暁大」という人は、この「強い責任観」のほうを「社会的基準」とすることに「反対」しているんだね。

はい。
「被差別者(被害者)」の側が「差別者(加害者)」の責任の重さを判断する考え方を、「重要だ」とは思っていますけれども、それを「社会的基準として採用」することは「よくない」と思っているんですね。
「社会的基準として採用」というのは、「被害者側が〈レベル100〉傷ついたから、加害者側に〈レベル100〉の罰則」とか、そういう「基準」として制度設計してくことを意味していると解釈できます。

どうして「反対」しているんだろうね。

傍線部(e)の直後には、
「とんでもない責任のインフレ」と呼ばれる状態に陥るのだという。
という「のだ文」がありますね。
「のだ文」は、「理由の文」として機能することもあります。
「インフレ」は「膨張」という意味ですから、「責任がどんどん膨れ上がってしまう」ということを述べていると考えられます。
直後にそのことを説明しているとみられる引用がありますので、確認していきましょう。
「何をしたことになっているのか」の定義権を行為解釈者に委ねることによって、水銀をたれ流す企業の行為責任の剔出(てきしゅつ)に成功した「強い」〔責任〕理論は、一方で、指を動かし料理をしただけで「世界の秩序を乱した」ことにされてしまう魔女たちの責任をも承認してしまうのであった。もちろん、こうした魔女たちの災難は、何も宗教的なコスモロジーによって因果関係の知が規定されていた時代特有のものとはいえない。「社会が階級闘争で引き裂かれれば、ユダヤ人が労働者を扇動したと言われ」、「金融危機が起これば、ユダヤ人が金融制度を陰謀でコントロールして危機を引き起こしたと言われ」〔……〕続けてきた現代の「魔女」ユダヤ人のことを想起してもらえばよい。サルトルが『ユダヤ人』で鋭く指摘したように、すべての「悪しき」結果の原因をユダヤ人の行為に見いだす反ユダヤ主義の論理は、原因の除去という「善行」に専心することを鼓舞し、みずからの行為責任への反省を曇らせることとなる。このとき、反ユダヤ主義者たちはあくまで忠実に「強い」〔責任〕理論を己が行動原理として行為していることに注意しよう。魔女狩りを禁じえない責任理論の行き着く先は、無理やりにでも「悪い」出来事の原因を誰かの行為に見つけだし、自らの行為の責任をやすんじて免除する、壮大な無責任の体系とはいえないだろうか。(『責任と正義』)

水銀をたれ流す企業の行為責任の剔出(てきしゅつ)に成功した
という部分は、「水俣病」の訴訟についてのことを述べています。
被害を受けた被害者側が、メチル水銀を垂れ流した企業の責任を訴え続けたことによって、「企業の責任」という結論が出た大きな事件でした。
「強い責任論」にもとづいて、「被害を受けた(と感じる)側」から「責任者」を追及していくことは、重要な運動になるのです。

ああ~。
たしかに「公害問題」なんかは、「被害を受けたと感じる側」が「自分たち以外のどこかに責任がある」という前提で運動しなければ、「加害行為」を発見することができないよね。

そのとおりです。
しかし、こういう「強い責任観」には問題もあります。北田はここで「魔女狩り」について言及しています。
中世のヨーロッパでは「魔術」によって人に害をなすことを危険視し、その疑いをもつ者を次々と迫害していったことがありました。ペストが流行したときなどは、ハーブの知識がある女性が人々の健康増進に活躍したのですが、男性医師たちは、生命に関わる仕事は神職者がおこなうべきとする神学的立場から、ハーブを用いた調理をする女性たちを危険視します。
他にもいろいろな経緯があるのですが、「神職者以外が生死にかかわる医療行為を行った」「そこには魔術がほどこされていたのではないか」という「言いがかり」をつけて、ハーブを用いて料理を担う女性を「魔女」とみなして弾圧する時代がありました。疫病の流行そのものが、この「魔女」のせいにされたりもしたのですね。
こういった事象に似たことが大規模で起きたのは、第二次世界大戦中の「ユダヤ人迫害」です。特にナチスドイツは、世界の混乱の原因を「ユダヤ人」に見出そうとしました。
当然ながら、世界の混乱の原因は「魔女(とみなされた人)」のせいでも「ユダヤ人」のせいでもありません。しかし、「世界が傷ついたのはあいつらのせいだ」という言説は当時は信じられ、実際に「魔女(とみなされた人)」も「ユダヤ人」も厳しい迫害を受けました。
さて、「誰かに責任をなすりつけている」うちは、「責任を追及している側」は「責任を免れる」ことができます。つまり「無責任な立場」でいられることができるのです。
社会学者の北田暁大が「強い責任理論」を社会基準に採用することに反対する理由はここにあります。
「何かのマイナスな現象」が起きた時に、「これはあいつのせいだ! 罰則を与えよ!」と「責任追及」することが「当たり前」になり、実際に「ではあの人には罰則100、あの人には罰則200」という社会になっていくと、「責任がある」とみなされる人は膨大に増えていき(インフレが起こり)、一方では、「批判している側」は「無責任な立場でい続ける」という「壮大な無責任」の体系が構築されていく危険があります。
問6 傍線(e)「北田は、「強い責任理論」が反公害運動や反差別運動において重要な役割を果たしたことを認めたうえで、「強い責任理論」を社会的規準として採用することに反対している」とあるが、それはなぜか。その説明として最も適切なものを次の中から一つ選べ。

引用の内容をふまえて、〈問6〉の選択肢を検討しましょう。
なお、傍線部(e)の直後に
北田によれば、「とんでもない責任のインフレ」と呼ばれる状態に陥るのだという。
という「のだ文(統括文)」がありますので、この「責任のインフレ」の話題に言及していない選択肢はすべて×です。
選択肢検討
1 「強い責任理論」を導入すると、行為者が結果を予見できた場合にしか、差別の責任を追及できないことになってしまうから。

「責任のインフレ」の論点がありませんので、〈核心不在〉です。
また、〈選択肢1〉の説明は、従来の「弱い責任理論」に該当するものなので、〈逆〉の説明とも言えます。
2 「強い責任理論」が「道徳的行為・態度選択の指針を与える規範理論」として採用されると、壮大な無責任の体系が広がり、アイデンティティ・ポリティクスも反差別運動も消滅するから。

「壮大な無責任の体系」という論点の言及はありますが、「アイデンティティ・ポリティクスも反差別運動も消滅する」という説明は筆者の主張と異なります。
「アイデンティティ・ポリティクス」というのは、(このあと説明しますが)「何らかのアイデンティティをもとに結束した集団による政治活動」のことです。
〈第⑨段落〉によれば、「強い責任理論」がまかりとおると、この運動はますます拡大していくことになります。
(*そもそもこの設問は「北田」の意見を聞いているわけですから、「北田」の意見をふまえて「筆者」が意見を展開している部分ではじめて出てくるワードを安易に用いるべきではありません。)
3 「強い責任理論」は、悪徳企業やヘイトスピーチを行うマジョリティの責任の追及には成功したが、結果の意図性や原因が特定できない社会問題に対しては、現状では有効性が認められないから。

「壮大な無責任の体系」について言及していないので〈核心不在〉です。
また、「強い責任理論」が「結果の意図性や原因が特定できない社会問題」に対して「現状では有効性が認められない」とは述べられていません。
北田はむしろ「有効性があるからこそ、社会に負の影響がある」という心配をしています。
4 「強い責任理論」においては、社会に起こる問題の責任が行為の解釈者によって追及されることになり、差別者も自らを被差別者であると主張できるようになることで、無責任の体系が広がっていくから。

引用文の内容に整合していますし、「無責任の体系」にも言及しています。
落ち度がないので、これが正解です。
5 「強い責任理論」に基づいて社会の問題を解決しようとすると、「不快」という精神的な苦痛が問題視されるようになり、行為者への責任追及ではなく、苦痛を生み出す経済的・社会的背景に原因を見出すようになるから。

「壮大な無責任の体系」について言及していないので〈核心不在〉です。
また、「行為者への責任追及ではなく」が「逆」です。
自分のことは棚に上げて、「行為者への責任追及」ばかりが乱発されることで、むしろ「加害者側」が「被害者側」を「行為者」とみなし、そこに「責任」をなすりつけるような状態になってしまうことを北田は心配しています。
第⑨段落(前半)
つまり、北田は、魔女狩り・ユダヤ人排斥という不当な論理を排除できないという理由から、(4)「強い責任理論」を、「道徳的行為・態度選択の指針を与える規範理論」としては採用できないと退けている。

「つまり」というのは、前段落の引用文を受けています。
ちょうど、この〈傍線部4〉は、引用の前にあった〈傍線部e〉と同義関係になっています。
〈ポイント〉
具体例(引用)の「前」と「後」は、「同義表現」または「因果関係」になりやすい。

〈確認問題5〉で問われていますので、選択肢を検討しましょう。
〈確認問題5〉傍線部4「『強い責任理論』を、『道徳的行為・態度選択の指針を与える規範理論』としては採用できない」とあるが、北田はなぜこのように考えるのか。適切でないものを次から選べ。
選択肢検討
ア 指を動かし料理をした者を「世界の秩序を乱す魔女」だとする言説を否定できなくなるから

引用文中で説明されていたことと整合しています。
イ 実際に水銀を垂れ流して自然や人体に害を与える企業の行為責任を問うことができなくなるから

これは北田が指摘している「問題点」にはあたりません。
むしろ傍線部(e)で述べられていた
「強い責任論」が反公害運動や反差別運動において重要な役割を果たした
というところに該当します。つまり、北田自身も「重要」と認めている内容にあたる「例示」であると言えます。
この「水銀」の話題があるところの前後の文脈を見ても、
水銀をたれ流す企業の行為責任の剔出(てきしゅつ)に成功した「強い」〔責任〕理論は、一方で、指を動かし料理をしただけで「世界の秩序を乱した」ことにされてしまう魔女たちの責任をも承認してしまうのであった。
とありますので、構造として、「魔女狩り」の話とは「対比」されていることになります。
したがって、「水銀の話」は、北田が「強い責任理論」を「規範理論としては採用できない」とする理由にはあたりませんので、この〈選択肢イ〉が「適切でない」ものとなります。
これが正解です。
ウ ユダヤ人が金融制度をコントロールして社会危機を引き起こしたという理論を排除できなくなるから

引用文中で説明されていたことと整合しています。
エ 「悪い」出来事の原因を他者に見出すことで、誰もが自らの行為の責任を免除することができるから

引用文中で最後に指摘されていた「壮大な無責任の体系」の説明として適格です。
第⑨段落(後半)

〈第⑨段落〉は、「ところで」という「転換」のディスコース・マーカー(論理の流れを示す目印)から始まりますので、「主張が発展」するはずです。
そのつもりで読み進めていきましょう。
ところで、そのような「強い責任理論」が「道徳的行為・態度選択の指針を与える規範理論」として採用され、「責任のインフレ」が起こり、「壮大な無責任の体系」が広がっているのが現状ではないだろうか。『責任と正義』は二〇〇〇年代初頭の著作だが、北田はマジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスの問題を予見していたといえる。引用文の「反ユダヤ主義者」を「トランプを支持した白人男性」に、「ユダヤ人」を「移民」に入れ替えれば、いま私たちがポリティカル・コレクトネスをめぐって直面している状況である。(f)かつてマイノリティのものだったアイデンティティ・ポリティクスの「責任」観は、いまやマジョリティによって簒奪(さんだつ)されている。トランプ大統領は、アメリカにおける白人男性の「足の痛み」は移民という行為が招いたものであり、移民たちに「痛み」の「責任」がある、と主張した。かつて差別者の「責任」の追及を可能にした当事者の「足の痛み」は、フェイクや妄想が入り混じった主観的な「足の痛み」にかわっている。たとえば「逆差別」という言葉が知られるように、いまやマジョリティが「被差別者」のようにみずから振る舞い、マイノリティの「責任」を追及するのである。

「アイデンティティ・ポリティクス(アイデンティティ政治)」とは、「ジェンダー、人種、民族、性的指向、障害などの特定のアイデンティティに基づく集団の利益を代弁して行う政治活動」ことです。「何らかの共通のアイデンティティになるものを持った人々が、共通の政治的目標で結束すること」なのですね。
たとえば小池都知事が、都知事選において「都民ファースト」と繰り返し述べたことは、「他県の人よりもまずは東京都民を大切にする」という意味であり、一種の「アイデンティティ・ポリティクス」だと言えます。
次に出てくる「ポリティカル・コレクトネス」とは、「特定の集団の構成員に不快感や不利益を与える表現をなくそうとすることです。代表的には「人種、信条、性別、体型などの違いに対して、偏見や差別を含まない中立的な表現を使用すること」を意味します。たとえば、「サラリーマン」を「ビジネスパーソン」と言い換えたり、「看護婦」を「看護師」と言い換えたりすることは、「ポリティカル・コレクトネス」の一例です。「サラリーマン」という表現には「女性」が含まれていませんから「女性差別」になります。一方、「看護婦」という表現には「男性」が含まれていませんから「男性差別」になります。
この「ポリティカル・コレクトネス」の実例が増えてきた理由は、「嫌な思いをしている側」が「嫌だ」と訴え続けてきたからです。つまり、「嫌な思いをした」と「主張すること」が、実際に社会構造を変える力を持ってきたのです。したがって、「ポリティカル・コレクトネス」の背景にあるのは、「嫌な思いをしたのだから、相手が悪いはずだ」と言えるということであり、「嫌な思いをしたと訴えることで対立する相手をやりこめることができる」という「新しい考え方」なのです。

ある意味では、ちょっと「言ったもん勝ち」みたいなところあるよね。

これが本当に「弱者(少数派)」から提出されている「嫌だ」なのであれば、「差別されている側を救う運動」になりますので、大切なことです。
しかし、この「嫌だと思った」という「主張」は、「強者(多数派)」から出すことだって可能なのです。
たとえばですけど、「強者」って、「言うこと聞くはず」と思っている相手が、言うことを聞かなかったりすると、「独特の被害感情」を持つんですよ。「私の言うことを聞いてくれるはずの人が聞いてくれなかった」という「嫌な思い」を持つんですね。会社の「いやな上司」にこのタイプがけっこういます。

ああ~。
本当は「加害者側」のくせに「被害者のふり」するのがうまい人って、ドラマでよく出てくるよね。

「本当に自分が被害者だと思い込んでいるパターン」もありますよね。
実際には「自分が他人の尊厳を踏みにじってむちゃくちゃな要求をしている」だけなのに、相手が「さすがに無理です」と拒否すると、「要求を受け入れられなかった私ってかわいそう」となってしまう。
これってそもそも「相手が要求を聞くはず」と思い込んでいる時点で相手をかなり見下しているんですけど、本人にはその自覚がなくて始末が悪かったりします。
このように、「私は傷ついた。だからあんたが悪い」と主張する方法論は、「強いほう」から提出することも可能なのです。そこに問題があります。

ああ~。
「傷ついた。だからあんたが悪い」と主張する方法論は、これが本当に「少数派(弱者)」からの訴えであれば、社会を平等に近づける運動だと言えるよね。
でも、「多数派(強者)」からの訴えがまかりとおってしまうと、もともとは弱者が強者に対して一矢報いるためのものだった手段が、「多数派(強者)」に「逆利用」されてしまっていることになるよね。

まさにそうなります。
本文に出てきた「アイデンティティ・ポリティクス」という政治活動は、もともとは「弱者が結束して、自分たちの権利を主張するための活動」なのですね。
たとえば、「会社員」の中では数的弱者になる「女性」が「女性というアイデンティティ」のもとに結束して女性の権利向上を目指したり、「同性同士で婚姻関係を結びたいと思っているパートナーの集団」が「同性婚を求める運動」をしたり、様々な活動があります。政治家などがそれらの主張を代弁することも「アイデンティティ・ポリティクス」です。その運動のなかで、たとえば、「サラリーマン」「ファイヤーマン」といった呼称は「女性の会社員」「女性の消防士」を排除した言い方で差別的なので、「ビジネスパーソン」「ファイヤーファイター」としていこうというように「表現」を変えていくことが「ポリティカル・コレクトネス」です。
つまり、「アイデンティティ・ポリティクス」の運動も、その過程で起こる「ポリティカル・コレクトネス」のはたらきも、もとは「マイノリティによる、マイノリティのためのもの」なのです。
ところが、本文では「マジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスの問題」と述べられていますね。
これは、「私たちは傷ついた。ゆえに相手が悪い」という、本来であれば「マイノリティ」から「マジョリティ」に訴えかけるための論法を、逆に「マジョリティ」が「マイノリティ」を攻撃する手段として使用していることを意味しています。
たとえば、「電車に女性専用車両があるって、男性差別だよな。俺、傷ついちゃったよ。」といったことを「男性」が言い出すのは、「マジョリティによるアイデンティティ・ポリティクス」の例です。

電車に「女性専用車両」があるのは、長い歴史の中で女性がいやな思いをし続けてきたという「差別問題」を一定量緩和させる「手法」であるのに、「長い間いやな思いをさせてきた側」の「男性」が、その背景にも目を向けずに「そんな車両があっていやな思いをした」と言うのは、ちょっと問題があるよね。

大きな問題があります。
しかしながら、「傷ついたこちらが被害者であって、被害者がいるということは、加害者がいる。責任者を出せ」という「手法」は、ある意味「誰でも採用できる方法」なのですね。
傍線部(d)で述べていることは、そういう「手法」を「多数派」が取るようになったということです。
アメリカでは大統領選挙のときにトランプがこの手法を用いました。

ほほう。

たとえば、アメリカはもともと「移民」によって成立している国なので、本来は多くの移民で成立しています。
ところが、人口増加や経済不況の影響もあり、徐々に「移民の枠」を「絞る」ようになっていきます。「アメリカに一定期間住んでいる層」からしてみると、「移民」は「邪魔者」になっていくのですね。
「マイノリティ」である「移民側」からすると、「アイルランドなまりは汚い」とか「メキシコ人は野蛮」などとレッテルを貼られて排斥されることは「差別」にあたりますから、「出身地域」などを拠り所に結束して「反差別運動」をします。これはもともとあった「少数派による反差別運動」です。
ところがトランプは、「移民がたくさん来ることによって、もともといた人々に回すための福祉費用が足りなくなっている」とか「移民による犯罪も増えて、もともといた人々の安全が脅かされている」といったように、「もともといた人が傷ついている。ゆえに移民は加害者だ」という論調をとりました。これで「もともといた人」は「対移民(対少数派)」で結束を強めて、トランプにかなりの票が入ります。
この例などは、「本来は少数派の手段であった方法論を、多数派が逆利用した例」の典型だと言えます。
ここまでの展開をおさえて、〈問7〉を解きましょう。
問7 傍線(f)「かつてマイノリティのものだったアイデンティティ・ポリティクスの「責任」観は、いまやマジョリティによって簒奪されている」とは、どういうことか。最も適切なものを次の中から一つ選べ。

「簒奪(さんだつ)」というのは、もともとは「帝王(君主)の継承権がない者が、帝王(君主)の地位を奪い取ること」を言います。
現在の一般的な用い方としては「権力を奪い取ること」とか、シンプルに「奪い取ること」という意味で使用されます。
この傍線部でいう「責任観」というのは、「傷ついた弱者がいた場合、傷つけた強者に責任がある」という「責任観」のことです。これまで、この手法を使用できたのは「弱者(少数派)」でした。ところが、この手法で責任を追及する論理が、むしろ「強者(多数派)」が「被害者サイド」に回って、「弱者(少数派)」に責任追及をするための手段として「奪われている」ということを述べています。
答案の〈核心〉としては、
(論点a)「傷ついた弱者がいた場合、傷つけた強者に責任がある」という「責任観」
(論点b)この責任観によって「弱者」は「強者」の責任を追及できた
(論点c)しかし、この手法が逆に「強者」の側に奪われている
という3ポイントになります。
選択肢検討
1 かつては、アメリカへの移民などのマイノリティは差別を受けやすいがゆえに救済の対象であったのに、現在では、白人男性などのマジョリティの生活を脅かす加害者となっているということ。

論点a・b・cがどれもありません。〈核心不在〉です。
また、結論部分は「加害者となっている」のではなく、「加害者とみなされている」と表現するほうが正確です。
2 かつては、マイノリティがマジョリティによって「逆差別」の責任を追及されていたのに、現在では、マジョリティのヘイトスピーチが「市民」の精神的苦痛の責任を問われるものとなっているということ。

「マイノリティがマジョリティによって「逆差別」の責任を追及されていた」というのは、「かつて」ではなく、「いま」のほうの話なので、不適当です。
後半も、傍線部が述べている「マジョリティがマイノリティの責任を問うようになった」こととは逆のことです。
3 かつては、マイノリティは差別の被害を訴えることができていたのに、現在では、マジョリティが主観的な被害を訴えることばかりとなり、マイノリティが主張することは許されなくなっているということ。

「マイノリティが主張することは許されなくなっている」とまでは言っていません。
「言い過ぎ」であり、不適当です。
また、「責任観」に該当する(論点a)や、「マイノリティの方法論をマジョリティがうばった」とする(論点c)がありません。
4 かつては、痛みは被害を受けた自分たちにしか分からないとして無自覚な加害者の責任を追及する主張は、主にマイノリティのものであったのに、現在では、マジョリティも唱え得るものになっているということ。

(論点a・b・c)にすべて言及できているので、これが正解です。
「マジョリティも唱え得る」くらいの説明ですと、「簒奪」のニュアンスをあんまり出せていないのですが、内容は間違っていないので、他の選択肢に比べると「よい」です。
5 かつては、マイノリティが客観的にも明らかな差別の被害を訴えていたのに、現在では、マジョリティがフェイクや妄想が入り混じった主観的な被害者意識からマイノリティの責任を問う声が大きくなっているということ。

かつてマイノリティが主張していた「差別の被害」が「客観的にも明らか」なのかどうかは不明です。
また、この選択肢は「責任観」に該当する(論点a)や、「かつてはマイノリティが被害を訴えるためのものだった方法論を、いまやマジョリティが利用している」という(論点c)がありません。
第⑩段落
たいして、「市民」たる自覚を持つ者たちから見れば、マジョリティによるヘイトスピーチは「安心」を損ない、「秩序ある社会」という「見かけ」を壊すものでしかない。「市民」の「尊厳」が傷つくことは、「不快」という精神的な苦痛と不可分であった。行為者の意図や予見可能性とかかわりなく、また、ヘイトスピーチがあらわれる経済的・社会的背景を考察することもなく、「不快」の責任を排外主義者らに帰責し(彼らの言動に起因するとし)、問いただす。差別主義者も、反差別主義者も、「足の痛み」の責任をたがいに追及しあう。いまや「差別における責任観」=「強い責任理論」が社会的な規準として採用され、「とんでもない責任のインフレ」が起こり、「(g)どこにでも責任があるがゆえにどこにも責任がない、無責任の体系」がひろがっている。

〈第⑨段落〉では、本来であれば「マイノリティ」が「マジョリティ」の有責性を追及するための手段が、「マジョリティ」が「マイノリティ」の有責性を追及するためのものに利用されてしまっているという話題がありました。
「多数派」が「少数派」を攻撃する手段になってしまっているのですね。たとえば「ヘイトスピーチ」というものは、社会の中で「多数派である集団」が、「少数派である集団」を排斥するために実施されます。
「『マイノリティ』のふるまいによって『マジョリティ』が『嫌な思い』をしたから、その件で『有責性』のある『マイノリティ』はこの社会から出ていけ」
などと攻撃するわけです。
しかし、この「マジョリティからマイノリティへの攻撃」という「行為」は、ある種の「いじめ」ですから、十分「社会秩序を乱している行為」になりますし、当然ながら「攻撃を受けるマイノリティ」は「不快」に思うことになります。
すると今度は「マイノリティ」の側が、「マジョリティにこんなことをされて不快になった(傷ついた)。この責任はマジョリティにある。責任をとって罰を受けよ」という運動を起こすことになります。

そうすると、もうお互いが「相手が悪い」と言っているだけの不毛な争いが頻発して、解決できない問題になってしまうね。

近年の人間関係のトラブルって、このパターンが異様に多いんですよ。
Aさんに、「どうしてBさんに嫌なことをしたのか?」と聞くと、「だって、Bさんが失礼なことをしてきたから」と答える。「それならば」と、逆にBさんに「どうしてAさんに嫌なことをしたのか?」と聞くと、「いやいや、先にAさんがいじわるをしてきたから」と答える。
これをずっと遡っていくと、「出どころ」がうやむやになって、「どちらが先」かがまったくわからなくなります。しかしながら、お互いが「向こうが先に嫌なことをしてきた」と思っています。
このパターンを調整するのが非常に困難なのは、「お互い」が、「やり返しただけだから自分に非はない」と考えているところです。「自分も〈15〉くらい悪かったかもしれないけれど、相手が〈先〉に〈85〉の悪いことをしてきたのだから、自分が謝る必要はない」と「お互い」が言うパターンが多いのですね。

うわあ。
これ「あいだに入って調整する人」が一番の被害者だよね。

社会全体でこういうことが大量に起きているんですよ。
「相手」に「責任」を追及できるぶんだけ、みんな「自分には責任がない(少ない)」と「言える」のです。
このことが問われているのが〈問8〉ですね。
問8 傍線(g)「どこにでも責任があるがゆえにどこにも責任がない」とは、どういうことか。本文に即して七十字以内(句読点を含む)で説明せよ。

傍線部内の「どこにでも責任がある」というのは、直前の「責任のインフレ」という表現が「言い換え」にあたります。
さらに直前にある「強い責任理論が社会的な基準として採用され」という部分にも言及して説明すると、次のような説明ができます。
行為者の意図や予見可能性ではなく、被害者側から相手の責任を追及する判断することで、あらゆる行為者に責任の所在が発生する

「どこにも責任がない」というのは、さらにその前に書いてある「帰責」という表現や「責任をたがいに追及しあう」という表現に注目しましょう。
そのように、問題の「責任」を「相手側」に見出そうとすることで、「追及している側」は責任逃れをし続ける、ということが書ければOKです。
そこまで入れてまとめると、次のような解答例になります。
記述解答例
行為者の意図や予見可能性ではなく、被害者側から相手の責任を追及することが膨大になるため、誰もが責任の所在を自分側には見出そうとしなくなること。

詰めきったあァーー!

採点基準としてはだいたい次のような感じです。
テキストについている「解答例」や「採点基準」とは少し違います。
〈論点a〉意図や予見可能性ではない (1点)
〈論点b〉被害者側から相手【行為者】の責任を追及する【判断する】 (3点)
〈論点c〉〈b〉のような行為が膨大になる【無限に繰り返される】 (3点)
〈論点d〉誰もが責任の所在を自分側に認めなくなる (3点)

こうなってくると、「追及する側」としては、ある意味「無敵の論法」になるね。

「相手」に「意図」があったかどうかは問題とされないので、「追及される側」が、一方的に「敵」とみなされて攻撃対象になってしまうと、いわば「負け戦」の状態になります。
たとえば、何か言葉をかけたら「その言葉に傷ついた」と言われる可能性があり、かといって何も言葉をかけなかったら「無視されて傷ついた」と言われる可能性があります。
実際に今の法律だと、小学生Aさんが小学生Bさんに「砂場で遊ぼう」と「言った」としても「言わなかった」としても、相手の取り方次第で「いじめ」に認定される可能性があります。ひとたび「あの人の行為で傷ついた」という「対象」にされると、何をしても(何もしなくても)有責性を問われてしまうのです。

もうこれ「おはよう」とかの「定型文」しか言えなくなるよね。

「この言葉で傷ついた」という「表現」を「そうではない表現」にしていくことが、本文で出てくる「ポリティカル・コレクトネス」という営みなんですね。
たとえば今の小学校では「あだ名禁止」にする学校がたくさんあります。「あだ名」で傷つく可能性があるからです。これも一種の「ポリティカル・コレクトネス」ですね。

男の子は「よしおくん」、女の子は「よしこさん」というみたいに、かつては「くん」「さん」で呼び分けていたものを、「さん」で統一しているのも「ポリティカル・コレクトネス」かな。

まさにそうですね。「男女差別」と受け取られかねない表現の「区別」を消しているわけですから。
また、たとえばですが、「おじさん」「おばさん」というのも状況によっては「差別語」になります。

そうすると一般的な年長者に対しては「先輩さん」「年配者さん」とかにしなきゃいけなくなるのかもね。

「先輩さん」はセーフとして、「年配者さん」は、「年をとっていることを揶揄している」と受け取られて相手が傷つく可能性があるのでアウトでしょうね。

良し悪しはおいておいて、「言葉」がどんどん消えていくわけだな。

「本来、悪い意味ではない言葉」までアウトになっていってしまう風潮は、社会にある種の「息苦しさ」を与えるでしょうね。
最近『不適切にもほどがある』というドラマがヒットしましたけれど、「昭和」から「令和」にタイムスリップしてきたおじさんは、発言の多くを「不適切」とみなされてしまうことに息苦しさを感じていました。
もちろん本当に「不適切」な発言は反省してもらわなければなりませんが、すべてを「不適切」としてしまう社会風潮にも「それはそれでおかしくないかな」と主張するようなドラマでしたね。
第⑪段落
しかし、人間は意図もせず、結果も予見できない行為の責任をとれるものなのか。差別主義者も反差別主義者もみずからを「足の痛み」を抱えた「弱者」だと相手に提示して、「責任」=「負債」を他者に負わせようとしている。ポリティカル・コレクトネスが社会を覆う状況にだれもが息苦しさを覚えるのは、「とんでもない責任のインフレ」=「無限の負債」を感じるためである。そのうっとうしさから逃れようと、すべての「負債」を肩代わりしてくれる犠牲の羊(スケープゴート)を探し出し、「魔女狩り」のように「炎上」させ、「自らの行為の責任をやすんじて免除する」ことが繰り返される。

「一方的な負け戦」になることを防ぐには、「自分も攻撃側になる」方法があります。
だから、「お互い」が「自分の方が被害者だ」という立場をとって、相手に「責任追及」を繰り返す争いが頻発します。そうすると、社会全体としては「こういう表現はNG」「こういった行為もNG」という「ポリティカル・コレクトネス」が随所で発生します。
これを筆者が「息苦しい社会」と述べているのは、その背景に「責任の膨張」=「無限の負い目」があるからです。
ときどき芸能人などが目立った行動(悪いとみなせる行動)をとると、いまの社会はSNSでもテレビ番組でもこぞって叩きますよね。これも、叩いているあいだは「攻撃側」にいられるからであり、「自分自身」の「ふだんの負い目」をいっとき忘れられるからなのかもしれません。

たいして悪いことしてない人もこともむちゃくちゃ言うもんね。

心理学的にみれば、「叩いている人」が「むちゃくちゃ弱い人」なんですよ。
「自分が攻撃を受ける側になるのが耐えきれないから、常に攻撃側に立とうとする」という屈折した心理傾向がはたらいていますからね。
もちろん、刑法にふれる「悪さ」をした人を「しかるべき人」が糾弾するのは大切なことですが、いまの日本は、刑法にふれていない芸能人でも平気でボコボコにしますからね・・・。
第⑫段落
行為者(の意図や予見可能性)ではなく、行為の結果を中心とする責任理論の転換は、近代リベラリズムにおける無自覚な差別を批判することを可能にした。しかし、いまやそのような責任理論は、マジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスに流用され、ポリティカル・コレクトネスをめぐる言説のうっとうしさの原因となっている。

〈第⑫段落〉は、いままでのことを繰り返してまとめているだけなので、特に新しい論点は出てきていません。
補足説明は以上です。