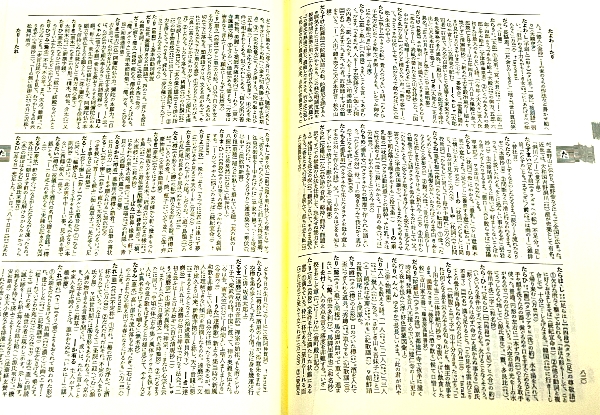「差別」の話の「第4回」になります。
今日は〈⑥段落〉の後半と〈⑦段落〉について考えていきましょう。
⑥段落(後半)
「足の痛み」には、肉体的苦痛だけではなく精神的苦痛、社会的・経済的な不利益もふくまれる。また、行為者のアイデンティティ(日本人、男性、健常者等々)も差別か否かを判断するための重要な要素となる。差別を禁止する法の制定は、ヘイトスピーチなど明確な差別表現には有効かもしれないが、反差別運動が法の根拠やその正当性じたいを問い直す運動だったことを考えれば、差別を禁止する法とは矛盾でしかない。

「足の痛み」という比喩は、
「加害者は意図していないけれども、被害者は傷ついている」ことを意味しています。
被害者(被差別者)の側が、「これは差別ですよ!」と言うことによってはじめて、「差別問題」は「議題」に上がります。
その「被害者側(被差別者側)」の「痛み」は、「身体の痛み」だけではなく、「精神的な痛み」も含まれますし、「出世しにくい・就職しにくい」といった「社会的」なものや、「十分な金銭的支援を得られない」といった「経済的」なものも含まれます。

「苦痛」にもいろいろなものがあるんだね。

さらに、「加行為者(差別者)」の「アイデンティティ」も重要な要素になります。
たとえば、プロ野球の「巨人ファン」が同じ「巨人ファン」の悪口を言っても、言われた側は「差別」とは感じにくいかもしれません。ところが、「阪神ファン」が「広島ファン」の悪口を言っていたら、「広島ファン」は傷つき、「差別だ」と感じるかもしれません。
つまり、「差別者」「被差別者」の「所属カテゴリー」が違うからこそ、「された側」は「差別」と感じやすいわけです。その点で、「行為者(差別者)」がどういう帰属性を持っているかというのは、「それが差別かどうか」を判断するときに重要な要素になります。

そうすると、「同じ発言」であっても、「誰が言うか」によって、「差別」とされることもあれば、「差別」とされないこともあるということになるね。
「同じ発言」であっても、「Aさん」と「Bさん」で「罪の重さ」が違ってしまうケースがたくさん出てくることになるね。

まさにそこが問題なのですね。
「Aさん」と「Bさん」が、どちらも「意図せず」に同じ「悪い行動」をした場合、「近代法」に基づければ「罪の重さ」は変わらないはずなのです。
ところが「反差別運動」は、そういった「法のあり方」そのものを「だめだ」と言っていることになります。「差別問題」は、「された側」が「傷ついたかどうか」によって、「罪の重さ」が変化してくるので、「同じ発言」であっても、「Aさんは無罪」だけど「Bさんは有罪」ということが発生しうるのですね。
そうすると、「ヘイトスピーチ」のような「意図的な差別」については、「法の制定」は意味がありますけれども、「無意識の差別」「意図的ではない差別」については、そもそも「された側」が「差別された!」と声を上げなければ「罪」として登録されないので、「法制度」のもとで「これこれこういうことをしたら有罪」という「ルール」を作れないことになります。
「これこれこういうことをしたら、人によっては有罪だけど人によっては無罪」って、法制度としておかしいですよね。
つまり、「それを差別とみなす」のが「被害者側」である「差別問題」は、「行為者」によって「有責性の強弱」がブレるので、「こういうことをしたら罪になる」ということを「誰にとっても例外なく定める」法制度とは「相反する考え方」になります。
本文ではそれを「矛盾する」と述べていることになります。

ああ~。
つまり「反差別運動」というのは、「法律の考え方がそもそもおかしい」と言っている側面があるんだね。

そうです!
「同じことをしたら誰でも同じように罰せられる」というのが「法制度」なのですが、
「反差別運動」の場合は、「同じ行為であっても、傷つく人と傷つかない人がいる。傷ついた場合のみ罰を与えよ!」と言っているのですね。

たしかに、
同じように「壁ドン」されたとして、「行為者がイケメンだったら傷つかないから無罪」「行為者がイケメンじゃなかったら傷つくから有罪」っていうことになるもんね。
「民法」ならいいけど、「刑法」としてそれを規定するのは難しいよね。

この文章では最初のほうに「罰則」という語が出てきましたね。
「罰則」を定めるのは「刑法」の話であり、この文章は「刑法」の話をしていると考えましょう。
「民法」は「主に人と人の利害関係が衝突したときに解決を図るための取り決め」であって、「罰則」がありません。
「民法」は、多くの場合、「損をしている側」と「得をしている側」が争って、その利害関係を決めるものなので、対立に敗れたからといって逮捕もされませんし、国家による罰則も受けません。
そういう意味で、「被害者(と思っている側)」が、「加害者(とみなせる側)」の責任の重さを主張するということは、「民法」ではよくあることです。
しかし、この文章では、「刑法」の制度において、「差別問題」については、「被害者側」が「加害者側」の責任を決定すると述べています。
それまでの法律の考え方では、「加害者側」の責任を決定するのは、「加害者側の意図」「加害者による未来予見性」「加害者のおかれた状況」などですから、「差別問題については被害者が加害者の責任の重さを判断する」という仕組みは、まさに「これまでの考え方が逆転している」ということになります。
⑦段落
反差別言説において、「内なる差別」「内なる偏見」「内なる優生思想」といった言葉がしばしば登場する。たとえば、相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で入所者一九人を刺殺し、入所者・職員計二六人に重軽傷を負わせた事件を扱った報道番組は「〝戦後最悪〟の障害者殺傷事件が投げかける「内なる偏見」と題されていた。これまで表面化しなかった差別や偏見の存在に社会や個人が気づいたときに、この(3)「内なる」という表現・レトリックがもちいられる。差別は無自覚な行為であり、社会においてしばしば日常的な慣習あるいは偶発的な言動のうちに起こる。たとえ差別を意図せず、その結果を予見できなかったとしても、私たちにはその責任(有責性)がある、とみなすために、「内なる」というレトリックがもちいられる。たとえば、一九七〇年代を中心に活躍し、新左翼が差別問題にコミットすることに大きな影響を与えた津村喬は、自身の著作『われらの内なる差別』(一九七〇年)は、「差別の構造化、構造の差別化」が重要だという問題意識から、当初「差別の構造」というタイトルだったが、出版社の意向によって「われらの内なる差別」に変更されたと述べている。そのために「人道主義」という「卑俗なレッテル」を貼られることになったとしている。いいかえれば、「内なる……」というレトリックによって、差別が政治や経済といった「構造」の問題ではなく、人間性や内面の問題として捉えられたわけである。このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。しかし、いっぽうで、(d)このような反差別運動を可能にした責任観が大きな問題をもたらしている。

「レトリック」とは「修辞」のことです。「修辞」とは、「ことばを工夫して表現すること」を意味します。

「レトリック(修辞)」にはどんなものがあるんだ?

たくさんありますが、もっともポピュラーなものは「比喩」ですね。
他には、「倒置」「省略」「反語」「皮肉」「擬人法」といったものですね。
いずれにしても「レトリック」というのは、「するすると平易に読んでほしくないところ」だと考えておきましょう。読者にちょっと「立ち止まってほしい」からこそ、こういう「素直ではない」表現を使用するのです。

なんで立ち止まってほしいんだろうね。

重要だからです。
重要だから「手の込んだ表現」をするのです。
ということは「レトリック(修辞)が施されているところ」というのは、「表現としてわかりづらいけれども、内容としては重要」という箇所になるのですね。
そのため、傍線部が引かれやすい箇所になります。

ところで、この傍線部は、
「内なる」という表現・レトリック
とあるけれども、この「内なる」という表現には、どんなレトリックが施されているんだ?

これは「比喩」とも言えますし、「省略」とも言えます。
そのどちらも施されているとも言えます。
ここでは、「内なる差別」というのは、「差別の気持ちが一人一人の心の内側にある」ということを意味していますから、「内」というのは「個々人の心の中」を示しています。
「心の内側」とか、「精神の内部」というように「ことばを補う」ことで言っていることが伝わるので、「省略」が起きているということです。
また、「心」の「内部」に「差別・偏見・優勢思想」が「ある」というのは、人間の心的世界(精神世界)を「容器」のようにみなしていることになります。これは一種の「比喩(隠喩・暗喩)」ですから、「レトリックとして比喩(隠喩・暗喩)がほどこされている」と言うことができます。
〈補問〉傍線部(3)とあるが、「内なる」という表現は、どういうことを意味しているか。40字以内で説明せよ。

傍線部の直前に、「これまで表面化しなかった差別や偏見の存在に社会や個人が気づいたときに」とあります。
この「表面化しなかった差別や偏見」が、「内にある」ということが書ければよさそうです。「内なる」という表現をきちんと説明するために、続く文脈を見ていきましょう。

直後は具体例だね。

「具体例」を読み飛ばしてしまうことはできませんが、「具体例そのもの」は重要度は低いです。
したがって、「具体例が終わってすぐのところ」に重要な表現があるだろうというねらいをつけたうえで、具体例を読んでいきましょう。
たとえば、一九七〇年代を中心に活躍し、新左翼が差別問題にコミットすることに大きな影響を与えた津村喬は、自身の著作『われらの内なる差別』(一九七〇年)は、「差別の構造化、構造の差別化」が重要だという問題意識から、当初「差別の構造」というタイトルだったが、出版社の意向によって「われらの内なる差別」に変更されたと述べている。そのために「人道主義」という「卑俗なレッテル」を貼られることになったとしている。

もともと津村は「差別は構造の問題だ」と考えていたわけです。
たとえばですが、小学校で運動会などをやって、「赤組」が勝ったとします。すると、「赤組」の子どもって、「白組」に対して、「白組負けたんだから給食も少なめにしろ」とか、「赤組のほうがえらいんだから、ブランコも赤組優先」とか、いろいろ言い始めるんですよ。
赤組の子どもたちのなかに、もともと白組をさげすんでいる感情があるというよりは、「運動会で勝ち負けがついた」という「構造」によって、結果的に差別が起き始めているんです。
しかし、「差別の気持ち」を「私たちみんなの心の中にある差別の気持ち」とすると、「人間性が高い人は差別をしない」「人間性が低い人は差別をする」というような、「そもそもの人の道」の問題になってしまいますね。
津村の思いとしては、「差別」はもともと「構造」の問題であって、「人の精神性」が中心的主題になる「人道主義」の問題ではありません。ですから、「差別問題」を「人道主義」の話にしたくないわけです。
ところが、本のタイトルが「われらの内なる差別」となってしまったことで、「人道主義の本だ」という低俗な断定的評価を受けることになってしまったのですね。

タイトルでだいぶ印象が変わっちゃったんだね。

ただ、例示はそこまで深く理解できなくていいので、むしろ例示が終了したところに着眼してください。
「例示の前後」は「同義関係」または「主張と根拠の関係」になりやすいところであり、要約的にも重要な箇所になります。
いいかえれば、「内なる……」というレトリックによって、差別が政治や経済といった「構造」の問題ではなく、人間性や内面の問題として捉えられたわけである。このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。しかし、いっぽうで、(d)このような反差別運動を可能にした責任観が大きな問題をもたらしている。

そもそも、
~のだ
~のである
~のではないか
~ということである
~ということだ
といった「統括文」には注意を払ってほしいのですが、特に、
つまり~のである。
という「『つまり』つきの統括文」は、重要度が高いです。
さて、ここは「いいかえれば~わけである」という文になっています。
*「いいかえれば」は「つまり」と似た使い方をします。
*「わけである」は「のである」と似た使い方をします。
したがって、ここは「重要度が高い統括文」だと考えられます。

あ! ここに「内面」という語があるね!

そうですね!
これは「人の内面」のことを意味しています。
つまり「内なる」という表現は、「人の内面」という意味だと読解できます。
「人の内面」というのは、「精神の内部」とか「心の内側」などと説明しても「同じ意味」になりますね。
その論点を取り入れて、答案を作成しましょう。
記述解答例
人の内面(心の内側・精神の内部)には、表面化しにくい差別や偏見の感情が存在しているということ。
〈補問〉傍線部(3)とあるが、「内なる」というレトリックが用いられるのはなぜか。40字以内で説明せよ。

これは傍線部(3)の直後に「~ため」という表現がありますので、そこを拾いましょう。
下書き
たとえ差別を意図せず、その結果を予見できなかったとしても、私たちにはその責任(有責性)がある、とみなすため

40字を超えてしまっているね。

こういう場合は、〈核心〉にならないであろう「ひらがな部分」を削っていきましょう。
解答例
差別を意図せず、結果が予見不能だったとしても、行為者に責任(有責性)があるとみなすため。

続く「傍線部(d)」が述べている「責任観」も、ここを指していると考えられます。
このような「(自己)責任」観を打ち出すことで、マジョリティ(差別者)もまたマイノリティ(被差別者)と連帯して、差別者を批判することが可能になった。しかし、いっぽうで、(d)このような反差別運動を可能にした責任観が大きな問題をもたらしている。

では、今日はここまでにして、この部分の補足説明は次回にまわします。