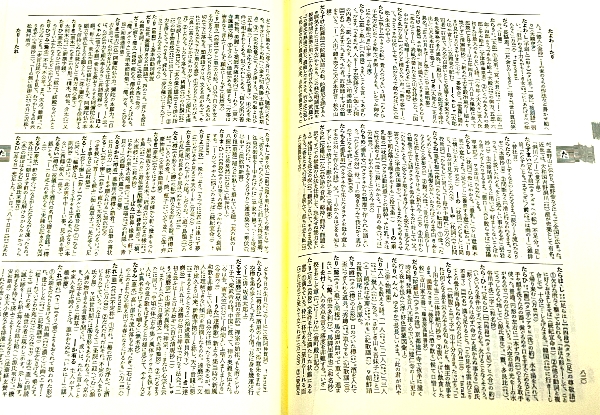問1
① 端的
② 即興
③ 示唆
④ 越境
⑤ 遮断
問2
最大のポイントは「所与」という語です。

漢文には「為 A 所 B 」という構文がありまして、「AのBする所と為る」と書き下します。
訳は「AによってBされる」となります。
Bのところに「与」があると「為 A 所与」になりますね。「Aの与ふる所と為る」と書き下し、「Aによって与えられる」と訳します。
この「所与(あたふるところ)」という部分だけを取り出して、熟語になったのが「所与(しょよ)」です。
このように、「所与」は、「(誰かに)与えられたもの」という意味です。そのことから、「すでに与えられているもの」「はじめからあったもの」という意味で使用されることがあります。

その意味で、「所与(しょよ)」は、「既存(きそん)」という語に近いですね。
この段落のテーマは「名づけについて」なので、この傍線部でいう「所与性」とは、「既存の名称」であると判断できます。
それをふまえているのは〈選択肢ウ〉だけです。「語句の意味」から考えて〈ウ〉が正解になります。
〈選択肢ウ〉の「当然である」というのは、傍線部内の「正当な」の言い換えとして成立しています。

ところで、「すでに与えられているもの」を示す難しい語に「アプリオリ」というものがあります。
「アプリオリ」は、「先天的・先験的」などと訳される語で、「あらかじめ備わっていること」を意味します。対義語は「アポステリオリ」で、「後天的・後験的」などと訳します。
その点で、「アプリオリ」を説明する際に、選択肢で「所与」という語を用いることがありますので、セットで覚えておくといいです。
問3
空欄【A】

主張① ⇒ (たとえば)具体例 ⇒ 主張①
という構造に注目したい問題です。
「具体例」があると、その前後には「同じ主張」が繰り返されている可能性があります。
(あるいは、「前」が「主張」で、「後」が「理由(説明)」になっているケースもあります。)
特に、【空欄 A 】がある文は、「つまり~のである」という、「強い統括文」になっています。
「つまり文」「のだ文」は、「前に書いてある大切なことを統括する文」ですから、同じ意味内容が「前」にあるはずです。
ところが、「前」は「具体例」ですので、例が始まる前までさかのぼって「同じ意味内容」を探す必要がありますね。
具体例の直前(「たとえば」の前)までさかのぼると、
既存の社会が与える名前の体系から離脱して、その物との不断の付き合いの中から、
(たとえば一匹の虫~~~二つの草花を同じ仲間と考える感覚がある。)
つまり、その名前には、子供とその物との出来事を含んだ【 A 】が示されているのである。
という表現があります。
ポイントは、
a.既存の社会が与える名前の体系から離脱
b.不断の付き合い
というところです。
たとえば私たちの身のまわりにある「物」の名前は、すでに決まっていて、「私たち」と「その物」との「直接的経験による関係」はまったく加味されていません。
「机」も「椅子」も「テーブル」も、もともと「机」「椅子」「テーブル」と呼ばれています。それらは「既存の名前 = 所与の名前」なのです。
けれども、「子ども」は、「車」を「車」と呼ばずに、「ブブーブー」と呼んだり、「猫」を「猫」と呼ばずに「オニャンコポン」と呼んだりします。
「すでに使われている【クルマ】【ネコ】という既存の名前(所与の名前)」を無視し、「その子ども」の前で車が「ブブーブー」という音を出したとか、「その子ども」の前で猫が「オニャンコポン」と鳴いたといったような「直接関係」で対象に名前を付けることをよくします。
その「直接の関係」を、筆者は「不断の付き合い」と述べていることになります。
【空欄 A 】には、「子供とその物」との「直接的につながっている関係」の類似表現が入るはずです。
〈選択肢検討〉
〈ア〉
「生きた関係」という表現は、あまり「説明的な選択肢」ではありませんが(やや比喩的な印象がある選択肢ですが)、意味的には「不断 ≒ つながっている」関係を示しています。
したがって、「他がもっと×」であれば、結果的に〈ア〉が正解になります。
〈イ〉
「絶対」とは、「比較・対立する相手がいない」ことを意味する語です。対義語は「相対」です。
この「絶対」が語としてふさわしくないので、〈イ〉は×になります。

何かに名前をつけるとき、子どもは「一人一人の思い」で命名しますね。
それは「主観的」ということです。
「主観」というのは、「それぞれの思い」のことです。
「aさん」と「bさん」の「思い」は、比較することができますね。
「比較することができる」ということは、「主観」とは「相対的」なものなのです。
ということは、「子供それぞれの思い(主観)」というのは、「絶対」とは逆の性質であることになります。
先ほど読解したように、子どもは、「その子供」と、「そのモノ」との具体的な関係の中で、「名前」を付けるのでした。そのような営みは、「その子供」の「思い」が極めて重要な意味を持ちます。
たとえば、「野良猫A」に対して、「よしお」は「ポックル」という名前をつけ、「しぶしげ」は「ブルッポム」という名前をつける、ということが起きます。
そのような「名前の付け方」は「それぞれの思い」で達成されているので、「主観的」と言うべきです。
「絶対的」というのは、「一人一人の思いは関係ない(誰がやってもそうなる)」ということなので、本文の文脈から考えると「逆」になります。

「絶対」とは、「コロコロ変わらない」ということなのですね。
たとえば、「キムタクのかっこよさって、絶対的!」などと言う場合、その表現の意味するところは、「キムタクのかっこよさは、評価する人や、時や、場所によって変化しない。誰がいつどこで見ても同じようにかっこいい」という意味です。
たとえば、「日常言語が相対的(主観的)であるのに対して、数字は絶対的(客観的)である」などという文を考えてみましょう。
「ちょっと! 俺のチャーハン少ないよ!」と言ったとして、この場合の「少ない」というのは「日常言語」です。しかし、「少ない」という言葉でイメージされる量は、個人個人で異なるはずですね。小学生が「多い」と思うチャーハンも、お相撲さんにとっては「少ない」と思うかもしれません。一人一人が違うのですから、これを「相対的」と言います。一人一人の「主観」というものは、「相対的」なものなのです。
一方、「チャーハン800グラム」といえば、その量は、明確な客観的基準をもって示されたことになります。ハカリで「800」を計れば、誰が測っても量が増減することはありません。「状況によって変わらない」ので、「客観的」とは「絶対的」だと言えます。
こういう意味合いで、
主観 ≒ 相対
客観 ≒ 絶対
という関係になります。
ここまで考えて本文に戻ってみましょう。
「子供とその物との出来事を含んだ絶対的な関係」とは、言い換えれば、「子供とその物との出来事を含んだ決して揺るがない関係」という意味になります。
しかし、たとえば、「同じ猫」に対してであっても、雨に打たれて震えていれば「ブルブル」と名づけることがあるでしょうし、カツオ節をガリガリかじっていれば「くいしんぼう」と名づけることもあるでしょう。
つまり、その子供の「命名行為」は、その状況に応じたものになるのですから、「絶対的(揺るがないレベルで固定化されている)」とは言えません。
〈ウ〉
「決められた関係」は、むしろ「既存の社会が与える名前の体系」に該当する表現です。
子供は、そこから離脱(無視)するわけですから、〈逆〉の意味になる選択肢です。
〈エ〉
「入り組んだ関係」は、考えさせられる選択肢が、×です。
「入り組む」というのは、「ものごとが複雑になる」という意味です。その「複雑」という部分が、この段落の論点に整合しません。
子どもの命名体験というのは、「水面に字を書いているように動いているから、【字書き虫】と呼ぼう」というように、むしろ「シンプル(単純)」なものだと言えます。
その命名体験が「入り組んでいる(複雑である)」という文脈は「つまり」より前にはないので、【空欄 A 】の時点で、そこに「入り組んだ関係」という語句を入れる根拠は存在しません。

以上の考察により、〈イ〉〈ウ〉〈エ〉は×となりました。
「不断(切れていない)」 ≒ 「つながっている・関係している」ということを意味している選択肢としては、やはり、「生きた」が最もよいですね。
正解は〈ア〉です。
空欄【B】
直前にある「定義文」に着眼してみましょう。
遊戯的交渉における子供の働きかけとは、その子供に対して世界が生き生きとした固有の姿を現わすということ
とあります。
つまり、「子供の働きかけ ≒ 世界が姿を現わすこと」というように、イコール関係が成立していることになります。
図示すれば、
子供 → 働きかける → 世界
子供 ← 姿を現わす ← 世界
という構造になりますが、重要なことは、「どちらが先に働きかけているか」という説明がないことです。つまり、ここでは、「互いに働きかけている」ということを述べているに過ぎないのです。
そのことに最も近いのは、〈選択肢イ〉の「相互交渉」です。これが正解です。
選択肢検討
〈ア〉
「連続性」という表現は、間違っているわけではありませんが、意味内容の整合性は「弱い」です。
「子供は働きかける ≒ 世界は姿を現す」という本文の表現は、「それぞれが互いに関係しようとしている」ということです。
「連続性」というと、単純に「つながっている」という意味合いだけになってしまうので、〈選択肢イ〉に比べると劣る選択肢です。
〈イ〉
【空欄 B 】がある一文は、「したがって」で始まっています。
「したがって」があるということは、【空欄 B 】がある一文は、直前の文の影響を強く受けます。
直前の文には「遊戯的交渉」という語句がありますので、「相互交渉」という語句は、「話題としてかなり近い」と考えることができます。
さらに、次の〈⑤段落〉には、「相互交渉」という語句が存在しています。〈⑤段落〉から、「山言葉」の話が始まりますが、それは〈④段落〉の内容と、大きく見れば同じことを述べています。

〈④段落〉では、「子ども / 虫・草木」という関係です。
それが、〈⑤段落〉では、「人々 / 自然物・自然現象」という関係に拡大されています。
話題として出しているものは変更されていますが、「それによって言いたいこと」は同じなので、〈⑤段落〉で使用されている「相互交渉」という語句は、そのまま〈④段落〉の「子ども/虫・草木」に当てはめることができます。
〈ウ〉
〈ウ〉の「呼応関係」は最も迷う選択肢です。しかし、〈イ〉に比べると劣るので×にします。
〈イ〉に比べると劣るポイントは、「語句の意味」です。
「呼応」は「まずAが呼んで、それにBが応える」という意味であり、そこには一種の「順番」が存在します。
ところが、「子供-世界」の関係は、どちらが先に呼びかけ、どちらがそれに応えるのか、という前後関係が曖昧です。
子供が名前を付けたから世界が姿を現したのか、世界が姿を現したから子供がそれに名前を付けたのか、明確にすることはできません。
「子供が呼ぶ→世界が応える」あるいは「世界が呼ぶ→子供が応える」といったようなくっきりした「順番」がわかりにくいということです。
〈エ〉
〈選択肢エ〉の「意味産出」は、周辺の話題に存在せず、他の選択肢との比較のうえで、最も無関係だと言えます。
また表現的にも、直前の「~との」という言葉とのつながりが悪いです。
「論点不在」「表現未熟」と考えて、×にします。
問4
「理由」を問う問題なので、「理由表現」は最優先で確認しましょう。
(前段の内容)「名前は、事物の秩序と緊密に応答しあっていた」ということは、
民俗学が教える象徴的な事例 すなわち
特定の聖地を「ナシラズ」といい、特定の神木を「ナナシノキ」と呼ぶ習俗の存在によっても裏書きされる
これは、神聖な場所や物に対する人々の畏怖が、日常的な世界からの敬遠と遮断を強いたのである(*のだ文・のである文は、「理由」として機能することもある)
同時に
そこには、空間や事物の存在のあり方を決定づけ、それを経験世界へと占有せずにはおかない名前の威力が表明されている。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
名づけることは、「所有する」ことであったからである。(理由)

ところで、「裏書き」という語は、「文書・書画などの裏面に文字を書くことや、書いたもの」を意味します。
この「裏書き」をする場合というのは、具体的には、「書画の軸物の裏に鑑定の結果を書く」とか、「小切手などの支払いを受ける際、その裏に住所・氏名を書き、押印して、領収の証明をする」場合を指します。
つまり「裏書き」とは、実体的には、「別角度からの証明」を意味するのです。
したがって、現代文の文章で「裏書き」という語が出てきたら、「証明」だと考えればよいです。
しかし、この設問は、「裏書き」にスポットが当たっているわけではなく、「そのような習俗があるのはなぜか」と問われているので、「裏書き」の意味がわからなくても特別な問題はありません。
〈⑤段落〉の最後には、「名づけることは、所有することであったから」と、〈理由表現〉が明示されています。
したがって、ここが〈最重要論点〉になります。
つまり、名づけてしまうと、その対象を人間の経験世界へと取り込んでしまうことになってしまうため、聖地や神木には、あえて名前を付けなかったのだと考えられます。

さらに考えてみましょう。
では、なぜ「所有すること(人間の経験世界へと取り込むこと)」を避けたのでしょうか?
もしもこれが記述問題であれば、答案に使いたい熟語は「畏怖」です。
その共同体における「聖地や神木」に、「名前をつける」ことによって、「人間の経験世界に取り込んでしまう」ことを、「畏れ多い」と感じたからこそ、人々は名前を付けなかったのです。

そんなわけで、もしもこれが記述問題なら、次のような答案になります。
〈記述問題なら……〉
名づけることは、人間の経験世界へと占有することであるため、畏怖の対象であり、日常的な世界から敬遠・遮断すべきであった特定の聖地や神木には、あえて名前を付けなかったから。
選択肢検討
〈ア〉
「所有する(人間の経験世界に占有する)」という論点がないので、〈核心不在〉で×です。
また、「それ以外はすべて名前が付いている」が〈事実のミス〉です。たしかに、「名前をつけること」が、「人間の認識世界そのもの」であると言うことはできますが、そのことは、「名前がない場所以外のすべての物事に名前が付いている」ことを意味するわけではありません。
〈イ〉
正解です。
〈ウ〉
前半はだいたいOKです。
後半の「里の人々の所有」が〈事実のミス〉です。
「里」であろうが、「都市」であろうが、とにかく「人間世界」が「持たない」ための措置が「名前をつけない」ことなのですから、たとえ「里」の共同保有であっても、人間が「有」してしまってはダメなのです。
〈エ〉
「所有する(人間の経験世界に占有する)」という話題がないので、〈核心不在〉で×です。
また、「別の里人や後代の人に理解しづらい」という話題は本文に存在しませんので、〈事実のミス〉です。
〈オ〉
「所有する(人間の経験世界に占有する)」という話題がないので、〈核心不在〉で×です。
また、「名前を付けることは、他の場所や物との違いを明確にすること」が〈事実のミス〉です。
本文の文脈は、「名前を付けないことで、他の場所や物との違いを明確にする」ということであって、その「違い」は、そこが「神聖な場所(畏怖する場所)」だということです。
したがって、「名を付けることで特別扱いする」という説明は、本文と〈逆〉です。

正解は〈選択肢イ〉です。
問5

この問題で重要視しておきたいディスコース・マーカー(論理の流れの目印)は、
傍線部直後にある「このような」という「要約系の指示語」です。
このような
そのような
こういった
そういった
こういう
そういう
という「要約系指示語」があったら、次の2つの観点が重要です。
(1)「要約系指示語」は、前の部分を広くまとめているので、「要約系指示語」が関わる記述問題の場合、「前にある複数の論点」が必要になる。
(2)「要約系指示語」の直後にある「名詞(名詞句)」は、直前で中心的な話題になっている「キーワード」と考えられる。
さて、この問題は「ヤマトタケル」の物語がどのようなものかわからなくても、「言いたいこと」を的確に拾っていけば正解は出せる問題です。
傍線部直前の「ヤマトタケル」の話題は、あくまでも「例示」として提出されているものであり、むしろ「ヤマトタケル」の話が始まる直前に着眼し、「言いたいこと」を回収してくる必要があります。
したがって、
(名前の)固有性の強さ故にまた、名前は人々の想像力を刺激し動かして、物語の発生を促さずにおかない。
というところが、記述であれば〈核心〉として「使う」場所です。
なお、傍線の直後にも、
このような物語の産出は~
とあることからも、「物語の産出」が主要な論点であると判断できます。

ざっくり記述解答を作ると、次のようになります。
〈ひとまず答案〉
「ヤマト」の政治象徴的な意味と、「タケル」の反逆性を持つ意味によって、「英雄の悲劇」という物語が産出されたように、名前の固有性は、人々の想像力を刺激し、物語の発生を促すということ。
さらに見ておくと、直前の段落の最終部分では、「願望の地政学」という語が出てきます。そして、次のようにまとめられている。
ある空間や場がもつ意味や性格と、そこに込められた人々の願望とは、名前のうちにすべてが要約されていた。
〈⑧段落〉の冒頭には、「この固有性の強さの故にまた~」という「話題の連結」のラベルがあるので、この〈⑦段落〉の最終文にある「願望」の話は、〈⑧段落〉にも引き継がれていると考えたほうが妥当です。
補足事項として答案に入れられるとよいでしょう。

たとえば、「明日、転校性が来ることになった。伊集院慶喜くんだ」と先生が言ったとします。
そうするとみんなはきっと、「金持ちそう……」とか、「和歌をたしなみそう……」といったように、「勝手なイメージ」を作り上げるでしょう。
こういう「イメージ」は、ある意味では、「こうだったらいいな」という「願望」を映し出したものだと言えます。
〈記述想定答案〉
「ヤマト」の政治象徴的な意味と、「タケル」の反逆性を持つ意味によって、「英雄の悲劇」という物語が産出されたように、名前の固有性は、人々の想像力を刺激し、願望を含んだ物語の発生を促すということ。

「ヤマト」はヤマト政権とかかわりがありそうだから、英雄に違いない。
「タケル」は「猛々しい」だから、戦いに明け暮れる毎日だったに違いない。
などと、人々は名前から「英雄」の「戦いの日々」という物語を想像したということですね。
〈選択肢検討〉
〈ア〉
「つぎはぎ」という語句は、「ヤマトタケル」のところではなく、「熊野」と「吉野」の話題で出てきました。「ヤマトタケル」の話題においては、「つぎはぎ」は無関係です。
「隙間を埋めるための物語」が、傍線部直前の意味内容と異なります。
傍線部直前には、「名前の内に、この英雄物語の悲劇的展開を決定づける動因がひそんでいた」と説明されていますので、〈傍線部ウ〉で述べていることとしては、「名前そのものの内部から、物語が生成された」と読解するべきです。
〈イ〉
「レベルが違う意味」というものが、何を言っているのか不明です。
「謎を解こうとする」という話題も、その話題とみなせる箇所は、傍線部直後の「そして」以降で展開されているところですので、〈傍線部ウ〉の説明としてはズレています。
〈ウ〉
傍線部直前の話題に言及されていないので、〈核心不在〉で×です。
また、「様々な地方の特色について語る」という話題も、傍線部とまったく関係ありません。
〈エ〉
「平定」という表現と、「反逆」「悲劇」という表現が、噛みあわないです。
また、「ヤマトタケルという名前は、~物語の象徴的な意味を与えられた」という因果関係も、本文とは整合しません。
本文では、「名前が背負う「物」が語りだす」とあり、これは、「名前から物語が生まれる」ということになります。
傍線部直後でも、「このような物語の産出」と書かれています。
ところが、〈選択肢エ〉の前半のように、「名前が、物語の意味を与えられた」と表現してしまうと、「物語から名前が産出」されたことになってしまいます。〈因果のミス〉で×です。
〈オ〉
〈記述想定答案〉に最も近い選択肢です。正解です。
問6
〈ア〉B
「いったん付けた名前を変える」ことを、「人々」が「繰り返している」という話題はありません。
「子供」にかんしていえば、「命名の変更」を遊戯的交渉のうえでおこなっているという文がありましたが、それはあくまでも「子供」の話であり、〈選択肢ア〉のように、「人々」を主語にした話題ではありませんでした。その意味で〈組み合わせのミス〉であるともいえます。
また、「(命名の変更の)繰り返しによって自分たちの生活世界を作り出し続けている」と述べてしまいますと、裏返せば、「命名の変更の繰り返しがなければ、自分たちの生活世界が作り出されない」という意味になってしまいます。それは「現実的」にみておかしいですね。
私たちは何千年も前から「山」は「山」と呼び、「川」は「川」と呼んでおり、むしろ「名前が変更されないケース」のほうがずっと多いはずですが、生活世界は連綿と作り出されています。
〈イ〉A
「山言葉」と「里言葉」の段落が、やや読解しづらいのですが、〈⑤段落〉に整合しているので、〈A〉と考えます。

細かく確認していきましょう。
「山言葉」と呼ばれる名前の一群がある。沖言葉などとともに忌み言葉として、里言葉に対するものである。すなわち、山中では里での日常の言葉を使うことは禁忌とされ、特別の名前がつくられていた。
「里での日常の言葉」とありますので、ここでの登場人物は「普段は里で暮らしている人々」ということになります。その「普段は里にいる人々」は、「山中」に入る際には、「普段の言葉(里言葉)」を使用することは避けて、「非日常の言葉(山言葉)」を使用する習慣があった、という文脈になります。
「忌み言葉」というのは、「使用することを避ける言葉」ということです。この文脈では、「山言葉や沖言葉は、普段は(里では)避けて使用しない」ということになります。逆に、「山中(非日常)」においては、「里言葉(日常言語)のほうを避けて使用しない」ということになります。
時間がない中で手早く読むと、ここは、「山に住む人」と「里に住む人」がいて、その両者のあいだで別々の言語が形成されてきた、と読んでしまいがちなところであるが、「山中では里での日常の言葉」を使用しない、という文脈をおさえて、主語は「日常的に里に住む人」であると解読します。「すなわち」の直後が重要です。
したがって、〈選択肢イ〉の、「里の人々が山言葉を使うのは~」という部分は、親切に書けば、「里の人々が山に入る際に山言葉を使うのは~」とすべきところでした。やや不親切な選択肢です。
「里の人々が山に入る際に山言葉を使うのは~」と書いてあれば、文中の、「山中では里での日常の言葉を使うことは禁忌」という文脈に一致していることが、いっそうわかりやすくなります。
いずれにせよここは、「日常/非日常」という「切り替え」が話題になっているのであり、主語は「里の人」と考えておきましょう。
生徒のみなさんの生活で考えれば、「クラスで使用している言語」と「職員室で使用する言語」は、意識的に区別するはずですね。
「普段はクラスにいる人々(みんな)」は、「職員室(非日常の空間)」に入る際は、「クラスの言葉」を使用することを避けます。教室に入るときには「失礼します」とは言いませんが、職員室に入るときは「失礼します」と言うと思います。
同じ校舎の中にあっても、こういう「使い分け」をするのは、「クラス」と「職員室」が、質的には異なる空間であることをみなさんが理解しているからです。
本文にはくわしく書いていませんが、歴史的に見て「里」に暮らす人々にとって「山」は神聖なものでした。多くの里文化では、山に入る際には、たとえば水をかぶって祈りを捧げるなど、うやうやしく儀礼をとりおこなったのです。現在でも一般人は入れない「山」は数多くあります。その理由はそこが聖なる場所だからです。
本文では「里」に対して「山」が神聖なものだという文脈は特にないので、あまり踏み込みすぎると「深読み」になってしまいますが、歴史的・文化的に考えれば、そういうことを述べている段落だと言えます。
「里」と「山」は、物理的には地続きではあるけれども、精神的には分断されている、という内容がつかめればよいです。
〈ウ〉B
「人間に了解できない事物は減っていく」という話題が本文にありませんので、〈事実が違う〉で×です。
名前というものは、付ければ付けるほど、了解できない事物が増えていくことすらありえます。たとえば、医学は進歩し、身体の不調に様々な病名を付けましたが、むしろその発見や定義が「次の謎」を呼び、新種のウィルスや病状が次々と顕現化するということが起こっています。したがって、「現実的」にみても理屈がおかしいと考えて、〈B〉とします。
〈エ〉A
〈⑦段落〉における「願望の地政学」の話題と整合しています。〈A〉です。

お疲れさまでした!