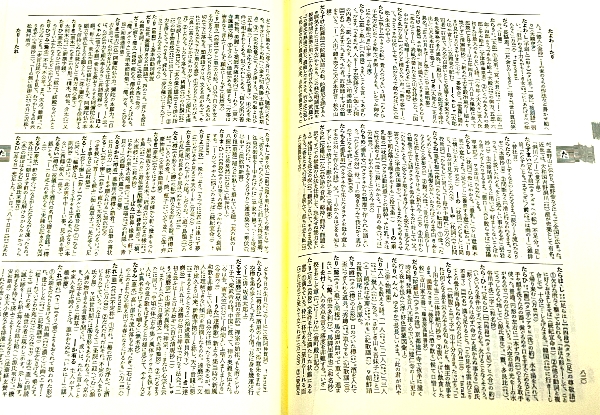問3

〈傍線部B〉がある〈⑩段落〉の直前〈⑨段落〉では、「遊園地」と「原っぱ」が対比されています。
遊園地 ⇒ あらかじめそこで行われることがわかっている建築
原っぱ ⇒ そこでおこなわれることが空間の「中身」を創ってゆく場所

傍線部でいう〈先回り〉とは、「遊園地」の側の特徴ですね。

ああ~。
「ジェットコースター」では「ジェットコースターに乗る」ことしかできないし、「観覧車」では「観覧車に乗る」ことしかできないから、ある意味で「そこですることがあらかじめ決められている」と言えるよね。

さて、問いは、
「空間がそこで行なわれるだろうことに対して先回りしてはいけない」
という傍線部に対し、「なぜか」と理由を問うものです。
「なぜか」の問題は、「主語(目的語)ー述語」という論理構成を確認しましょう。
論理構成としては、
「空間がそこで行なわれるだろうことに対して先回りしては」が「長い主語」であり、
「いけない」が「述語」という関係になっています。
空間がそこで行なわれるだろうことに対して先回りしては ー いけない
主 語 ( 主 部 ) 述 語

「空間が」が「主語」で「先回りし」が「述語」なんじゃないの?

日本語の長い文は、内部に「主語」と「述語」が複数存在します。
そのため、「この文の主語は何か」という問いは、超シンプルな文でないと成立しないのです。「この述語に対する主語は何か」であれば答えようがありますが、「この文の主語は何か」という問いはそもそも成立しない文がたくさんありますね。
「主語」というのは、「述語」をこれと決めたものに対して、「この述語の主語はこれ」と決めていくものです。
たとえば、「先回りし」の主語は何か? と聞くのであれば、「空間が」が正解になります。
しかし、「いけない」の主語は何か? と聞くのであれば、「空間がそこで行なわれるだろうことに対して先回りしては」という「長い主語」になります。連文節なので「主語」ではなくて「主部」ということも多いのですが、いろいろ言い出すとかえって混乱するので、ここでは連文節であっても「主語」と呼んでいます。

たとえば、「ゾウは鼻が長い」という「文」の「主語は何か?」って質問は成り立つの?

答えがひとつに決まらないという点で、根本的には成り立ちません。
「ゾウは鼻が長い」という文について、「長い」という述語における主語は何か?と聞くのであれば、「鼻は」が主語であるといえます。
しかし、「鼻が長い」という連文節を「述部」だと考えると、「ゾウは」が主語になります。
あるいは、この文は「生き物だ」という結論が省略されているとも言えます。その意味で、「ゾウは鼻が長い生き物だ」という文だと考えて、「生き物だ」の主語は何か?と聞くのであれば、「ゾウは」が主語であると言えます。
ほかにも、「明日は雨が降る」という文で考えたときに、「この文の主語は何か」という質問は成り立ちません。
「降る」という述語における主語が何か?と聞くのであれば「雨が」が主語になります。
しかし、「雨が降る」という連文節を「述部」だと考えると、「明日は」が主語になります。
あるいは、「明日は雨が降る日だ」という文の「日だ」が省略されていると考えると、「日だ」に対応する主語は「明日は」になります。
このように、複雑な日本語文において「文の主語は何か」と聞くのはナンセンスです。「この述語に対する主語は何か」という質問なら、答えることができます。
とにかく、まずは「述語」を決めることが重要です。

「述語」からさかのぼらないと「主語」は特定できないんだな。

はい!
とにかく常に意識してほしいことは、「主語や目的語」といった「前提項」は、必ず「述語から考える」ということです。
さきほど「述語が省略されることもある」と述べましたが、「なぜか」と問われているときに結論部が省略されることはありませんから、表出されている結論部を「述語」と考えてください。

この文だと、「いけない」が「述語」になるね。

そうですね。
そう考えると、主語は、
「空間がそこで行なわれるだろうことに対して先回りしては」
という「長い主語(主部)」になります。
したがって、この問いの答案の構文は、次のようにできます。
空間がそこで行なわれるだろうことに対して先回りしてしまうと【 】から。
(→いけない)

さて、「なぜか?」の問題というのは、次の2つのことで答案の構成要素が決まります。
(1)「主語(または目的語)」と「述語」のあいだに「飛躍」があるので、その「飛躍」を埋める論点を拾う。
(2)「主語(または目的語)」のほうに「意味不明瞭」な部分があれば、それを一般表現に書き直して説明する。
主語(または目的語)という「前提項」と「述語(結論)」のあいだに「飛躍」があるからこそ「なぜか」という問いが設定できます。ここに「飛躍」がなければ「なぜか」と問うことはできません。そのため(1)の作業が必要になります。
また、「主語(または目的語)」という「前提項」が「意味不明」だと、そもそも論理がスタートできないので、(2)の作業が必要になります。
(1)(2)の作業をどちらからやったほうがいいのかは文脈によるので、やりやすいほうから考えてみましょう。

じゃあ、今回の問題は(2)をまず考えてみたいんだけど、「先回り」とか意味わかんないよね。

そうですね!
「先回り」というのは明らかな比喩表現なので、本文別箇所の表現を利用して、一般的な表現で説明したいところです。
すると、こんなふうにできます。
〈下書き〉
空間が、特定の行為のための空間になり、あらかじめそこで行なわれることがわかっている場所になってしまうと、【 】から。

ああ~。
傍線部直前の部分と、前の段落〈⑨段落〉にあった「遊園地」の定義の部分を利用したわけだな。
そうすると、【 】の中には、「原っぱ」のほうの特徴を書いて、「(原っぱの特性みたいなものが)生まれない」という感じで書けばいいことになるよね。

そうですね!
そうすると、次のような〈下書き〉ができます。
〈下書き〉
空間が、特定の行為のための空間になり、あらかじめそこで行なわれることがわかっている場所になってしまうと、行為と行為をつなぐものそれ自体がデザインできなくなるから。

うーん。
でも、「行為と行為をつなぐものそれ自体」というのも、ちょっと比喩的でわかりづらいね。

そうですね。
そのため、〈⑨段落〉の内容を補って説明すると、次のような〈下書き②〉ができます。
〈下書き②〉
空間が、特定の行為のための空間になり、あらかじめそこで行なわれることがわかっている場所になってしまうと、たまたま居合わせた人間の行為と行為のつながりによって何をするか決めるような営みがなくなるから。

ああ~。
たしかに『ドラえもん』とかは、「空き地」にたまたま集まったメンバーで「何しよっか~」なんて考えたりするよね。

そうですね!
のび太、ジャイアン、スネ夫たちは、「空き地」を何にでも使いますね。
「野球」であったり、「リサイタル」であったり、「演説」であったり、「ケンカ」であったり、「仲直り」であったり、「恐竜の訓練」であったり……、その用途は決められていないのです。
また、のび太は、「しずかちゃん」と会えば「あやとり」をするかもしれません。「出木杉」と会えば「勉強を教わる」かもしれません。「誰とも会わない」のであれば、「射撃」のトレーニングをするかもしれません。つまり、何をするかは、誰と出会うかによっても多彩に変容するのです。
また、本文で「たまたま」と書かれているとおり、「空き地」で実施される行為の内容は、「人」「状況」に応じて決定されていくのです。もちろん、「今日の放課後、野球やろうぜ!」と予定して集合することも多いでしょうが、ジャイアンの機嫌によって突如「リサイタル」に代わる可能性も大きいのです。「野球」から「リサイタル」への突然の変質を許容できるところも、「空き地」が「空き地」たるゆえんだといえます。遊園地ではこうはいきません。

たしかに『ドラえもん』ってそうだよね。

先ほどの〈下書き②〉を圧縮すると、次のような記述想定答案ができます。
〈記述想定答案〉
特定の行為の場であることがあらかじめわかっている空間では、たまたま居合わせた人間の互いの行為のつながりによって何をするか決めるような営みがなくなるから。
〈採点基準〉⑧点
a.特定の行為 ②
b.あらかじめわかっている ②
c.たまたま居合わせた人間 ②
d.互いの行為のつながりによって ②
e.何をするか決めるような営み ②

最も近い選択肢は④です。
〈選択肢④〉
遊園地のように、その場所で行われる行為を想定して設計された空間では、行為相互の偶発的な関係から空間の予想外の使い方が生み出されにくくなるから。

「予想外」という表現については、文中根拠が発見しづらいのですが、これは〈反転解釈〉と考えればよいです。
遊園地のほうが、「あらかじめそこで行なわれることがわかっている」場所だと説明されるのであれば、その〈対比項目〉である「原っぱ」は、「あらかじめそこで行われることがわからない場所」と説明することが可能です。
対比なのかどうかが不明瞭な場合にこのような書き方をするのは危険ですが、ここでの「遊園地」と「原っぱ」は、明らかに対比されているのであるから、問題ないと考えましょう。
不正解の選択肢
①
「先回り」してしまう空間は、「遊園地」の特徴なので、「先回り」の説明に「原っぱ」の話題を使用するのは「逆」になります。
また、「手がかりがきわめて少ない」というのも、「先回り」の内容説明になりません。
また、「原っぱのように → 遊びの手がかりがきわめて少ない」という対応もおかしいです。本文では「原っぱ」について、「いろんな手がかりがある」と述べています。
②
「先回り」してしまう空間は、「遊園地」の特徴なので、「先回り」の説明に「原っぱ」の話題を使用するのは「逆」になります。
「使用規則や行動基準が規定されていない」というのも、「先回り」の内容説明になりません。
③
「明確に定められた規則に従うことが自明とされた空間」がおかしいです。「遊園地」はたしかに「すべきことが決まっている空間」ではありますが、「規則」が「明確」であり、「従う」ことが「自明」とまでは述べられていません。
また、「主体性」という論点が周辺にありません。
⑤
「容易に推測できて」という論点が周辺にありません。
また、「興味をそいでしまう」という論点が周辺にありません。
補足(⑬段落について)

なお、〈問3〉を解くうえではあまり関係がないのですが、「青木の文章の引用」のあと〈⑬段落〉の、一節は非常に興味深い部分です。
このような空間に自由を感じるのは、そこではその空間の「使用規則」やそこでの「行動基準」がキャンセルされているからだ。「使用規則」をキャンセルされた物質の塊が、別の行為への手がかりとして再生するからだ。

なぜここを問題にしなかったのか、もったいない限りですねえ・・・

どういうことなんだ・・・?

青木は「工場をアトリエやギャラリーに改装した例示」を挙げています。
たとえば、本来は工場であるがために、煙突をつけるための「屋根の凹み」や、電源を引くための「ケーブル通路」や、換気ダクトを取り付けるべき「穴」などがあるでしょう。
それらがあり、そのうえで「本来の目的をキャンセルされている」ことが、「自由」の感覚をもたらしているのです。
同じことは、先ほど述べた「ドラえもんの空き地」にも言えることです。たとえば「ドラえもんの空き地」には「土管」があります。「土管」の本来の用途は、当然別にあるはずですが、何かの理由で使用されず、空き地に野ざらしになっています。
子どもたちは、その陰に隠れたり、上に登ってステージにしたり、中に入って風雨を凌いだりします。「本来の用途」がキャンセルされ、実に多彩な使われ方をします。

ああ~。
それは実に自由だねえ。

「物体」ではなくても、このような感覚はありうることです。
たとえばみなさんも、「急に先生が来なくなって自習になった時間」は、思わぬ解放感をもたらし、結果的にすごく勉強が進んだ、という経験をしたことがあるのではないでしょうか。
「もともと自習」だったのではなく、「もともとは授業」であった時間が「キャンセル」され、その時間を「転用」できたことが、「自由」の感覚をよりいっそう浮き立たせるのです。
いずれにせよ、本文では、「原っぱもおなじ」と述べられています。
原っぱは、単なる無機質な平面ではなく、雑草が生えたでこぼこのある空間です。そのでこぼこは、ある観点では、雨上がりに小鳥が水遊びをする場所かもしれません。しかし、別の観点では、子どもたちがサッカーのゴールに見立てる場所かもしれません。また別の観点では、別の子どもたちが、「ドロケイ」の「牢屋」に見立てる場所かもしれません。
違う目的を持っていたものが、「キャンセル」され、違う目的を持ったものに「変わる」という変身の可能性の幅が、「自由」の感覚を促しているのです。

たしかにそうだな。

これを、「まったくの自由」のために、何もかもを平らにして、すべすべの無機質な空間にしてしまったら、何かをする「手がかり」はかえって失われてしまい、結果的に「多彩な行為」は生成されにくくなります。
すると、逆説的に、「自由」の感覚はむしろ減退してしまうでしょう。

ああ~。
「手がかり」がないとかえって不自由な感じはするよね。

いま読解してきた〈⑬段落〉の内容は、直接的には設問になっていませんが、「問4」を解くうえでは大切な前提になります。
ここをふまえて「問4」に入っていきましょう。
問4

〈⑬段落〉の内容をふまえて〈⑭段落〉を読んでいきましょう。
「木造家屋」を再利用したグループホームでは、先に述べたような「目的のキャンセル」は行われていません。
「玄関」は「玄関」として使うでしょうし、「台所」はやはり「台所」として使用するでしょう。
わざわざ水道をひいて「物置」を「風呂」にしたり、わざわざ外側に階段を取り付けて、「2階のバルコニー」を「玄関」にしたりするような使い方は、いかにも不都合ですから、そんなことはしませんね。
その意味で、「工場をアトリエとして使う」というものとは異なり、「家屋」を「家屋」として使っている点では変わりがないのです。
そのため、「使用規則」も「行動基準」も、何ら変更されているわけではありません。しかし、「暮らし」は、別の「暮らし」へと再編成されていくのです。

そりゃ住む人が変わればそうなるよね。

たとえば、ある家族が、中古の家を購入したとします。
「台所」は以前の所有者のときから「台所」でしたし、「リビング」は「リビング」でしたし、「屋根裏」は「屋根裏」でした。
以前の所有者も、リビングでテレビを見たでしょうし、台所でお皿を洗ったでしょう。玄関で「行ってきます」と言ったでしょうし、「ただいま」とも言ったでしょう。このように、暮らしの「型」はほとんど同じなのです。
しかし、夕飯のおかずの種類、水道の蛇口のひねり方、扇風機が首を振る角度、その他さまざまな微細な営為が変質していきます。その家屋との「関わり方」が編みなおされていくのです。

そりゃそうだね。

傍線部周辺はこうなっています。
からだと物や空間とのたがいに浸透しあう関係のなかで、別のひととの別の暮らしへと空間自体が編みなおされようとしている。その手がかりの充満する空間だ。青木はいう。「文化というのは、すでにそこにあるモノと人の関係が、それをとりあえずは結びつけていた機能以上に成熟し、今度はその関係から新たな機能を探る段階のことではないか」、と。そのかぎりで高齢者たちが住みつこうとしているこの空間には「文化」がある。

「ある」
を述語とした場合、主語は
「文化」が
になります。
その前にある、
「高齢者たちが住みつこうとしているこの空間には」という部分は連用修飾節ですね。
連用修飾節には主に「目的語(節)」と「補語(節)」があります。
Aが、○○に 向かう
という文であれば、「○○に」は「対象」になっていて、述語に必須の前提になるので、「目的語(節)」と言えます。
その一方、
Bが、△△に ある/ない
という場合、「△△に」という部分は「場所」を示しています。「場所」は、述語の「対象」ではないので、これは「目的語(節)」ではありません。「補語(節)」のようなものですね。
論理の関係性でいえば「おまけ」になる部分なのですが、「どういうことか」という問題の場合、傍線部内にある「表現のかたまり」は「言い換えて説明する」という方針がありますので、「少なくとも傍線部よりはイラストにしやすい表現にする」というつもりで言い換えましょう。
傍線部の「高齢者たちが住みつこうとしているこの空間には」の「この空間」というのは、段落の先頭にあった「木造家屋を再利用したグループホーム」を意味していますので、代入すると次のように説明できます。
高齢者たちが住みつこうとしている木造家屋を再利用したグループホームには、「文化」がある。

さて、傍線部内でもっとも「解決しなければいけない語句」は「文化」ですね。
「文化」というのは非常に意味広範な語で、一種の「多義語」ですから、筆者がどういう意味で「文化」という語を使用しているのか、その定義を答案化したい問題です。
そもそも「 」がついている表現は、筆者が「ちょっと立ち止まってほしい」表現になりますので、「普通の意味」ではないケースが多いです。
「 」がついている表現は・・・
(1)強調(目立たせたい)
(2)区別(「 」をつけないと語句の係り受けがわかりにくい)
(3)俗語(いわゆる~ という意味での「 」)
(4)(筆者の)造語(一般に通用している語ではない)
(5)特殊な意味(辞書的な意味とは違う意味で用いている)
(6)皮肉(辞書的な意味とは逆の意味で用いている)

このうち、(1)(2)は単純に「 」をはずしてかまいませんが、(3)(4)(5)(6)であれば、その表現が文脈上どういう意味になるのかを示す必要があります。
ここでも、筆者特有の意味で「文化」という語を用いている可能性がありますね。
傍線部を含む一文に「そのかぎりで」という指示表現がありますので、指示する内容を確認しましょう。
そこに、「文化」の説明が書いてあります。
文化というのは、すでにそこにあるモノと人の関係が、それをとりあえずは結びつけていた機能以上に成熟し、今度はその関係から新たな機能を探る段階のことではないか。
そのかぎりで高齢者たちが住みつこうとしているこの空間には「文化」がある。

「そのかぎりで」というのは、「その意味で」とか「その点において」と言っていることと同じだから、直前との密接性がとても高いよね。
しかも直前の文は「文化というのは~」と述べられている。
「AというのはB」という表現は、「AとはB」という表現と同じで、いわゆる「定義文」だよね。少しざっくり言うと、
「モノと人」が、「いままでのつながり方」を超越して、「新しいつながり方」になる
というようなことを言っているのかな。

そうですね!
傍線部の直前に「そのかぎりで」というつなぎ言葉があって、この「文化の定義」が傍線部と連結しているわけですから、めちゃくちゃ重要な部分ですね。
このことに言及している選択肢が〈選択肢➂〉しかないので、③が正解になります。

ふむふむ。
でもこれ、身近なことに当てはめて考えるとどういう感じなんだろうね。

このことは、「子どもの遊び」を例にとってみるとわかりやすいでしょう。
子どもは、「目的を持ったモノ」を目的どおりに使用することを好みません。
「いかにはみだすか」が重要なのです。
その「はみだし方」にこそ、子どもの遊びの天才性があると言っても過言ではありません。
お箸を太鼓のバチにする。机の下をぬいぐるみたちの家にする。ナベをかぶって取っ手をツノに見立て怪獣になる。そういった「はみだし方」こそが、本当は「文化」なのです。

ああ~。
子どもってそういうことするよね。

文化というものは、「決まりきったモノ」を「決まりきったとおり」に使うような営為ではないのですね。
麦わら帽子をさかさまにして、摘み取った花を入れるような「はみだし」こそが、文化なのです。
麦わら帽子を、購入した直後に「花かご」にする人はきっといません。帽子として十分に使用し、帽子としての営みが成熟したからこそ、「花かご」のほうにはみだせるのです。
その「工夫」にはみだす瞬間にこそ「文化」が認められる、と言うことができるでしょう。
さて、そういった営為を「文化」とみなすのであれば、「木造家屋を再利用したグループホーム」には、「それまでの暮らしの型」からはみだそうとする(再編成されようとする)「新しい暮らし」が生成されるという点で、「文化がある」ということになります。
以上のことから、次のような〈記述想定答案〉が成立します。
〈記述想定答案〉
高齢者たちが住みつこうとしている木造家屋を再利用したグループホームには、人と物との関係が従来以上に成熟し、新たな機能を探る段階が認められるという点で、文化があるということ。
〈採点基準〉⑧点
高齢者たちが住みつこうとしている (別表現でも可)
木造家屋を再利用したグループホーム ②
人と物との関係が従来以上に成熟 ➂
新たな機能を探る段階が認められる ➂
(「文化」という語自体はなくてよい)

最も近い選択肢は③です。
〈選択肢③〉
木造家屋を再利用したグループホームという空間では、そこで暮らす者にとって、身に付いたふるまいを残しつつ、他者との出会いに触発されて新たな暮らしを築くことができるということ。

傍線部直前で述べていることは「モノ」と「人」の関係なのですが、それを〈選択肢➂〉では「暮らす者」と「他者」の出会いにしてしまっていますね・・・。
ただ、青木の引用文の直前には、
別のひととの別の暮らしへと空間自体が編みなおされようとしている
と書かれているので、「他者との出会いに触発」と書いても問題はありません。
もちろん、理想的には「そこにあるモノや、ともに暮らす人との関係において・・・」などと書きたいところですが、×にするほどの「悪表現」とはいえません。
このように、「理想的な選択肢」とは言えませんが、他の選択肢すべてに決定的な×が入るので、結果的にこの〈選択肢③〉が正解となります。
まあ、現代文の世界では「他者」は「人」とは限らないので、広い意味で「モノ」を含んでいる「他者」だと解釈することもできなくはないですね・・・。
不正解の選択肢
①
「伝統的な暮らしを取り戻す」が「逆」です。
②
「便宜をはかるために設備が整えられている」「快適な生活が約束されている」が「本文根拠なし」です。
④
「空間としての自由度がきわめて高く」が「逆」です。
また「暮らしの知恵を生かすように暮らすことができる」が「本文根拠なし」です。
⑤
「多様性に対応が可能」「個々の趣味に合った生活を送ることができる」が「本文根拠なし」です。