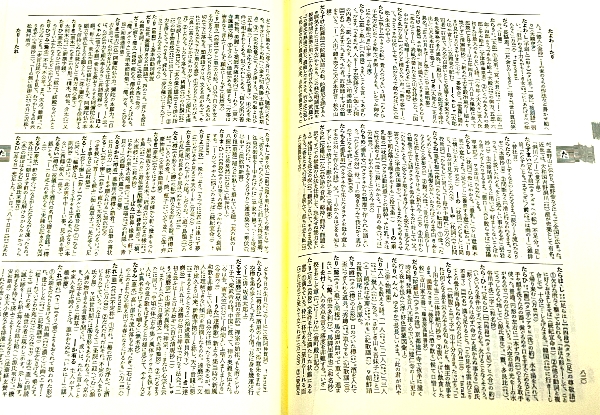論理的構文について
「一文」を論理的に書く場合、典型的には次のような構文になります。
〈a〉主題(原則的に「主語」 *傍線部の「目的語」を「主語」として書く場合もある)
〈b〉定義(主題の概念規定)
(b´)対比(それは何ではないのか)*他に比べると重要度は低い
〈c〉論拠(どうして結論のようになるのか/どういう点で結論のようにいえるのか)
〈d〉結論(主に述語)

〈a〉〈b〉〈c〉〈d〉を「論理の四要素」と呼ぶことがあります。
(b´)の「対比」は、他の四要素に比べると重要度は低く、あくまでも「補足事項」と考えましょう。
なお、注意点がひとつあります。日本語の論理学では「主語」と「目的語」を区別しないので、たとえば傍線部では「目的語」であったものを、「解答」では「主語」として書くことがあります。そのため、「傍線部」と「答案」で「主語の書き方が異なっている」ということはありえます。
〈答案の表現について〉

まず、答案の「構成要素」や「表現」について重要なことを書いておきます。
(1)「本文に書いてある内容」で構成する。
(あるいは本文表記から十分に読解可能なことで構成する。)
(2)冗長な表現は、大まかな意味内容を省かないように端的にまとめる。
(明らかな並列表現の片側だけ拾うことをしない)
(3)「比喩」や「例示」は一般化する。(一般的に伝わる表現になおす)
→「比喩」は「実態」のほうを書く。
→「例示」は「その例示によって言いたいこと」のほうを書く。

とはいえ、傍線部の別箇所から「正解に必要な論点」を拾っていった際、
「比喩ともいえるし一般表現ともいえる」
「例示ともいえるし一般表現ともいえる」
というような「曖昧な表現」が、実際にはかなりあります。
そのような「どちらともいえない表現」は、
(a)選択肢なら、かなり高い確率で「一般化」されている
(b)記述なら、無理せずそのまま使用してよい
(ただし解答欄に入らない場合は端的にまとめる)
と考えましょう。

ああー。
たしかに「真剣に取り組む」とか、もとは比喩だけど、一般的に意味通じるよね。

そうですね。
ポイントは、「課題文を読んでいない第三者」にも「意味が通じるかどうか」です。
「傍線部外」にある「答案に必要な論点(情報)」が「ちょっと比喩っぽいな」と思っても、「課題文を読んでいない第三者」に意味が通じるのであれば、記述問題の場合は無理しないでそのまま書いても大丈夫です。
さきほどの「真剣に取り組む」くらいの表現は、記述問題ならそのまま書いて問題ありません。
ただ、選択肢の問題の場合は、そういう表現をそのまま使用することはまずありません。
そもそも選択肢の問題は、本文にある表現をそのまま使うと問題の難易度がかんたんになりすぎてしまいますから、普通の一般表現であってもけっこう言い換えてきますからね。
問3

〈問3〉は、〈傍線部A〉について、「筆者はどのようなことを根拠として、そう判断しているのか」という問題です。
「傍線部そのもの」の意味内容を聞いているのではなく、「そう判断する根拠」を聞いている問題です。その意味で、「そのようにいえるのはなぜか」というタイプの問題に似ていますね。
「根拠」が問われている問題は、筆者が「傍線部」のように判断している〈理由・論拠・前提〉を探して拾うのですが、この手の問題は、「傍線部そのもの」の意味内容も解答に混入してくる傾向があります。
たとえば、「AはBである」という傍線部に対して、「そう判断する根拠は何か」「そのようにいえるのはなぜか」などと問う場合、
「A´がB´であるのはxであるから」とか、
「xであるために、A´はB´であるということ」というように、
「A´(Aの説明)」や「B´(Bの説明)」、すなわち「傍線部そのものの意味内容」が解答に混じってきやすいのです。
このように、「判断の根拠」を問う問題は、多くの場合、「①傍線部そのものの意味内容」+「②そのように言える根拠」という論点で解答が構成されやすいと考えておきましょう。
①と②はどちらが先に書かれていても問題ありませんし、日本語として文の中に混じっていて、①と②が明確に区別できないような場合もあります。
~ このように、生きとし生けるものの本来的同一性、およびこの世とあの世の間の絶えざる循環の思想は、日本の芸術や宗教を貫く思想なのです。これは日本において、森の面積がまだ国土の六十七パーセントを占めているという状況は、この思想の一つのあらわれでしょう。われわれはこの点において、すぐれた文明の伝統をもっていると言わねばなりません。しかしA現代の日本人は、この文明の伝統を意識しているとは思えません。

傍線部内の「この文明の伝統」については、直前に、
「この点において、すぐれた文明の伝統をもっている」と書かれています。
ところがここにも指示語があるので、さかのぼっていくと、
このように、生きとし生けるものの本来的同一性、およびこの世とあの世の間の絶えざる循環の思想は、日本の芸術や宗教を貫く思想なのです。
という表現に行き当たります。
(1)「このように」という「要約系指示語」ではじまっている。
(2)「~なのです」という「統括文」になっている。
という二つのポイントにより、「重要文」であることがわかります。
〈傍線部A〉に代入すると、
現代の日本人は、「生きるものはもともと同一であり、生と死が循環している」という思想による「文明の伝統」を、意識しているとは思えない。
と言っていることになります。

じゃあ、何か別の思想でも意識しているのかな?

はい。
傍線部の直後には、「近代文明の原理である自然征服を、無条件に善とする思想」とあります。
これは、〈傍線部A〉の中にある「この文明の伝統(日本の文明の伝統)」と「対比」されている思想です。
このことをもうちょっとくわしく説明している箇所が〈③段落〉にあります。
③この危機から人類を救い出すためには、当面の対策も必要ですが、まずその哲学を変えねばなりません。近代文明を指導したデカルトやベーコンの考え方は、人間と自然を峻別し、自然を客観的に研究する自然科学の知識によって、自然を征服する技術をもとうとする思想です。かくて、自然科学は飛躍的に発展し、人類は、自然について三百年前にもっていた知識とは比較できないほどの精密な知識をもつようになった。そしてそれとともに自然征服の技術は飛躍的に進み、人間は自然から、それまでは到底考えられないような豊かな富を生産することができるようになった。そしてその代償に、地球環境の破壊という、まさに人間は、自分の生きている土台を根本から崩壊させるような危機に直面したわけです。

傍線部直後には、「近代文明の原理である自然征服」という表現があるのですが、それが〈③段落〉でいっそう詳しく説明されています。
そもそも〈傍線部A〉は、
「日本人が、日本の文明の伝統を意識していない」
というものでしたよね。
ということは、「対比されている項目」を利用して書き直すと、この〈傍線部A〉は
日本人は、日本の文明の伝統ではなく、近代文明の原理のほうを意識している。
と言えるわけです。
これを、さきほど見た〈➂段落〉の部分を利用してもうちょっとくわしく言うと、
日本人は、人間と自然を峻別し、自然を客観的に研究する自然科学の知識によって、自然を征服する技術をもとうとする思想を意識している。
ということになります。
このへんの論点は「傍線部そのものの意味内容」ともいえる部分なのですが、問題の性質上、「正解の選択肢」に混入してくる可能性があります。
とはいえ「設問」そのものは「このように判断する根拠」を聞いているわけですから、「根拠」を探しましょう。

「日本人が、(古来日本にはなかった)自然を征服する思想のほうを意識している」と筆者が「判断」している「根拠」としては、傍線部の直後に書いてある「実際に自然をばんばん破壊している」というところを答えればいいんだろうな。

そうですね!
「自然破壊が進んでいる」という論点は答案に必須です!
〈傍線部A〉の直後、〈②段落〉で述べられていることが「根拠」になりますね。
②戦後日本においても、近代文明の原理である自然征服を、無条件に善とする思想はあまねく広がり、その著しく発展した工業生産の代償として自然破壊が日本のいたるところで進んでいる。もちろん、日本における工業汚染は、世界一厳しい規制によってある程度解決されたわけですが、しかし金儲けイッペントウに凝り固まった日本人は、あるいはゴルフ場の拡大に、あるいはリゾート施設の建設に夢中であり、私などのような反時代的な学者の意見を聞くこともなく、ますます自然破壊は進んでいる。また日本経済の繁栄は木材や紙の浪費をもたらし、熱帯雨林の破壊に一役買っていることも否定できません。私は、二十一世紀における人類の最大の問題は、この環境破壊にあると思っているのです。酸性雨、オゾン層の破壊、地球の砂漠化、熱帯雨林の破壊、森の死滅、どれをとってみても、人類の生存を脅かす現象ばかりです。こういう現象が無限に複合化して、まさに人類社会の基盤そのものをクツガエそうとしているのです。

この、傍線部の直後の一文が「答案の核」になります。
戦後日本においても、近代文明の原理である自然征服を、無条件に善とする思想はあまねく広がり、その著しく発展した工業生産の代償として自然破壊が日本のいたるところで進んでいる。
ここでの「近代文明の原理である自然征服」というのは、先ほど見た〈③段落〉の内容を使うといっそうくわしく書けますので、〈記述想定答案〉としては次のようなものができますね。
〈記述想定答案〉
人間と自然を峻別し、自然を客観的に研究する自然科学の知識によって自然を征服する技術をもとうとする思想が戦後の日本で広がり、それによって発展した工業生産の代償として自然破壊が進んでいること。

なんかそれっぽくなったね。

あとは、字数的にみてさらに論点(情報)を入れられるのであれば、「じゃあどうして日本人はそうなってしまったのか」という論点(情報)を入れられるといいですね。
〈②段落〉には「金儲け一辺倒に凝り固まった」と書かれていて、〈③段落〉には、「自然征服の技術は飛躍的に進み、人間は自然から、それまでは到底考えられないような豊かな富を生産することができるようになった」と書かれています。
つまり、「自然征服」は「金(富)を生む」のですね。そしてその代償として「自然破壊」が起きるのです。
本文で挙げられている「ゴルフ場」や「リゾート施設」などは、典型的な「自然征服&富の発生&自然破壊」の例になりますね。
制限字数が短ければここまで書けないのですが、答案に入れられるのであれば、この「利益追求」という論点(情報)もあったほうが、「日本人がどうしてそうなってしまったのか」ということをくわしく説明できたことになります。
〈記述想定答案+α〉
人間と自然を峻別し、自然を客観的に研究する自然科学の知識によって自然を征服する技術をもとうとする思想が戦後の日本で広がり、利益追求型の工業生産が発展した代償として自然破壊が進んでいること。

最も近い選択肢は②ですね。
②が正解です。

でも、②には、「自然を対象化」なんていう「本文にない語句」があって、こういうことがあると自信をもって選べないよね。

「対象化」という語は、
ある物事を自分(主体)から切り離して(主観を排して)客観的にとらえること。
という意味を持ちます。
〈③段落〉にある「人間と自然を峻別し、自然を客観的に研究する」という表現における「峻別」は「きちんと分ける」ということですから、
「人間と自然を峻別し、客観化する」ということは、「(人間が)自然を対象化する」という表現でまとめることが可能です。
その意味で〈選択肢②〉にある「自然を対象化」という語は、本文の意味内容をコンパクトにまとめた表現であるといえます。
超難関大になると「記述」でこういうことを求めてくるのですが、多くの受験生は「記述」でそこまではできません。「人間と自然を峻別し、自然を客観的に研究する」と書ければ十分です。ただ、「選択肢」ではこういうことをしてくると考えておけるといいですね。
問5

「答案」については、以下の表現は用いないという「ルール」があります。
比喩的表現(言いたいことのたとえにすぎない)
例示(言いたいことの部分にすぎない)
慣用表現(ほぼ比喩表現といえる)
ことわざ(ほぼ比喩表現といえる)
誇張表現(実態よりも大げさな表現)
口語・俗語(説明に似つかわしくない)
こういったものを「一般的に伝わる表現」になおしていくことを「一般化」といいます。
さて、こういった表現が「傍線部そのものの内部」に存在する場合には、何が何でも言い換えます。その作業は絶対に必要です。
その一方、こられの表現が「傍線部の外側」に存在していて、そこが「解答の構成要素としての論点」になると判断される場合は、できるかぎり言いかえて使用します。
「大胆な言い換えが難しいな・・・」「これ、このまま書いても意味通じると思うなあ・・・」「比喩っぽいけど、一般表現ともいえるんじゃないかな・・・」と判断したときは、そのまま使用してください。なぜなら、書かないよりはマシだからです。
このように、記述の採点は、「論点言及(構成要素の確保)」と「表現成熟(一般的表現への置換)」の二段階になっていることがあります。
論点言及 → 表現成熟

答案に必要な論点を見つけ出していれば「①点」、それが比喩的な表現であった場合、一般的な表現に言い換えられていれば「さらに①点」という感じかな。

点数の配分は試験によって差がありますし、そこまで厳密なルールを設けていない場合もありますが、みなさんが入試問題を解いてトレーニングをしていくうえでは、「論点言及」と「表現成熟」の二段階で考えておくといいです。
なお、「選択肢問題」の場合は、この「表現成熟」をほぼ間違いなくやってきますので、「本文にあるこの表現をこんなふうに言い換えたんだな」という考えをもって正解の選択肢を分析してみてください。

この「問5」の傍線部には、「地獄への道」という「比喩表現」や、「火を見るより明らか」なんていう「慣用表現」があるね。

はい!
「慣用表現」というのも一種の比喩ですね。
傍線部内の比喩表現を答案にそのまま出すことは絶対にできません。
さて、この設問は、傍線部に対して、「ここには筆者のどのような考えが表れているか」となっています。つまり、「傍線部の表現そのもの」に対して、「この表現によってどういうことを言いたいのか」と聞いていることになります。
このような聞き方をしている以上、「傍線部そのものによって示されている筆者の考え」を答えることになりますので、「地獄への道」の「一般的言い換え」や「火を見るより明らか」の「一般的言い換え」は、答案に必須の論点になります。

直前には「森を食い潰す」とか「森の破壊」なんて書かれているから、それが「地獄」のことかな。

その観点は大切ですね。
ただ、前の段落とのからみで考えると、「森の破壊」は昔からあったことで、それが進んでいくと、「もっとひどいことが起きる」という文脈になっています。

「人類の文明全体の崩壊」というやつだな。

そうです!
森の破壊が進むと → 人類の文明全体の崩壊が起こる
と筆者は考えていることになります。
「森の破壊」が「文明全体の崩壊」に至るわけですから、傍線部の「道」という比喩は、この「経緯」のことを意味しているといえますね。
したがって、「森の破壊」という論点と、「人類の文明全体の崩壊」という論点は、答案に必須の論点です。どちらも、一般的に理解可能な語句ですので、答案にはそのまま使用することができます。

「火を見るより明らか」というのは、「明白だ」「明らかだ」「疑いの余地がない」「当然だ」といった意味だよね。

はい!
そうすると、「森の破壊」「人類の文明全体の崩壊」「明白・当然」という3つの論点が入っているものは〈選択肢④〉になりますね。
これが正解です。