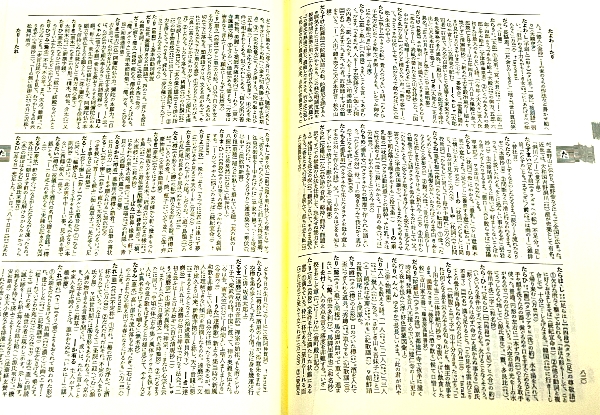- 次の「詩」と「鑑賞文」を読んで、後の問いに答えよ。
- 詩「馬と暴動」 石原吉郎
- 鑑賞文
- 問1 傍線部①の空欄【 】に適語を入れると、「何の前ぶれもなく」という意味になる。ふさわしい漢字一字を記せ。
- 問2 傍線部②の空欄【 】に適語を入れると、「整っていなくて、見苦しく」という意味になる。ふさわしい漢字一字を記せ。
- 問3 空欄【A】に入る語を漢字一字で記せ。
- 問4 空欄【B】には、「韻文」の対義語が入る。漢字二字で記せ。
- 問5 傍線部(ア)は、「寧ろ」と書く言葉で、「二つを比べて、よりよいほうを選ぶ」という意味である。漢文に由来する語であり、古典語から現在にいたるまで長く用いられている。このように、古典語で用いられていた語が現在でも用いられているものとして、次の①~⑩の語の意味を【選択肢】から選べ。
- 選択肢
- 問6 「詩のことば」というのは、「作者によって書かれたもの」を「読者が一方的に解釈するもの」である。ただし、もしも「読者による批評」が、何らかの方法で「作者」に届いたとしたら、「作者の主観」と「読者の主観」が「双方向性」を持って影響を与え合うと言える。このように、「二つ以上の存在がもつ主観をお互いが共有するような関係」を「〇〇〇性」という。「〇〇〇」にあてはまる語を漢字三字で記せ。
- 問7 〈問6〉の正解の「同義表現」を二つ記せ。
- 問8 〈問6〉の正解には、「接頭語」が用いられている。次の①~⑥の語の【 】に接頭語または接尾語をつけて、右の意味になるようにせよ。
次の「詩」と「鑑賞文」を読んで、後の問いに答えよ。
詩「馬と暴動」 石原吉郎
われらのうちを
二頭の馬がはしるとき
二頭の間隙を
一頭の馬がはしる
われらが暴動におもむくとき
われらは その
一頭の馬とともにはしる
われらと暴動におもむくのは
その一頭の馬であって
その両側の
二頭の馬ではない
ゆえにわれらがたちどまるとき
われらをそとへ
かけぬけるのは
その一頭の馬であって
その両側の
二頭の馬ではない
われらのうちを
二人の盗賊がはしるとき
二人の間隙を
一人の盗賊がはしる
われらのうちを
ふたつの空洞がはしるとき
ふたつの間隙を
さらにひとつの空洞がはしる
われらと暴動におもむくのは
その最後の盗賊と
その最後の空洞である

以下はその鑑賞文です。
鑑賞文
石原吉郎の詩は、①【 】突に「私」が出たり、【 】突に「ただしい」が出たり、【 】突に、「なのだ」が出たりすることが多い。さきほどの「馬と暴動」もそれだ。論理ではなく感覚。だが感覚は、岩のように動かないもの、動じないもの、閉ざされるもの。そんな強さと、ゆがみがある。日本語の表現として異常とは言わないが壊れている。
それは石原吉郎の「戦争・戦後」体験によるものだろう。彼は帰国しても、戦後日本の世界のなかで自分の場所をもてなかった。抑留されたのに、日本で彼を迎えた人は、彼がソ連にいたというだけで、冷たかった。彼は、詩のことばにとびついた。自分の体験はどういうものだったのか。それを戦後の日本のなかで整理できない彼は、その苦しみのなかで、詩のことばにめぐりあうのである。石原吉郎の日本語が壊れているのは、日本という国と、日本語という国のなかで生きることができなくなったあかしである。
彼が戦後の日本社会のなかで生きていくために、詩のことばを選んだということ。詩のことばにすがったということ。ぼくはそのことを重要なものと考えたい。詩のことばを選ぶということはどういうことか。
詩は、自由なものである。それが日本語としてどう崩れていようと、乱れたものであろうと、②【 】様であろうと、詩の世界では、ゆるされる。(ア)むしろあわれなもの、さびしいもの、どこにも行き場のないようなものにこそなさけをかける。そしてそれらを【 A 】護する。抱【 A 】する。それが詩のもつ、あたたかみである。まわりにあるすべてのものが信じられなくなったとき、石原吉郎には、詩のことばが見えた。
個人が体験したことは、【 B 】で人に伝えることができる。その点、【 B 】はきわめて優秀なものである。だが【 B 】は多くの人に伝わることを目的にするので、個人が感じたこと、思ったことを、捨ててしまうこともある。個別の感情や、体験がゆがめられる恐れがある。【 B 】は、個人的なものをどこまでも【 A 】護するわけにはいかない。その意味では冷たいものなのである。詩のことばは、個人の思いを、個人のことばで伝えることを応援し、支持する。その人の感じること、思うこと、体験したこと。それがどんなにわかりにくいことばで表されていても、詩は、それでいい、そのままでいいと、その人にささやくのだ。石原吉郎の詩は、そうした詩のことばの「思想」によって支えられ、生きつづけることができた。
(荒川洋治「空隙」による)

ここから問題です。
問1 傍線部①の空欄【 】に適語を入れると、「何の前ぶれもなく」という意味になる。ふさわしい漢字一字を記せ。
問2 傍線部②の空欄【 】に適語を入れると、「整っていなくて、見苦しく」という意味になる。ふさわしい漢字一字を記せ。
問3 空欄【A】に入る語を漢字一字で記せ。
問4 空欄【B】には、「韻文」の対義語が入る。漢字二字で記せ。
問5 傍線部(ア)は、「寧ろ」と書く言葉で、「二つを比べて、よりよいほうを選ぶ」という意味である。漢文に由来する語であり、古典語から現在にいたるまで長く用いられている。このように、古典語で用いられていた語が現在でも用いられているものとして、次の①~⑩の語の意味を【選択肢】から選べ。
① おしなべて
② やにわに
③ ゆくりなく
④ なかんずく
⑤ やおら
⑥ あながち
⑦ あまつさえ
⑧ いたずらに
⑨ おずおず
⑩ つくづくと
選択肢
ア 落ち着いてゆっくりと イ 必ずしも・一概に ウ つまるところ・さしあたり
エ 思いがけず・不意に オ すべて一緒に・総じて カ とりわけ・特に
キ じっくりと・よくよく ク すぐさま・突然 ケ そればかりでなく・おまけに
コ むだに・むやみに サ おびえたりしてためらうさま
問6 「詩のことば」というのは、「作者によって書かれたもの」を「読者が一方的に解釈するもの」である。ただし、もしも「読者による批評」が、何らかの方法で「作者」に届いたとしたら、「作者の主観」と「読者の主観」が「双方向性」を持って影響を与え合うと言える。このように、「二つ以上の存在がもつ主観をお互いが共有するような関係」を「〇〇〇性」という。「〇〇〇」にあてはまる語を漢字三字で記せ。
問7 〈問6〉の正解の「同義表現」を二つ記せ。
問8 〈問6〉の正解には、「接頭語」が用いられている。次の①~⑥の語の【 】に接頭語または接尾語をつけて、右の意味になるようにせよ。
① 【 】元気 うわべだけ元気そうにする
② 【 】寒い 何となく寒々としている
③ 【 】返事 いい加減な返事
④ 【 】ざかしい ずるがしこい・利口ぶっている
⑤ 気色【 】 怒りを態度に出す・むっとする
⑥ 道【 】 行く道の途中・歩きながら
⑦ これみよ【 】 得意そうなさま
⑧ あらず【 】 ないほうがよい・あっても無意味