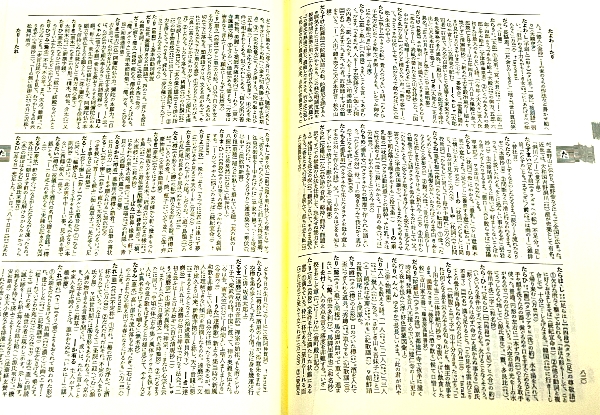今は昔、~
今は昔、紫式部、上東門院に歌詠み優の者にてさぶらふに、大斎院より、春つ方、「つれづれにさぶらふに、さりぬべき物語や候ふ」と尋ね申させ給ひければ、
今は昔【今となっては昔のことだが】、紫式部が、上東門院【中宮彰子】に、歌を詠むのが優れた者としてお仕えするときに、大斎院【選子内親王】から、春のころ、「退屈でございますので、(こんなときに)ふさわしい物語はございますか」とお尋ね申し上げなさったので、

「大斎院」は「選子内親王」のことです。その方が、ひまを持てあまして、「こんなとき読むのにちょうどいい物語」を求めてきたのですね。
「内親王」の行為なので、「せ給ひければ」という「二重尊敬(最高敬語)」がついていますね。
「已然形 + ば」なので、その後ろは「求められた側」の行為が始まる可能性が高いです。
文脈的に「上東院(彰子)」か「紫式部」の行為が始まるでしょうね。
御草子どもとり出ださせ給ひて、「いづれをか参らすべき」など、選り出ださせ給ふに、紫式部、「みな目慣れてさぶらふに、新しくつくりて参らせさせ給へかし」と申しければ、「さらばつくれかし」と仰せられければ、源氏は作りて参らせたりけるとぞ。
(上東門院は)物語の書物などを取り出しなさって、「どれを差し上げるのがよいか」などと、お選びになるときに、紫式部は、「すべて見慣れてございますので、(物語を)新しくつくって差し上げなされよ」と申し上げたところ、「そうであるなら(あなたが)作りなさいよ」とおっしゃったので、『源氏物語』を作って差し上げたということだ。

「させ給ひて」「させ給ふに」といった「二重尊敬(最高敬語)」がありますので、「上東門院(彰子)」の行為だと考えます。
そのとき近くにいた「紫式部」が、「(大斎院にとっては)どの物語も見慣れてるでしょうから、新しく作って差し上げなさるのがいいのでは?」と申し上げるのですね。
すると、上東門院(彰子)は、「じゃあ作ってよ」と紫式部におっしゃるわけです。「仰せられ」も最高敬語と考えましょう。尊敬語「仰す」に尊敬の助動詞「らる」がついた「二重尊敬(最高敬語)」です。
こういったいきさつで、『源氏物語』ができたということですね。
助詞「に」や「ば」を転換点にして主体者が変化していることに着眼しましょう。必ず変わるわけではないのですが、変わることが多いです。
なお、接続助詞「を」「に」「が」「ど」「ば」などの直後に、人物名・役職名などが明記されている場合、そこで主体者が変わります。主体者が変わり、その人物を明記しないとわかりにくいからこそ、主体者が明記されるのです。
いよいよ心ばせすぐれて、~
いよいよ心ばせすぐれて、めでたきものにてさぶらふほどに、伊勢大輔参りぬ。それも歌詠みの筋なれば、殿いみじうもてなさせ給ふ。
(紫式部は)ますます心くばりが優れて、すばらしい女房としてお仕えするうちに、伊勢大輔が(女房として上東門院ともとに)参上した。それ【伊勢大輔】も歌詠みの家系であるので、殿【藤原道長(上東門院の父)】はたいそう大切に扱いなさる。

いきなり主語のない文がくるのですが、こういう場合には、「それまでの展開で登場していた人」の行為になります。
ここまでで出ていたのは「大斎院」「上東門院(彰子)」「紫式部」ですね。
さて、ここは「尊敬語」がついていないですし、「さぶらふ(お仕えする)」とあるわけですから、「紫式部」のことを書いていると考えます。
そんなとき「伊勢大輔」という新しい女房がくるのですね。
「伊勢大輔」の家系も「歌詠み」の家柄だったので、「殿(藤原道長)」は「伊勢大輔」を大切に扱います。「殿」の行為にも最高敬語(二重尊敬)がついていますね。
「彰子」は「道長」の娘ですから、その娘の近くに「教養ある女性」が集まることは、道長にとってうれしいことなのです。
余談ですが、「彰子」の周囲には、「紫式部」「和泉式部」「赤染衛門」「伊勢大輔」といったように、当代随一の女流作家たちがゴロゴロいるのです。
奈良より年に一度、八重桜を折りて持て参るを、紫式部、取り次ぎて参らせなど、歌詠みけるに、式部、「今年は大輔に譲り候はむ」とて、譲りければ、取り次ぎて参らするに、殿、「遅し遅し」と仰せらるる御声につきて、
奈良から年に一度、八重桜を折って持って参上するのを、紫式部が、取り次いで(上東門院に)差し上げるなど(してその際に)、(毎年)歌を詠んだが、(紫)式部は、「今年は大輔に(その役目を)譲りましょう」として、譲ったので、(伊勢大輔が)取り次いで差し上げるときに、殿【道長】が、「(歌を詠むのが)遅い遅い」とおっしゃる御声につづいて、

式部が「譲りければ」とあるので、直後は「譲られた側」の行為になる可能性が高いです。
譲れられたのは「伊勢大輔」ですね。「伊勢大輔」が「八重桜の取り次ぎ役」になったのです。
「まゐらす」という謙譲語は、本動詞で用いる場合「差し上げる」の意味になります。
そのあと、「遅し遅し」とおっしゃるのは「殿(道長)」の行為になります。さすがに書かないとわかりにくいので、「殿」と明示しているわけですね。
このように、「主語を書かないことが多い」古文の文章においても、さすがに書かないとわからない場合はちゃんと書かれます。ということは、主語が書いていないものについても、当時の人々は文構造でわかっていたことになりますね。
いにしへの 奈良の都の 八重桜 今日九重に にほひぬるかな
遠い昔の、奈良の都の八重桜が、今日はこの宮中で九重に美しく咲いたことよ

「九重」は「宮中」を意味します。
昔の中国の王城が、9つの門で守られていた構造に由来するのですね。

ああ~。
これは「八重桜」ですけれども、「九重(宮中)」に咲いておりますねえ・・・ってうまいこと言ったんだな。
「取り次ぎつる程もなかりつるに、いつの間に思ひつづけけむ」と、人も思ふ、殿もおぼしめしたり。
「取り次いでいる時間もなかったのに、いつの間に思いついたのだろう」と、(周囲の)人も思い、殿【道長】もお思いになった。

「思し召す」は、尊敬語「思す(おぼす)」+尊敬語「召す」であり、「二重尊敬(最高敬語)」になります。
めでたくて候ふほどに、~
めでたくて候ふほどに、致仕の中納言の子の、越前守とて、いみじうやさしかりける人の妻に成りにけり。逢ひ始めたりける頃、石山に籠りて音せざりければ、つかはしける、
(伊勢大輔は)すばらしくおりますうちに、官職を退いた中納言の子で、越前守として、たいそう慎み深かった人【高階成順】の妻になった。逢い始めたころ、(成順が)石山寺に籠って連絡がなかったので、送った歌は、

前の部分の最後のほうの話題の中心は「伊勢大輔」なので、この「めでたくて候ふうちに」の主語は「伊勢大輔」だと考えます。女房としての資質がすばらしかったのでしょうね。
「致仕」は注意書きにあるように、「官職を退く」ということです。官職を退いた中納言の子どもで、越前守で、たいへん慎み深かった人の妻になったのですね。
この人【夫】は「高階成順」という人です。「やさし」という形容詞は超重要語ですよ。もともとは「痩せてしまうほどの」ということなので、「消え入りたい・はずかしい・つらい」という意味になりますが、ここでの使い方のように、心情ではなくて「人物像」に用いている場合には「慎み深い・控えめだ・優美だ・殊勝だ」といった意味になります。
「たいそう慎み深い人」と訳しておきましょう。
みるめこそ あふみの海に かたからめ 吹きだに通へ 志賀の浦風
と詠みてやりたりけるより、いとど歌おぼえまさりにけり。
海藻は(淡水の)近江の海では採るのがむずかしいだろうが、せめて吹き通るだけでもしてほしい。志賀の浦からの風。
【あなたは近江の石山寺に籠っているからその姿を見ることはむずかしいが、せめてあなたからの風の便りだけでもこないものかな】
と詠んで、送ったことにより、いよいよ歌の評判がすぐれていった。

海松布(みるめ)は海藻のことです。
近江の海というのは琵琶湖のことですが、琵琶湖は淡水の湖なので、ワカメやコンブみたいな海藻は存在しないのですね。
夫である成順が籠っている「石山寺」は近江にありますから、伊勢大輔は、「近江の湖では海松布(みるめ)が取りにくいよね・・・」という表現で、「石山寺に籠っているあなたの姿を見ることはできないよね・・・」と言っているのですね。

それで「志賀からの風だけでも吹いてほしいなあ」っていうことで、「風の便りくらいくれないのかなあ」って言っているわけか。
こりゃあ、歌の評判も上がるってもんだよね。
まことに子孫栄えて、~
まことに子孫栄へて、六条の大弐、堀河の大弐など申しける人びと、この伊勢大輔の孫なりけり。白河院は曾孫おはしましけり。一の宮と申しける折、参りて見まゐらせけるに、「鏡を見よ」とて、たびたりけるに、たまはりて、
君見れば ちりもくもらで 万代の よはひをのみも ます鏡かな
御返し、大夫殿、宮の御をぢにおはします、
曇りなき 鏡の光 ますますも 照らさむかげに かくれざらめや
本当に子孫が繫栄して、六条の大弐、堀河の大弐などと申し上げる人々は、この伊勢大輔の孫であった。白河院はひ孫でいらっしゃった。(白河院が)一の宮と申し上げた折、(伊勢大輔が)参上してお会い申し上げたところ、(白河院が)「鏡を見よ」と、お与えになったのを、(伊勢大輔は)いただいて、
一の宮を見るとすこしも曇らないで、これから万代の年齢が続くことを映す鏡だなあ
ご返歌を、一の宮のおじでいらっしゃる大夫殿が、
曇りのない鏡の光【一の宮の威光】がますます(世を)照らすような、その光の恩恵を受けないことがあろうか、いや受けるはずだ。

「かげ」は、現代語では「シャドー(光によってできる黒い部分)」を意味することが多いですけれども、古文では「光そのもの」や「光によって生じるもの」を広く意味します。
そのため、「物陰(見えていない部分)」のほうを意味するよりも、「光・姿・形」を意味することが多いです。
現代語でも「月影」とか「人影」とかいう場合、「光」や「かたち」のほうの意味で用いられています。
ここでの「かげにかくる」という表現は、「光が照らすエリアにはいる」という意味合いです。

白河院の発する光が照らすエリアに入らないことがあるか、いや入る!
と言っているわけだな。

「かげ」はそもそも「光によって生じるもの」を意味しますので、「恩恵」という意味でも使います。
この歌についても、「白河院の神々しい力の恩恵を受けないことがあろうか、いや、受けるに違いない」という意味で解釈できますね。
(以下余白)