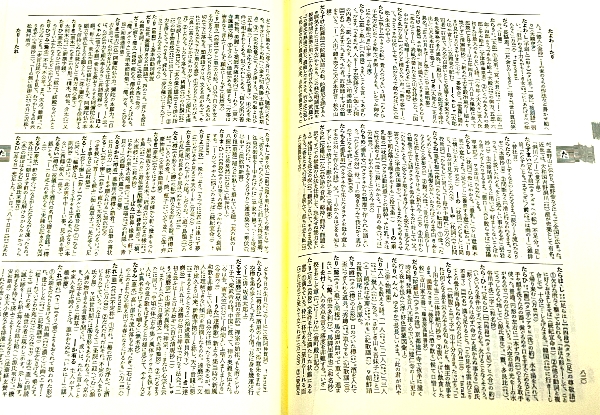- 南陽宋定伯、年少時、夜行逢鬼。
- 問之、鬼言、「我是鬼。」
- 鬼問、「汝復誰。」
- 定伯誑之言、「我亦鬼。」
- 鬼問、「欲至何所。」
- 答曰、「欲至宛市。」
- 鬼言、「我亦欲至宛市。」
- 遂行数里。
- 鬼言、「歩行太遅、可共逓相担、何如。」
- 定伯曰、「大善。」
- 鬼便先担定伯数里。
- 鬼言、「卿太重、不是鬼也。」
- 定伯言、「我新鬼。故身重耳。」
- 定伯因復担鬼、鬼略無重。如是再三。
- 定伯復言、「我新鬼、不知有何所悪忌。」
- 鬼答言、「唯不喜人唾。」
- 于是共行、道遇水。
- 定伯令鬼渡、聴之了然無水音。
- 定伯自渡漕漼作声。
- 鬼復言、「何以作声。」
- 定伯曰、「新死、不習渡水故爾。勿怪吾也。」
- 行欲至宛市、定伯便担鬼著肩上、急執之。
- 鬼大呼、声咋咋然。索下、不復聴之。
- 径至宛市中、下著地、化為一羊。
- 便売之、恐其変化唾之。
- 得銭千五百、乃去。
- 当時有言、「定伯鬼売、得銭千五。」と。
南陽宋定伯、年少時、夜行逢鬼。
南陽の宋定伯は、年少き時、夜行きて鬼に逢ふ。
なんやうのそうていはくは、としわかきとき、よるゆきてきにあふ。
南陽の宋定伯は、若いとき、夜に出かけて幽霊に出会った。

「少」は、「わかシ」と読みます。ここでは連体形なので「わかキ」ですね。
漢文では、年が若いことは「少」を用いまして、「若」を使うことはありません。

「鬼」は、「ツノが生えていて金棒持ってるやつ」ではないです。漢文で「鬼」が出てきたら「幽霊」のことだと思ってください。
「おに」と読むと誤解が生じるので、「き」と読むのがふつうです。

「逢」は、「思いがけず、偶然に出会う」ということです。
訳は「出会う」でOKです。
問之、鬼言、「我是鬼。」
之に問へば、鬼言ふ、「我は是れ鬼なり。」と。
これにとへば、きいふ、「われはこれきなり。」と。
これ【幽霊】に問いかけると、幽霊は言った、「私は幽霊だ。」と。

○○は是れ△△
のかたちで、「○○は△△である」という意味になります。
このときの「是」は、英語でいう「be動詞」みたいなものです。
鬼問、「汝復誰。」
鬼問ふ、「汝は復た誰ぞ。」と。
きとふ、「なんぢはまたたれぞ。」と。
幽霊は問う、「おまえはいったい誰だ。」と。

「汝」は「なんぢ」と読みます。「おまえ」という意味ですね。
「なんぢ」と読んで「おまえ」という意味で用いる字は、他に「若」「而」「女」「乃」「爾」など、けっこうありますね。

「復」は「まタ」と読みます。
もともとは「元に戻る」ということなのですが、「(状態を元に戻して)もう一度」というニュアンスで、「ふたたび・さらに」という意味で用いられます。
また、その「反復」のイメージが「強める」意味に結び付き、「疑問・反語」や「否定」を強調する意味でも用いられます。
「疑問・反語」を強調しているのであれば「いったい(~か)」と訳し、「否定」を強調しているのであれば「決して(~ない)」などと訳します。
ここでは「誰」が「誰だ?」という疑問を示していますので、「復」は「疑問を強調している」ものと解釈して、「いったい誰だ」と訳しましょう。
定伯誑之言、「我亦鬼。」
定伯之を誑きて言ふ、「我も亦鬼なり。」と。
ていはくこれをあざむきていふ、「われもまたきなり。」と。
定伯はこれ【幽霊】をあざむいて言った、「私もまた幽霊である。」と。

「亦」は、直前に「も」がついて、「~もまた」と読みます。
「亦」という字と「又」という字は「また」以外の読みがないこともあり、送り仮名の「タ」を出しません。
一方、「復」や「還」は、「まタ」とも読みますし、「かへル・かへス」などとも読みます。そういう違いもあって、「復」「還」を「まタ」と読む場合には、送り仮名の「タ」を出すことが多いです。
鬼問、「欲至何所。」
鬼問ふ、「何れの所にか至らんと欲する。」と。
きとふ、「いづれのところにかいたらんとほつする。」と。
幽霊は質問した、「どこに行こうとしているのか。」と。

「何所」は、「いづレノところニ(カ)」と読んで、「どこに~か」と地理的な場所を問う疑問用法になります。
まれに地理的な場所を聞いているわけではない「何所」がありまして、その場合は「何」を「なに」と読むこともあります。この漢文でもあとのほうに出てきます。

「欲」は、動詞の上に位置して、下の動詞から返って、「(未然形)ント欲ス」と訓読します。
「~したいと思う」「~しようとする」などと訳しましょう。
答曰、「欲至宛市。」
答へて曰く、「宛市に至らんと欲す。」と。
こたへていはく、「ゑんのいちにいたらんとほつす。」と。
(定伯が)答えて言うには、「宛県に立つ市に行こうとしている。」と。
鬼言、「我亦欲至宛市。」
鬼言ふ、「我も亦宛の市に至らんと欲す。」と。
きいふ、「われもまたゑんのいちにいたらんとほつす。」と。
幽霊は言った、「私もまた宛県に立つ市に行こうとしている。」と。
遂行数里。
遂に行くこと数里なり。
つひにゆくことすうりなり。
(二人は)そのまま数里ほど行った。(そのまま行ったのは数里である)

「遂」は「遂行」の「遂」で、「進んでいく」という意味合いがあります。
動詞の場合は「とグ」と読み、「とげる」と訳します。
副詞のように使う場合は「つひニ」と読みます。
「流れでそうなった」というニュアンスならば「そのまま」と訳します。
「最終的には」というニュアンスならば「とうとう・結局」などと訳します。
どちらかというと、「流れでそうなった」という文脈で使用されて、「そのまま・こうして」と訳すことが多いですね。

他に「つひ二」と読む漢字には、「終」「卒」「竟」があります。
これらは「最終的には」とう意味で用いられることが多く、「とうとう・結局」と訳します。
終 (終に) とうとう・結局
卒 (卒に) とうとう・結局
竟 (竟に) とうとう・結局
遂 (遂に) そのまま・こうして・とうとう・結局
*「遂に」は、「そのまま」の意味で用いることが多い。
鬼言、「歩行太遅、可共逓相担、何如。」
鬼言ふ、「歩行すること太だ遅し、共に逓ひに相担ふべし、何如。」と。
きいふ、「ほこうすることはたはだおそし、ともにたがひにあひになふべし、いかん。」と。
幽霊は言った、「歩くのがあまりに遅すぎる、二人で交代で背負っていくのがよい、どうだろうか。」と。

「太」は「はなはダ」と読み、「非常に・たいへん」という意味になります。「あまりに~すぎる」と訳してもいいですね。
「はなはダ」と読む字としては、どちらかというと「甚」のほうがよく出てきます。

「如何」は「いかん」と読みます。訳は「どうであるか」「どうだろうか」などになります。
状態・是非・程度などを問うことばで、ここでは「二人で交替で背負って行くのがよい」という提案について、「どうだろうか」と聞いています。
定伯曰、「大善。」
定伯曰く「大いに善し。」と。
ていはくいはく、「おほいによし。」と。
定伯は言った。「大変よいことだ。」と。
鬼便先担定伯数里。
鬼便ち先づ定伯を担ふこと数里。
きすなはちまづていはくをになふことすうり。
幽霊はすぐに、まず定伯を背負って行くこと数里。

「便」は「すなはチ」と読みます。「都合がよく、差し障りがない」ことを示し、それが「時間的に滞りがないこと」を示す場合は「すぐに」と訳します。
「論理的に妨げがないこと」を示す場合は「つまり」と訳します。
漢文で使用される場合はたいてい「すぐに」のほうの意味ですね。

里は「人間が歩いてだいたい1時間くらいの距離」です。だいたい4キロくらいですね。
鬼言、「卿太重、不是鬼也。」
鬼言ふ、「卿は太だ重し、是れ鬼ならずや。」と。
きふ、「けいははなはだおもし、これきならずや。」と。
幽霊は言った、「おまえは非常に重い、さては幽霊ではないのではないか。」と。

「卿(けい)」は本来は敬称ですが、とくに敬意をこめず「お前」と訳すような場合でも使用されます。
定伯言、「我新鬼。故身重耳。」
定伯言ふ、「我は新鬼なり。故に身重きのみ。」と。
ていはくいふ、「われはしんきなり。ゆゑにみおもきのみ。」と。
定伯は言った、「私は幽霊になったばかりだ。だから体が重いだけだ。」と。

「耳」は「のみ」と読みます。「助詞」なので書き下し文ではひらがなになります。
「~だけ」という「限定」の意味になります。「~なのである」「~なのだ」という「強調」の意味にもなります。
ここでの文脈なら、限定でも強調でもどちらでもいいですね。
同じように「のみ」と読む字には、「已」「爾」などがあります。
定伯因復担鬼、鬼略無重。如是再三。
定伯因りて復た鬼を担ふに、鬼略重さ無し。是くのごときこと再三なり。
ていはくよりてまたきをになふに、きほぼおもさなし。かくのごときことさいさんなり。
定伯はそこで今度は幽霊を担ぐと、幽霊はほとんど重さがなかった。このようなことを何度も繰り返した。

「因」は「頼ってしたがう」という意味をもつ字です。因果関係を示す接続詞としても用います。
動詞なら「よル」と読み、「頼る・したがう」などと訳します。
接続詞なら「よりテ」と読み、「そこで・そのため」などを訳します。
定伯復言、「我新鬼、不知有何所悪忌。」
定伯復た言ふ、「我は新鬼なり。何の悪忌する所有るかを知らず。」と。
ていはくまたいふ、「われはしんきなり。なんのをきするところ有るかをしらず。」と。
定伯はまた言った、「私は幽霊になったばかりだ。(だから、幽霊が)どんな忌みにくむところがあるのかを知らない。」と。

「何所」は、多くの場合は「いづレノところニ(カ)」と読んで、「どこに~か」と場所を問う疑問用法になります。最初のほうに出てきましたね。
しかし、ここでは「鬼」が「悪忌(いやがること)」は「どんなところなのか」と問うているので、「地理的な場所」を聞いているわけではありません。
「どこ?」と聞いているのではなく「なに?」と聞いているのですね。
そのためここでの「何」は「なんの」と読みます。

質問があったので補足します。
ここの「何」を「いづれの」と読んでも間違いとは言えません。
ただ、どちらかというと「なんの」と読んでおいた方がいいです。
理由を述べます。
この文章の最初のほうに出てきた文と比較してみましょう。
欲至何所 (いづれのところにかいたらんとほっする)
ここでは「何所」が「目的語」に該当しますが、直前の動詞は「至」です。
つまり、「どこの場所に行くのか?」と聞いていることになります。
それに対して、ここでの文は
有何所悪忌 (なんのをきするところあるか)
となっています。「所悪忌」が目的語に該当し、直前の動詞は「有」です。
つまり、「忌みにくむところはあるのか?」と聞いていることになります。
ここでの「所」は、いわば「形式名詞」のような役割を果たしていて、「実際の存在する土地としての場所」を意味しているわけではありません。しかも「あるか?」と聞いているので、「ない」という返答もありうるわけです。
「いづれの」と問う場合は、「学校」「公園」「市役所」などといった「暗黙の選択肢」があって、そのうちの「どれにいくのか」という聞き方になります。つまり「どこかに行く」ことが「前提」となっていて、それが「どこ」なのかと聞いていることになります。この場合に「何」を「なんの」と読むのはおかしいです。
現在でも「なにに行くの?」とは聞きません。
一方で、「何か忌みにくむところはあるか?」という聞き方は、「有るか?」と聞いていることもあり、「どこかを選択する」というニュアンスとはちょっと違いますね。そのため、ここは「何」を「なんの」と読んでいます。
鬼答言、「唯不喜人唾。」
鬼答へて言ふ、「唯だ人の唾を喜ばざるのみ。」と。
きこたへていふ、「ただひとのつばきをよろこばざるのみ。」と。
幽霊は答えて言った、「ただ人の唾を好まないだけだ。」と。

「唯」は「たダ」と読みます。
「限定」を示します。
于是共行、道遇水。
是に于いて共に行くに、道に水に遇ふ。
ここにおいてともにゆくに、みちにみずにあふ。
そこで(また)一緒に行くと、道中で川に遭遇した。

「於是」と書いて、「是に於いて(ここにおいて)」と読む表現が、「四面楚歌」でも出てきましたね。「そこで」と訳します。
ここでの「于」は、「於」と同じはたらきをする語で、「于是」も「ここにおいて」と読みます。意味は同じで「そこで」と訳します。
定伯令鬼渡、聴之了然無水音。
定伯鬼をして渡らしめ、之を聴くに了然として水音無し。
ていはくきをしてわたらしめ、これをきくにれうぜんとしてみづおとなし。
定伯は幽霊を先に渡らせて、その様子を聞いていたが、まったく水音はしなかった。

A 令 B P という「使役構文」で、
A B をして P(未然形)しむ
と読みます。「令」は助動詞なので、書き下し文ではひらがなになります。
訳は
A は B に Pさせる
となります。
定伯自渡漕漼作声。
定伯自ら渡るに、漕漼として声を作す。
ていはくみづからわたるに、さうさいとしてせいをなす。
定伯が自分で渡ると、ざわざわとと音がした。

「自ら」は、「みづから」と読む場合は「自分で」という意味です。
「おのづから」と読む場合は「自然に」という意味です。
ここでは「みづから」と読んでいますので、「自分で」の意味です。
鬼復言、「何以作声。」
鬼復た言ふ、「何を以つて声を作す。」と。
きまたいふ、「なにをもつてせいをなす。」と。
幽霊はまた言った、「どうして音がするのか。」と。

「何以」は、「何を以つて(なにをもつて)」と読みます。
(1)「理由」を尋ねて、「どうして」と訳す。
(2)「手段・方法」を尋ねて、「どうやって」と訳す。
どちらかの用法になります。
ここでは文脈上(1)がいいですね。
定伯曰、「新死、不習渡水故爾。勿怪吾也。」
定伯曰く、「新たに死し、水を渡るに習せざるが故のみ。吾を怪しむこと勿かれ。」と。
ていはくいはく、「あらたにしし、みづをわたるにしふせざるがゆゑのみ。われをあやしむことなかれ。」と
定伯が言うには、「死んだばかりで、川を渡るのに慣れていないだけだ。私を怪しむな。」と。

「勿」は、「なカレ」と読みます。
(1)禁止(~するな)
(2)教戒(~してはいけない)
(3)否定の命令願望(~しないでくれ)
などの訳になりますが、(1)(2)(3)それぞれの境界はあいまいなので、状況にあわせて柔軟に訳しましょう。
同じような使い方をする漢字はいろいろありますが、「莫」を覚えておきたいですね。
(例)君莫笑 (君笑ふこと莫かれ) (訳)あなたは笑わないでくれ

「也」は、「なり」とか「や」とか読むと思うんだけど、ここでは「置き字」の扱いになるの??

基本的には、「断定」で用いるなら「なり」、「疑問・反語」で用いるなら「や」と読むことが普通です。
ただ、「断定」の「なり」を読むと、なんだかリズムが悪い時には、無視してしまうこともあります。その場合「置き字」とみなします。
特に「命令文」の場合、「吾を怪しむこと勿かれなり」って読むと、ちょっとリズムが悪いですよね。最後の「なり」がなんだか余計な印象です。
そのため、「命令文」にある「也」は高い確率で読みません。
行欲至宛市、定伯便担鬼著肩上、急執之。
行宛の市に至らんと欲し、定伯便ち鬼を担ひて肩の上に著け、急に之を執らふ。
ゆくゆくゑんのいちにいたらんとほっし、ていはくすなはちきをになひてかたのうへにつけ、きふにこれをとらふ。
そうこうしているうちに宛の市に到着しそうになると、定伯はすぐに幽霊を担いで肩の上にのせ、いきなり幽霊を捕まえた。
鬼大呼、声咋咋然。索下、不復聴之。
鬼大いに呼び、声咋咋然たり。下ろさんことを索むれども、復た之を聴かず。
きおほいによび、こゑさくさくぜんたり。おろさんことをもとむれども、またこれをきかず。
幽霊は大声をあげて叫んだ。(幽霊が)下ろしてくれと求めたけれども、決してこれを聞き入れなかった。

「復」は、「ふたたび」ということなので、
不復~。(復た~ず。)
で「二度としない」という意味になります。
ただ、「回数」を問題としているのではなく、「強い否定」を表す場合も多く、その場合は、「決して~ない」「まったく~ない」などと訳すといいですね。ここも「二度としない」と訳すと文脈に合わないので、「決してしない」と訳しましょう。
径至宛市中、下著地、化為一羊。
径ちに宛の市中に至り、下ろして地に著くれば、化して一羊と為る。
ただちにゑんのしちゅうにいたり、おろしてちにつくれば、くわしていちやうとなる。
すぐに宛県に立つ市中に至り、下ろして地面におさえつけると、(幽霊は)化けて一匹の羊となった。
便売之、恐其変化唾之。
便ち之を売り、其の変化せんことを恐れて之に唾す。
すなはちこれをうり、そのへんくわせんことをおそれてこれにつばきす。
すぐにそのままこれ【幽霊が化けた羊】を売って、それが変化することを心配して、これに唾を吐いた。
得銭千五百、乃去。
銭千五百を得て、乃ち去る。
ぜにせんごひやくをえて、すなはちさる。
(定伯は)銭千五百を得て、そこで立ち去った。

「乃」は「すなはチ」と読みます。
順接で用いることが多いのですが、その場合も、ものごとが一筋縄ではいかず、時間的・論理的に何らかの引っかかりを生じるニュアンスがあります。
(1)そこで・そして
(2)しかし・かえって
(3)やっと
(4)なんと・意外にも
など、「前件」と「後件」のあいだにちょっとした「間」があったり、ちょっとした「屈折」があったりするときに用いられやすいです。(2)にかんしては逆接的な用い方ですね。
ここでは、「いろいろあって、そして、次がある」という文脈なので、(1)の用い方だと考えましょう。たいていは(1)で訳して大丈夫です。
当時有言、「定伯鬼売、得銭千五。」と。
当時言へる有り、「定伯鬼を売り、銭千五を得たり。」と。
たうじいへるあり、「ていはくきをうり、ぜにせんごをえたり。」と。
当時(の人々)はこう言った、「定伯は幽霊を売って、千五百の銭を手に入れた。」と。

以上です!