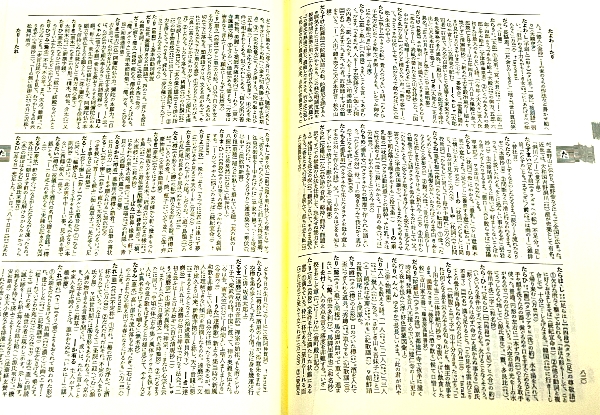和氏の璧

「和氏の璧」という物体が出てきますので、それについて見ておきましょう。
「楚」の国にいた卞和(べんか)という男が、山中で玉の原石を見つけました。それを楚の厲王に献上しましたが、鑑定人がただの石だと言ったので、厲王は怒り、卞和の左足を切断する刑に処しました。厲王が亡くなった後、卞和は同じ石を武王に献上しましたが、やはりただの石だと思われ、今度は右足切断の刑に処せられました。文王が即位した後、その石を抱いて泣き続けている卞和に理由を聞き、その原石を磨かせたところ、名玉になったのです。文王は、その名玉に卞和の名をつけて「和氏の璧」と呼びました。

そののち、「和氏の璧」は趙の恵文王の手にわたりましたが、秦の昭王が、「秦にある15の城(都市)と交換しようよ」と提案してきます。
実は「秦の昭王」は、15の城(都市)を渡すつもりはなく、「和氏の璧」をただで手に入れようとしていたのですが、恵文王の使いとして秦に派遣された藺相如は、髪の毛をグワーッと逆立てて「オレの頭はこの璧といっしょに粉々に砕けちっゾ!!」とブチ切れました。
璧は従者に持って帰らせることに成功したのですが、藺相如は、(わざとではありますが)ブチ切れてしまった手前もありますし、「璧」を持って帰らせてしまってますから、何らかの処分があるだろうと、秦の昭王からの命令を待ちました。ところが昭王は「あっぱれ。おめえは賢いやつだな」という感じで藺相如を許し、趙に帰しました。
藺相如は「璧を完う(へきをまっとう)」したのです!!

ああ~。
いま「完璧」っていうのは、この「璧を守るミッションを完遂した」というエピソードから来てるんだな。

そうですね。
現在では、「傷ついていない、完全無欠な状態のこと」を「完璧」といいますね。
ちなみに、この「和氏の璧」は、「15の城(都市)」ほどの価値があるので、「連城の璧」と呼ぶこともあります。
完璧而帰(璧を完うして帰る)

それでは、「書き下し文」と「現代語訳」を見ていきましょう。
「書き下し文」の下にある「点線囲い」の中が「現代語訳」です。
なお、書き下し文の漢字につけてあるルビは、現代仮名遣いでの読み方です。
趙恵文王、嘗得楚和氏璧。
趙の恵文王、嘗て楚の和氏の璧を得たり。
趙の恵文王は、ある時、楚の「和氏の璧」を手に入れた。
秦昭王、請以十五城易之。
秦の昭王、十五城を以つて之に易へんことを請ふ。
秦の昭王は、(秦の)15の城【都市】を、和氏の璧に交換することを請願してきた。

漢文では、「訓読み」がある漢字が熟語(連語)ではなく「一文字」で出てきたときは慣習的に「訓読み」で読みます。
たとえば「城」は、この部分では「十五城」という連語になっているので「じゅうごじょう」と読みますが、「一文字」で出てきていれば「しろ」と読みます。
なお、中国で「城」という場合、日本のお城とは異なり、「城壁で囲まれた都市」を指すので、ここでは「15の都市」を「璧」と交換したいと申し出ていることになります。
ちなみに「城壁」の「壁」と「和氏の璧」の「璧」は字が違うので気をつけてください。
「完璧」の「璧」は、下が「玉」です!!!
欲不与畏秦強、欲与恐見欺。
与へざらんと欲すれば、秦の強きを畏れ、与へんと欲すれば、欺かれんことを恐る。
(恵文王は)秦に璧を与えないとすれば、秦の武力【秦が攻めてくること】を恐れ、秦に璧を与えようとすれば、だまされるだろう【15の都市はもらえないだろう】と恐れた。

「~んと欲す」というのは、「~しようとする」「~したいと思う」ということです。
藺相如願奉璧往。
藺相如璧を奉じて往かんことを願ふ。
(すると)藺相如が、和氏の璧を(大事に)持って(秦に)行くことを願い出た。
曰、「城不入、則臣請、完璧而帰。」
曰はく、「城入らずんば、則ち臣請ふ、璧を完うして帰らん。」と。
(藺相如が)言うことには、「城が手に入らなければ、和氏の璧を完全な状態で持ち帰らせてください。」と。

「則」は、「すなはち」であり、現代仮名遣いであれば「すなわち」と読みます。
「則」の前には、たいてい「仮定条件」の「ば」があります。
もし~すれば(ならば)、そのそきは(その場合は)、~する。
というように、「則」の前を「仮定条件」として訳すことになります。
「レバ」に続くことが多いので、俗に「レバ則」などと呼ばれます。

「臣」は、「臣下」のことですから、「藺相如」自身のことを指しています。
「(臣下の)私は願い出る(こうしたいと思う)、~」ということです。
逐語訳すると、
「私はこうすることを願い出る、璧を完全なままで持ち帰ろう。」
ということです。「仮定条件」も含めて自然な言い方にまとめてしまうと、
「もし、城(都市)が手に入らなければ、そのとき私は璧を完全なままで持ち帰ってもいいだろうか」
という訳になります。

「而」は置き字なんだね。

「接続」を表す置き字です。
「而」のかたちはもともと「ヒゲ」だと言われており、「下に垂れ下がっている」というイメージです。そのことから、「話が下に続くよ」という目印でそこに置かれていると考えてください。
(1)このように、根本的には「下に続く」ということであり、直前に読む語に「テ」「シテ」などの送り仮名をつけることが多いです。
(2)ただ、文脈的に「予期した内容とは逆になるつながり方」になることもあり、その場合、直前に読む語に「ドモ」「ニ」「モ」などの送り仮名をつけます。
(1)が「順接」、(2)が「逆接」の用法と言われますが、基本的には(1)が多いですね。
もともとこういう「接続」の意味を含んでいるので、置き字ではなく、「接続詞」として読むこともあります。
「而シテ」「而レドモ」「而ルニ」「而モ」というように「送り仮名」がついている場合は、「接続詞」と考えて書き下し文にも出しましょう。
なお、「而シテ」の場合は「順接」で、「そして」と訳します。
「而レドモ」「而ルニ」「而モ」の場合は「逆接」で、「しかし」と訳します。
既至
既にして至る。
やがて(藺相如は秦に)到着した。
秦王無意償城。
秦王城を償ふに意無し。
秦王は城【都市】を報償として与える意志がなかった。

『十八史略』は、「略」なので、細かいところが省かれているのですが、ここは、もとの出典の『史記』によれば、次のような展開があります。
藺相如が「和氏の璧」を秦王に渡すと、秦王は周辺の人たちに見せて、周囲もわあわあ喜びます。
藺相如はその様子を見て、「あれ、城と交換する気がないな」と確信します。
そこで藺相如は、「その璧についている傷のことを秦王に教えます。」と嘘をついて、いったん「和氏の璧」を手元に取り返します。
相如乃紿取璧、怒髪指冠、卻立柱下曰、「臣頭与璧倶砕。」
相如乃ち紿きて璧を取り、怒髪冠を指し、柱下に卻立して曰はく、「臣の頭璧と倶に砕けん。」と。
藺相如はそこで(秦王を)だまして和氏の璧を奪い、怒りで髪の毛が冠を突き上げるほどであり、柱の下立って言うことには、「私の頭は璧と一緒に(柱にぶつけて)砕けるだろう。」と。

「乃」は、「すなはち」であり、現代仮名遣いなら「すなわち」と読みます。
これ、もともとは「耳たぶ」のかたちであって、「ちょっとぐにゃっとした状態でくっついている」ということになります。
前の出来事に「くっついて」いることを示すのですが、「耳たぶ」の「曲がっている」様子から、「何らかの屈折」を意味しているともいわれます。
(素直にはつながりにくいものをつなげていると言われます)
主に、
① そこで ② しかし ③ なんと(まあ)・意外にも
などと訳します。
「くっついている」ことに意味の比重があれば、①のように訳します。感情的な「屈折」のほうに意味の比重があれば、「②しかし」「③なんとまあ・意外にも」などと訳します。
「いちおうつながっているのだけれども素直ではないつながり」のことですので、前件と後件のあいだにいったん間があることを含み、「やっと」などと訳すこともあります。
さて、この場面は、シンプルに「①そこで」と訳しておけばOKですが、「藺相如」が大胆な行動に出る場面ですので、「前件と後件が思いがけないつながりをしている」というイメージで、「③なんとまあ」などと訳しても問題ないですね。
遣従者懐璧間行先帰、身待命於秦。
従者をして璧を懐きて間行して先づ帰らしめ、身は命を秦に待つ。
従者に璧を抱えさせ抜け道を通らせて先に帰らせて、自分自身は(秦王からの)命令を秦で待った。

ここでの「遣」は「使役」の意味となる助動詞です。
「をして」がありますので、「従者」に何かをさせたことになります。
何をさせたのかというと、
「璧を抱えさせ、抜け道を通らせて先に帰らせた」
ということになります。

ここに置き字の「於」がありますね。
「於」は「場所」を示します。ここでは「秦」に残ったまま待っていたことを示していることになります。
秦昭王賢而帰之。
秦の昭王賢として之を帰らしむ。
秦の昭王は、(藺相如を)賢い人【優れた人】として帰らせた。

ここでは「使役」の漢字はありませんが、送り仮名に「しむ」がありますので、「帰らせた」と訳します。

また置き字の「而」があるね。

ここも「順接」でいいですね。
ここでは「賢い人と判断して、そして、趙国に帰らせた」という意味合いになります。

母国に帰ることができてよかったね。

ここで「秦」が「藺相如」に罰を与えることはなかなかできません。「大義名分」がないからです。
『史記』によれば、「『璧』と『十五の城(都市)』を交換しよう」と「秦」のほうから持ち掛けておいて、わざわざ「藺相如」が出向いているのに、「璧」を預かってキャッキャしていて、「都市」の話はなかなか出してこないわけです。
この時点で、けっこう「趙」側に対して失礼なことをしていますよね。
その様子から「藺相如」は、「都市を与える気がない態度だ」と「みなし」て、「璧」を取り返すわけです。つまり、「秦側は約束を守ろうする態度を取らなかった」という「展開」に持ち込むわけですね。
もともと超側は「都市」をもらえるとはあんまり思っていないので、「璧」を傷つけずに持ち帰るほうが「優先ミッション」になります。「藺相如」はそのことを重々理解しているので、「璧」を無事に持ち帰るための「口実」をうまくつくって、機を逃さずに実行したのですね。

そいつはたしかに賢いね。

とはいえ、実際の現場では「秦の昭王」がテンション上げてブチ切れて「藺相如」を処刑してしまう可能性だってあるわけですから、「藺相如」のメンタルは鋼鉄レベルですよね。
ここで「藺相如」が秦からの処分を待って、そのうえで許されているからこそ、「趙には非がなかった」という「構図」ができあがるのです。もしも「藺相如」も従者といっしょに帰ってしまっていたら、周囲の国々は「え、趙が悪いんじゃない?」と思うかもしれませんよね。

ああ~。
「処分を待って、許されているわけだから、周囲がごちゃごちゃ言うことじゃないよね」となるよね。
「藺相如」は、ちゃんと「趙」の「評判」も守ったのだな。

ここまでは「書き下し」と「現代語訳」ができるようにしておきましょう。
このあとの部分は、「澠池之会(めんちのかい)」という別の話なので、ここの「書き下し文」や「現代語訳」などは試験で問いません。
ただ、「だいたいのストーリー」と、「不」がついている部分の「読み方」だけは注意しておきましょう。
澠池之会
秦王趙王に約して澠池に会す。
秦王は趙王と約束して、澠池で会合した。
相如従ふ。
藺相如が(趙王に)随行した。
酒を飲むに及び、秦王趙王に瑟を鼓せんことを請ふ。
酒宴が始まると、秦王は趙王に大琴を弾いてくれるように求めた。
趙王之を鼓す。
趙王は(しかたなく)大琴を弾いた。
相如復た秦王に缶を撃ちて秦声を為さんことを請ふ。
(そこで)藺相如は秦王に缶をたたいて、秦の音楽を演奏するように求めた。
秦王肯んぜず。
(しかし)秦王は承知しなかった。

「肯」は動詞で用いると「肯ず(がへんず)」と読みます。
「がへんず」の意味は「承知する」ということです。
もともと、「肯定する」という意味の「肯ふ(かふ)」という語がありまして、それに上代の打消の助動詞「ぬ」の連体形「に」がついて、さらに「す」がついて、「かへにす」と言っていました。この場合、もともとは「肯定しないことをする」という意味なのですが、撥音便がおきて「がへんず」と読むようになり、この場合の「ん」がもともと打消の助動詞「に」であったことも忘れられていき、やがて「承知する・聞き入れる」という意味で用いられるようになりました。
否定の助字である「不」とセットになる場合、「不肯」で「がへんぜず」と読みます。
相如曰はく、「五歩の内、臣頸血を以つて大王に濺ぐを得ん。」と。
藺相如は言った、「(私と王とは、わずか)五歩の距離、私は(自分の)首の血を大王に注ぎかけることができるでしょう。」と。
左右之を刃せんと欲す。
(秦王の)側近が藺相如を斬ろうとした。
相如之を叱す。
(すかさず)藺相如が側近をどなりつけた。
皆靡く。
(側近は)皆たじろいだ。
秦王為に一たび缶を撃つ。
秦王は(やむをえず)趙王のために缶を一度たたいた。
秦終に趙に加ふる有る能はず。
(こうして)秦はとうとう(この会合において)趙を凌駕することができなかった。

「能」は、否定の助字「不・弗」を伴うと、「あたはず」と読みます。
それ以外のときは、連用修飾語として「能く(よく)」、または動詞として「能くす(よくす)」と読みます。
趙も亦盛んに之が備へを為す。
(その後、)趙も大いに秦に対する防備を固めた。
秦敢へて動かず。
(そのため)秦も無理には動かなかった。