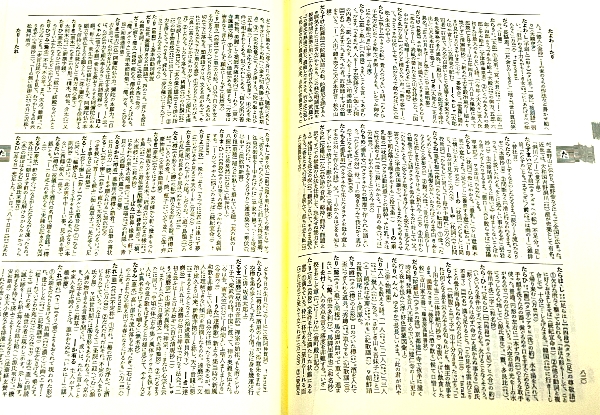権利の上に眠る者
学生時代に末弘厳太郎先生から民法の講義を聴いたとき、「時効」という制度について次のように説明されたのを覚えています。金を借りて催促されないのをいいことにして、ネコババを決め込む不心得者が得をして、気の弱い善人の貸し手が結局損をするという結果になるのはずいぶん不人情な話のように思われるけれども、この規定の根拠には、権利の上に長く眠っている者は民法の保護に値しないという趣旨も含まれている、というお話だったのです。この説明に私はなるほどと思うと同時に、「権利の上に眠る者」という言葉が妙に強く印象に残りました。今考えてみると、請求する行為によって時効を中断しない限り、単に自分は債権者であるという位置に安住していると、ついには債権を喪失するというロジックの中には、一民法の法理にとどまらない極めて重大な意味が潜んでいるように思われます。

「債権」というのは、「お金を貸したときに、返してもらう権利」のことです。この「債権」は、「返して」と言い続けない限り、「5年」または「10年」で消失してしまうのですね。
これは「民法」の話ですけれども、このように、「する」ことをせずに「である」の状態を存続させてしまうと、その「である」ことすらなくなってしまうことは、「民法以外」の分野でもいろいろ当てはまりそうですね。
たとえば、「教員」は、「属性」としてはたしかに「教員」ですけれども、その人が「授業」をしないでごろごろしていたら、すぐに「教員である権利」を失ってしまうでしょう。つまり、「教員」としての「確固たる内在性」ではなくて、「授業」を「する」という「行動の継続」によって、教員「である」という資格を保持できるわけです。
例えば、日本国憲法の第十二条を開いてみましょう。そこには「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と記されてあります。この規定は基本的人権が「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であるという憲法第九十七条の宣言と対応しておりまして、自由獲得の歴史的なプロセスを、いわば将来に向かって投射したものだと言えるのですが、そこに先ほどの「時効」について見たものと著しく共通する精神を読み取ることは、それほど無理でも困難でもないでしょう。つまり、この憲法の規定を若干読み替えてみますと、「国民は今や主権者となった、しかし主権者であることに安住して、その権利の行使を怠っていると、ある朝目覚めてみると、もはや主権者でなくなっているといった事態が起こるぞ。」という警告になっているわけなのです。これは大げさな威嚇でもなければ、空疎な説教でもありません。それこそナポレオン三世のクーデターからヒトラーの権力掌握に至るまで、最近百年の西欧民主主義の血塗られた道程が指し示している歴史的教訓にほかならないのです。

もう本当にぐうの音もでないですよね。
たとえば選挙でいうと、いまの日本の投票率って、市議選なんかだと20パーセントくらいになることも多いんですよ。8割は眠っているわけです。
そうすると、為政者にとっては、2割を操作することなんてけっこう簡単なんですよ。それで権力の座について、好きなように政治ができるわけです。国政でいうと、憲法を改正して、言論を統制することだってできてしまうんです。
選挙に行かない8割は、「まさかそんなことはあるまい」とか呑気なことを言うんですけど、そういうことはある日突然起きるんですよ。
けれども、選挙に行かなかった人が文句をいう筋合いなんてないですよね。
「である」だけの状態でいて、「する」をしないと、いつかその「である」もなくなってしまうんですよ。
アメリカのある社会学者が「自由を祝福することは易しい。それに比べて自由を擁護することは困難である。しかし自由を擁護することに比べて、自由を市民が日々行使することは更に困難である。」と言っておりますが、ここにも基本的に同じ発想があるのです。私たちの社会が自由だ自由だと言って、自由であることを祝福している間に、いつのまにかその自由の実質は空っぽになっていないとも限らない。自由は置き物のようにそこにあるのでなく、現実の行使によってだけ守られる、言い換えれば日々自由になろうとすることによって、初めて自由でありうるということなのです。その意味では、近代社会の自由とか権利とかいうものは、どうやら、生活の惰性を好む者、毎日の生活さえ何とか安全に過ごせたら、物事の判断などは人に預けてもいいと思っている人、あるいはアームチェアから立ち上がるよりもそれに深々と寄りかかっていたい気性の持ち主などにとっては、甚だもって荷厄介な代物だと言えましょう。

自由については、
祝福する < 擁護する < 日々行使する
というように、右にいくにしたがって難度が上がるのですね。
そうですよね。「自由を日々行使する」って意外と難しいことは、みなさんも経験済だと思います。学校に行って、授業を受けて、部活に出て、家でも宿題をやって・・・という生活のなかでは、「自分のしたいことをする時間」を積極的に設置しないといけません。学校の指示は、みなさんの自由を奪いにくるんですよ。隙間時間で勉強しようとか言ってくる。それを自分の意志でやるなら「自由な選択」であり、なんの問題もありませんけど、人に強制されるものではありませんよね。
これって、社会もそうなんです。「社会システム」というものは、「個人」の「自由」を奪いにきます。物理的なところでいうと、「選択肢」を減らしてきます。マイナンバーカードの保持とか、保険証の廃止とか、「社会システム」は「こうしないといけないよ」と強制してくるのですね。そういう場合に問題点を指摘し続けないと、「個人の選択肢」はどんどん減っていくんですね。それは「自由」が制限されていくのに近いことです。
ところが、世の中には「物事の判断は人にしてもらいたい人」とか、「アームチェアに深々と寄りかかっていたい人(何にもしないでそこにいることが好きな人)」などがいますよね。
先ほどの話で言うと「選挙に行かない人」はこういう人です。だって、自分の地域や国の代表を自分で選ぶことを放棄しているのですから。
でも、「代表を選ぶ」ということを「する」ことをしていないのですから、かりに「アームチェアに座っているだけの人は消費税50%」という法案が通っても、文句をいえないですよね。
「アームチェアに座り続けている」存在「である」だけだと、いつのまにかその「である」が脅かされていくのです。
近代社会における制度の考え方
自由人という言葉がしばしば用いられています。しかし自分は自由であると信じている人間は、かえって、不断に自分の思考や行動を点検したり吟味したりすることを怠りがちになるために、実は自分自身の中に巣食う偏見から最も自由でないことがまれではないのです。逆に、自分が「とらわれている」ことを痛切に意識し、自分の「偏向」性をいつも見つめている者は、何とかして、より自由に物事を認識し判断したいという努力をすることによって、相対的に自由になりうるチャンスに恵まれていることになります。制度についてもこれと似たような関係があります。

少し比喩的な話をしましょう。
ミヒャエル・エンデの小説に「自由の牢獄」という話があります。
ある男が、神を冒涜したことで、「自由の牢獄」に閉じ込められてしまうのです。しかし、そこには無数の扉があって、どの部屋からも出ていくことができます。だから、物理的には閉じ込められているわけではないのです。
ところが、その男は出ていくことができません。扉Aを開けたら荒野かもしれませんし、扉Bを開けたらお腹を空かせたライオンがいるかもしれません。つまり、どの扉が「最善の扉」なのか、選択できなくなってしまうのです。
こういう「主体的な選択」がしにくいときって、「ラッキーセブンってことで、7番目の扉を選ぼう!」とか、「俺はオレンジが好きだからオレンジの扉が正解だ!」とか、もともと持っている偏見や先入観「のみ」で物事を決めてしまいがちですよね。
逆に、「いやいや、ラッキーセブンなんて、いままで信じていたけど、本当かどうかわからないぞ!」といったように、自分の中に巣くっている偏見や、根拠のない思い込みを一回客観視して、冷静に物事を見極めたほうが、「自由を獲得するよい選択」ができる可能性が上がるわけです。少なくとも、あんまり考えないでノリで行動する人よりは、「自由を獲得するチャンス」は広がります。そういう点で、「相対的」に自由になる可能性が高いのだといえます。
民主主義というものは、人民が本来制度の自己目的化──物神化──を不断に警戒し、制度の現実の働き方を絶えず監視し批判する姿勢によって、初めて生きたものとなりうるのです。それは民主主義という名の制度自体について何より当てはまる。つまり自由と同じように民主主義も、不断の民主化によって辛うじて民主主義でありうるような、そうした性格を本質的に持っています。民主主義的思考とは、定義や結論よりもプロセスを重視することだと言われることの、最も内奥の意味がそこにあるわけです。

「制度」というものは、本来その上位に「本来の目的」があるはずですね。
たとえば、消費税でいえば、「社会保障につかう(国民の生活を守るため)」という「本来の目的」があります。
ところが、大多数の国民は、その「本来の目的」を忘れてしまい、「消費税10%」という制度に慣れきってしまい、その制度のほうを守ろうとしてしまいます。こういうのを「自己目的化」といいます。「本来の目的(そのモノに込められた魂)」のほうを見ないで、「モノ」そのものを大切にしてしまうので、「物神化」ともいいます。魂のこもっていないモノ自体を、神様のように扱ってしまうということですね。
さて、消費税の話に戻ると、「消費税によって国民が苦しんでいる」という現状がありますよね。そうすると、「国民の生活を守る」という「主目的」を、「消費税」は達成できていないばかりか、その「主目的」に逆行している制度になっているともいえます。
だからこういう場合に、「本来の目的」のほうをちゃんと見て、機能していない(あるいは逆効果になっている)「モノ(制度)」のほうを民衆が批判していくことが「民主主義」なのですね。
民主主義にとっては、「どういう結果になったか」ということよりも、「どういうプロセスでその結果になったのか」ということのほうが重要なのです。
王様が勝手に「徴兵制なし」というくらいだったら、国民がみんなで議論に参加して「いや、国を守るために徴兵制あり」と決めるほうが、「民主主義」にとっては「正義」なのです。
このように見てくると、債権は行使することによって債権でありうるというロジックは、およそ近代社会の制度やモラル、ないしは物事の判断の仕方を深く規定している「哲学」にまで広げて考えられるでしょう。

「貸したお金」は「返して!」と言い続けないと「貸した」という事実さえいつか消滅してしまいます。
まさに、「である」は「である」のままでは「である」ではなくなってしまいます。言い換えると、「する」ことによって「である」のままでいられるのですね。
このことは、「債権」の話だけではなくて、「近代社会の制度」や、「近代社会の道徳的価値観」や、「物事の判断基準の底にある哲学」といった、いろいろなものに当てはめることができそうだと、筆者は述べています。

「モラル」は「道徳」っていう意味なんだね。

はい。
近い言葉に「倫理」という語があります。英語では「エシックス」です。
さて、「倫理」を辞書で引くと、「道徳。モラル。」という意味が記載されていますので、一般的には同じ意味のように扱われます。
ただ、あえて区別して言えば、
「道徳」は、「社会的にどう行動するかという規範」のことで、「倫理」は、「人としてどう行動するかという規範」のことだと言えます。
哲学者の池田晶子は、「道徳」は「強制」で、「倫理」は「自由」と区別しました。
自分がしたくなくても、社会的にそうすべきであればそうするのが「道徳的行為」であり、自分自身の自由意思で「人としてこうすべきだ」と思ってするのが「倫理的行為」であるといえます。
「プディングの味は食べてみなければ分からない。」という有名な言葉がありますが、プディングの中に、いわばその「属性」として味が内在していると考えるか、それとも食べるという現実の行為を通じて、美味かどうかがその都度検証されると考えるかは、およそ社会組織や人間関係や制度の価値を判定する際の二つの極を形成する考え方だと思います。身分社会を打破し、実在論を唯名論に転回させ、あらゆるドグマを実験のふるいにかけ、政治・経済・文化などいろいろな領域で「先天的」に通用していた権威に対して、現実的な機能と効用を「問う」近代精神のダイナミックスは、まさに右のような「である」論理・「である」価値から、「する」論理・「する」価値への相対的な重点の移動によって生まれたものです。もしハムレット時代の人間にとって “to be or not to be” が最大の問題であったとするならば、近代社会の人間はむしろ”to do or not to do”という問いがますます大きな関心事になってきたと言えるでしょう。

「プリン」のなかにそもそも「おいしい」という「確固たる性質」が存在していると考えるのが「実在論」の考え方です。
その一方、「いやいや! 実際に食べてみて、食べた人が美味しいと感じて、これは〈美味しいプリンだ〉と名付けるからこそ「プリンのおいしさ」は成り立つのだと考えるのが「唯名論」の考え方です。
たとえば、みなさんは漢文で「性善説」を学びましたね。あれは「実在論」です。人間にはそもそもの性質として「善」が内在しているから、悪い方に導かれさえしなければ悪いことなんかしないんだ、という考えです。
その意味では「性悪説」も「実在論」ですよ。
こういうふうに、「もともと善」とか「もともと悪」とかの立場を取らずに、実際に行ったことを見ていって、「Q太郎」の「行動A」は「よい行動」、「行動B」も「よい行動」、「行動C」も「よい行動」、「行動D」は「悪い行動」・・・。「よい行動」のほうが多いから、「Q太郎はよい人間」と名付けていくのが「唯名論」です。

そうすると、「王様はいい政治をするに決まってる」とか「天皇は神様のような存在」というように、実際の行為を見ずに「そもそもすばらしい属性を持っている」と考える「前近代的な価値観」は、「実在論」に近いといえるね。

そうですよね。
家庭における保護者とか、教員のあり方とかも、昭和期までは「ぶんなぐっても正義」みたいなところがありましたよね。
「保護者」や「教員」は、「子どもよりも知的」で、「子どもに愛情を注ぐ存在」としての「属性」がそもそもあるとみなされてきたんです。少なくとも日本の法制度はそういう立場で作られています。
でもそんなことないですよね。ダメな保護者もダメな教員もたくさんいるんです。平成から令和にかけては、「そもそもの性質」という見えないものではなくて、「体罰をしない」とか「わかりやすい授業をする」といったような「実際の行為の集積」によって、「いい保護者」「いい先生」と名付けられるようになってきました。
そういう点では、「社会制度」とか「家庭制度」といったものが、「実在論」的な考えから、「唯名論」的な考えに変化してきたのが近代の特徴だといえますね。
前近代では、「王様」も「天皇」も「将軍」も「親」も、「先天的(アプリオリ)」に「上級な性質を持っている」とみなされてきましたけど、近代に入り、現代に至る過程で、「そうじゃないんだ。先天的にそういう権力が備わっているわけではないんだ。王様だって天皇だって将軍だって親だって、ダメなことをしていたらダメな存在なんだ」という価値観に変化していったのですね。
フランス革命などは、その典型的な転換点ですね。
もちろん、「『である』こと」に基づく組織(例えば血族関係とか、人種団体とか)や価値判断の仕方は将来とてもなくなるわけではないし、「『する』こと」の原則があらゆる領域で無差別に謳歌されてよいものでもありません。しかし、私たちはこういう二つの図式を想定することによって、そこから具体的な国の政治・経済、その他さまざまの社会的領域での「民主化」の実質的な進展の程度とか、制度と思考習慣とのギャップとかいった事柄を測定する一つの基準を得ることができます。そればかりでなく、例えばある面では甚だしく非近代的でありながら、他の面ではまた恐ろしく過近代的でもある現代日本の問題を、反省する手がかりにもなるのではないでしょうか。

まあそうは言っても、「社長に就任したばかりの人」は、「社長としての実績」はその時点ではゼロなわけだから、初日から唯名論にもとづいて「いい」「悪い」を見ていくのは困難だよね。

そうですよね。ある程度は「この人は先天的に資質があるに違いない」と信じて、まずはやらせてみるフェーズが必要ですよね。
あるいは、「保護者」なんかも、「唯名論的立場」だけで評価するわけにもいかないですよね。県会議員とか総理大臣とかはダメだったら変えることもできますけど、保護者は簡単には変えられないですからね。
このように、社会のいたるところに、「実在論」でものを考えなければならないケースはまだまだあります。
それに「唯名論」が万能なわけでもないので、「なんでもかんでも唯名論で考えるぞ!」っていうのもダメですよね。

「唯名論」のほうがいい気がするけど、万能ではないんだね。

そうですね・・・。
たとえば、「評価に時間がかかるもの」とか「評価しきれないもの」ってありますよね。
最後のほうで筆者が例に挙げますが、「芸術」とかはそうですよね。
「芸術活動」なんかは、むしろ「ある造形物」に「アート」の「本質」を見出だそうとするものですよね。そのとき「その時代のその地域の世間一般の尺度」を持ち出して、「いい」「悪い」とか言い出すのはナンセンスです。

ああ~。
たしかに、展覧会会場にトイレをおいた、マルセル・デュシャンの作品なんかは、そのときの現実的な評価基準でいえば「ダメな作品」だけど、そこになんらかの「アート性」を見出だせるなら、「芸術」としては成り立つよね。


そうですよね。
だから「芸術」なんかは、「唯名論」的立場でよしあしを評価すべきものではありません。
「する」価値と「である」価値との倒錯
厄介なのは、「『する』こと」の価値に基づく不断の検証が最も必要なところでは、それが著しく欠けているのに、他方さほど切実な必要のない面、あるいは世界的に「する」価値のとめどない侵入が反省されようとしているような部面では、かえって効用と能率原理が驚くべき速度と規模で進展しているという点なのです。

前者でいえば、それこそ「政治」の分野などに言えるでしょうね。
本来であれば、政治家の行動は「することの積み重ね」で評価しなければなりません。ところが、その人が有名な政治家の子どもであるとか、血筋がいいとか、見た目がいいとか、元アイドルであるとか、「である」だけで評価されてしまうことが多いです。
細かい話をすると、選挙前に「マニュフェスト」を掲げますけれども、当選後にそれを「する」かどうかが検証されることってほとんどないんですよ。
「私は〇〇をします!」と言って、それを信じた人が投票するんですけど、たいていの候補者は議員になったあとにそれをしません。「する」をしないのですね。にもかかわらずあまり批判されないというのは、大きな問題ですよね。
後者でいうと、たとえば「学校の評価方式」などがそれに当たるといえそうです。いまの学校システムだと、なんでもかんでも「目に見えるもの」で提出させて、それをコツコツ点数化していく方式になりすぎています。「する」ことだけで評価しているのですね。
でも、もしかしたら、学校の宿題があまりにも簡単すぎて、バカバカしいから提出しない生徒っているかもしれませんよね。そのときのその生徒の「能力」について、「する」をしていないからバカである、とみなすのはおかしいですよね。
いまの学校システムだと、「真の天才」を評価する「能力」がないんですよ。先生たちは、自分たちの持っているモノサシに基づいて指示をして、それを「する」生徒しか評価できないのです。
こういう状態で「真の天才」を、「評価能力をもたない学校」が「バカである」とみなしていたら、それこそバカな社会ですよね。こういう点に、「する」だけで評価するシステムの反省点があります。
それは特に大都市の消費文化において甚だしいのです。私たちの住居の変化──「である」原理が象徴している床の間つき客間の衰退に代わって、「使う」見地からの台所・居間の進出や家具の機能化──とか、日本式宿屋──ご承知のようにある部屋の客であることから食事その他あらゆるサービスの享受権が「流れ出」ます。なじみの客ほどそうです──がホテル化していく傾向などはまだそれなりの意味もありましょう。しかし例えば「休日」や「閑暇」の問題になるとどうだろうか。都会の勤め人や学生にとって休日はもはや静かな憩いと安息の日ではなく、日曜大工から夜行列車のスキーまで、むしろ休日こそ恐ろしく多忙に「する」日と化しています。最近も「レジャーをいかに使うか」というアンケートをもらったことがあります。レジャーは「『する』こと」からの解放ではなくて、最も有効に時間を組織化するのに苦心する問題になったわけです。それだけでありません。学芸の在り方を見れば、そこには既にとうとうとして大衆的な効果と卑近な「実用」の基準が押し寄せてきています。最近もあるアメリカの知人が、アメリカでは研究者の昇進がますます論文著書の内容よりも、一定期間にいくら多くのアルバイトを出したかで決められる傾向があるという嘆きを私に語っていたことがあります。

ああ~。
たしかに、休日は何もしないでゴロゴロしていたいものだけど、「する=GOOD」という価値観にどっぷりつかっていると、「何もしないで過ごすなんてバカだ」とか「もったいない」とか「正気なの?」とか言われるよね。
でも、ただたんに「である」でいたいときって、けっこうあるよね。

そうですよね。
旅館なんかも、そもそもいい旅館は、ただ「いい部屋」があって、「いい温泉」があって、お客はほったらかしでいいんですよ。「である」の質がよければいいんです。
でも、いまの社会の評価基準だと、サービスマンがあれこれ世話を焼いてくれないと、「気が利かない」とか「何もしてくれない」とか、「マイナス評価」につながってしまいます。
「する」ことを評価するという価値観が社会を侵食しすぎると、人間関係だって「する」で評価しあうようになってしまいますよね。

ああ~。
たとえば友人関係とか恋人関係とかも、「何も話さないでいっしょにいられればいい」っていう価値観があっていいと思うけど、『今日好き』とか見ていると、「僕は君のためにこんなことをしてあげられる」とか「退屈させない」とか「ずっと王子様のようにもてなす」とか、「する」のオンパレードだよね。

教員の評価とかも、「どれだけ偏差値上げたか」とか「どれだけ生徒を熱く鼓舞してやる気にさせたか」とか、「何をしたか」で査定されるじゃないですか。
でも、その「する」によって、かえって生徒のマイナスになっていることだってたくさんあるんですよ。ですから、「教員A」は、生徒のマイナスになる「する」を一切しなかった、なんていう評価基準があったっていいんですけどね。
学問や芸術における価値の意味
アンドレ・シーグフリードが『現代』という書物の中でこういう意味のことを言っております。「教養においては──ここで教養とシーグフリードが言っているのは、いわゆる物知りという意味の教養ではなくて、内面的な精神生活のことを言うのですが──しかるべき手段、しかるべき方法を用いて果たすべき機能が問題なのではなくて、自分について知ること、自分と社会との関係や自然との関係について、自覚を持つこと、これが問題なのだ。」そうして彼はちょうど「である」と「する」という言葉を使って、教養のかけがえのない個体性が、彼のすることではなくて、彼があるところに、あるという自覚を持とうとするところに軸を置いていることを強調しています。ですから彼によれば、芸術や教養は「果実よりは花」なのであり、そのもたらす結果よりもそれ自体に価値があるというわけです。こうした文化での価値基準を大衆の嗜好や多数決で決められないのはそのためです。「古典」というものがなぜ学問や芸術の世界で意味を持っているかということがまさにこの問題に関わってきます。

そもそも、時代によって、「相手のための行為」って変化していくじゃないですか。
たとえば、昭和初期の大人である「P次郎」が、「泣いている子ども」のためを思って「いつまでも泣いていたらいかん!」と叱ったとします。
でもこの行為を、「今」の価値観で評価すると、「P次郎の行為は冷たい」というように、マイナス査定される可能性がありますよね。
だから、「何をしたか」だけで「その存在」の「本質」を見ようとするのは、けっこう無理があることだといえます。
この場合でいうなら、「する」だけで判断するのではなくて、「相手への思いやりに基づいていたのだから、P次郎はいい人だ」というように、「そもそもP次郎はいい人間」なの「である」という見方をしないといけない場面もあるわけです。

ああ~。
たしかに、「する」だけを見て「よい評価」「悪い評価」をしていくと、そもそも見方によって判断が分かれるものだってあるよね。

有名な話に「モハメド・アリの井戸」というのがありまして、
ボクシングの世界チャンピョンの「モハメド・アリ」が、獲得した賞金をつかって、砂漠に井戸を掘ったんですよ。

いいことだね。

でも、その井戸に動物が集まり過ぎて、周囲の植物をぜんぶ食べちゃって、風の通り道になって、ますます植物が育たなくなって、周辺の砂漠化がすすんでしまった。

悪いことだね。

でも、そのことが教訓になって、そういう井戸の掘り方はやめよう、という反省点を得られて、似たようなケースが激減したから、結果的に大規模な砂漠化が起きなかった。

いいことだね。

こんなふうに「あるひとつのアクション・イベント」って、「どこから見るか」「どこで見るか」によって、「いい」とも「悪い」ともいえますよね。
ということは、「する」ことで評価するって、実際には相当難しいんですし、不可能であるともいえます。
ただ、この場合に、「モハメド・アリ」が「いいことをしよう」と思って井戸を掘ったわけですから、結果はひとまず措いておいて、この「いいことをしよう」と思ったことそのものは、心の在り方として褒めるべきことだと言えます。こういうときには、「である」の観点を持ち込まないと、アリを評価できなくなってしまいますね。

ああ~。
たとえば幼稚園児が、親がごはんを作るのを手伝いたくて、一生懸命手伝ったらかえって台所がぐちゃぐちゃになってしまったときに、その結果(「する」の観点)だけを見て叱るわけにはいかないよね。
むしろ「手伝いたい」っていう気持ち(「である」の観点)がうれしいよってほめるポイントだよね。

そうです、そうです。
だから、教育現場が「する」論理だけになってしまうと、大問題ですよ。むしろその子が「どうあろうとしたのか」という「である」の論理を持ち込まないと、心がくさってグレていく子どもがたくさん出現しますよ。

そういう点では、「ある一つのモノサシ」で「意味がある」とか「意味がない」とか議論すること自体について、「ちょっと待って」と言ったほうがいいことってありそうだね。
そもそも「そのモノサシ」が、ゆがんでいる可能性だってあるし、「社会に必要とされるモノサシ」が「別のモノサシ」になることだってあるからね。

そうですよね。
まあ、政治や経済の世界でいえば、「国民が豊かになった」とか「経済成長してお金持ちになった」といったように、「結果で判断される」のはたしかですよね。実際にどのくらい恩恵をもたらしたのか、というポイントで判断されるのが政治や経済です。
だから、さきほどの「アリの井戸」の話でいえば、これが「政治家」であるなら、「井戸を掘ったからいい政治家だ!」とか、「いや、砂漠化につながったから悪い政治家だ!」といったように、「結果論のモノサシで評価される宿命」をもっています。
けれども、これが「芸術活動」や「教育活動」であったなら、安易にすぐ「いい/悪い」と評価するのはいったん控えないといけないですよね。
「これがいい芸術か」とか「Q太郎はいい子なのか」といったことを多数決で決めるわけにもいきません。

なんていうか・・・「その場だけのモノサシ」で決めていい問題ではないよね。

そうですよね。
「この芸術の価値は?」とか「この子のよさは?」とかいったものは、「その場だけにある短期的な価値観」だけで決めるものではなく、「昔からあるたくさんの芸術作品」とか「昔からの人々の心」とか、かなり長期的なモノサシを取り出して、あれこれ考えないとわからないですよね。
たとえば、「落ち着きがない子」って、日本の学校では注意されますけど、アマゾンでは英雄なんですよ。外敵の襲来をいち早く見つけるヒーローなんです。
このように、「芸術性」とか「人間性」とかは、「ある地域」「ある時期」だけの価値観で決めていいものではないですね。
政治や経済の制度と活動には、学問や芸術の創造活動の源泉としての「古典」に当たるようなものはありません。せいぜい「先例」と「過去の教訓」があるだけであり、それは両者の重大な違いを暗示しています。政治にはそれ自体としての価値などというものはないのです。政治はどこまでも「果実」によって判定されねばなりません。政治家や企業家、特に現代の政治家にとって「無為」は価値でなく、むしろ「無能」と連結されてもしかたのない言葉になっています。ところが文化的創造にとっては、なるほど「怠ける」ことは何物をも意味しない。先ほどのアルバイトにしても、何も寡作であることがりっぱな学者、りっぱな芸術家というわけでは少しもない。しかしながら、こういう文化的な精神活動では、休止とは必ずしも怠惰ではない。そこではしばしば「休止」がちょうど音楽における休止符のように、それ自体「生きた」意味を持っています。ですから、この世界で瞑想や静閑が昔から尊ばれてきたのには、それだけの根拠があり、必ずしもそれを時代遅れの考え方とは言えないと思います。文化的創造にとっては、ただ前へ前へと進むとか、不断に忙しく働いているということよりも、価値の蓄積ということが何よりだいじだからです。

「政治」や「経済」というものは、ひとまず今存在する「モノサシ」によって、今生きている人々に対して「いいこと」をするための活動ですよね。
だから、「モノサシ」そのものは「今通用しているモノサシ」を使わざるを得ないんですね。今の国民の「豊かさ」を考えるときに、50年前の価値観とかを持ち出してもダメなんです。
その一方、「芸術」などは、その「モノサシ」自体を作り変える活動ともいえますよね。

「である」を見るべきものと、「する」を見るべきものと、いろいろな現象があるのだけれども、「である」で考えなければならないものに「する」を持ち込みすぎたり、逆に「する」で考えなければならないものに「である」を持ち込みすぎたりするのは、たしかに問題だね。
(以下余白)