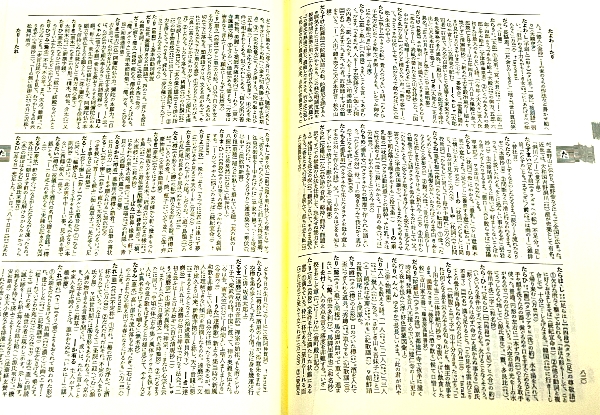問1 傍線部①~⑤のカタカナを漢字で記せ。
① 含意
② 奉納
③ 過言
④ 彼我
⑤ 抹消

①の「含意(がんい)」ということばは、耳慣れないかもしれませんが、評論ではよく出てきます。
意味は「表面に現れない意味を含みもつこと」です。
本文には、
「アメリカ社会の日常が、キリスト教の宗教的含意によって満たされていたということだ」
と書いてありますね。
これは「アメリカ社会の日常に、よく見ると、キリスト教の宗教的な意味が含まれている」ということを示しています。
たとえば、アメリカでは食事の前にお祈りをするご家庭が多いです。「キリスト教における神」に感謝しているのですが、アメリカ人がこれを「さあ、宗教的行為を実施するぞ!」と深く考えているとまでは言えません。わりと適当に済ませているご家庭もありますし、「アーメン」しか言わない人もいます。つまり、「食事の前のお祈り」は、「日常的な習慣」として受け止められている営みだと言えます。
「日常」のなかに「宗教的含意」があるというのは、このように「普通のこと」として習慣化していることに、よく見ると「宗教的な意味」が含まれているということを述べていることになります。

④の「彼我」っていうのは、「ヒガ」って読むんだね。

文字通り「彼」と「我」ということなので、「相手と自分」「あちらとこちら」という意味になります。
スポーツの試合などで「彼我の戦力差はいちじるしいものだ。このままでは負けてしまう」という場合、「彼」は「相手チーム」のことで、「我」は「自分チーム」のことを意味しています。
問2 傍線部(ⅰ)と同じ意味になる熟語を漢字二字で記せ。
「シンボル(symbol)」は、熟語でいうと「象徴(しょうちょう)」です。

「物体」などの「知覚しやすいもの(A)」と
「観念」や「概念」などの「知覚しにくいもの(B)」があり、
AによってBが連想される
(AがBを暗示している)
関係になっている場合、AをBの「象徴」といいます。外来語でいうと「シンボル」です。
たとえば「学校の校章」などは、その「物体」を見ることによって、「学校の理念」が連想されるものになっているので、「校章(A)」は「学校の理念(B)」の「象徴(シンボル)」であるといえます。
みなさんの校章でいうなら、「鏡」と「碇」のマークが示されています。
「鏡」は「いつでも自分をみつめなおそう」という「理念」を示しており、「碇」は「安易に流行に流されずに、信念をどっしりと降ろしておこう」という「理念」を示しています。
その点で、「鏡と碇」は、みなさんの学校の理念を象徴しているといえます。
問3 傍線部(ⅱ)と対になる言葉を、本文から漢字二字で抜き出せ。
「イスラーム」という「文化」の違いは、女性たちが被るスカーフという実に目に見えやすい形で現象している。その、目に見える違い、つまり「文化の違い」ということがにわかに、現代においてなお人々が厳格に宗教的に生きているイスラーム社会、(ⅱ)特殊な社会というイメージを生み出す。「文化の違い」はたしかに、スカーフの有無という可視化される差異として現象しているけれども、たとえば永年の生活習慣としてそれが行われているという点に注目すれば、私たちの社会もまた、現れ方は異なるけれども、同じような態度が見られることに気がつくだろう。

「特殊」は、「性質・内容などが他と著しく異なること」を意味します。
対義語は「普遍」です。「全体に広く行き渡ること」「例外なくすべてのものにあてはまること」を意味します。
本文中に「普遍」という語は存在しますので、正解は「普遍」です。

なんか、古文で出てくる「あまねく」っていうことばに似ている意味だね。

古語の「あまねし」という形容詞は、「普し」または「遍し」と書きます。
「普」という文字は、「おひさま」の上に陽光がぶわーっと広がっている字なのですね。
「遍」という文字は、「扁」が「戸に掛ける木片(表札のようなもの)」の象形であり、「平らであること」を意味します。「しんにょう」は「行くこと・移動すること」を意味するので、「遍」は「平らに広がったところを巡る」という字になります。
つまり、「普」も「遍」も、「広く行きわたる」という意味になります。
問4 傍線部(ア)とあるが、「日本人は宗教心が希薄だ」と「日本人自身」が感じるのはなぜか、傍線部(ア)を含む段落の内容を踏まえて、五十字以内で説明せよ。

傍線部(ア)のある段落の最後のほうに、ちょうどその理由が示されています。
同じことはこの日本社会についても言えるかもしれない。(ア)日本人は宗教心が希薄だと、日本人自身が言うのをよく聴く。たいていの場合、「それに較べてイスラームの人々は宗教熱心で、私たちとはぜんぜん違う」という言葉があとに続くのだが、でも、そうした日本人自身の意識とは正反対に、日本社会を体験したイスラーム教徒が強調するのは、日本社会がいかに宗教的であるか、ということだ。何十万という人々が神社に初詣に出かけ、柏手を打ったり、何事か祈願して絵馬をホウノウしたり、おみくじを引いたり、七五三で神社にお参りに出かけたり、仏壇に朝晩供えものをしたり、お盆に坊さんを呼んで法事をしたり……私たちにとってそれは、とりたてて宗教的な行為というわけではなく、親がやってきたから自分も何となく繰り返している日常の一こま、あるいは年中行事のひとつに過ぎないとしても、それはたしかに宗教的な意味に浸潤されている行為なのだ。そして私たちは、それを当たり前の日常として生きているがゆえに、その宗教性は空気のように自然化されてしまっており、ことさらに宗教的な行為とは感じなくなってしまっているだけなのかもしれない。

たしかにここが理由のように思えるけど、
私たちは、それを当たり前の日常として生きているがゆえに、その宗教性は空気のように自然化されてしまっており、ことさらに宗教的な行為とは感じなくなってしまっているから。
って書くと、82字になっちゃうね。

要点を落とさずに、50字に圧縮しましょう。
字数を縮めるだけではなく、次の作業を意識します。
(1)「私たちは」という表現も「日本人は」などと客観化した表現にしましょう。「日本では」などとしてもいいでしょう。
(2)「それ」という指示語を答案に残すのはよくないので、解決していきたいです。「それ」が指している意味内容としては「宗教的行為」などと書くのがいいですね。
(3)「空気のように」という表現は「比喩」なので、カットしたほうがいいです。
(4)「ことさらに宗教的な行為とは感じなくなってしまっている」という表現の「ことさら」は、「特別」ということなので、そう書いてしまったほうが字数を詰められます。また、「宗教的な行為」は、(2)の時点で書いておけば再び書く必要はないので、「特別なこととは感じない」などと短く表現することが可能です。
そうすると、次のような「下書き」ができます。
下書き
日本人は、宗教的行為を当たり前の日常として生きているがゆえに、その宗教性が自然化されており、特別なこととは感じないから。60

まだ60字あるぞ。

冗長な「ひらがな部分」をコンパクトにしていきましょう。
記述問題で字数を詰める場合は、「ひらがなを短くしていくこと」が基本戦略です。
解答例
日本人は宗教的行為を当たり前の日常として生きるため、宗教性は自然化され、特別なものと感じないから。49

詰めきったあぁァー!
採点基準
〈主題(主語)〉 1点
日本人は
*「日本人にとって」「日本では」なども可
〈論点a〉 3点
宗教的行為を当たり前の日常として生きている
*「宗教的行為」「当たり前」「日常」で「1点」ずつ
〈論点b〉 2点
宗教性が自然化される
*「宗教性」と「自然化」で「1点」ずつ
〈論点c〉 1点
特別なものとは感じない
*「特に意識しない」「特に気にしない」など、同趣旨なら加点

これが大学入試などになると、要点を落とさずに40字以内で書く水準になってきますね。
そういった場合には、「要点的な言い換え」も駆使しながら、いっそうコンパクトにしていく必要があります。
たとえば、次のようになります。
解答例(40字以内)
宗教的行為が日常の習慣である日本では、宗教性は自然化され、特に意識されないから。40

たしかに、表現は詰まっているけれども、「要点」としては「50字」のときと変わっていないね。

「大学入試」だと、このように要点を「キュッと」して、端的に書かなければならない傾向が強いですね。
問5 傍線部(イ)について筆者はどのように考えているのか。説明として最適なものを次から選べ。

傍線部(イ)のある段落に続く⑤⑥⑦⑧段落を読むと、筆者の考えが書かれています。
要点をまとめると次のようになります。
⑤ムスリム女性は、自分のまわりのすべての女性たちがスカーフを被っているから自分も被る。それは女性たちにとってまず、宗教的行為というよりも地域に根ざした生活習慣としてある。
⑥永年の生活習慣としてそれが行われているという点では、私たちの社会(日本社会)もまた、同じような態度が見られる。
⑦つまり、私たち(日本)と彼ら(ムスリム)は、実はそんなに違わない。
⑧「文化が違う」ということは、彼我(相手と自分)のあいだの異質性を意味するものではなく、反対に、理解しあう可能性を表すものとなる。

たとえば、「つばめ小学校」と「すずめ小学校」では、「グーパー」の掛け声が違うとします。
「つばめ小学校」では、「グーパージャス!」であり、
「すずめ小学校」では、「グーパーグーパーグッパッパ!」だとします。
さて、この小学生たちが「コンコルド中学校」にあがったときに、「つばめ」と「すずめ」で「グーパー」をやることになると、この「掛け声」の違いに衝撃を受けますね。きっとお互いに、「え、やり方おかしくない?」と思うことでしょう。

ああ~。
たしかに、「掛け声」はけっこう違うね。
「つばめ」と「すずめ」は、お互いに「あいつらの掛け声やべえぞ」って思うだろうね。

しかし、「つばめ」は「つばめの伝統的文化」を守っているわけですし、「すずめ」は「すずめの伝統的文化」を守っているわけですよ。
その結果、「掛け声」という「表面的行為」に「違い」が発生したわけですね。
ということは、「自分たちの伝統的文化を守る」という「連綿とした営み」は、「つばめ」も「すずめ」も「同じこと」をしていると言えますよね。

ああ~。
「表面的な行為」は「違う」のだけれども、「連綿と続いている文化的習慣のとおりに生きている」という「根本的な生き方」は「同じ」だと言えるね。

そうすると、たとえば「イスラムの人々」と「日本の人々」との「行動パターン」は、「その地域の文化様式にしたがい日常的な習慣を形成する」という点では「同じ」であるので、「お互いそういうところあるよね!」と「理解しあうこと」だって可能になりますね。
筆者の主張をそこまでつかんで、選択肢を検討しましょう。
選択肢検討
ア 他文化と自文化との違いは目に見えやすい形で現象するが、その根底には理解不可能な本質的な違いがある。

「理解不可能な本質的な違い」が「本文と逆(主張と矛盾)」で×です。
筆者は、⑧段落で、「理解しあう可能性を表す」と述べています。
イ 他文化の中にある自文化との相違点は、共通点を確かめることで、いっそう際立ったものとして現れる。

「いっそう際立ったものとして現れる」が、「本文根拠なし」または「主張と矛盾」で×です。
筆者は、⑧段落で、「理解しあう可能性を表す」と述べていますので、「共通点を確かめる」ことのほうを重視しています。
「選択肢イ」の書き方だと、「違いを見つける」ことのほうを重視していることになってしまいますね。
ウ 他文化には自文化とは異質に見えるところがあるが、日常の習慣として自明視されると意識されなくなる。

「混乱系」の選択肢であり、×です。
筆者はたしかに、「自文化」が「日常の習慣」になると「意識されなくなる」と述べていますが、「他文化」についてはそうは言っていません。
「他文化」について「異質」に見えるところは、ずっと異質に見えているわけですから、「選択肢ウ」は「組み合わせが違う」という観点で×になります。
エ 他文化と自文化との可視的な差異は、他文化に対する偏見の表れにすぎず、実際には差異は存在しない。

「差異は存在しない」が、「主張と矛盾」で×です。
筆者は「表面的な差異」は「存在する」と述べています。しかしながら、その「表面的な差異」が生成されていていった根本的な「行動様式」においては、むしろ「同じところがある」と述べています。したがって、「差異が存在しない」と言っているわけではありません。
オ 他文化に自文化とは異なるところがあっても、それがその地域での生活習慣だとわかれば理解可能である。

⑧段落にある
「文化が違う」ということは、彼我(相手と自分)のあいだの異質性を意味するものではなく、反対に、理解しあう可能性を表すものとなる。
という主張と完全に一致します。
「選択肢オ」が正解です!
問6 傍線部(ウ)についての説明として明らかに不適当なものを次から一つ選べ。

「不適当なもの」を選ぶ問題ですね。
こういうときにうっかり「適当なもの」を選んでしまうことが多い人は気を付けてください。

ああ~。
よくやっちゃうんだよね。

「設問の条件に短く線を引くくせ」をつけておくといいですよ。
この問題であれば「不適当」に線を引くんです。
頭だけではなく、「手で気を付ける」習慣があると、ミスが劇的に減ります。
では、⑧⑨段落を見ていきましょう。
⑧「文化の違い」をこのようなものとして考えるならば、「文化が違う」ということは、彼我のあいだの通約不能な異質性を意味するものではなく、反対に、人がそれぞれの社会で生きている現実の細部の違いを越えて、理解しあう可能性を表すものとなる。「理解する」とは、それを丸ごと肯定することとは違う。むしろ、私たちは「理解する」からこそ、そこにおいて、批判も含めた対話が、他者とのあいだで可能になるのではないだろうか。そして、理解することなく「これが彼らの文化だ、彼らの価値観だ」と丸ごと肯定しているかぎり、抹消され、私たちの目には見えないでいる、その文化内部の多様な差異やせめぎあい、ゆらぎや葛藤もまた、私たちが「理解」しようとすることで立ち現れてくるだろう。
⑨他文化を自分たちとは異質だ、特殊だと決めつける視線、それは、自分たちもまた、形こそ違え、実は彼らと同じようなことをしている、同じように生きている、という、批判的な自己認識を欠いたものである。そして、この、自文化に対する批判的な自己認識を欠落させた視線が、かつて自らの「普遍性」を僭称し、他文化を「野蛮」と貶めたのではなかっただろうか。文化相対主義とはまずもって、そうした自文化中心主義的な態度に対する批判としてあることを私たちは確認しておこう。自文化中心的に他文化を裁断することを戒めるため、自文化をつねに相対化して考えることの大切さ。したがって、(ウ)そのような文化相対主義は、自文化に対する批判的な認識を欠いて、他文化を自文化とは決定的に異なった特殊なものとして見出す「文化相対主義」とは、ぜんぜん別物である。

「そのような」という指示語は、前の部分を広く指す指示語です。たいていは「複数の論点」をまとめて示しています。
〈要約系の指示語〉
このような・そのような
こういった・そういった
こうした・そうした
こんな・そんな
★前の部分を広く指す(複数の論点をまとめて指す)

「そのような」が指しているのは、おおむね次の部分です。
文化相対主義とはまずもって、そうした自文化中心主義的な態度に対する批判としてあることを私たちは確認しておこう。自文化中心的に他文化を裁断することを戒めるため、自文化をつねに相対化して考えることの大切さ。
要点を取り出してみると、ここでいう(傍線部ウが意味する) 文化相対主義 は次のようなものになります。
自文化中心的な態度に対する批判としての「文化相対主義」
他文化を裁断することを戒める「文化相対主義」
自文化をつねに相対化する「文化相対主義」
「相対化」というのは、「絶対化」の逆です。つまり、「相対化」とは、「それだけを絶対のものとして扱わない」ということです。
ここでは「自文化」を「相対化」するとなっていますね。つまり、「自分自身の文化を、たくさんある文化の中のひとつに過ぎないものとして扱う」ということを意味しています。

ああ~。
さっきの「グーパー」の例でいうと、
「つばめ小学校」が、「すずめ小学校」に対して、「あいつら、グーパーグーパーグッパッパとか言うんだよ。ウケる! 未開の地かよ!」とか言い出すと、「つばめ」は「自分たちの文化を絶対視している集団」になってしまうということだね。

そうですね。
「自分たちとは違うやり方だけど、そういう文化もあるんだね。向こうからしたら、自分たちのほうもきっと異質に見えるだろうね」と考えるのが、「傍線部ウ」で述べている「文化相対主義」ということになります。
ちょっとややこしいのですが、「傍線部ウ」のような 文化相対主義 のことを、筆者は、「他文化を自文化とは決定的に異なった特殊なものとして見出す「文化相対主義」とは、ぜんぜん別物である。」と述べていますね。
文化相対主義 という語句を使ってはいますが、筆者にとっては、〈良い 文化相対主義 〉と、〈悪い「文化相対主義」〉があるということになります。

そういえば、本文には、シンプルに 文化相対主義 と書いているものと、「 」付きで「文化相対主義」と書いているものがあるね。

とてもいい指摘をしてくれました!
筆者は、〈良い 文化相対主義 〉と〈悪い「文化相対主義」〉を区別していて、〈悪い〉ほうには「 」を付けています。
筆者は別のところで、自文化中心的な「文化相対主義」というものもあるとして、そちらを否定しています。筆者が否定している「文化相対主義」は、文化を「丸ごと」でとらえて、わかったつもりになり、自文化の「丸ごと」を肯定したり、逆に他文化の「丸ごと」を攻撃するような態度のことです。
本来であれば、文化相対主義という考え方は、世界を一元化していくグローバリゼーションに対抗する「良い考え方」として位置づけられるものなのですが、文化を「丸ごと」でとらえて、「自分はよい」「相手は悪い」という区別の仕方をしていると、〈悪い「文化相対主義」〉になってしまいますよ、と筆者は述べています。そのあたりのことは⑩段落でくわしく語られていますね。
その一方、「傍線部ウ」で述べられている 文化相対主義 は、⑧段落で述べられているように、「自文化と他文化が理解しあえるという前提に立って、対話をとおして、文化の内側にある差異なども理解していこうとする態度」を意味しています。

この設問は、「傍線部ウ」の 文化相対主義 について「不適当」なものを選ぶ問題だから、気をつけて選ばないといけないね。
選択肢検討
ア 他文化を自己中心的には捉えず、自文化を常に相対化して考える。

直前で述べていることと同じです。
適当です。
イ 他文化との対話を通して、その文化内部の多様な差異や葛藤を見る。

⑧段落で述べられていることに一致しています。
適当です。
ウ 他文化を理解不可能な異質なものと考えず、理解可能なものと捉える。

⑧段落で述べられていることに一致しています。
適当です。
エ 「これが彼らの文化だ、彼らの価値観だ」と他文化を丸ごと肯定する。

⑧段落で、
「理解する」とは、それを丸ごと肯定することとは違う。
と述べられています。
ということは、「他文化を丸ごと肯定する」という説明は、筆者の主張とは逆になります。
したがって、この選択肢が「不適当」なものになります。これが正解です。
オ グローバリゼーションとは異なる、新たな普遍性をはらんでいる。

次の⑩段落、⑪段落で筆者が述べていることに一致しています。
適当です。
問7 本文の内容に合致するものとして最適なものを次から選べ。

本文全体をふまえて正誤を考えましょう。
選択肢検討
ア 日本人は宗教心が希薄だとよく言われるが、それは日常において宗教的な意味を持つ行為があまり見られないという日本社会の特殊な事情に由来する。

「日常において宗教的な意味を持つ行為があまり見られない」が「本文に矛盾」で×です。
「お参り」「お供え」「お盆」など、日本にも宗教的な行為はたくさんあります。
イ 他文化を理解不可能な特殊なものと決めつけるような文化相対主義は、自文化を無条件に肯定し、他文化を不当に貶める自文化中心主義に結びつく。

⑨⑩段落で述べられていることに一致しています。
これが正解です。
ウ 人がそれぞれの社会で生きている現実の細部の違いを強調し、文化の独自性を主張することによって、グローバリゼーションに対抗するべきである。

「文化の独自性を主張することによって」が「主張に矛盾」で×です。
筆者は、そのような態度を批判しています。
エ 「文化」が現代世界を理解するための重要なキーワードとなっているが、現実問題としては、他文化との対話や複数の文化の共存は不可能である。

「他文化との対話や複数の文化の共存は不可能」が「主張に矛盾」で×です。
筆者は⑧段落で「理解は可能」としており、「対話」の重要性を指摘しています。
オ アラブ社会とアメリカ社会と日本社会に共通しているのは、実際には永年の生活習慣に宗教的な根拠が何も存在していないという点である。

「実際には永年の生活習慣に宗教的な根拠が何も存在していない」が、「主張に矛盾」で×です。
むしろ筆者は、「どの社会においても宗教的な根拠をもつ生活習慣が存在している」と述べています。