問1
傍線部(を含む一文)の構造を確認しよう。
歴史学の存在そのものが、 / この巨大な領域に / 支えられ、養われている。
主語 目的語(補語) 述語
主語
「歴史学」という言葉は、【指示語/比喩表現】には該当せず、このままでも十分意味が伝わる表現なので、このまま答案に出してかまわない。ただし、「歴史」ではなく「歴史学」であるので、「学」を落としてしまわないように注意しよう。
ここでは、「歴史学」という「学問」が、何を基盤にして成り立つのかということを問うているのである。
目的語(補語)
傍線部内に指示語がある場合、とにかくその指示内容を過不足なく表現する。
さしあたって歴史は、書かれたこと、書かれなかったこと、あったこと、ありえたこと、なかったことの間にまたがっており、画定することのできないあいまいな霧のような領域を果てしなく広げている、というしかない。
「この巨大な領域」が指している箇所はここになる。
「あいまいな霧のような」という比喩は、直前の「 ~ 画定することのできない」「という「実態」をたとえている表現なので、実態のほうを書いていればカット可能である。
さて、「書かれたこと、書かれなかったこと、あったこと、ありえたこと、なかったこと」は、あっさり短くしたいのであるが、「列挙的表現」なので、「このうちの2つを拾う」という書き方はできない。ここについては、
(1)書かれたこと
(2)書かれなかったこと
(3)あったこと
(4)ありえたこと
(5)なかったこと
の各要素を省かずに圧縮する必要がある。これがこの問題の最大の難しさである。自力で表現を考えなければならないが、「要素」としては落としていないことを伝えられる書き方にしよう。
答案では、〈①段落〉で述べられている「あったことか(事実か)/書かれたことか(記述されていることか)」ということを超えて、〈②段落〉で述べられる「書かれなかったこと」や「これから書かれるかもしれないこと」にまで意識が向いていることを表明しておくことが必要である。
たとえば「壇の浦の戦い」において、「安徳天皇が九州にたどりつくことはなかった」というのが現段階の定説だが、未来において、「安徳天皇は鹿児島までたどりついていた」という新発見があったら、「あった」に変わりうるのである。また、たとえば「邪馬台国の場所」は、「九州にあった」「近畿にあった」「九州になかった」「近畿になかった」などという「狭間」に立っていて、まさしく「画定できない歴史」の代表である。
そのように、歴史学が依拠する「あいまいな領域」というのは、「あったこと/書かれたこと」という単純な図式ではなく、「書かれなかったこと」「なかったこと」「ありえたこと」などにまたがっているのである。
以上により、次のような〈下書き ver.01〉が成立する。
〈下書き ver.01〉
歴史学は、事実や記録の実在や非実在、さらに可能性にまでわたり、画定できないまま果てしなく広がる領域に支えられ、養われているということ。
述語
「支えられ、養われている」は、比喩的である。なぜなら、「支える」とか「養う」とかいった表現は、本来であれば生命体に使用する表現であるからだ。いわば「擬人法」なのである。
支える
「支える」については、文脈上、「画定できずに果てしなく広がる領域があるからこそ、歴史学が成立する」といえるので、
歴史学は、 ~ 領域によって成立し、~
歴史学は、 ~ 領域があってはじめて成り立ち、~
歴史学は、 ~ 領域がなければ成り立たず、~
などと書くことができる。
養われる
「養われている」については、認められるであろう解答の方向性が二通りある。
ひとつは、「歴史学を歴史学たらしめる領域」が「果てしなく広がる」ということは、依拠する情報量が増えるということであるから、「歴史学そのもの」も「成長・発展」していくと推論することができる。
そのことから、「成長」「発展」といった表現で説明することができる。
もうひとつの観点として、たとえるなら「乳児」が「保護者」から「食事を与えられる」ように、「歴史学」は「画定できずに果てしなく広がる領域」から「生命を維持する何か」を「与えられている」といえる。その観点で考えると、傍線部の直後の表現に着眼できる。
この巨大な領域のわずかな情報を与えてきたのは、長い間、神話であり、詩であり、劇であり、無数の伝承、物語、フィクションであった。
「学問」の生命活動に必要なものは「情報」であるといえるので、この部分を拾って説明することもできる。この場合、「養われている」については、「情報を与えられている」とか「情報を得ている」などと書ければよい。
以上により、次のような〈下書き ver.02〉が成立する。
〈下書き ver.02〉
歴史学は、事実や記録の実在や非実在、また可能性にまでわたり、画定できないまま果てしなく広がる領域を基盤として成り立ち、また発展している【 or 情報を得続けている】ということ。
「果てしなく広がる」という表現が少々比喩っぽいが、これは傍線部の「外側」にある表現なので、このまま使用してよい。意味的には、傍線部の「巨大」に対応しているので、「果てしなく広がる」の論点はカットすべきではない。

「少し比喩っぽいなあ、でも通じなくもないなあ」と考えられる表現について、方法論としては、
「傍線部の内側」なら「言い換える」
「傍線部の外側」なら「使用可能」
と考えておきましょう。
「本文別箇所を参照しないと伝わらない表現」であればそのまま使用することはできませんが、「答案内で意味内容が成立している」のであれば問題ありません。
たとえば「真剣に臨む」とか「薄氷をふむ思い」とか「真実に肉薄する」とか、もともとは比喩ですけれど、「それだけで意味が伝わる表現」として成り立っています。
したがって、「ちょっと比喩っぽいかなあ」と感じる表現であっても、それが
(1)傍線部の外側にある
(2)本文別箇所を参照しなくてもそれはそれとして伝わる
のであれば、答案に用いて大丈夫です。
ポイントは、「本文別箇所を参照しなくても伝わるかどうか」です。
ただ、「圧縮」は可能なので、「無限に拡大する」とか「増殖し続ける」とか、前後関係の都合で縮めることはかまわない。
以上により、次のような〈答案〉が成立する。
〈答案①〉
歴史学は、事実や記録の実在や非実在、また可能性にまでわたり、画定できないまま膨張し続ける領域によって成り立ち、発展しているということ。
〈答案②〉
歴史学は、記録の有無だけでなく、事実の不在や可能性さえ含み、画定できないまま無限に増える事柄のすべてを学問の基盤とし、情報を得続けているということ。
〈論点チェック〉
歴史学は (ないと減点) 「学」がないものは減点
事実や記録の実在や非実在、可能性 ② 取り込み不足は①点
画定されない ① 「境界化できない」なども可
果てしなく広がる領域 ① 同趣旨なら加点
基盤として成立している ① 同趣旨なら加点
成長・発展している ① 「情報を得続けている」なども可
問2
傍線部をの論理関係を確認すると、
歴史そのものが、 【主語】
他の無数の言葉とイメージの間にあって、相対的に勝ちをおさめてきた
【述語】に係る連体修飾句
言葉でありイメージなのだ 【述語】
となる。
真ん中にあるのは「長い連体修飾句」になるので、この傍線部を「主部ー述部」と分けた場合、「述部」は非常に長いものになる。
ひとまず〈設問意図〉を探ろう。「どういうことか」の問題は、傍線部内の「未読の第三者に伝わりにくいところ」を解決することが基本方針である。
その「伝わりにくいところ」の代表は次の3つである。
指示語 → 指示内容を書く。
比喩的表現 → 文脈上の実態を書く。
意味広範な語 → 文脈に応じて規定する。
(多義的表現)
その観点で見ると、「相対的に勝ちをおさめる」という表現が「擬人法」であるため、「比喩的表現」にあたる。そこを解決することがこの問題の「中心的な設問意図」だと考えられる。
相対的に勝ちをおさめてきた
まず、傍線部が「のだ文(統括文)」であるので、原則的に前文と同内容になっているはずである。すると、前文には、
歴史とは、そのような自己像をめぐる戦い、言葉とイメージの闘争の歴史でもあった。
と書かれている。読点(、)でつながっており、「戦い」「闘争」と繰り返されているのであるから、
そのような自己像をめぐる戦い ≒ 言葉とイメージの闘争
という関係になる。
ということは、「そのような自己像をめぐる戦い」における指示語を解決していけば、答案の「核」を構成することができる。
その指示内容には、
(a)ある国、ある社会の代表的な価値観によって中心化され
(b)その国あるいは社会の成員の自己像を構成してきた
と書いてある。そこに言及できれば、「勝ちをおさめる」という内容を説明したことになる。
以上により、次のような〈下書き ver.01〉が成立する。
〈下書き ver.01〉
歴史自体が、他の無数の言葉とイメージを退け、国や社会の代表的な価値観で中心化され、成員の自己像を構成してきた言葉でありイメージであるということ。
傍線部内の「相対的」という語は、「負けた(選ばれなかった)言葉とイメージ」と、「勝った(選ばれた)言葉とイメージ」がある、という相対関係を表しているので、「他の無数の言葉とイメージよりも優先された」とか、「無数の言葉やイメージの中から選ばれた」などと書ければよい。
さて、「言葉とイメージ」という表現は、「傍線部の外部を読まなくても理解可能な表現」であるので、このまま答案に出してかまわない。字数が苦しければ「イメージ」を「表象」などと言い換えてもよい。

大前提として、私たちの「答案」という「説明」を読む人は、「傍線部」と「問い」だけを読んでいる人と仮想されます。
逆を言えば、「傍線部」と「問い」の「情報」だけは、相手も「すでに持っている」と考えます。
その関係において、傍線部の「イメージ」という表現を、答案で「表象」などにすることは、意味するところが変わらなければ問題ありません。
「あ、『イメージ』を『表象』と言い換えたんだね」ということはわかるからです。
もちろん、「イメージ」という表現のままで解答欄に入るのであれば、いたずらに言い換える必要はありません。
答案の半分くらいが「傍線部内の表現のまま」で済むことだってあるのです。
したがって、次のような〈下書き ver.02〉が成立します。
〈下書き ver.02〉
歴史自体が、無数の言葉とイメージから選び取られ、国や社会の代表的な価値観で中心化され、成員の自己像を構成してきたものだということ。
「中心化」という語がやや比喩的にみえるかもしれないが、「中心化」は「対象のうち最も目立つ側面だけに注意を集中して、それ以外の部分を無視すること」という意味をもつ述語であるので、そのまま使用してよい。
これで提出してよい水準だが、ひとつ気になる点がある。このパラグラフの先頭に、
歴史を、記憶の一形態とみなそうとしたのは、
と書いてあることである。
歴史は、「この世に起きたすべての出来事」ではなく、「記憶(誰かが覚えたこと)」の「一形態」なのだという「考え方」について、このパラグラフは語られているのだ。
つまり、「歴史 ≒ 記憶の一形態」というのは、このパラグラフの「主題」であるといえる。
その観点でいうと、傍線部で述べられている「言葉とイメージ」というのは、「記憶の一形態」のことなのである。
さらに言うと、直前の段落ではこう述べられている。
歴史とは個人と集団の記憶とその操作であり、記憶するという行為をみちびく主体性と主観性なしにはありえない。つまり出来事を記憶する人間の欲望、感情、身体、経験を超越してはありえないのだ。
「とは」という表現があることから、ここは「歴史」を「定義」している箇所だといえる。「歴史」とはそもそも「個人と集団の記憶とその操作」なのである。ここを使用してもいいだろう。
したがって、「表象(言葉とイメージ)」というものについて、
◆記憶の一形態としての表象(言葉とイメージ)
◆操作された記憶としての表象(言葉とイメージ)
という論点を補充したほうが、このパラグラフの内容を「読めている」ことになる。
そもそも傍線部の論理関係は、次のようなものであった。
歴史そのものが ≒ 言葉でありイメージなのだ。
主語S ≒ 述語P(主語Sの別名・たとえ)
*「主語」が「主題主語」になっている。
このように、「主語S ≒ 述語P」型の論理関係になる場合(主語が「主題主語」になる場合)、暗に「論拠の補充」が求められていることが多い。
あくまでも字数次第ではあるのだが、【論拠】とみなせるものが明示されているのであれば、答案に補充したほうがよい。ここでは、次のような三段論法が成り立つ。
歴史そのものが ー 記憶の一形態(操作された記憶)
記憶の一形態(操作された記憶) は 言葉・イメージ
↑ ↑ ↑
【主 語】 【論 拠】 【述 語】
よって、「歴史そのもの」≒「言葉・イメージ」である。
したがって、【論拠】とみなせる「記憶の一形態」または「記憶/操作」という表現は、できれば答案に補充する。
以上の考察から、次のような〈解答例〉が成立する。
〈解答例〉
歴史自体が、国や社会の代表的な価値観で中心化され、成員の自己像を構成する過程で、他を退けて選抜された、記憶の一形態としての言葉やイメージだということ。
〈別解〉
歴史自体が、操作された記憶として、無数の言葉と表象から選び取られたものであり、国や社会の代表的な価値観で中心化され、成員の自己像を構成してきたものだということ。
〈論点チェック〉
歴史自体が、 (ないと減点) *「歴史は」でも可
国や社会の代表的価値観で中心化 ②
成員の自己像を構成 ①
記憶の一形態 ① 「記憶とその操作」「操作された記憶」なども可
他を退けて選ばれた言葉やイメージ ② 「イメージ」は「表象」などでも可
*「言葉とイメージ」に該当する意味内容がない答案は減点。
問3
傍線部の論理関係は、次のようになっている。
歴史は ー 人間だけのものだが、
【主語①】 【述語②】
記憶のほうは ー 人間の歴史をはるかに上回る ひろがりと深さを持っている。
【主語②】 (連体修飾句) 【述語②】
ここでは、「歴史」と「記憶」が「対比」されていることがわかる。
ということは、むしろ「歴史」のほうの論点を拾って、「歴史は~することによって、記憶よりも狭くて浅くなってしまう」というかたちで書けば、「記憶」が「歴史」よりも「ひろがり」と「深さ」があることを説明したことになる。
さて、直前には、
量的に歴史をはるかに上回る記憶のひろがり
とある。これでは内容を説明したことにならないので、さらにさかのぼると、
(a)熱力量学的な差異としての物質の記憶、遺伝子という記憶
(b)これらの記憶形態の延長上にある記憶としての人間の歴史
という情報に着眼できる。(b)が人間の歴史であることに対し、(a)ははるかにそれを超えるものになる。
したがって、
(ⅰ)熱力量学的な差異としての物質の記憶
(ⅱ)遺伝子という記憶
といった論点は確保しておけるとよい。
なお、段落冒頭にある「情報技術における記憶装置(メモリー)」は、(ⅰ)の具体例である。
その一方、「歴史は人間だけのもの」といえる根拠は、〈傍線部ウ〉のすぐ前に書いてある。
歴史は局限され、一定の中心にむけて等質化された記憶の束にすぎない。
「人間の歴史」のほうの意味内容の説明としては、ここを使えばよい。すると、次のような〈下書き ver.01〉ができる。
〈下書き ver.01〉
歴史は、局限され、一定の中心にむけて等質化された記憶の束にすぎないが、記憶は量的にそれをはるかに上回り、熱力量学的な差異としての物質や、遺伝子にまで存在するから。
ただ、経緯としては、まず、「膨大な記憶の量」があり、その記憶の中から、人間の手で「局限」「中心化」「等質化」したものが「歴史」として形成されるわけであるから、「記憶の話」→「歴史の話」と表現したほうが、手短に表現しやすくなる。
したがって、次のように書けば字数を圧縮できる。
〈下書き ver.02〉
記憶は、熱力量学的な差異としての物質や、遺伝子にまで存在するが、歴史は、その記憶を局限し、一定の中心にむけて等質化した記憶の束にすぎないから。
さて、「一定の中心にむけて」と「束」は、比喩的であるので、本文においてどういう「実態」を示しているのかのほうを書いておきたい。
「一定の中心にむけて」という表現については、〈問2〉で確認した「歴史の定義」のところで、次のように説明されていたところが使用できる。
歴史とは、個人と集団の記憶とその操作であり、記憶するという行為をみちびく主体性と主観性なしにはありえない。つまり出来事を記憶する人間の欲望、感情、身体、経験を超越してはありえないのだ。
ここでは、「歴史」というものは、「個人と集団の記憶とその操作」であるとされ、「(人間の)主体性と主観的なしにはありえない」と述べられている。そして具体的に「人間の欲望、感情、身体、経験を超越してはありえない」と言い換えられている。
「歴史」が「人間の主体性と主観性」を「超越してはありえない」ということは、「人間が記憶を操作して歴史を構築する」にあたり、「人間の主体性と主観性」の「内側」でしかその操作ができないことを意味している。
したがって、傍線部の「一定の中心にむけて等質化した記憶の束」と表現は、「人間が主体的かつ主観的に等質化した記憶のまとまり」などと説明することができる。

「束」は「まとまり」などと言い換えてもいいですし、本文別箇所の「集積」という語を使うなどしてもいいですね。
「主体的かつ主観的に」というのは、もっとも短く述べるのであれば「恣意」などと言うことができる。「恣意」という語は本文に存在しないが、「主体的かつ主観的な行為」は「恣意的な行為」といえるので、答案作成上問題ない「圧縮」である。
「主体」と「主観」をそのまま答案に用いるのであれば、どちらか一方のみを答案に出すのは避けたい。明らかに並列されている語句は、書くなら両方書くほうがよい。
〈解答例〉
記憶は、熱力量学的な差異としての物質や、遺伝子にまで存在するが、歴史は、その記憶を局限し、人間が恣意的に等質化した集積にすぎないから。
〈論点チェック〉
記憶は、 (ないと減点)
熱力量学的な差異としての物質や、 ①
遺伝子にまで存在するが、 ①
歴史は、 (ないと減点)
記憶を局限し、 ①
人間が恣意的に ① *「人間が主体的かつ主観的に」なども可
等質化した ①
集積にすぎないから。 ① *「まとまり」なども可
「等質化」という語は、やや比喩的に思えるかもしれないが、「どれも似たようなものになって多様さが失われること」を意味する熟語であるので、そのまま使用してよい。むしろこの答案におけるキーワードであるとみなせるので、そのまま書くほうがよい。

多くの場合、傍線部に密接に関わっている「熟語」は、記述問題の場合そのまま書くほうがいいです。
「選択肢問題」の場合には、正解にその熟語が存在すると「簡単な問題」になってしまうこともあり、その熟語をさらにかみくだいて説明してくる可能性があります。
さて、選択肢問題であれば、次のような考え方で「さらにかみくだいて説明してくる」可能性があるので、念のためふれておこう。
+α「等質化」について

この「+α」のところは「記述解答」には無関係なので、時間がない人は読み飛ばしてOKです。
範囲を限定した場所に「出来事の情報」を集めるためには、「出来事それぞれ」の情報形態にできるだけ差がないほうがよい。
たとえば年表をイメージしてみよう。「伊藤博文が暗殺された」という情報も、「広島に原爆が落ちた」という情報も、一行で語られる。それらの出来事における、関わった人間の数や、熱意の差や、規模の大小や、影響の有無などは、「年表」においてはほとんど考慮されない。
「織田信長の本能寺焼き打ち」と「豊臣秀吉の北野大茶会」は、かかわった人間のモチベーションとか、熱意とか、葛藤とかは、まったく違う種類の出来事だが、「こんなことがあった」という年表的な歴史的記述としては、「同じ程度の字数」で語られることになる。同じ「ひとつぶんの出来事」なのである。
つまり、「等質化」とは、「本来は多様な出来事が、同水準に簡素化される」ことであると解釈できる。しかし残念ながら、「規格をそろえる」とか、「等しく簡易的に変質させる」とかいった表現が別箇所に存在しない。そのため、そのように書くことは控えなければならない。あくまでも本文を入口にできる解釈(本文を根拠にした解釈)を目指さなければならない。
ここでは、前段落である〈⑤段落〉の、
歴史そのものが、他の無数の言葉とイメージとの間にあって、相対的に勝ちをおさめてきた言葉であり、言葉でありイメージなのだ。
という箇所に着眼してみよう。
この「言葉でありイメージである」というのは、等質化した結果の「情報形態」と言える。
さまざまな記憶形態にやどる膨大な記憶を、人間の操作で選択し、局限し、「言葉とイメージ」の形態にして集積したものが歴史なのである。
具体的には、次のようなことである。
本来であれば、誰かがくしゃみをしたり、風が吹いたり、かえるがゲコゲコと泣いていたりという、あらゆる出来事が「存在」している。
そういった「万物の出来事」を見届けていった「万物の記憶」は、我々人間の記憶機関のみならず、書物や、写真に記憶されている。USBメモリーやフロッピーディスクといった「デジタル媒体」にまで記憶されている。生物のDNAという「物言わぬ生命機関」にまで、記憶されている。ということは、「取り出す」ことができないだけで、石や、草花にも「何かが記憶されている」と考えるほうが、むしろ自然である。
このように、「万物の記憶」は、人間の取り扱える範囲を超えて保存されている。それらすべての記憶を比喩的に表現すれば「神の記憶」とでも言えるだろう。
しかし人間は、人間が操作できる範囲でしかそれらを取り扱うことができない。それが「歴史」である。そういう「歴史」として取り扱ううえで、情報はどうしても「等質化(規格化)」される。
例を挙げれば、
a.言語
b.書物
c.絵
d.写真
e.動画
といったものになるだろう。(a)(b)は「言葉」で、(c)(d)(e)は「イメージ」だ。
したがって、選択肢問題であれば、次のような「正解」がありうる。
〈選択肢なら・・・〉
記憶は、人智の届かない物質の内部や生命現象にまで存在するが、歴史はそれらの記憶のなかで人間が扱えるものだけを対象とし、さらに言語や形象といった規格に矮小化したものであるから。
問4
この問いの要求の大部分は、列挙された〈例示的表現〉を一般化しよう、ということである。
歴史という概念そのものに、何か強迫的な性質が含まれている。歴史は、さまざまな形で個人の生を決定してきた。個人から集団を貫通する記憶の集積として、いま現存する言語、制度、慣習、法、技術、経済、建築、設備、道具などすべてを形成し、保存し、破壊し、改造し、再生し、新たに作りだしてきた数えきれない成果、そのような成果すべての集積として、歴史は私を決定する。私の身体、思考、私の感情、欲望さえも、歴史に決定されている。人間であること、この場所、この瞬間に生まれ、存在すること、あるいは死ぬことが、ことごとく歴史の限定(信仰もつ人々はそれを神の決定とみなすことであろう)であり、歴史の効果、作用である。
直後には、「言語、制度、慣習、法、技術、経済、建築、設備、道具」と、語句がざっと並んでいる。仮にこれらが、「言語、制度、慣習のすべてを~」といった表現で、並んでいるのが2、3個であれば、「言語、制度、慣習」と、答案に書き込んでしまってよい(書くべきである)。
しかし、「言語、制度、慣習、法、技術、経済、建築、設備、道具」と、かなりの語句が列挙されており、しかも最後に「など」と書かれている。「など」というからには、書こうと思えば、「仕事、遊戯、交通、郵送」といったように、いくらでも続きを列挙できるはずである。
したがって、ここは、筆者にとっては「例示的」な列挙だと考え、一気に圧縮できる「一般表現(抽象表現)」を考えるほうがよい。もしも、そのような表現が文中にあれば、もちろんそれを使用するのがよいが、この設問においては、そのような表現が存在しないので、自分で考えるしかない。
〈 枚 挙 or 一 般 化 〉
(1)並列、列挙されている語句群は、どれか1つを出すなら、すべて出す必要がある。
(2)字数的に(1)が困難であれば、語句群すべてを抽象化した一般表現に直す必要がある。
その観点でみると、本問は、以下の4項目をがバーッと圧縮する語彙力が求められている設問であるといえる。
(a)現存する言語、制度、慣習、法、技術、経済、建築、設備、道具
(b)形成し、保存し、破壊し、改造し、再生し、新たに作りだしてきた
(c)私の身体、思考、私の感情、欲望
(d)人間であること、この場所、この瞬間に生まれ、存在すること、あるいは死ぬこと
構文自体は、次のようにすればよい。
〈答案の構文〉
歴史は、個人から集団を貫通する記憶の集積として、現存する(a)のすべてを(b)し、(c)や、(d)を限定する効果と作用をもつということ。
あとは、〈a〉〈b〉〈c〉〈d〉に、それらを圧縮した表現を入れると、次のような〈解答例〉が成立する。
〈解答例〉
歴史は、個人から集団にいたる記憶の集積として、現存する社会習俗の一切を構成し続け、そこに生きる個人の心身や生の在り方を限定する効果と作用をもつということ。
〈論点チェック〉
歴史は、 (ないと減点)
個人から集団にいたる記憶の集積として、 ①
(a)現存する社会習俗のすべてを ① 内容が整合していれば加点
(b)構成し続け、 ① 内容が整合していれば加点
そこに生きる (ないと減点)
(c)個人の心身や ① 内容が整合していれば加点
(d)生の在り方を ① 内容が整合していれば加点
限定する効果と作用をもつ ① 「決定づける」なども可
問5
a散逸
b超越
c機会
d信仰
e矛盾
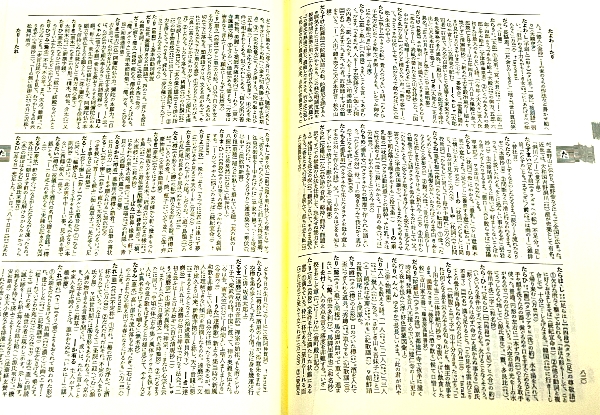
コメント